Page Top

風評被害とは、根拠のない噂や誤解に基づく情報が拡散し、企業や個人の評判や信頼が損なわれる現象のことです。特に、SNSの普及によって情報が瞬時に広がる現代では、風評被害が大きなリスクとなっています。
そこで本記事では、風評被害の原因やリスク、発生しやすい場所を詳しく解説し、対策方法や実際に風評被害が発生した際の適切な対処法についてもご紹介します。
<この記事で紹介する3つのポイント>
目次
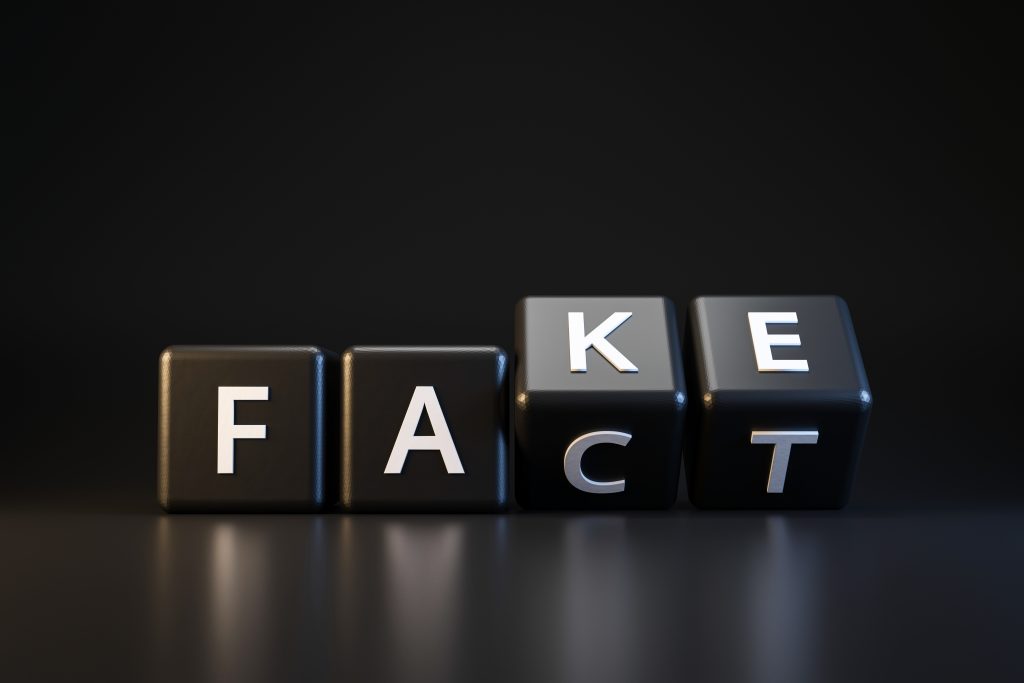
風評被害とは、根拠のない噂や憶測によって企業や個人が不当な損害を被る現象のことです。風評被害の本質を理解するには、風評被害が生じる根本的な原因や、誹謗中傷との違いを把握することが重要です。
風評被害の根本的な原因は、不正確な情報の拡散と、その情報を信じる人々の心理にあります。インターネットやSNSの普及により、情報の伝播速度が飛躍的に上がった現代社会では、事実確認が不十分なまま情報が広まりやすくなっています。
また、人々の不安や恐れといった負の感情が、根拠のない噂を信じさせる要因となっています。このような情報環境と人間心理の相互作用が、風評被害を引き起こす根本的な原因となっているのです。
風評被害は、誹謗中傷とは異なる性質を持っています。誹謗中傷が個人や組織に対する悪意ある中傷であるのに対し、風評被害は必ずしも悪意から生じるものではありません。むしろ、不確かな情報や誤解に基づいた噂が広まることで、意図せずに経済的・社会的な損害をもたらすのが風評被害の特徴です。
例えば、ある地域の産品に対する安全性の疑念が根拠なく広まり、売上が激減するといった事態が風評被害に当たります。このように、風評被害は悪意の有無にかかわらず、深刻な影響を及ぼす可能性があるのです。

近年、風評被害対策の重要性が急速に高まっています。その背景には、情報技術の発展による情報拡散の加速と、消費者の価値観の変化という2つの大きな要因があります。
これらの要因が、企業や組織にとって風評被害のリスクを増大させ、対策の必要性を一層高めているのです。
近年、ソーシャルメディアの浸透により、情報の伝播速度が飛躍的に上がりました。総務省の調査によると、20〜30代の70%以上、60代以上でも50%以上がSNSを利用しています。この高い利用率から分かるように、SNSは個人が容易に情報を発信し、瞬時に多くの人々と共有できる環境を生み出しました。
その結果、風評被害のリスクが増大し、一度広まった誤情報の収束が困難となっています。このような状況下において、企業は迅速かつ適切な対応を求められるようになり、風評被害対策の重要性が高まっているのです。
消費者の価値観が「モノ消費」から「コト消費」へとシフトしています。現代の消費者は、単に製品を所有するだけでなく、その背景にある体験や情緒的価値を重視する傾向にあります。そのため、企業の評判や社会的責任は、消費者の購買決定に大きな影響を与えるようになりました。
たとえ大企業の製品であっても、不正や品質問題、環境への悪影響などが明らかとなれば、消費者は購入を控える可能性が高くなります。このような消費者の意識変化により、風評被害対策は企業にとってブランド価値を守る重要な課題となっているのです。
風評被害は、さまざまな形で企業や個人に影響を及ぼします。ここでは実際に起こった風評被害の具体例を紹介します。これらの事例から、風評被害が引き起こす深刻な影響や対策の重要性を理解できるでしょう。
ある企業では、商品の原材料偽装や製品不良が発生した際、同社の他の商品にも同様の問題があるのではないかという憶測が広まりました。この根拠のない噂により、金融機関の信用不安や預金引き出しの騒ぎが起こり、企業の資産が大幅に減少する事態に発展しました。
このケースは、一部の製品に関する問題が、企業全体の信頼性を揺るがし、経済的な損失をもたらす風評被害の典型例といえます。風評被害は、事実とは異なる情報が拡散されることで、予想以上に大きな影響を及ぼす可能性があるのです。
ある企業において、一人の従業員がSNSに不適切な投稿を行ったことがきっかけとなり、企業全体のコンプライアンス意識の低さを指摘されるという事態が発生しました。さらに、この出来事をきっかけに、当該企業の営業方法に問題があるという噂がSNS上で拡散されました。
この事例は、個人の不適切な行動が企業全体のイメージを損なわす可能性を示しています。SNSの普及により、従業員の個人的な発言が企業の評判に直結する今日、企業には従業員のSNS利用に関するガイドラインの策定や教育の徹底が求められています。
ある企業の経営者が反社会的勢力と関係があるという根拠のない噂が広まりました。実際には全く関係がなかったにもかかわらず、経営者と同姓同名の犯罪者が存在したことから、その企業が犯罪者の企業であるとSNS上で誤った情報が拡散されたのです。
この事例は、事実確認が不十分なまま情報が拡散されることの危険性を示しています。根拠のない噂は、企業の信頼性を著しく損なわす可能性があり、その影響は長期にわたることもあります。このような事態を防ぐためには、正確な情報を迅速に発信し、誤った情報を訂正する体制を整えることが重要です。

風評被害は、企業にさまざまな悪影響を及ぼします。その影響は多岐にわたり、売上の減少・人材確保の困難・企業イメージの低下など、経営の根幹を揺るがす可能性があります。
そのため、これらのリスクを理解して適切に対処することが、企業の持続的な成長と発展にとって不可欠なのです。
風評被害は、企業の売上に直接的な打撃を与えます。根拠のない噂や憶測が広まると、消費者は当該企業の商品やサービスの利用を避ける傾向にあります。例えば「この企業の商品はすぐに壊れる」といった噂が広まれば、新規顧客の獲得が困難になるだけでなく、既存顧客も離れていく可能性があります。
さらに、取引先との関係にも悪影響を及ぼし、契約の打ち切りや取引量の減少につながることもあります。このように、風評被害は企業の収益基盤を直接的に脅かす深刻なリスクといえます。
風評被害は、企業の人材確保にも大きな影響を与えます。就職・転職支援サイト「エン・ジャパン」が自社メディア「人事のミカタ」で実施したアンケートによると、就職・転職活動時に89.1%の人が口コミサイトや口コミ検索で企業情報を調べるそうです。
このことから、企業の評判は優秀な人材を引き付ける上で極めて重要であることが分かります。ネガティブな噂が広まっている企業に、あえて就職や転職を希望する人は少ないでしょう。
結果として、企業の成長に不可欠である優秀な人材の確保が困難となり、長期的な競争力の低下につながる可能性があります。
風評被害は、企業のイメージを著しく損なう可能性があります。ネガティブな噂や憶測が広まると、顧客や株主、取引先からの信頼が低下し、批判が増加する傾向にあります。このような状況下では、新規顧客の獲得が困難になるだけでなく、既存の顧客離れも加速する可能性があります。
さらに、株価の下落や投資家からの信頼喪失など、資金調達面でも悪影響が生じる恐れがあります。企業イメージの低下は、短期的な業績悪化のみならず、中長期的な企業価値の毀損にもつながる重大なリスクとなるでしょう。

風評被害はさまざまな媒体を通じて拡散されますが、特にインターネット上のプラットフォームにおいて注意が必要です。SNS、ブログ、Webサイト、マスコミの報道など、それぞれの特性を理解して適切に対応することが重要となります。
以下では、風評被害が発生しやすい場所とその特徴について解説します。
SNSは風評被害が発生する場所の筆頭です。匿名性が高く、多くの人々と簡単につながれるSNSでは、情報が瞬時に拡散されます。一度の投稿が発端となり、短時間でフォロワー以外の利用者にまで情報が広がる可能性があります。また、不満を感じたことをきっかけに、虚偽の投稿をする事例も見られています。
SNSの特性上、悪質な投稿に対して法的措置を取ることは可能ですが、利用者数の多さから風評被害を完全になくすことは困難です。そのため、常時モニタリングと迅速な対応が求められます。
風評被害の発生源として、ブログはSNSに次いで注意が必要です。無料で匿名登録が可能なブログサービスは、個人の意見を気軽に発信できる場として広く利用されています。フリーメールアドレス1つで登録でき、氏名や住所などの個人情報入力が不要な場合も多いため、責任の所在が不明確になりやすいという特徴があります。
また、投稿者自身で簡単に削除できるため、証拠の保全が難しいという側面もあります。さらに、検索エンジンに素早くインデックスされるブログもあり、風評被害の拡散速度が速いのも課題の一つです。
Webサイトも風評被害の発生源となり得ます。特に、動画共有サイトなどのユーザー生成コンテンツ(UGC)プラットフォームでは、企業や個人を対象とした過剰な批評や根拠のない噂が投稿されることがあります。
これらのサイトは多くの場合、SNSやブログと連携しているため、一つの投稿が複数のプラットフォームで同時に拡散される可能性があります。また、サジェストや検索結果にネガティブな内容が表示されることで、風評被害が助長されるケースもあります。そのため、自社に関連するキーワードの検索結果を定期的にチェックすることが重要です。
マスコミの報道も、風評被害の原因となり得ます。インターネットやSNSが普及した現在でも、テレビや新聞などのマスメディアは高い信頼性を持ち、その影響力は依然として大きいです。多くの報道は、事実確認を経て正確な情報を発信していますが、中には事実と異なる内容が含まれており、風評被害を引き起こすケースもあります。
また、報道の仕方によっては、たとえ内容に誤りがなくても、必要以上にネガティブなものとして受け取られてしまいます。こうした報道が視聴者や読者の不安や不信を煽れば、風評被害につながる恐れがあるでしょう。
風評被害は、一度発生すると収束が困難なため、事前の予防策が非常に重要です。効果的な対策として、社内でのSNSガイドラインの作成、クライシスコミュニケーション体制の整備、そしてWeb上の自社関連投稿のモニタリングが挙げられます。
これらの方法を組み合わせることで、風評被害のリスクを大幅に軽減することが可能です。
風評被害の発生源が自社の従業員である可能性も考慮し、公式のSNSガイドラインを作成することが重要です。このガイドラインは、自社用SNSアカウントの運用ルールのみならず、従業員の個人アカウントの利用に関する指針も含めるべきです。
正社員やアルバイトを問わず、全ての従業員に対して教育を実施し、ガイドラインの内容を十分に理解させることが必要です。具体的には、企業情報の取り扱い、プライバシーへの配慮、適切な表現方法などを明確に定めることで、従業員の不用意な発言による風評被害のリスクを低減できます。
クライシスコミュニケーションとは、企業にリスクが発生した際に、顧客、取引先、メディアなどに対して行う対外的な危機管理対応を指します。風評被害のような事態が発生した場合、関連部署間で迅速に情報を共有し、適切な対応策を講じる必要があります。
そのためには、誰が判断を下すのか、どのような基準で意思決定するのか、経営陣への報告タイミングはいつかなど、具体的なエスカレーションフローを事前に決めておくことが重要です。このような体制を整備することで、風評被害が発生した際の被害を最小限に抑えることができます。
風評被害を早期に検知し、適切に対応するためには、インターネット上の自社に関する投稿を日常的にモニタリングすることが不可欠です。一見些細な投稿でも、予期せぬきっかけで拡散される可能性があるため、自社に関連する小さな記事や短い投稿も見逃さないようにチェックする必要があります。
モニタリングの結果、リスクとなる可能性がある投稿を発見した場合は、事前に整備したエスカレーションフローに従って速やかに対応することが重要です。継続的なモニタリングにより、風評被害の芽を早期に摘み取ることができます。
風評被害が発生した場合には、迅速かつ適切な対応が求められます。ここでは効果的な対処方法として、ソーシャルリスニングによる事実確認、クライシスコミュニケーションに基づく行動、そして情報発信者の特定について説明します。
これらの方法を適切に組み合わせることで、風評被害の拡大を防ぎ、早期収束を図ることができます。
風評被害が発生した際、まずは事実関係の把握が重要です。ソーシャルリスニングツールを活用し、情報収集や分析を行うことで、状況を正確に把握できます。具体的には、投稿内容の真偽、反応している人々の属性、拡散の範囲などを総合的に分析します。
これにより、企業が受ける可能性のある影響を予測し、最適な対処方法を検討できます。また、正確な情報をSNSやプレスリリースで発信したり、ステークホルダーに適切に情報共有したりすることで、風評被害の拡大を防ぐことが可能です。
風評被害発生時は、事前に整備したクライシスコミュニケーション体制に基づいた行動が重要です。適切でない情報発信は、事態をさらに悪化させる可能性があるため、企業の公式見解を慎重に検討し、承認を得てから発表する必要があります。
シエンプレ デジタル・クライシス総合研究所の調査によると、炎上事例の48%が24時間以内にメディアでコンテンツ化されているそうです。このスピードに対応するためには、迅速な意思決定と情報発信が求められます。クライシスコミュニケーション体制を効果的に機能させることで、風評被害のリスクを最小限に抑えることができるでしょう。
風評被害に対して法的措置を講じる可能性を考慮し、情報発信者の特定を急ぐことが重要です。多くのソーシャルメディアでは、匿名での利用が可能なため、発信者を特定するには専門的な手続きが必要となります。
まず、投稿されたサイトに対して発信者情報の開示を求め、必要に応じてIPアドレスの開示を請求します。その後、プロバイダーを特定し、発信者情報の開示を請求します。この行動自体が将来的な風評被害の抑止力となり、実際に発信者が特定できれば損害賠償請求も可能となります。迅速な対応が風評被害の拡大防止につながるのです。

風評被害を受けた企業が信頼を取り戻し、評判を回復するためには、戦略的かつ継続的な取り組みが必要です。特に、SNSなどのメディア戦略の見直しと、ステークホルダーとの関係強化が重要です。
これらの手法を適切に組み合わせることで、失われた信頼を徐々に取り戻し、企業イメージの向上につなげることができます。以下では、これらの手法について詳しく説明します。
風評被害による信頼回復には、SNSをはじめとするメディア戦略の見直しが不可欠です。炎上が起きたからといって、SNSの利用を中止するのは得策ではありません。むしろ、SNSは顧客と直接コミュニケーションを取れる重要なマーケティングツールとして活用すべきなのです。
風評被害収束後は、ポジティブなメッセージを発信したり、ユーザーのコメントや評価に誠実に対応します。そうすることで、悪いイメージを払拭し、関係修復を図ることができます。必要に応じて他のメディアも活用し、総合的にイメージ戦略の修正を検討することも重要です。
風評被害からの回復には、顧客だけでなく、従業員、取引先、株主、提携企業など、すべてのステークホルダーとの関係強化が重要です。企業の持続的な発展には、これらのステークホルダーとの信頼関係が不可欠であるためです。ステークホルダーを軽視し、顧客対応のみに注力すると、企業の信頼性が低下し、長期的な経営に悪影響を及ぼす可能性があります。
直接対面でのコミュニケーションを取ったり、改善策の進捗状況を定期的に報告したりするなど、積極的に良好な関係性を維持・強化する取り組みが求められます。このような努力を通じて、企業全体の信頼回復を図ることができるでしょう。
風評被害とは、事実無根の情報や誤解に基づく噂により、企業や個人の評判が損なわれる現象です。そんな風評被害は、売上の低下や信頼性の喪失、ブランドイメージの悪化を招く可能性があります。対策として、正確な情報発信や、SNSでのリアルタイムなモニタリングが重要です。また、社員教育や社内体制の強化も有効です。
DYMのSNS広告サービスでは、風評被害に対する迅速かつ的確な対応策を提案し、企業さまのリスク管理をサポートいたします。詳しくは、下記のリンクよりご覧いただけます。
風評被害を未然に防ぐためにも、ぜひDYMのSNS広告サービスをご検討ください。
DYMの「SNS広告」サービスページはこちら

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。