Page Top

人事業務の煩雑さや採用難、離職率の高さなど、多くの企業が人事領域で課題を抱える中、注目を集めているのがHRTech(HRテック)です。AIやクラウド技術を活用し、採用から育成、評価まで幅広い人事業務を効率化するソリューションとして急速に市場が拡大しています。
この記事では、HRTechの基本概念から主要サービス、市場動向、導入のポイントまで分かりやすく解説。業務効率化や人材戦略の強化を目指す企業にとって役立つ情報をお届けします。
<この記事で紹介する5つのポイント>
目次

HRTechとは「Human Resources(人事)」と「Technology(技術)」を掛け合わせた言葉で、AIやビッグデータなどの最先端技術を活用して人事業務を効率化・高度化するサービスや技術のことです。採用、育成、評価、勤怠管理など、人事業務全般をカバーするため、企業の人材戦略に欠かせない存在となっています。
HRテックの基本概念は、テクノロジーを活用して人事業務の効率化と戦略的な人材マネジメントを実現することにあります。従来、人の手で行われていた膨大な業務や、勘と経験に頼りがちだった採用・評価・配置などの意思決定をデータとテクノロジーの力で最適化します。
例えば、採用においては応募者データの一元管理や選考プロセスの効率化、人材育成では個々の能力やスキルを可視化し最適な研修を提案、勤怠管理では打刻データをリアルタイムで収集し労務リスクを軽減するなど、人事業務のさまざまな場面でテクノロジーが活用されています。多様化する働き方や複雑化する人事戦略において、HRテックは人事部門の強力な味方となります。
従来の人事システムは「記録」や「管理」に重点を置いたものが多く、主に給与計算や社員情報の一元管理など、定型業務の効率化が目的でした。これに対しHRTechは、データ分析や人工知能を活用した「予測」や「最適化」に重点を置いています。
従来のシステムは社内サーバーにインストールする「オンプレミス型」が主流でしたが、HRTechではクラウド型のSaaSが中心となっています。これにより導入コストが低減され、リモート環境でも利用しやすくなりました。また、使いやすいUIや外部サービスとの連携機能が充実し、より人事戦略の実現に直結するソリューションへと進化しています。
さらに、従来のシステムが人事担当者の業務効率化を主目的としていたのに対し、HRTechは社員自身が活用するセルフサービス型の機能も充実させ、組織全体の生産性向上や社員エンゲージメントの強化にも貢献しています。
HRTechが注目される背景には、少子高齢化による労働人口の減少があります。限られた人材を最大限活用するために、採用・育成・配置を最適化する必要性が高まっています。また、働き方改革の推進により、多様な勤務形態や評価制度に対応した柔軟なシステムが求められています。
デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速も大きな要因です。企業活動のあらゆる分野でデジタル化が進む中、人事部門も例外ではありません。データを活用した客観的な人事戦略の立案や、業務効率化によるコア業務への集中など、DXによる変革が期待されています。
さらに、テクノロジーの進化によりAIやビッグデータを活用したサービスが手頃な価格で利用できるようになったことも普及を後押ししています。クラウドサービスの発達により、中小企業でも高度なHRテックを導入しやすくなっています。

HRテックは人事業務のさまざまな場面で活用されています。カテゴリーごとに特徴的なサービスやソリューションが登場しており、企業はそれぞれの課題に応じて最適なものを選択できます。
採用管理・候補者管理の分野では、応募者情報の一元管理や選考プロセスの効率化を実現するサービスが多数提供されています。採用管理システム(ATS)と呼ばれるこれらのツールは、応募者のデータベース化、面接日程の自動調整、選考状況の可視化などの機能を持ち、採用業務の負担を大幅に軽減します。
AIを活用した書類選考や、動画面接システムなども普及しています。AIによる選考では、過去の採用データから最適な人材像を学習し、応募者の適性を客観的に評価することが可能です。また、データ分析により採用活動のボトルネックを特定し、効果的な採用戦略の立案にも役立てられます。
採用管理・候補者管理のHRテックを導入することで、採用コストの削減や採用の質の向上、採用リードタイムの短縮など、多くの効果が期待できます。採用担当者は定型業務から解放され、候補者とのコミュニケーションや採用戦略の検討など、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。
人材育成・教育研修の分野では、eラーニングプラットフォームやスキル管理システムなどが提供されています。これらのツールは、社員一人ひとりのスキルを可視化し、個々に最適な学習コンテンツを提供することで効果的な人材育成を実現します。
AIによる学習推奨機能を持つシステムも登場しており、社員の現在のスキルレベルや将来のキャリアプランに基づいて、最適な学習内容を提案します。また、学習の進捗状況や理解度を分析し、より効果的な研修プログラムの設計にも活用できます。
動画コンテンツやインタラクティブな教材、ゲーミフィケーション要素を取り入れたコンテンツなど、学習効果を高める工夫も進んでいます。場所や時間を選ばず学習できる環境を整えることで、社員の自発的な成長を促進し、組織全体の競争力向上につながります。
勤怠管理・労務管理の分野では、クラウド型の勤怠管理システムや労務手続きの自動化ツールが普及しています。スマートフォンやPCからの打刻、位置情報を活用したリモートワーク管理、残業アラート機能など、多様な働き方に対応した機能が充実しています。
労務手続きの自動化ツールでは、入退社手続きや年末調整、社会保険手続きなどを電子化し、業務効率を大幅に向上させています。また、各種申請のワークフローを自動化することで、承認プロセスのスピードアップや透明性の確保にも貢献しています。
さらに、勤怠データや労務データの分析機能も充実しており、残業の多い部署の特定や働き方の傾向分析など、労務リスクの早期発見や働き方改革の推進に役立てることができます。勤怠管理・労務管理のHRテックは、コンプライアンス強化と業務効率化の両立を実現します。
評価・報酬管理の分野では、目標管理や評価プロセスのデジタル化、報酬決定の最適化を支援するツールが提供されています。評価プロセスをシステム化することで、評価の透明性や公平性を高め、社員のモチベーション向上につなげることができます。
目標管理システムでは、組織目標と個人目標の連動や、定期的な進捗確認、フィードバックの記録などが可能で、継続的なパフォーマンス管理を実現します。360度評価やピア評価など、多角的な評価方法にも対応しており、より客観的で公正な評価を支援します。
報酬管理の面では、市場データや社内の評価データを分析し、最適な報酬設計を支援するツールも登場しています。社員の能力や成果に応じた報酬体系の構築や、報酬水準の公平性確保など、戦略的な報酬管理を実現します。
エンゲージメント・組織診断の分野では、社員の意識調査や組織の状態分析を行うツールが提供されています。定期的なサーベイによって社員の満足度やエンゲージメントを測定し、組織課題の早期発見や改善策の立案に役立てることができます。
リアルタイムのフィードバック機能を持つツールも普及しており、年に一度の調査ではなく、常に組織の状態を把握することが可能になっています。また、AIによる自然言語処理を活用し、社員の声から潜在的な課題やニーズを抽出する機能も進化しています。
組織診断ツールでは、データ分析によって部署間の連携状況やコミュニケーションの流れを可視化し、組織パフォーマンスの向上に必要な施策を提案します。エンゲージメント・組織診断のHRテックは、組織の「健康状態」を把握し、戦略的な組織開発を支援します。
HRテックの新興分野として、健康管理やウェルビーイング支援のツール、社員間コミュニケーションを活性化するプラットフォーム、オンボーディング(入社後の適応支援)ツールなどが注目されています。特に健康管理分野では、ウェアラブルデバイスと連携したヘルスケアプログラムや、ストレスチェックを自動化するシステムなどが普及しています。
また、メタバースやVR技術を活用した仮想空間での研修や面接、採用イベントなども登場しています。地理的な制約を超えたコミュニケーションや体験型学習を実現することで、新たな可能性が広がっています。
さらに、ダイバーシティ&インクルージョンを促進するためのアナリティクスツールや、社内での副業・兼業マッチングプラットフォームなど、多様な働き方を支援する新しいサービスも増えています。

HRテック市場は国内外で急速に成長しており、企業の人事戦略における重要性が高まっています。テクノロジーの進化と人事課題の多様化を背景に、市場はさらなる拡大が予測されています。
グローバルのHRテック市場は、2023年時点で約300億ドル規模とされています。成長率は年間15〜20%に達し、2030年までに800億ドルを超えると予測されています。特に北米市場が全体の約40%を占め、市場をリードしています。
成長を牽引しているのは、採用管理システムや人材開発プラットフォーム、エンゲージメント測定ツールなどです。特にAIやビッグデータを活用した高度な分析機能を持つサービスへの需要が高まっています。
また、新型コロナウイルスの影響によるリモートワークの普及や、タレントマネジメントの重要性の高まりが市場拡大を加速させています。特に中小企業向けのクラウドベースのサービスが急成長しており、市場のすそ野が広がっています。
日本のHRテック市場は2022年時点で約3,000億円規模とされ、年間20%以上の成長を続けています。特に勤怠管理や労務管理、採用管理の分野での導入が進んでいます。
日本市場の特徴としては、労働法制への対応や、日本特有の雇用慣行に合わせたカスタマイズ性の高さが重視される傾向があります。また、大企業だけでなく中小企業でも導入が進んでおり、クラウドベースの低コストサービスの普及が進んでいます。
一方で課題としては、人事データの活用に関するリテラシーの不足や、既存の業務プロセスとの統合の難しさが挙げられます。また、日本企業特有の年功序列や長期雇用などの雇用慣行との整合性をどう取るかという点も課題となっています。
HRテック市場は今後も拡大が続き、2027年には日本国内で約5,000億円規模に達すると予測されています。この成長を支える要因としては、働き方改革の進展や人手不足の深刻化、経営戦略における人的資本の重要性の高まりなどが挙げられます。
特に注目される分野としては、AIを活用した採用マッチングや、社員のスキル可視化・育成支援、エンゲージメント向上のためのツールなどがあります。また、健康経営やウェルビーイングの観点からのサービスも今後拡大が見込まれています。

HRテックを効果的に導入するためには、単にツールを選んで導入するだけでなく、戦略的なアプローチが必要です。ここでは、導入を成功させるための重要なポイントを解説します。各ステップを丁寧に進めることで、企業の人事課題解決に真に役立つHRテック活用が可能になります。
HRテック導入の第一歩は、導入の目的を明確にすることです。単に「業務効率化」といった漠然とした目標ではなく、「採用コストを20%削減する」「離職率を5%下げる」など、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。
目的を明確にする際は、現状の課題を洗い出し、それらの中でも特に優先度の高いものに焦点を当てます。すべての課題を一度に解決しようとするのではなく、もっとも影響の大きい課題から取り組むことで、導入効果を最大化できます。
また、人事部門だけでなく、経営層や現場の管理職など、さまざまなステークホルダーの意見を取り入れることも重要です。それぞれの立場から見た課題や期待を把握することで、より実効性の高い導入目的を設定できます。
HRテック導入に際しては、自社の人事業務における課題を具体的に洗い出すことが不可欠です。例えば、採用においては「応募者の管理に時間がかかりすぎている」「選考基準が担当者によってバラつきがある」といった具体的な課題を特定します。
課題の洗い出しには、現場の声を直接聞くことが効果的です。人事担当者だけでなく、現場のマネージャーや一般社員からもフィードバックを収集し、多角的な視点から課題を把握します。また、業務プロセスを可視化し、どの工程に無駄や非効率があるかを特定することも有効です。
適切なHRテックシステムを選定するには、複数のサービスを比較検討することが重要です。機能や価格だけでなく、自社の業務フローとの親和性やカスタマイズ性、拡張性なども考慮に入れて総合的に判断しましょう。
比較検討の際は、以下の点を確認することが有効です。まず基本機能が自社の課題解決に適しているか、使いやすいUIであるか、モバイル対応しているかなどの基本要件を確認します。次に、既存システムとの連携が可能か、データ移行は容易か、セキュリティ対策は十分かといった技術面も検証します。
また、導入企業の事例や口コミを調査し、実際の使用感や効果を把握することも大切です。可能であれば、無料トライアルやデモを活用して、実際に操作感を確かめることをおすすめします。導入後のサポート体制や、機能アップデートの頻度なども確認しておくとよいでしょう。
HRテックの導入を成功させるためには、綿密な導入計画の策定が不可欠です。スケジュール、担当者、必要なリソース、リスク対策などを含む包括的な計画を立て、関係者全員で共有します。
導入計画では、まず「いつまでに」「何を」「誰が」「どのように」実施するかを明確にします。特に重要なマイルストーンを設定し、進捗を管理するための指標も決めておきましょう。また、想定されるリスクとその対策も事前に検討しておくことが重要です。
さらに、段階的な導入を検討することもおすすめします。一度にすべての機能を導入するのではなく、優先度の高い機能から順に導入することで、リスクを分散させつつ、早期に効果を実感することができます。導入の各フェーズで振り返りを行い、必要に応じて計画を修正することで、より効果的な導入が可能になります。
HRテックの導入を成功させるためには、経営層や人事部門だけでなく、実際に利用する従業員の協力と理解が不可欠です。導入の目的や期待される効果を丁寧に説明し、従業員の不安や疑問に対応することが重要です。
特に新しいシステムへの移行に際しては、「なぜ今までのやり方を変える必要があるのか」という疑問を持つ従業員も少なくありません。導入によって従業員自身にもたらされるメリットを具体的に示し、変化への抵抗感を和らげることが大切です。
また、社内のキーパーソンを「チェンジエージェント」として活用することも効果的です。各部署や層から影響力のある人物を選び、先行して研修を行い、周囲への普及を促進する役割を担ってもらいます。
HRテックの効果を最大化するためには、既存システムやデータベースとの連携が重要です。人事情報や給与情報、勤怠情報など、さまざまなデータを連携させることで、より包括的な人材管理や分析が可能になります。
データ連携にあたっては、まず自社内にどのようなデータが存在し、どのシステムで管理されているかを把握することが第一歩です。その上で、連携の方法や頻度、責任者などを決定します。API連携が可能か、マスターデータの管理方法はどうするかなど、技術的な側面も検討が必要です。
また、データ連携においてはデータの品質確保も重要な課題です。不正確なデータや重複データが混入すると、分析結果の信頼性が損なわれます。定期的なデータクレンジングや、入力ルールの標準化などを通じて、高品質なデータを維持する体制を構築することが大切です。

HRテックは多くのメリットをもたらす一方で、導入や活用においていくつかの課題も存在します。これらの課題を事前に認識し、適切に対処することで、より効果的なHRテック活用が可能になります。
HRテックの導入には、ライセンス料やカスタマイズ費用、トレーニングコストなど、さまざまな費用が発生します。特に大規模な組織では、全社的な導入に多額の投資が必要になることがあります。また、導入後も保守費用や機能追加のための追加投資が継続的に発生します。
特に初期導入時のカスタマイズや既存システムとの連携において、想定外のコストが発生するケースも少なくありません。また、導入に伴う業務プロセスの見直しや教育にかかる間接的なコストも考慮する必要があります。
HRテック市場には多種多様なサービスが存在し、どのシステムが自社の課題解決に最適かを見極めるのは容易ではありません。機能や価格だけでなく、使いやすさ、拡張性、サポート体制など、さまざまな要素を総合的に評価する必要があります。
また、ベンダーから提供される情報だけでは実際の使用感や効果を判断しきれないケースも多く、導入後のミスマッチが発生するリスクがあります。特に日本企業特有の雇用慣行や業務プロセスに対応できるかどうかは、慎重な検証が必要です。
HRテックでは、従業員の個人情報や人事評価情報など、機密性の高いデータを扱うため、情報セキュリティの確保が重要な課題となります。特にクラウドサービスの場合、データが外部のサーバーに保存されるため、情報漏えいや不正アクセスのリスクが懸念されます。
また、従業員による不適切なデータアクセスや、アクセス権限の管理ミスによる内部からの情報漏えいリスクも存在します。さらに、個人情報保護法や各国のデータ保護規制への対応も必要です。
長年使い慣れた方法がある場合や、テクノロジーへの苦手意識がある従業員は、変化に対して不安や抵抗を感じる傾向があります。HRテックによるデータ収集や分析に対して、「監視されている」という懸念や、評価の客観性・公平性への疑問を持つケースもあります。テクノロジーによる意思決定への依存度が高まることで、「人間的な要素が軽視される」という不満が生じることもあります。
従業員の抵抗感に対応するためには、導入の目的や期待される効果を丁寧に説明し、従業員自身にもたらされるメリットを具体的に示すことが重要です。また、導入前の十分な研修や、移行期間中のサポート体制の充実を図ることで、不安感を軽減することができます。
HRテックを導入する際の技術的な課題として、既存システムとの連携の難しさがあります。特に古いシステムや独自開発のシステムとの連携は、技術的な互換性の問題や、APIの不足などにより困難な場合があります。
また、複数のHRテックサービスを併用する場合、それぞれのシステム間でのデータ連携や整合性の確保も課題となります。データ形式の違いや、リアルタイム連携の難しさなどにより、データの二重管理や手動での転記が必要になるケースもあります。

HRテック導入で直面する課題には効果的な解決策があります。コスト、セキュリティ、従業員の抵抗感などの課題を適切に対処することで、HRテックの価値を最大化できます。
HRテックの導入コストを抑えるには、段階的な導入アプローチが効果的です。最初から全機能を導入するのではなく、優先度の高い機能から始め、効果を確認しながら徐々に拡張していきます。また、無料トライアル期間を活用して実際の効果を検証し、投資対効果を見極めることも重要です。
クラウド型のサブスクリプションモデルを選ぶことで、初期投資を抑えつつ、必要に応じて機能やユーザー数を調整できます。さらに、導入の目的や期待される効果を明確にし、KPIを設定することで、投資の妥当性を継続的に評価することが可能になります。
セキュリティリスクに対しては、まずベンダーのセキュリティ対策を徹底的に評価します。ISO27001などの情報セキュリティ認証を取得しているか、定期的な第三者監査を実施しているかなどを確認します。また、データの暗号化やバックアップ体制、アクセス制御の仕組みも重要なチェックポイントです。
社内でも適切なアクセス権限管理を実施し、必要最小限の権限付与を原則とします。定期的なセキュリティ研修や、インシデント対応計画の策定など、技術面だけでなく運用面での対策も重要です。個人情報保護方針を明確にし、従業員に対して透明性を確保することで信頼性を高めます。
HRテックの導入は「ビッグバン型」ではなく、段階的なアプローチが推奨されます。まずは特定の部署や機能から試験的に導入し、効果や課題を検証します。成功事例を作った上で、他部署や機能へと展開していくことで、リスクを分散しつつ効果的な導入が可能になります。
段階的な拡張においては、短期・中期・長期の導入ロードマップを作成し、各段階での目標や評価基準を明確にすることが重要です。また、各段階での振り返りを行い、得られた教訓を次の段階に生かすことで、より効果的な導入が実現できます。
特定のベンダーに過度に依存すると、将来的なシステム変更や機能拡張が制限される可能性があります。これを避けるためには、標準的なデータ形式やAPIを持つシステムを選択し、データの可搬性を確保することが重要です。
また、システムの運用や基本的なカスタマイズは社内で対応できるよう、内部人材のスキル育成も並行して進めることが望ましいです。ベンダーとの契約においては、サポート内容やSLA(サービスレベル契約)を明確にし、将来的なデータ移行についても事前に条件を確認しておくことが重要です。
新システム導入の成否を左右する重要な要素が、従業員へのトレーニングです。単なる操作方法の説明だけでなく、導入の目的や期待される効果、従業員自身にとってのメリットを丁寧に説明することが重要です。
また、さまざまな学習スタイルに対応するため、集合研修、オンライン学習、マニュアルなど、複数の学習リソースを用意することも効果的です。導入後も継続的なサポート体制を整え、質問や問題に迅速に対応できる環境を整えることで、スムーズな移行と定着を促進できます。
HRテックを運用する上で、労働法や個人情報保護法などの法規制対応は不可欠です。特に、労働基準法の改正や個人情報保護法の強化など、法規制は随時変更されるため、常に最新の情報を把握し、システムを適切に更新することが必要です。
ベンダーとの契約時には、法改正への対応方針や更新頻度を確認し、必要に応じて契約内容に含めておくことも有効です。また、社内にも法規制対応の責任者を設け、継続的なモニタリングと評価を行うことが重要です。
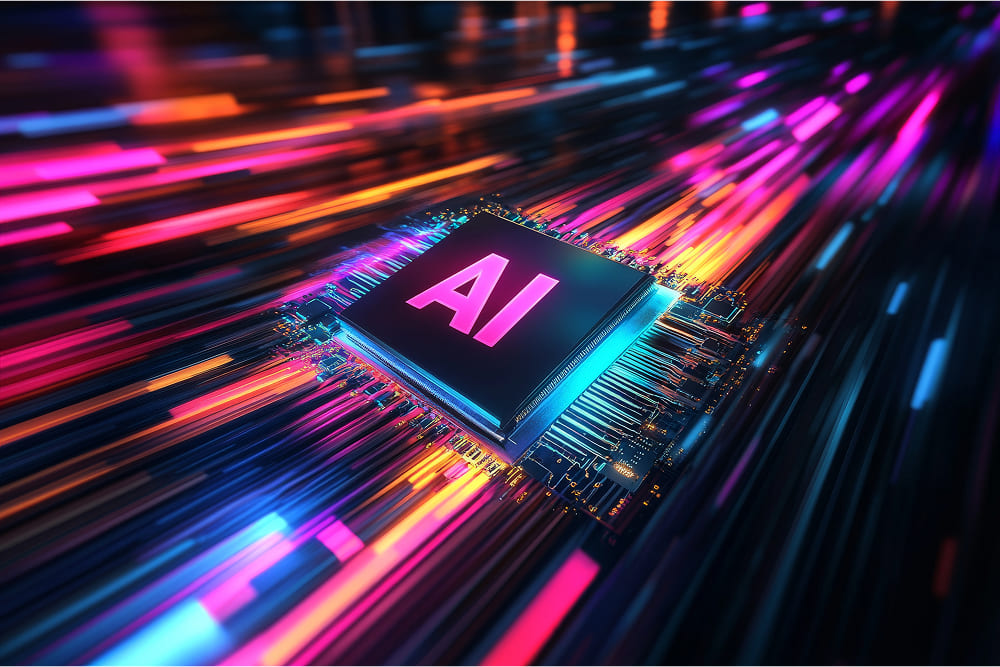
HRテック領域では常に新しいテクノロジーが導入され、人事業務の可能性を広げています。AIから仮想現実まで、さまざまな技術革新が人事業務に変革をもたらしています。ここでは、注目すべき最新テクノロジーとその活用方法について紹介します。
人事領域でAI・機械学習は急速に普及しています。採用選考では、応募者の履歴書や適性検査結果を分析し、最適な候補者を予測するAIが活用されています。また、社内の人材配置においても、個人のスキルや適性から最適なポジションを提案するAIが導入されています。
自然言語処理技術の進化により、面接の文字起こしと分析、従業員の声の感情分析なども可能になっています。さらに、チャットボットによる人事問い合わせ対応や、パーソナライズされた学習コンテンツの提案なども実用化されています。
人事データの分析技術「ピープルアナリティクス」は、採用から退職までの従業員データを分析し、人事戦略の意思決定を支援します。例えば、高業績者の特性分析から採用基準の最適化、離職リスクの予測と防止策の立案などが可能です。
また、組織のネットワーク分析により、情報の流れや協力関係を可視化し、組織の効率性や革新性を高める施策を導出することもできます。さらに、多様性指標の分析から、より包括的な職場環境づくりのための施策立案も進んでいます。
メタバースやVR技術を活用したバーチャル空間での採用イベントや研修が注目されています。地理的制約を越えて多くの候補者と接点を持てる採用イベントや、リアルな体験を提供できる没入型研修などが実用化されています。
また、海外拠点や在宅勤務者との仮想オフィス空間でのコミュニケーションも可能になり、物理的距離を越えるチーム形成や文化醸成をサポートしています。危険を伴う作業のシミュレーションなど、従来は難しかった実践的なトレーニングもVR技術で安全に実施できるようになっています。
グローバルな人材管理を支援するHRテックも進化しています。多言語対応の人事システムや、国ごとの法規制に対応した給与・労務管理ツールなどが普及し、グローバル企業の人事業務を効率化しています。
また、異文化理解を促進するための研修ツールや、グローバルタレントの発掘・育成を支援するプラットフォームも登場しています。時差のある拠点間での業務連携を支援するツールなど、グローバルな働き方を実現するためのソリューションも充実してきています。

HRテックは多くの企業で実際に活用され、人事業務の効率化や戦略的な人材マネジメントに貢献しています。ここでは、さまざまな分野におけるHRテック活用の事例を紹介します。
ソフトバンク株式会社では、新卒採用のエントリーシート選考にAIを導入しています。IBMのAI「Watson」を活用し、過去のエントリーシート1,500件を学習させることで、選考プロセスの効率化と公平性の向上を実現しました。この取り組みにより、エントリーシートの処理時間を75%削減しています。
参照:https://hrnote.jp/contents/b-contens-composition-softbankdouga-180903/
阪急阪神百貨店では、デジタル採用プラットフォーム「HireVue」を導入し、自己PR動画を活用した選考を行っています。AIが応募者の「言葉・表情・声色」から社会人基礎力を評価し、公平な選考を実現しています。
参照:https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sp/contents/column/20210528a.html
株式会社ウィルは、離職リスク可視化ツール「HR OnBoard」を活用し、入社後の定着率向上に取り組んでいます。このツールにより、入社後のフォローアップを強化し、早期離職の防止に成功しています。
参照:https://saiyo.employment.en-japan.com/blog/hr-tech
株式会社IT Worldでは、適性検査ツール「Talent Analytics」を導入し、採用のミスマッチを防止しています。このツールにより、応募者の適性を科学的に分析し、最適な人材の採用に成功しています。
参照:https://saiyo.employment.en-japan.com/blog/hr-tech
サッポロホールディングス株式会社は、新卒採用のエントリーシート選考にAIを活用しています。AIの導入により、選考にかかる時間を40%削減し、効率的な人材データベースの構築と運用を実現しています。
参照:https://vollect.net/hrpedia/recruitment-ai/
HRTechは人事業務の効率化だけでなく、戦略的な人材マネジメントを実現する強力なツールです。AIやビッグデータ分析などの最先端技術を活用することで、従来の人事業務の枠を超えた新たな価値創出が可能になりました。
HRTech導入においては、目的の明確化から始まり、システム選定、従業員の巻き込み、データ連携まで、計画的なアプローチが重要です。また、コストやセキュリティなどの課題にも適切に対処することで、より効果的な活用が実現します。
人材採用の悩みを抱える企業には、DYMのIndeed運用代行サービスがおすすめです。Indeed広告の運用に特化したプロフェッショナルチームが、広告設計から掲載後の改善まで一貫して支援します。採用効率の改善と採用コストの最適化を実現し、自社で運用する場合と比較して応募数が平均3倍以上に増加するなどの実績があります。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。