Page Top

就活の自己分析で重要な役割を果たすモチベーショングラフ。自分の人生を振り返り、モチベーションの変化をグラフで可視化することで、価値観や強み・弱みを明確にできる効果的なツールです。
本記事では、6つのステップによる具体的な作成方法から、自己PRや志望動機、面接対策への活用術、さらに作成時の注意点まで詳しく解説します。モチベーショングラフを活用して自己理解を深め、説得力のある就活を実現しましょう。
<この記事で紹介する3つのポイント>

モチベーショングラフとは、自分の人生を振り返り、「いつ、どんなときにやりがいを感じたか」「充実していたか」あるいは「どんなときにやる気をなくしたのか」「気持ちが落ち込んだか」というモチベーションの変化に焦点を当てて、過去の経験を整理していく自己分析の手法です。
一般的には、横軸に時間の流れ、縦軸にモチベーションのプラス・マイナスを設定し、モチベーションの波をグラフのように書き込んで作成していきます。自分がどんなときにやりがいや楽しさを感じてモチベーションが上がるのか、逆にどんなことがあると落ち込んでモチベーションが下がるのかを、わかりやすく可視化することができます。
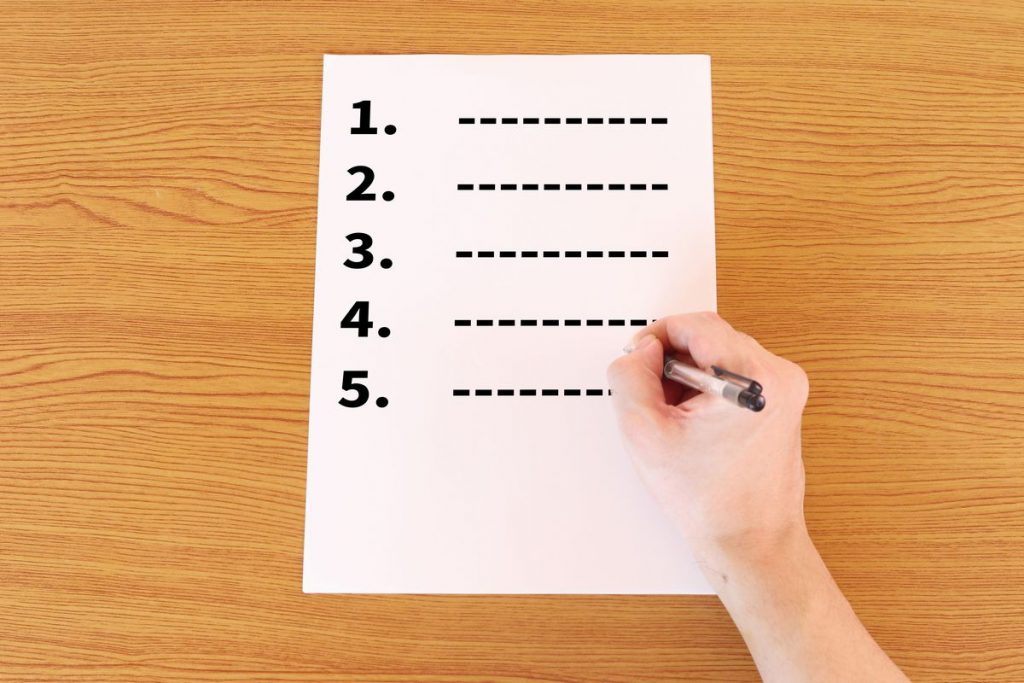
モチベーショングラフの作成は、6つのステップで進めていきます。各ステップを順番に実践することで、効果的な自己分析ツールとして活用できるグラフが完成します。
まず、モチベーショングラフの基本となる枠組みを作成します。左端に縦線を1本引いて、そこに「モチベーションの上下」を設定し、中央に横線を1本引いて「小学校から現在(大学・短大・専門学校)の時間の流れ」をそれぞれ設定します。
縦軸のモチベーションの高さは、上に100%、下にマイナス100%まで設定することで、波が大きくとらえられるため見やすくなります。Excelなどの表計算ソフトで作成しておくと、後から必要な書き込みを付け足していくことができて便利です。小学校入学以前の出来事からグラフ化したい人は、横軸を「幼少期」から始めても良いでしょう。
次に、横軸の時間軸を記入していきます。あまり細かく書くと思い出しにくい場合もあるため、幼少期・小学生・中学生・高校生・大学生とざっくりと時期を分けておくと良いでしょう。年齢ではモチベーションに関連する出来事が浮かびにくい場合は、このような区切りを設けると思い浮かべやすくなります。
また、部活動入部や留学など、自分にとって環境や人間関係が大きく変わったと感じる期間があれば、そういった独自の期間を設定しても良いでしょう。モチベーショングラフの書き方に絶対の正解はないため、適宜自分なりのアレンジを加えて作成していくことがポイントです。
これまでの出来事や経験を振り返りながら、横軸の時間の流れに沿って、モチベーションのアップダウンを点で表していきます。書くときは難しく考えすぎず、直感的に記入していく方が的確なアウトプットになるでしょう。
記入する出来事は「1番になった」「賞を取って評価された」など、必ずしも結果を伴うものである必要はありません。見た目は華々しいイベントであっても、自分にとって大切なものであるかどうかは、また別のことだからです。「ゲームの攻略法を考えることに熱中した」「友達の小さな心遣いがうれしかった」など、日常のささいな出来事の中にこそ、自身のモチベーションに大きく影響した象徴的な何かが見つかるかもしれません。
点が打てたら、次にそれぞれをつないで曲線にしていきましょう。この曲線があなたのモチベーションの軌跡となります。グラフで確認することで、当時の出来事やモチベーションの揺れ動きを客観視することができます。
時期ごとにモチベーションの高低があった部分に点を置き、線でつないでいきます。出来事が起きた年はいつかといった正確さにこだわるよりは、出来事によってモチベーションがどう変化したのかが大切です。記憶のままに、まず書いてみると良いでしょう。違っていれば、後から修正できます。この一連の流れを把握しておくことで、面接でも自分の行動や選択に対して一貫性のある説明ができるようになります。
モチベーショングラフを作成するときの最も重要な作業が、この深掘りです。モチベーションが高かったとき、低かったときについて「なぜ高く(低く)なったのか?」「そのとき自分は何を感じていたのか?」を考えて、書き出してみましょう。
「なぜ?」を3回以上繰り返して考えてみることがおすすめです。例えば、「高校のサッカー部で県大会ベスト4に入ったとき」にモチベーションが高かった場合、「なぜ?」→「チーム一丸となって高い目標を達成できたから」→「なぜ?」→「個々の強みを活かし、苦手な部分を補い合うチームだったから」→「なぜ?」→「自分が司令塔として、メンバーの意見を聞きながら戦略を立てる役割にやりがいを感じていたから」というように、表面的だった考えがさらに深掘りされ、自分の根底にある考え方が見えてきます。
最後に、モチベーションが上がっているときの共通点と、下がっているときの共通点を見つけます。これにより、自分の価値観や力を発揮できる環境、苦手としていることなどを理解することが可能です。
モチベーションが高いときの共通点からは、自分の強みを導き出すことができます。例えば、「努力が認められたとき」「目標を達成できたとき」が共通していれば、コツコツと目的に向けて努力する忍耐力や継続力という強みが見えてきます。一方、モチベーションが低いときの共通点からは、弱みを把握できるでしょう。山と谷ごとの共通点がわからないときは、家族や友人、キャリアアドバイザーなどに相談すると、良いアドバイスをもらえるかもしれません。
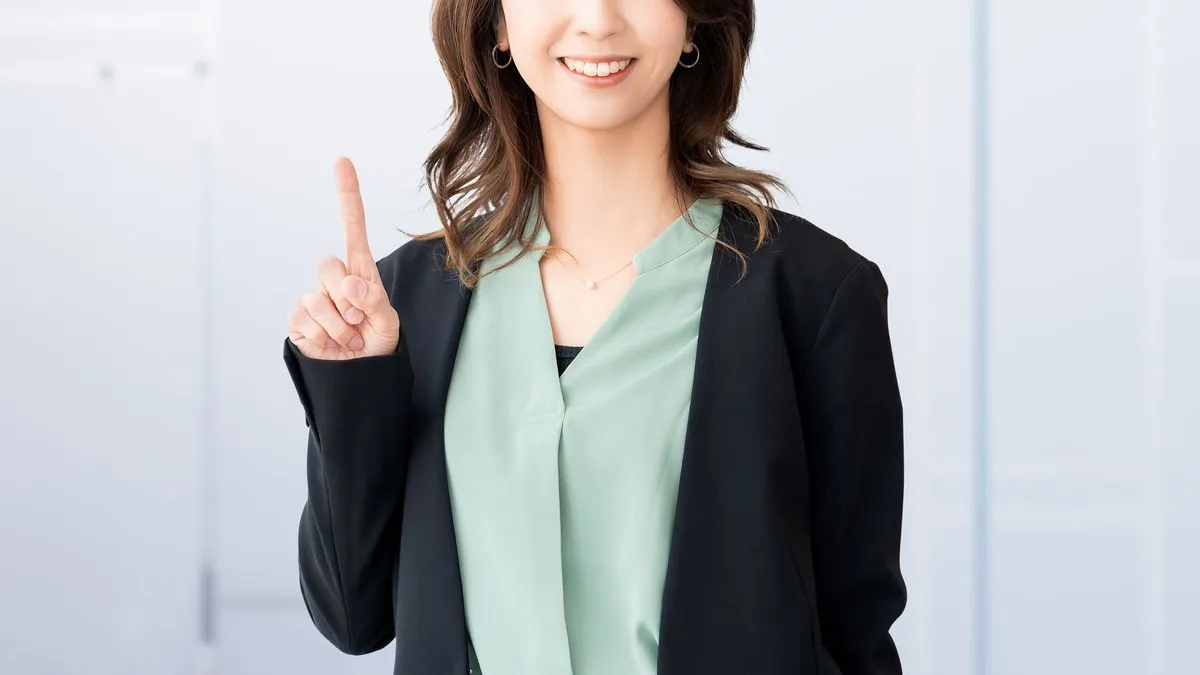
モチベーショングラフを作成することで、自分自身をより深く理解できるようになります。これまで記憶の奥にしまい込んでいた出来事を思い出して、「このことが自分にとって重要だったのか」と意外に感じるケースもあるでしょう。
モチベーショングラフの最大のメリットは、自分のモチベーションが上がる源泉を把握できることです。グラフの作成により、自分のモチベーションが上がる、もしくは下がるタイミングが分かり、どのような価値観や信念に基づいて考え、行動していたのかを把握できるためです。
無意識に選んでいたことも、実は特定の価値観や信念、こだわりに基づいていたことに気づきます。自分の価値観を知ることで、就活での自己PRや志望動機に一貫性を出せるのもメリットです。グラフ作成における、これまで継続して取り組んできたこと、力を発揮したことも分かります。これらの具体的な出来事は自分の強みにひも付けできるエピソードとして、アピールの材料になるでしょう。
モチベーショングラフの活用により、就活の軸が明らかになります。就活の軸とは、仕事や企業を選ぶ上で「これだけは譲れない」という条件のことです。さまざまな業界・企業の中から自分に合う企業を選ぶのは容易ではありませんが、就活の軸として「絶対に譲れない基準・条件」を持っていれば、選ぶ企業はおのずと絞り込まれます。
例えば、グラフの作成によって「新しいことにチャレンジしたときにモチベーションが高まる」ということが分かれば、就活の軸のひとつとして「新しいことにチャレンジできる環境」という軸が決まります。応募先企業には、海外進出や新規事業の拡大を続けている企業などが候補になるでしょう。就活の軸が定まれば、「なんとなく選んでしまった企業」に入社してミスマッチが起こるという失敗もなくなります。
モチベーショングラフの作成では自分の強みがわかるため、説得力のある自己PR・志望動機を作成できることがメリットです。モチベーショングラフの山となっている部分がモチベーションの高くなった出来事であり、自分の強み・長所としてアピールできます。
人生の中でモチベーションが高まった時点の出来事を掘り下げ、どのような強みなのかを分析しましょう。アピールできるエピソードが複数あれば、それが自己PR・志望動機の強い根拠づけとなり、より説得力が高まります。グラフで思い出した具体的なエピソードを交えて伝えることで、納得性の高い内容となるでしょう。
モチベーショングラフの作成では、ただ過去の振り返りをするだけでなく、将来像をイメージすることが大切です。分析の結果、分かった自分の強みや弱みに基づき、将来はどのようになりたいかをイメージできます。
将来像のイメージが具体的であれば、企業選びがよりスムーズになるでしょう。将来像は、「志望する会社に入社すること」ではなく、その後の活躍する姿をイメージするようにしてください。どのようなキャリアを歩むのかを考えることで、より自分に合う企業選びができます。
グラフで浮き彫りになった価値観はあなたが人生で大切にしてきた芯となる部分であり、これを軸として設定することで、企業選びや自己PRに一貫性が生まれます。
企業研究が深まるにつれ、企業の規模や仕事内容、給与、評価制度、福利厚生など比較検討する条件が増えていき、自分の中でも優先順位が付けにくくなることがよくあります。さらに就活が進んで、複数の企業に内定したときに、どこに行くべきかの決断がつかずに悩んでしまう人も少なくありません。
そんなときは、あらためてモチベーショングラフを見返し、過去の楽しかった出来事や、やりがいを感じた経験を振り返ってみることをおすすめします。「自分にはどんな環境が合っているのか」「頑張れるのはどんなときか」「仕事で何を得たいのか」を再確認し、企業選びの判断基準のひとつに加えることで、自分にとってより良い選択ができることでしょう。作成したモチベーショングラフは、自己分析に活用した後もすぐに確認できる場所に置いておくことがおすすめです。

モチベーショングラフで得た自分の価値観や成長の軌跡は、就活のさまざまな場面で活用できます。自己分析を深めて終わりではなく、実際の選考プロセスで効果的に活用することで、就活を有利に進めることができます。
モチベーショングラフは、エントリーシート(ES)などでよく求められる「自己PR」を作る際に活用できます。自己PRでは、自分の強みとそれを裏付けるためのエピソードを伝える必要があります。そこでモチベーショングラフの「山」に着目し、出来事の詳細を深く掘り下げてみてください。
モチベーションが高い状態で動いた時期は自分の強みが発揮できていたというケースが多く、具体的なエピソードを考える際にも、すでにモチベーショングラフに当時の状況や感情が書き込まれている可能性が高いでしょう。このようにして見つけた強みを自己PRに入れ込むことで、説得力のある自己PRを作ることができます。
グラフで見つけた強みについて、具体的な事例とともに説明することで、面接官に納得してもらえる内容になります。
複数企業のESの準備を並行して進めていると、「その企業ならではの志望動機がない」「どこでも同じような内容になってしまう」と頭を悩ませるケースは少なくありません。そのような場合は、モチベーショングラフを作成するときに深掘りしたエピソードを活用して、志望動機を考えてみましょう。
まず「自分はこんな環境なら頑張れた」「こんな人と一緒のときは充実していた」という経験と、応募企業のビジョンや仕事の特徴との間に接点を探してみましょう。それを見つけることで、「私は○○という環境の中でとてもモチベーション高く頑張れたことがありました(エピソード)。それは貴社の○○という部分と通じており…」と自分と企業を接続することができます。具体的なエピソードを交えた、その企業ならではの志望動機をまとめることができるでしょう。
モチベーショングラフを作ることは面接対策にもなります。多くの場合面接は一問一答で進んでいくわけではなく、一つの回答に対してさらに深掘りしていく形で進行します。面接官は深掘り質問をおこなうことで、学生の価値観や背景、考え方などを見極めようとしているのです。
面接前にモチベーショングラフを作成し「なぜそのような行動をしたのか」「なぜそのように考えたのか」といった背景や理由を整理していれば、自ずと面接のときでも説明できる状態になっているはずです。
特に面接では、過去のエピソードについて「どうしてそう思ったのか」「どうしてそのような行動をとったのか」など掘り下げた質問をされることが多く、モチベーショングラフで感情・思考を振り返る作業がその対策になります。
就活では避けて通れない「ガクチカ」を考える際にも、モチベーショングラフは大いに役立ちます。ガクチカは多くの場合、主体性を持って行動したこと、そこで経験した困難、それをどのように乗り越えていったか、という流れで説明します。
こういったエピソードを一から考えるとなるとなかなか思いつかないものですが、モチベーショングラフの「谷」と「山」の部分に着目してみましょう。多くの場合、大きく落ち込んだ「谷」の部分が「直面した困難」、そこから回復していく「山」の部分が「困難を乗り越えたプロセス」になっています。グラフの起伏が激しい部分を切り出すだけで、説得力のあるガクチカを作ることができるのです。
ガクチカは「なぜそのように行動したのか」など行動の背景まで問われる場合が多いため、当日の対策としても効果的でしょう。
明確にした価値観を就活の「軸」とすることで、企業研究と自己分析を効果的につなげることができます。モチベーショングラフによって自分の価値観やモチベーションの傾向が明確になり、就活における「軸」をしっかりと定めることが可能です。
例えば、部活動や委員会など新しいことに挑戦した時にモチベーションが上がっていれば、あなたはチャレンジ精神が旺盛であると言えます。就活においても「新事業に果敢に挑戦している企業」を一つの軸とすると良いでしょう。グラフで浮き彫りになった価値観はあなたが人生で大切にしてきた芯となる部分です。これを就活の軸として設定することで、企業選びや自己PRに一貫性が生まれ、自分にマッチした企業を見つけやすくなり、納得のいく就活を送ることができるでしょう。

モチベーショングラフを効果的に活用するためには、作成時にいくつかの注意点を意識することが重要です。ただ作成するだけでは十分な効果を得られないため、以下のポイントを押さえて取り組みましょう。
モチベーショングラフはただ書くだけで終わりにするのでなく、可視化した心のアップダウンそれぞれについて、「なぜ?」「どうして?」と深掘りすることが大切です。感情を振り返るとき、「楽しかった」「落ち込んだ」といった感情しか出てこないことがあるかもしれません。
そのようなときは、出来事の5W1Hを掘り下げてみることをおすすめします。「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように」について考えていくと、より細かく具体的な感情を見つけられるでしょう。それにより、大切にしている価値観やこだわり、物事に向き合うときのスタンスなど、自分自身の特徴にあらためて気づくことができます。理由を深掘りして考えておくと、面接での受け答えも説得力のあるものになっていくでしょう。
重要なのはモチベーショングラフを完璧に書き上げることではありません。過去を思い出しながら出来事を整理し、その工程で自己理解を深めることこそが重要なのです。そのため、最初から完璧に作ろうとせず、ざっくりでも良いのでまず完成させることを意識して取り組むようにしましょう。
完璧主義の人は、一つもミスなくモチベーショングラフを書き上げたいと思ってしまい、細部にこだわりすぎてなかなか先に進めなくなってしまいがちです。また、綺麗に作ることに意識が集中するあまり「作ることそのもの」が目的となってしまう場合もあるでしょう。完成させた後にふと思い出すこともあるはずですから、必要に応じて後から調整できるように余白は十分とっておきましょう。
作成したモチベーショングラフは、自分だけで分析するのではなく、周りの人に見てもらうことをおすすめします。第三者に見てもらえば、より客観的な視点で分析できるためです。自分だけの分析では主観が入り、思い込みによって分析が偏る可能性があります。
第三者が見ることで、自分では気づけなかった強み・弱みが見つかるかもしれません。面接では、「周りの人からはどんな人だと言われますか?」という質問をされることもあります。第三者の意見を聞いておけば、スムーズに回答できるでしょう。
また、ほかの人のグラフと見比べてみるのもおすすめです。モチベーションが上がる瞬間は人それぞれで、自分にとっての当たり前は相手にとって当たり前ではないということに気づくことができれば、強みの再発見にもつながるかもしれません。
多くの学生は、幼少期または大学生時代のどちらかを起点として振り返りを始めます。ここで気を付けるポイントは時間配分です。幼少期の出来事を考えすぎるあまり項目が多くなって、大学時代に行きつくまでに集中力が途切れてしまっては本末転倒でしょう。
年齢や学年で区切りをつけて、ある程度の項目をピックアップできたら、いったん次の時代に進むようにしましょう。最初から緻密なグラフを作成するのではなく、まずは自分自身のことをざっくりと振り返る気持ちで取り組むようにしてください。特定の時期にこだわらずバランスを大切にすることで、全体を通して一貫した自己理解を深めることができます。
モチベーショングラフは、過去のモチベーションの変化を可視化することで自己理解を深める効果的な自己分析ツールです。6つのステップで作成し、自分のモチベーションの源泉や価値観を明確にできます。就活では自己PRや志望動機の作成、面接対策に活用でき、説得力のあるアピールが可能になります。
作成時は感情の深掘りや第三者の視点を取り入れることが重要です。時間配分に注意し、分析まで丁寧に行うことで、就活における強力な武器となるでしょう。
新卒採用でお困りの企業様は、優秀な人材との出会いをサポートするDYMの新卒採用サービスをご検討ください。学生一人ひとりの価値観や強みを理解した効果的な採用活動を実現できます。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。