Page Top
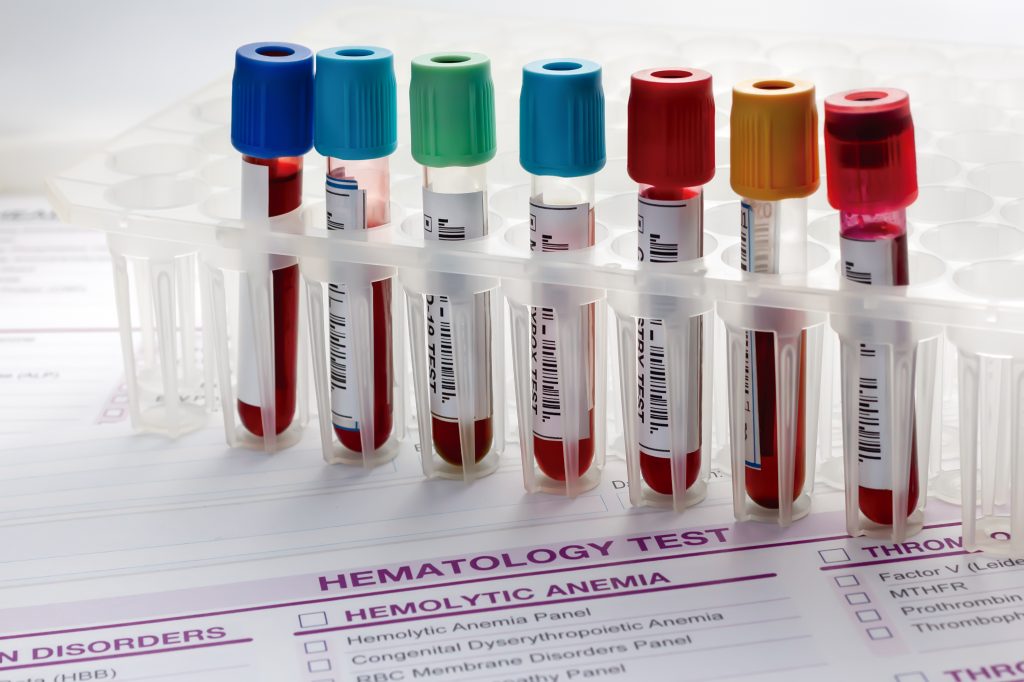
厚生労働省が定めているがん検診の指針(がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針)では、腫瘍マーカー検査を健康診断で行うことについては触れられていません。しかし近年は、オプション検査として健康診断に腫瘍マーカー検査を取り入れる自治体や健診機関が増えています。
健康診断を受ける際には腫瘍マーカー検査も受けた方が良いのでしょうか。腫瘍マーカー検査結果の正しい解釈についても解説します。
<この記事で紹介する3つのポイント>
目次
腫瘍マーカー検査は、血液や尿などを採取して検体中の腫瘍マーカーの値を調べる検査です。
腫瘍マーカーとは、がん細胞やがん細胞の影響を受けた細胞が出す特殊なたんぱく質などの物質を指します。何らかの腫瘍がある目印(マーク)になるため「腫瘍マーカー」と呼ばれます。
腫瘍マーカー検査の目的や方法、費用などについて説明します。
健康診断において腫瘍マーカー検査は、がんの早期発見が可能なため、がん検診の補助的な役割を果たします。
本来、腫瘍マーカー検査の多くは、健康診断の目的ではなく、がんの進行のスピードや再発・転移のリスク評価などの目安として使うために開発されてきました。
これに対して健康診断での腫瘍マーカー検査は、がんが疑われる人をふるい分ける「スクリーニング」のために行われます。がんそのものを確認するのではなく、腫瘍マーカーという関連物質の量でがんが疑われるかどうかを判断しているのです。
ただし、腫瘍マーカーを作らないがんもあるため、腫瘍マーカー検査ですべてのがんを発見できるわけではありません。
腫瘍マーカー検査は血液や尿などを採取して行います。健康診断であれば、通常の採血や採尿の際にまとめて検体を採取することも可能です。
採取した検体は専門の装置で分析・測定し、場合によっては試薬などを加えて反応を見ます。これらの結果から、腫瘍マーカーの判定がなされるという流れです。なお、一定の期間が必要な検査もあり、結果が手元に届くまでに1週間以上かかる場合もあります。
健診機関や医療機関によって異なりますが、腫瘍マーカー検査1項目につき2,000円から5,000円の費用がかかります。
ただし、腫瘍マーカー検査にはいろいろな種類があり、必要に応じて複数の腫瘍マーカー検査を組み合わせて使う場合も少なくありません。実際に、6種類の腫瘍マーカー検査の費用では、10,000円から15,000円ほどの料金帯が多く見られます。
健康診断で「要精密検査」の結果が出たら速やかに指定の医療機関を受診しましょう。腫瘍マーカー検査の検査結果には、検査した腫瘍マーカーの値と基準値、精密検査の要否が記載されますが、腫瘍マーカー検査だけでがんの確定診断をすることはありません。
要精密検査の記載がある結果が届いて、「がんかもしれない」と考えると不安や恐怖が強くなり、受診をおっくうに感じるかもしれませんが、本当にがんであれば放っておくとどんどん進行してしまいます。
がんではなかったとしても「がんかもしれない」と悩むことがストレスとなり他の病気を引き起こす可能性も否定できません。腫瘍マーカー検査に限らず、健康診断で要精密検査の結果が出たら早めの受診が大切です。
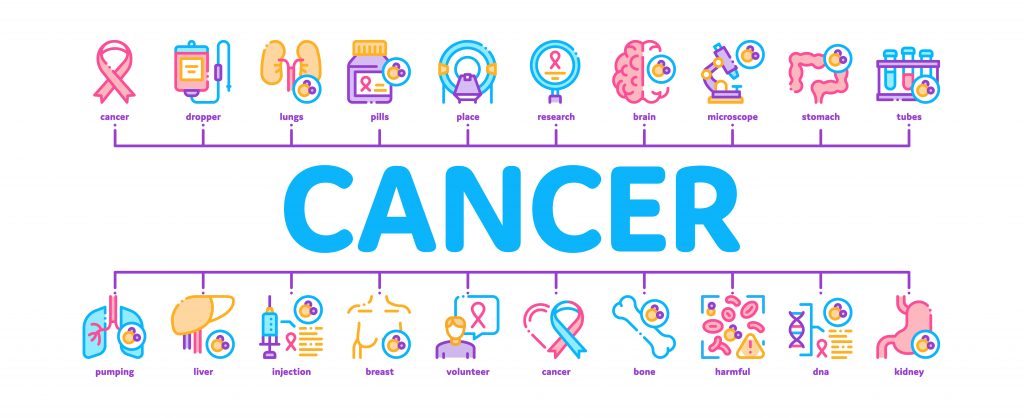
現在数多くの腫瘍マーカーが発見されていますが、実際に腫瘍マーカー検査として使われているのは50種類程度です。その中から、健康診断にも活用されている主要な腫瘍マーカーをご紹介します。
医療機関の腫瘍マーカー検査に含まれるのは、主に次の7つです。
男性のみを対象とした腫瘍マーカーでは、前立腺特異抗原(PSA)が挙げられます。PSAは、がんによって前立腺組織が壊れると血液中に放出される物質です。そのため、PSA腫瘍マーカーは、前立腺がんの早期発見に役立ちます。
PSAの基準値は年代によって異なり、年を重ねるごとに緩くなります。
PSAは日本泌尿器科学会が『前立腺がん検診ガイドライン2018年版』で「50歳以上を住民検診における対象年齢とすべきである」とするなど、腫瘍マーカー検査のなかでも基本的な健康診断の項目として定着しています。
人間ドックなどの任意型検診では40歳代からPSA基礎値の測定を推奨しており、市区町村などが行う住民向けの健康診断にも取り入れる自治体が増えています。
女性のみを対象とした腫瘍マーカーは次の2種類です。
高値になると卵巣がんの陽性率が高くなりますが、子宮内膜症や妊娠・月経などによっても影響を受ける値です。前述のCEA(がん胎児性抗原)も高値になりますので、組み合わせて判断することもあります。

健康診断でがんの検査を受ける動機として、一般的には「異常がない事を確認して安心したい」という思いと、「がんを早期発見して早期治療につなげたい」という理由が挙げられます。腫瘍マーカー検査でがんの早期発見はできるのでしょうか。
国が推奨するがん検診(厚生労働省のがん検診の指針)には、腫瘍マーカー検査に関する記載がありません。腫瘍マーカー検査の値はがんがあっても上がらない場合がありますし、がんがなくても上がってしまう場合もあります。
腫瘍マーカー検査は体内にがん細胞が発生したり、がん細胞が増えていたりする際に出る物質を調べる間接的な検査ですので、腫瘍マーカーだけで正確な判断をすることは不可能なのです。そのため、健康診断では基本項目には含まれておらず、オプションで腫瘍マーカーを選択する仕組みになっています。
ただし、PSA(前立腺特異抗原)のように、前立腺がん早期発見の有効性が認められている腫瘍マーカーもあるため、PSAにおいては健康診断に取り入れることが定着しつつあるのが現状です。
前立腺がん発見のための腫瘍マーカー検査、PSAはがん検診としての有用性が認められていますが、それ以外の腫瘍マーカー検査はがんの早期発見に限ると一般的ながん検診ほどの精度はありません。
がんの早期発見のためには、腫瘍マーカー検査と次に挙げる厚生労働省が定めた基本的ながん検診を併用することが肝心です。
腫瘍マーカー検査を複数組み合わせることでスクリーニングの精度は多少あがりますが、あくまで間接的な検査です。腫瘍マーカー検査を過信せず、一般のがん検診と組み合わせて受けましょう。
厚生労働省が定めた基本的ながん検診の他に、次のような検査もがんの早期発見のための健康診断で用いられます。
コンピュータ断層撮影(CT)検査は、X線を利用してデータを取得し、体を輪切りにするような断層画像を構成する検査です。骨や肺の内部などを観察するのに向いており、食道がん、胃がん大腸がんなどといった消化器系のがんの精密検査で用いられます。
検査によっては、体の状態を詳細に確認するために「造影剤」を使う場合もあります。造影剤としては消化器をよく見るために使うバリウムがよく知られていますが、カテーテルで直接血管に流し込むヨウ素もCT検査の造影剤です。特に血管造影剤はアレルギー反応を起こす場合があるため、慎重に使用されます。
CT検査では、トンネル状の専用ベッドに横たわった人の体に、輪状の機器がいろいろな角度と位置でX線を照射して、さまざまなデータを取得します。取得したデータはコンピュータで体を輪切りにしたような2次元の画像に再構成され、骨や血管、細胞組織、内臓など体内の詳細な構造が分かる画像ができ上ります。CT検査は同じX線を用いたレントゲン検査に比べると、情報量が段違いに多いのがメリットです。
CT検査はがんなどの病気の診断に大変役立ちますが、X線照射による被ばく量も多く、特に妊娠の可能性がある人には利用できません。費用は、保険適用(3割負担)の場合で7,000円ほど、保険非適用の場合は10,000円以上が目安です。

磁気共鳴画像法(MRI)検査では、強力な磁場と電波を組み合わせて、体の中の水分の水素原子を利用して体内のデータを取得し画像化します。20分から1時間かけてデータ収集するため、CT検査に比べても鮮明なデータを得えられます。また、MRIでは脳や筋肉、神経、血管の観察も可能です。
がんに関しては子宮がん、肝臓がん、骨肉腫(骨のがん)の精密検査で用いられます。さらに詳細にみるために造影剤を使ったり、経過を見るために数か月開けて再度MRI検査を行ったりする場合も少なくありません。
ただし、MRI検査は被ばくのリスクはないものの、多くの制約があります。MRI検査中に動いてしまうと画質が落ちてしまいますので、検査中は動かずじっとしていなければなりません。そのため、動きを止められない肺や心臓、胃や大腸などの臓器の検査には向かない検査です。
また、磁場や電波は体の中の金属にも反応してしまいますので、ペースメーカーや人工内耳はもちろん、タトゥーやアートメイクなどにも注意が必要です。
費用は、保険適用(3割負担)の場合で6,000円ほど、保険非適用の場合は20,000円ほどが目安です。
腹部エコー検査は超音波を用いた検査です。腹部に当てた超音波の反射波受信し画像化します。リアルタイムで腹部の様子を知ることができ、X線被ばくやアレルギーの心配もありません。そのため、腹部エコー検査は妊婦健診でも用いられています。
腹部エコーでは診察台に横たわり、検査技師が専用のジェルを塗ったプローベという超音波を出す特殊な器具を腹部に押し当て、気になる部位はその場でじっくり確認できます。検査時間はまちまちですが、おおよそ15分程度で終わります。
腹部エコー検査の機器は比較的コンパクトで、CT 検査やMRI検査ほどには費用も高くありません。そのため、現在では腹部の臓器を検査対象に、健診期間などが行う健康診断でも積極的に用いられています。
肝臓がんや胆のうがん、すい臓がん、膀胱がん、子宮がんなどを発見でき、乳がん検診のマンモグラフィーなどレントゲン撮影の精密検査としても用いられる場合があります。
ただ気体が超音波を伝わりにくくするため、肺や胃腸などで空気やガスがたまっている状態では、うまく検査できません。胃腸の検査では前日の夜以降食事を摂らない状況での検査が求められます。
内視鏡検査は、細くて自由に曲げられる管の先に小さなカメラを付けて体の中を直接見る検査です。
食道や胃、十二指腸などの上部消化管の検査をする場合には口から挿入し、大腸の検査では肛門から挿入します。消化管組織の病変が疑われた場合には、その場で生体検査用の組織を採取することも可能です。
胃の内視鏡は、厚生労働省が定めた基本的ながん検診としても位置付けられており、同時に咽頭・喉頭、食道の状態も観察できます。
大腸については、食事を制限しなければならない期間が長いことや下剤の服用が必要で受ける側の負担が大きいことから、厚生労働省が定めた基本的ながん検診には含まれていません。気管支や肺では、精密検査用の組織を取るためにとして内視鏡が使われる場合があります。

腫瘍マーカー検査では、検体の腫瘍マーカーの値が基準値を超えているかどうかを調べます。この検査結果は、次の4通りに分けられます。
腫瘍マーカーの検査結果の見方と疑われる病気について説明します。
腫瘍マーカー検査の結果が基準値範囲内であった場合、がんの可能性は低いと判断されます。しかし、がんがあっても腫瘍マーカー検査の値が上がらない場合もあります。例えば、日本人の約10%は、CA19-9抗原が検出されにくい体質だといわれています。
すべての腫瘍マーカーにおいて、一般的ながん検診も併用し、自覚症状があったら医療機関を受診して、精密検査を受けることが大切です。
腫瘍マーカーが陽性になった際には、がんが疑われます。擬陽性は、がんが無いにもかかわらず陽性反応を示すことです。偽陽性となる確率は、腫瘍マーカーによって異なります。腫瘍マーカーごとの偽陽性の特徴は、以下の通りです。
腫瘍マーカー検査の値が基準値より高くても、精密検査でがんが見つからなかった場合には、他の検査結果を確認して高値になっている原因疾患を探します。原因となる疾患が見つからない場合もあり、その際は経過観察をします。
腫瘍マーカー検査は一定数擬陽性が出る検査ですが、基準値を超えた場合は必ず精密検査を受けることが大切です。
健康診断のオプションで腫瘍マーカーをプラスしようと考えた際に、「保険適用できれば3割負担ですむのに」と思う方もいるかもしれません。健康診断の腫瘍マーカーは保険適用になるのでしょうか。
検診目的の腫瘍マーカー検査は、基本的に全額自己負担になります。腫瘍マーカー検査に保険が適用されるのは、診療を受けてがんが強く疑われた場合や、がんと診断された場合です。
健診機関によっては、男性向け・女性向けの腫瘍マーカー検査を組み合わせてセット料金にしていたり、3~5項目セットにして割安な料金にしたりしている場合もありますので、問い合わせてみると良いでしょう。
腫瘍マーカー検査の本来の目的は、がん治療の効果や有効性を確認して治療方針を調整したり、がんの進行スピードを評価したりすることです。また、がんの再発や転移の有無などを調べる際にも活用されています。
つまり、腫瘍マーカーは、がんの治療やがん患者さんの闘病、再発・転移の早期発見を補助する役割が大きい検査です。
そのため、進行中のがん治療と、術後の経過観察のために行う腫瘍マーカー検査は公的医療保険(患者の負担割合1~3割)の適用となります。

腫瘍マーカー検査はがん細胞や周辺の細胞が出す特有の物質を調べる検査です。もともとは、がんの患者さんの治療方針を決めるために使われていました。
現在は前立腺がんのみが、がんの早期発見における有効性を認められていますが、他の腫瘍マーカー検査も健康診断のオプションとしてつけられます。健康診断で腫瘍マーカー検査をする際には、一般のがん検診と併用することが大切です。
近年では、全従業員の健康維持を目的として、海外赴任者に対する健康診断を実施する企業も増えています。アジアやアメリカでの健康診断をお考えでしたら、ぜひご相談ください。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。