Page Top
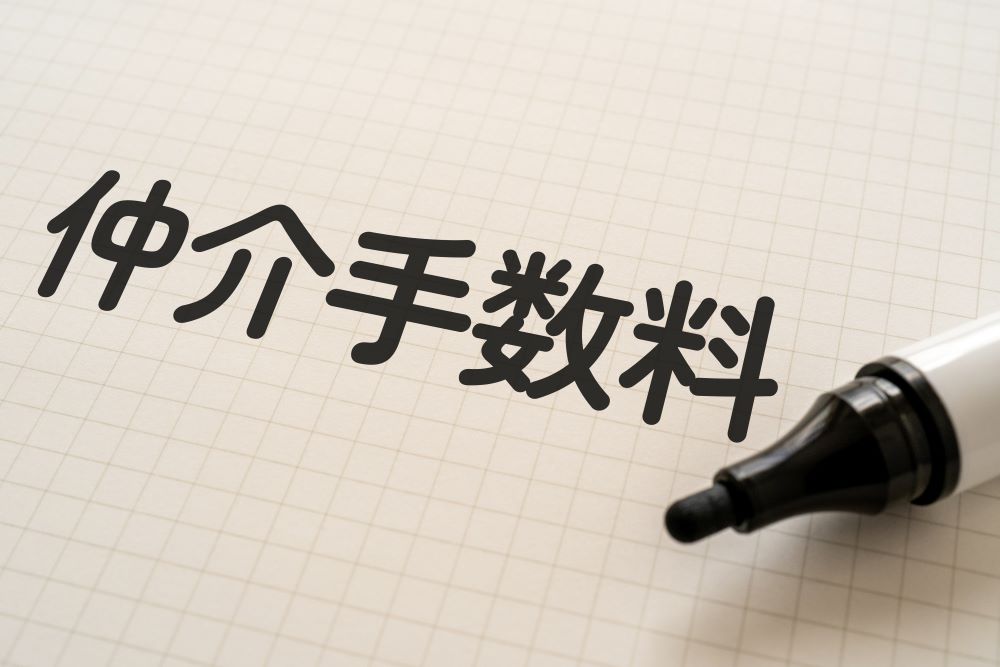
土地売買の際に避けて通れないのが仲介手数料です。その計算方法や相場、さらには節約のコツまで、本記事では徹底的に解説します。不動産取引の重要な要素である仲介手数料について正しく理解することで、より賢明な決断が下せるでしょう。初めての方でも分かりやすく、経験者にも新たな発見がある内容となっています。
<この記事で紹介する3つのポイント>
目次
そもそも、土地売買の「仲介手数料」とはどのようなお金なのでしょうか?実はスムーズに不動産取引するうえで、仲介手数料は欠かせない存在なのです。まず、土地売買における仲介手数料の役割や決定するタイミングなど、基本的な知識を深めていきましょう。
土地売買における仲介手数料は、不動産取引の重要な要素です。仲介手数料は、不動産業者が買主と売主の間に立って取引を仲介する際に受け取る報酬になります。仲介手数料の主な役割は、不動産業者の専門知識や労力の対価です。具体的には、物件情報の提供、価格交渉、契約書類の作成など、多岐にわたるサービスの対価となっています。
また、仲介手数料は取引の円滑化や安全性の確保にも寄与しており、専門家の介在によって法的リスクや詐欺などのトラブルを回避する効果があります。不動産取引において仲介手数料の支払いは避けられませんが、取引の透明性と信頼性を高める上で欠かせない費用なのです。
土地売買における仲介手数料は、一般的に売買価格が決まったときに金額が確定します。ただし、契約が成立しなかった場合は原則として手数料は発生しません。
そのため、手数料の支払いは売買契約成立後に行われます。不動産会社によっては、契約締結時に一部を前払いし、残りを決済時に支払うという方式を採用しているケースがあります。ほかにも、契約締結時または引き渡し時に一括で支払うパターンもありますが、詳しくは、後半で紹介します。
なお、仲介手数料の発生タイミングや支払い方法については、事前に不動産会社と確認し、合意しておくことが重要です。これにより、後々のトラブルを防げるでしょう。
仲介手数料の法的根拠は、宅地建物取引業法に定められています。この法律は、不動産取引の公正性と透明性を確保するために制定されました。具体的には、同法第46条に仲介手数料に関する規定があり、取引の種類や金額に応じて上限が設けられています。
国土交通省の告示により、土地売買の仲介手数料の上限は、売買価格の3.3%と定められています。ただし、200万円以下の取引では売買価格の5.5%が上限です。200万円超400万円以下の場合は、上限が売買価格の4.4%に設定されています。この規定により、消費者保護と適正な取引の促進が図られているのです。
仲介手数料の法的根拠を理解することは、取引の透明性を高め、不当な請求を防ぐ上で大切です。売主・買主双方が法律に基づいた適正な手数料を支払うことで、円滑な不動産取引が実現できるでしょう。
引用元:<消費者の皆様向け>不動産取引に関するお知らせ
お伝えしているように、土地売買の仲介手数料は取引価格に応じて計算されます。ここで注意したいのが、実際の上限額の計算方法です。詳しく見てみましょう。
土地売買の仲介手数料は「宅地建物取引業法」に基づいて計算されます。以下のように、売買価格に応じて段階的に上限額を算出します。
| 売買価格 | 計算式 |
|---|---|
| 200万円以下 | 売買価格×5.5% |
| 200万円超400万円以下 | 売買価格×4.4%+2万2,000円 |
| 400万円超 | 売買価格×3.3%+6万6,000円 |
ここで注意したいのが、調整額です。単純に手数料率だけで計算してしまうと正確な手数料を算出できません。そのため、売買価格が200万円を超える場合は「2万2,000円」や「6万6,000円」を加算して調整します。ただし、上記の計算式は消費税が10%であることを仮定しています。消費税が変動した際は、以下の計算式を用いて上限額を求めましょう。
| 売買価格 | 計算式 |
|---|---|
| 200万円以下 | (売買価格×5%)+消費税 |
| 200万円超400万円以下 | (売買価格×4%+2万円)+消費税 |
| 400万円超 | (売買価格×3%+6万円)+消費税 |
なお、仲介手数料の下限に決まりはありません。実際の手数料は不動産会社によって設定が異なる場合があるため、事前の確認が必要です。また、売買価格が高額になるほど、手数料率は低減していく傾向にあります。
では、土地売買の仲介手数料上限額を具体的に計算してみましょう。ここでは、1,000万円の土地を購入すると仮定し、計算式を当てはめていきます。400万円を超えているので、手数料率は3.3%が適用されます。
【1,000万円×3.3%+6万6,000円=39万6,000円】
1,000万円の土地の場合、仲介手数料の上限は39万6,000円と算出されました。同じように2,000万円の土地で計算すると、72万6,000円が上限です。
実際の取引では、上限額より低い金額で仲介手数料が決定することも少なくありません。交渉次第で、値引いてもらえるケースもあるでしょう。仲介手数料の値引きについては、後半で解説します。

土地売買の仲介手数料には、法律で定められた上限があることが分かりました。土地売買取引の場合、ほとんどの不動産会社が上限額を適用しています。つまり、上限額イコール相場と考えて差し支えないでしょう。
ただし、仲介手数料は必ずしも上限額が求められるわけではありません。地域や物件の特性によって相場が変動することもあります。また、取引価格に手数料率を乗じるため、土地の値段にも大きく左右されます。さらに深掘りしてみましょう。
土地売買の仲介手数料は、地域によって相場が異なります。都市部では取引価格が高くなる傾向があるため、仲介手数料も比較的高額になることが多いでしょう。一方、地方では取引価格が低めになるため、仲介手数料も都市部と比べて抑えられる傾向にあります。
また、同じ地域内でも、駅からの距離や周辺環境によって土地の価値が変動することに伴い、仲介手数料にも影響が出ます。例えば、都心の一等地と郊外では、同じ面積でも土地の価格に大きな開きがあり、仲介手数料にも差が生まれるのです。
さらに、地域の不動産市場の活況度合いによっても土地価格の相場は変化します。都市部など取引が活発な地域では競争が激しくなり、仲介手数料を上限より低く設定している可能性があります。しかし、取引が少ない地域では仲介手数料による収入が多く見込めないことから、不動産会社は経営維持のために上限いっぱいに設定されることもあるでしょう。
このように、地域の特性によって仲介手数料の相場が違ってくるケースがあるため、取引を検討する際は地元の不動産事情に詳しい専門家・会社への相談が賢明です。
土地・建物にかかわらず、仲介手数料自体はかかります。不動産であれば、上限額の計算式も同じです。土地売買における仲介手数料の相場は、物件の種類によって異なります。一般的に、更地や農地などの土地のみの取引では、建物付きの不動産と比べて手数料が低くなる傾向があります。これは、土地のみの場合、建物の評価や設備の状況確認などが不要になり、不動産会社の業務量が相対的に少なくなるためです。
一方、商業地や工業用地などの事業用途の土地では、取引金額が高額になることが多く、それに伴い仲介手数料も高くなります。また、再開発が進んでいるエリアの土地も地価が上昇する傾向があることから、仲介手数料がかさみやすいでしょう。
住宅地の場合、周辺環境や将来の開発計画によって土地価格が高くなるケースがあるため、仲介手数料が割高になることもあります。地域や不動産市場の状況によって土地価格が変動するため、具体的な取引を検討する際は、複数の不動産会社に問い合わせてみてください。
2024年7月から媒介報酬規制が見直されました。その理由は、物件の調査など不動産会社の業務負担に対して、仲介手数料による収益性が低いためです。現行の上限額では空き家など安い物件の取引で収益が見込めず、不動産会社が積極的に仲介できない状況が続いていました。そこで、空き物件の流通促進を図るべく、800万円以下の安い価格で宅地建物の売買が行われる際に、特例として上限を超えて最大33万円まで仲介手数料を請求できるようになったのです。
例えば、600万円の物件だと仲介手数料の上限は26万4000円になります。しかし特例を適用させることで、不動産会社は最大33万円まで仲介手数料として受け取れるのです。消費者の観点からすると、仲介手数料として支払う金額が増えてデメリットに感じてしまうかもしれません。しかし、従来であれば収益性が見込めず紹介を断られていた物件も、仲介してもらいやすくなるメリットがあります。
引用元:空き家等に係る媒介報酬規制の見直し

土地売買の際には、仲介手数料以外にもさまざまな費用が発生します。例を挙げると、登記費用や税金、ローンの諸費用などがあります。ここでは、売主側と買主側の双方の観点から、土地売買にかかる費用をチェックしていきましょう。
所有している土地を不動産会社に売却する場合、以下の費用がかかります。概要もまとめました。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 固定資産税の清算 | ・1月1日時点での不動産所有者に課税義務がある ・年の途中で売却した場合、所有者が1年分支払う ・公平性を保つため、固定資産税を日割りで清算するケースもある |
| 印紙税 | ・売買契約書に貼付する収入印紙代 ・契約金額に応じて税額が異なる (例)1,000万円超5,000万円以下の場合:2万円 ※2027年3月31日までに作成された契約書の場合、軽減措置として1万円に 減額される |
| 登録免許税 | ・土地の所有権移転に伴い、登記を変更する際にかかる税金 ・売買価格×2.0%※2026年3月31日までは1.5%・不動産1個につき1,000円 |
| 抵当権抹消費用 | ・土地のローンが残っている場合、抵当権を抹消してから売却する必要がある ・不動産1個につき1,000円 |
| 解体費用 | ・建物がある土地を更地にしてから売却する場合、解体費用がかかる ・40坪の木造住宅の解体相場:80~160万円 |
| 測量費用 | ・測量にかかる費用 ・必須ではないが、測量図を添付することで商品価値が上がる ・現況測量費用の相場:約35万円 |
| 地盤調査費用 | ・地盤調査にかかる費用 ・必須ではないが、地盤調査済土地の需要が高まっている ・地盤調査費の相場:約5万円 |
| 所得税・住民税 | ・土地の売却によって利益が出た場合、譲渡所得に対して所得税および住民税 がかかる |
これらの費用は物件や取引条件によって異なるため、事前に不動産会社や司法書士に確認するのが賢明です。売却益から差し引かれる諸費用を把握しておくことで、より正確な資金計画を立てられるでしょう。
引用元:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
引用元:土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
引用元:抵当権の抹消登記に必要な書類と登録免許税
土地を購入する際には、買主側も仲介手数料以外に負担する費用があります。主な項目と概要を表にまとめました。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 不動産取得税 | ・不動産を取得する際にかかる税金 ・不動産の評価額×4%※2027年3月31日までは3% |
| 印紙税 | ・売買契約書に貼付する収入印紙代 ・契約金額に応じて税額が異なる (例)1,000万円超5,000万円以下の場合:2万円 ※2027年3月31日までに作成された契約書の場合、軽減措置として 1万円に減額される |
| 登録免許税 | ・土地の所有権移転に伴い、登記を変更する際にかかる税金 ・売買価格×2.0% ※2026年3月31日までは1.5% ・不動産1個につき1,000円 |
| 固定資産税都市計画税 | ・1月1日時点での不動産所有者に課税義務がある ・年の途中で購入した場合、日割り生産で売主に支払うケースがある |
| 住宅ローンの諸費用 | ・住宅ローンを組んで土地を購入する場合、手数料や保証料などがかかる |
所有権移転の登録免許税に関しては、売主・買主どちらが負担しても問題ありません。当事者同士の話し合いによって決定します。
土地を購入する際は、土地代や仲介手数料だけでなく、買主側の追加費用を事前に把握したうえで資金計画を立てましょう。
引用元:不動産取得税
引用元:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
引用元:土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
計算式のところでも紹介しましたが、土地売買の仲介手数料には消費税が課されます。これは、不動産仲介業が消費税の課税対象となるサービスに該当するためです。消費税率は現在10%となっており、仲介手数料の総額に上乗せされる形で請求されます。例えば、消費税抜きの仲介手数料が30万円である場合、消費税3万円が加算され、合計33万円支払う計算になります。
ただし、消費税の計算は最終的な仲介手数料の金額に対して行われるため、値引きなどがあった場合はその後に消費税が計算されることに注意が必要です。また、消費税込みの金額で仲介手数料が提示されることもあるため、契約前にしっかり把握しておきましょう。

土地売買の仲介手数料は、決して安くありません。仲介手数料の負担を減らすためにできるコツと注意点を紹介します。
土地売買の仲介手数料を抑えるには、複数の不動産会社から相見積もりを取ることが効果的です。各社の提示する手数料や付帯サービスを比較することで、より有利な条件を見つけられる可能性が高まります。他社の見積もりを提示できれば、値引き交渉を進めやすくなります。少なくとも3社以上の不動産会社にアプローチして、見積もりを取りましょう。その際、物件の詳細情報や希望条件を明確に伝え、各社の対応や提案内容を細かくチェックしてください。
また、大手不動産会社だけでなく、地域に密着した中小の不動産会社も視野に入れるのもおすすめです。地域の事情に詳しい会社であれば、より柔軟な対応や独自のサービスを提供してくれる可能性があります。相見積もりを活用することで、最適な不動産会社を選択し、仲介手数料の節約につながるのです。
仲介手数料の値引き交渉における、具体的なポイントをお伝えします。
不動産会社選びの段階で、キャンペーンやサービスがあるかチェックしてみましょう。割引制度を設けている不動産会社であれば、効果的な仲介手数料の削減が見込めます。
複数の不動産会社から見積もりを取得したら、内容を比較してみてください。各社の提示額に差があれば、交渉の余地が生まれるでしょう。交渉の際は、他社の見積もりや市場データを活用して根拠を示すことが大切です。また「この金額なら契約可能」と交渉してみるのも有効です。
ただし、過度な値引き要求は避けるべきです。適切なサービスを受けるためには、仲介手数料は欠かせません。仲介手数料を値引きしすぎることによって、売買の優先順位が下がって後回しにされてしまったり、結局売買価格が高くなったりといったリスクがあります。双方にとって納得のいく金額で合意することが、円滑な取引につながるでしょう。
不動産会社のなかには、仲介手数料無料サービスを実施しているケースがあります。消費者からすると、不動産取引のコスト削減と柔軟な物件探しを可能にします。ただし、仲介手数料が無料である代わりに、専門家のサポート不足や自己責任での手続きといった負担がかかることもあります。
株式会社DYMの不動産仲介・オフィスコンサルティング事業部のサービスでは、多くの投資家が投資判断の精度向上を実感しています。東京や大阪など日本の主要都市7ヶ所に拠点があり、サービスを提供しています。豊富なデータとノウハウで、お客様のニーズに合わせた物件の紹介が可能です。法人向け不動産コンサルティングやオフィス移転の仲介などを検討する際は、ぜひ株式会社DYMのサービスをご活用ください。

土地売買における仲介手数料を支払うタイミングや支払い方法についても、改めてチェックしておきましょう。
仲介手数料の支払い方は、以下の3パターンあります。
売買契約時と引き渡し時に分割して支払うパターンが一般的です。契約や不動産会社によって、売買契約成立時または代金清算時に一括で支払うこともあります。支払いのタイミングは、取引の状況や不動産会社との合意によって異なることがあるため、しっかり確認しておきましょう。
なお、仲介手数料は手付金でまかなえるケースがあります。仲介手数料の支払い時期について不安がある場合は、不動産会社と十分に相談し、双方が納得できる形で決定することが望ましいでしょう。
お伝えしたように、仲介手数料の支払い方法には、一括払いと分割払いの選択肢があります。一括払いは取引完了時に全額支払うため、手続きが簡単です。一方、分割払いは複数回に分けて支払うので、一時的な資金負担を軽減できます。ただし、分割払いを選択する場合は、支払い期間や金利などの条件のチェックが必須です。
支払い方法の選択は、不動産会社との相談で決定します。原則、現金支払いですが、クレジットカード決済や銀行振込などに対応可能な場合もあるので、事前に確認しましょう。なお、分割払いを選択する場合は、追加手数料が発生する可能性があります。支払い計画を立てる際は、総支払額や金利などの条件を十分に理解し、自身の経済状況に合わせて最適な方法をご検討ください。
仲介手数料関連のトラブルを防ぐには、事前の確認と明確な合意が不可欠です。最後に、安心な取引の実現に向けて、気をつけたいポイントを紹介します。
土地売買の契約前には、不動産会社から提示された手数料の金額と計算根拠を必ず調べておきましょう。法令で定められた上限額を超えていないか、売買価格に応じた適切な金額であるかを精査することが大切です。また、手数料の支払い時期や方法についても明確に取り決めておくべきでしょう。さらに、手数料に含まれるサービスの範囲や、追加で発生する可能性のある費用がないかも確認が必要です。
契約書には、これらの事項が明記されているか丁寧にチェックしてください。不明点や疑問があれば、遠慮なく担当者に質問し、納得できるまで説明を求めることが重要です。こうした事前リサーチを怠らないことで、後々のトラブルを未然に防げるでしょう。
契約時に、仲介手数料の返金に関する事項のチェックも欠かせません。一般的に、売買契約が成立しなかった場合や、契約後に解除されたケースの返金条件が定められています。「ローン審査が通らなかった」といったお客様に責任がない原因による契約介助であれば、返金可能でしょう。ただし、自己都合による契約解除では返金は望めません。返金の範囲や条件は不動産会社によって異なるため、事前に詳細を把握しておくことが賢明です。
なお、契約前の調査や広告費用など、すでに発生した実費については返金対象外となることが多いでしょう。また、契約解除の理由や時期によっても返金額が変わる可能性があります。トラブル防止のためにも、返金規定を含む重要事項説明書の内容を十分に理解し、不明点があれば必ず質問して疑問を解決することをおすすめします。
土地売買の仲介手数料について、計算方法や相場、節約のコツを詳しく解説してきました。適切な仲介手数料の理解と交渉は、取引をスムーズに進める上で欠かせません。個人事業主や法人の方で、不動産取引に関するさらなる専門的なアドバイスや支援が必要な場合は、株式会社DYMの不動産コンサルティングサービスをご検討ください。豊富な経験と専門知識を活かし、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションを提供いたします。詳細は、DYMのサービスページでご確認ください。
DYMの「不動産仲介・オフィスコンサルティング事業」サービスページはこちら

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。