Page Top
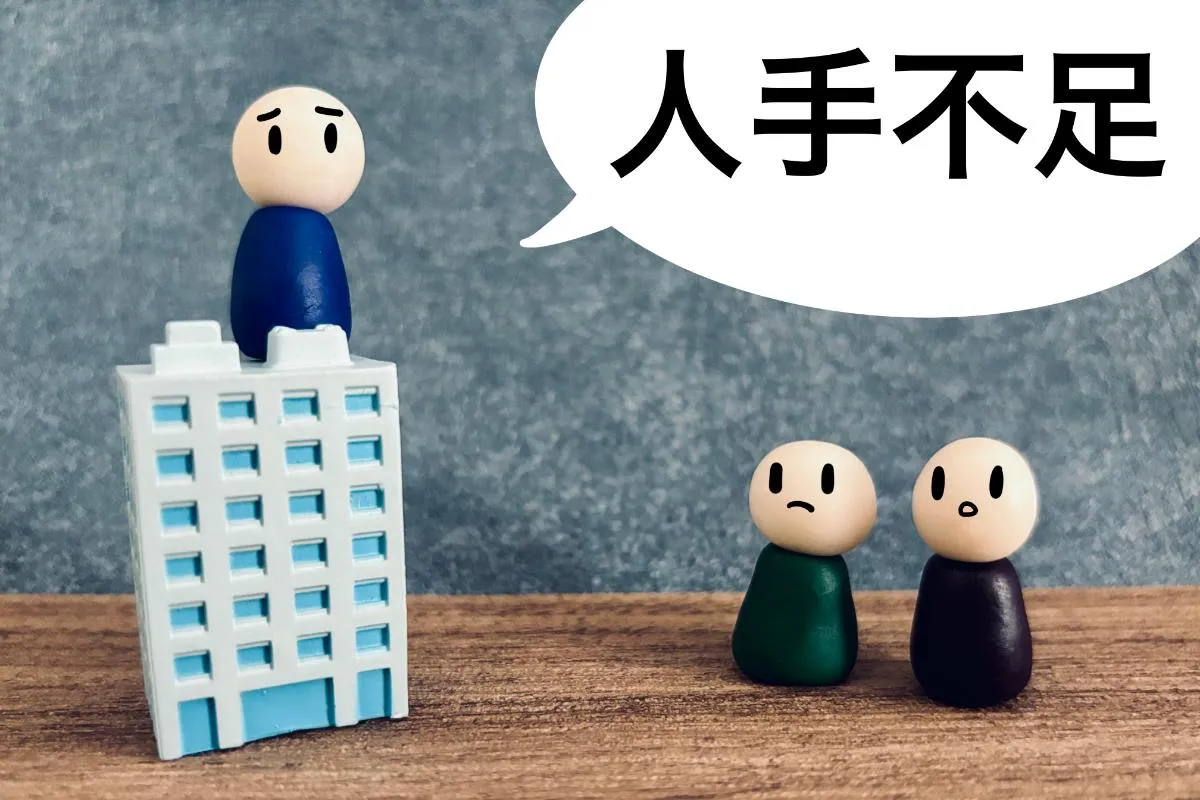
日本の介護業界は、社会の高齢化が加速する中で、深刻な人手不足に直面しています。採用活動を行う企業の担当者にとって、この問題は事業の継続性を左右する重要な課題です。介護サービスの需要は増え続ける一方、供給を担う人材の確保が追いついていないのが実情といえます。この記事では、企業の採用活動をサポートする専門家の視点から、介護業界が人手不足に陥っている現状とその根底にある原因を深掘りします。さらに、国や事業所が取り組むべき具体的な解決策まで、わかりやすく解説していきます。
<この記事で紹介する3つのポイント>

現在の介護業界は、客観的なデータからも危機的な人手不足の状態にあることが明らかです。厚生労働省の推計によると、2026年度には約25万人、さらに高齢化が進む2040年度には約57万人の介護職員が不足すると予測されています。これは、増え続ける介護サービスの需要に、担い手の供給が全く追いつかなくなる未来を示唆しています。
この状況は、雇用の需給バランスを示す有効求人倍率にも表れています。介護サービス職の有効求人倍率は、全産業の平均を常に大きく上回る水準で推移しており、企業が求人を出しても人材を確保することが極めて困難な「売り手市場」が続いています。
将来にわたる不足人数の予測と現在の求人倍率の高さは、介護の人手不足が構造的かつ長期的な課題であることを物語っています。採用担当者は、この厳しい現状認識を前提とした採用戦略の構築が不可欠です。
介護業界が深刻な人手不足に陥っている背景には、複合的な原因が存在します。これらの問題を構造的に理解することで、企業はより効果的な対策を講じることが可能になります。
主な原因は、「業務負担に見合わない賃金・待遇」「身体的・精神的に過酷な労働環境」「キャリアパスの不透明性と将来への不安」「ネガティブな社会的イメージと低い評価」「少子高齢化による生産年齢人口の減少」という5つの点に集約されます。
介護職の人材確保を困難にする根源的な原因の一つが、業務の負担と賃金・待遇の不均衡です。専門的な知識や技術が求められる専門職でありながら、その労働価値が給与に十分に反映されていないという課題を抱えています。
この問題の背景には、介護サービスの価格が国が定める介護報酬によって上限が決められているため、事業所が独自に給与を大幅に引き上げることが難しいという構造があります。その結果、介護職員の平均給与は、日本の全産業平均と比較して低い水準にとどまっているのが実情です。
政府もこの問題を認識し、「介護職員処遇改善加算」などの施策を講じてはいますが、依然として全産業平均との格差は残っています。業務の専門性や責任の重さに見合った賃金体系を構築できなければ、人手不足の悪循環から抜け出すことは難しいでしょう。
心身ともに負担が大きい過酷な労働環境も、介護職が敬遠される大きな理由です。この問題は離職率の高さに直結し、人材の定着を阻む深刻な障壁となっています。
身体的な負担としては、利用者を支える移乗介助や入浴介助などによる腰痛が職業病ともいえるほどです。また、多くの施設では夜勤が必須であり、不規則な勤務形態が体調を崩す原因となることも少なくありません。
精神的な負担も看過できません。認知症の利用者とのコミュニケーションに悩んだり、職員同士の人間関係にストレスを感じたりすることもあります。利用者の命を預かるというプレッシャーも常に伴います。このような身体的・精神的な負担が積み重なる労働環境を改善しない限り、働き続けたいと思える職場にはならず、人手不足は解消されないでしょう。

介護業界で働く人材が定着しにくい要因として、キャリアパスの不透明性と、それに伴う将来への不安が挙げられます。自身の成長や将来の展望を描きにくいと感じることが、早期離職の一因となっています。
介護の現場では、経験を積んで介護福祉士などの資格を取得しても、それが必ずしも昇進や大幅な給与アップに直結しないケースが少なくありません。事業所内の管理職のポストは限られており、専門性を高めてもそのスキルを評価し、キャリアアップにつなげる仕組みが十分に整備されていないのです。
このような状況は、職員のモチベーションの低下を招きます。「このまま今の仕事を続けていても、将来どうなるのだろうか」という不安は、他業種へ転職する動機になり得ます。企業が人材を定着させるためには、職員がキャリアプランを描けるような道筋を示すことが不可欠です。
介護の仕事に対する社会的なイメージが、人手不足を助長する一因となっています。いまだに「3K(きつい、汚い、給料が安い)」というネガティブな言葉で語られることが多く、これが新規参入を目指す人々にとって高い障壁となっているのです。
このようなマイナスのイメージは、介護職の専門性や社会的な重要性に対する理解が不足していることに起因します。介護の仕事は、高齢者の尊厳を守り、その人らしい生活を支えるための高度な知識と技術を要する専門職です。しかし、その実態が十分に社会に伝わっておらず、過酷な労働環境や待遇面の課題ばかりが強調されがちです。
こうした状況は、若者や転職を考える人々が介護業界を就職先として選択することをためらわせる原因となります。業界全体で仕事の魅力ややりがいを積極的に発信し、社会的なイメージを向上させていく取り組みがなければ、人材の確保はますます困難になるでしょう。
介護業界の人手不足を考える上で避けて通れないのが、日本社会全体の構造的な問題である少子高齢化です。この人口動態の変化は、介護サービスの需要と供給の両面に深刻な影響を及ぼし、人手不足を根本から悪化させています。
供給面では、働き手となる生産年齢人口(15歳~64歳)が減少し続けているため、労働市場全体で人材獲得競争が激化しています。その中で、待遇や労働環境の課題を抱える介護業界は、他の産業との競争において不利な立場に置かれやすいのです。
一方で需要面では、高齢者人口の増加に伴い、介護を必要とする人の数は右肩上がりに増え続けています。つまり、介護サービスの担い手は減る一方、サービスを必要とする人は増え続けるという、需要と供給のアンバランスが拡大しているのです。この構造的な問題の理解は、長期的な人材戦略を立てる上で不可欠です。

介護業界の人手不足を語る上で重要なキーワードが「2025年問題」です。これは、いわゆる団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になることで、日本の医療や介護の需要がピークに達し、社会保障制度に大きな影響を及ぼすとされる問題です。この「2025年問題」は、介護業界だけでなく、日本社会全体で向き合うべき喫緊の課題といえるでしょう。
2025年問題の核心は、第一次ベビーブーム期に生まれた「団塊の世代」が一斉に75歳以上の後期高齢者となる点にあります。75歳を過ぎると心身の機能が低下し、介護や医療を必要とする人の割合が急増するため、介護サービスの需要がこれまでにないレベルで爆発的に増加すると予測されているのです。
厚生労働省の推計によると、2025年には高齢者人口は約3,657万人にのぼるとされています。介護サービスの利用者数もこれに比例して増加し、在宅介護、デイサービス、訪問介護といったあらゆる介護サービスの必要性が高まります。
しかし問題は、この急増する需要に対して、介護職員の供給が全く追いついていないという現実です。この需要と供給の巨大なギャップこそが、2025年問題が介護業界にもたらす最大のインパクトです。企業は、このマクロな視点を持ち、戦略的な採用計画を立てることが求められます。
人手不足が深刻化する2025年以降、介護サービスの質の維持が困難になるという懸念が高まっています。介護職員一人ひとりが抱える業務量が増え、きめ細やかなケアを提供する余裕が失われてしまうためです。
職員が慢性的な疲労やストレスを抱えるようになると、利用者の変化を見逃したり、十分なコミュニケーションが取れなくなったりする可能性があり、介護事故のリスクも高まります。また、研修の時間が確保できず、職員のスキルアップが滞ることもサービスの質の低下を招きます。
さらに、人手不足は介護事業所の経営そのものを直撃します。介護保険法で定められた職員の配置基準を満たせなくなると、事業所は運営を続けられません。最悪の場合、人材を確保できずに倒産に追い込まれる事業所が増加することも考えられ、地域の介護インフラが崩壊する事態も危惧されています。
介護業界の人手不足は、事業所内だけの問題にとどまらず、社会全体、特に家族のあり方にも深刻な影響を及ぼします。その代表的なものが、「介護離職」と「介護難民」の増加です。
「介護離職」とは、家族の介護を理由に仕事を辞めざるを得なくなる状況を指します。介護サービスを十分に利用できないと介護の負担は家族に重くのしかかり、最終的に離職を選択する人が増える可能性があります。これは個人の経済的困窮だけでなく、日本全体の労働力損失という大きな問題です。
さらに、必要な介護サービスを受けたくても受けられない高齢者、いわゆる「介護難民」の増加も懸念されます。事業所の倒産などが相次げば、高齢者は適切なケアを受けられる場所を求めてさまようことになります。このように、介護の人手不足は、高齢者やその家族の生活を直接的に脅かす社会問題へと発展していくのです。

深刻化する介護業界の人手不足に対し、国や自治体、そして各介護事業所はさまざまな角度から解決策を講じています。
これらの対策は、国や自治体が主導する公的な支援制度と、各介護事業所が主体的に取り組める対策の2つのレベルで考えることができます。国の施策には職員の給与を引き上げる「処遇改善加算」や外国人材の受け入れ拡大、業務効率化を支援する「ICT導入補助金」などがあります。
一方、事業所レベルでは、働きやすい環境の整備や多様な働き方の導入などが挙げられます。これらの解決策を組み合わせ、多層的にアプローチしていくことが、人手不足という大きな課題を乗り越える鍵となるでしょう。
介護の人手不足という国家的課題に対応するため、国や自治体はさまざまな公的支援制度を設けています。これらの制度の活用は、事業所が人材を確保し、定着させる上で大きな助けとなります。
代表的な支援策として、まず介護職員の賃金改善を目的とした「介護職員処遇改善加算」があります。これは、事業所が要件を満たすことで介護報酬が上乗せされ、職員の給与アップが可能になる仕組みです。
次に、国内の労働力不足を補うため、経済連携協定(EPA)や在留資格「特定技能」により、海外から意欲のある人材を受け入れる門戸が広がりました。
さらに、業務の効率化と職員の負担軽減を後押しするため、ICTや介護ロボットの導入を支援する補助金制度も各地で設けられています。これらの公的支援を積極的に活用することが、人手不足解消に向けて重要です。
国が主導する人手不足対策の中でも、特に重要なのが職員の賃金に直接関わる「介護職員処遇改善加算」と定期的な「介護報酬改定」です。
「介護職員処遇改善加算」は、キャリアアップの仕組み構築や職場環境の改善に取り組む事業所に対して介護報酬を加算する制度です。事業所はこの加算分を職員の昇給や賞与などの形で分配しなければならず、職員の待遇改善に直結します。
また、3年に一度行われる「介護報酬改定」も、職員の処遇に大きな影響を与えます。近年では、人手不足対策として介護職員の賃上げにつながるような報酬改定が行われる傾向にあります。これらの制度を最大限に活用することが、人材の定着率向上と採用競争力の強化につながります。
国内の労働人口が減少する中で、介護人材を確保するための有効な手段として、外国人材の受け入れが積極的に進められています。
代表的な制度の一つが、在留資格「特定技能」です。一定の専門性と技能を持つ外国人が、最長5年間日本で働くことが可能です。もう一つの主要な制度が、二国間の経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者の受け入れです。日本の施設で働きながら国家資格取得を目指し、合格すれば継続して日本で働けます。
これらの制度を活用することで、事業所は新たな人材確保の道筋を得られます。ただし、受け入れにあたっては、言語や文化の違いを乗り越えるためのサポート体制の構築が、成功の鍵となります。
介護現場の業務効率化と職員の負担軽減を実現する切り札として、ICTや介護ロボットの活用、すなわちDXの推進が期待されています。国や自治体は、導入コストの課題を解消するため、さまざまな補助金制度を設けてDXを後押ししています。
補助金の対象となるのは、介護記録ソフトや見守りセンサー、移乗支援ロボットなどさまざまです。これらのツールを導入することで、記録作業の時間を短縮したり、夜間の巡視業務の負担を減らしたりすることが可能になります。
高額な初期費用が障壁となる場合も、「ICT導入支援事業」などの補助金を活用すれば負担を大幅に軽減できます。DXを推進していることは、採用活動においても大きな強みとなります。

国の支援制度と並行して、各介護事業所が主体的に取り組める対策も人手不足の解消には不可欠です。職員が日々の業務の中で直接的に魅力を感じるのは、事業所独自の取り組みであることが多いでしょう。
これらの対策は、新たな人材を惹きつける「採用力」の強化と、今いる人材の流出を防ぐ「定着率」の向上の両面から考える必要があります。具体的には、職員が心身ともに健康で、安心して長く働き続けられるような労働環境を整えることが基本となります。
例えば、休暇制度の充実や残業時間の削減、福利厚生の拡充などが挙げられます。また、介護ロボットやICTを導入して業務負担を物理的に軽減したり、多様な働き方を認めたりすることも有効です。これらの施策を通じて「働きやすい職場」を実現することが、人材獲得競争を勝ち抜くための重要な鍵となります。
人材の流出を防ぎ、定着率を高めるためには、職員が働きがいを感じ、長期的なキャリアを築ける労働環境の整備が最も重要です。
まず取り組むべきは、労働条件の改善です。年間休日数を増やしたり、有給休暇の取得を促進したりすることで、職員が心身ともにリフレッシュできる機会を確保します。
次に、精神的なケアや良好な人間関係の構築も欠かせません。定期的な面談で職員の悩みを吸い上げたり、メンター制度で新人をサポートしたりする仕組みが求められます。
さらに、キャリアパスの明確化も重要です。資格取得支援や研修プログラムを用意し、将来の道筋を示すことで、職員は希望を持って働き続けることができます。
介護職員の負担を直接的に軽減し、生産性を向上させる効果的な手段が、介護ロボットやICTツールの導入です。テクノロジーの力を活用することで、限られた人員でも質の高い介護サービスを提供できる体制を構築できます。
介護ロボットは、移乗をサポートするパワーアシストスーツや見守りシステムなど、特に身体的負担の大きい業務で真価を発揮します
一方、ICTツールは、インカムや介護記録ソフトなど、情報共有や記録業務の効率化に大きく貢献します。これらの導入は、単なる業務効率化にとどまらず、「職員を大切にする」という企業の姿勢を示すメッセージとなり、採用活動においても強力なアピールポイントとなります。
人手不足の時代においては、従来の採用の枠組みにとらわれず、多様な人材が活躍できる環境を整えることが不可欠です。働き方の選択肢を増やすことは、これまでアプローチできなかった層への門戸を開き、採用競争力を高めます。
例えば、子育て中の層やシニア世代などが活躍できるよう、短時間勤務制度や柔軟なシフト制度を導入することが有効です。 これと同時に、採用戦略そのものも見直す必要があります。未経験者や無資格者を積極的に受け入れ、入社後に育成する体制を整えることが重要です。資格取得支援制度などを設けることは、応募者にとって大きな魅力となります。多様な人材を受け入れ、育てるという視点が、持続可能な人材確保の鍵となります。

ここでは、介護業界の人手不足に関して、企業の採用担当者から寄せられることの多い質問とその回答をまとめます。人手不足問題の構造的な背景や、今後の展望について、より明確なイメージを持つことができるでしょう。
介護職の給料が他の産業に比べて上がりにくい根本的な理由は、その収入の大部分が公的な介護保険制度によって賄われているためです。具体的には、事業所の収入は国が定める「介護報酬」に基づいて決まります。
一般の民間企業であれば、自社の判断でサービスの価格を設定し、利益を上げて給与に還元できます。しかし、介護事業所の場合、サービスの価格は介護報酬によって上限が定められているため、自由に料金を値上げして収入を増やすことができません。この収入源が公定価格に縛られていることが、給与水準が上がりにくい最大の構造的な要因といえます。
国も「介護職員処遇改善加算」といった制度を設けていますが、財源が税金と保険料であるという制約から、大幅な賃上げは難しいのが現状です。事業所としては、加算を確実に取得し、最大限職員に還元していく経営努力が求められます。
結論から言うと、未経験・無資格からでも介護の仕事を始めることは十分に可能です。人手不足が深刻な介護業界では、経験や資格よりも、人柄や仕事への意欲を重視して採用を行う事業所が数多くあります。
無資格からでも、身体介護や生活援助、施設の清掃、食事の配膳といった業務からスタートし、現場の仕事を覚えながらキャリアを積んでいくことができます。「介護職員初任者研修」といった資格も、比較的短期間で取得可能です。
多くの事業所では、未経験者が安心して仕事を始められるように、入社後の研修制度や資格取得の費用を負担してくれる「資格取得支援制度」を充実させています。採用担当者としては、教育体制が整っていることを明確にアピールすることが、採用の間口を広げる上で非常に重要です。
もし現状のまま有効な対策が打たれず、介護の人手不足が放置され続けた場合、日本の介護システムは崩壊の危機に瀕する可能性があります。それは社会全体に影響を及ぼす深刻な事態です。
まず、最も懸念されるのが「介護難民」の激増です。適切なケアを受けられない高齢者が増え、家族にかかる介護負担は極限まで増大し、仕事を辞めざるを得ない「介護離職」がさらに深刻化します。これは労働力人口の減少を加速させ、日本経済全体にも悪影響を与えます。
また、運営を続けられる介護事業所においても、職員一人あたりの負担が増えることで、サービスの質は著しく低下する恐れがあります。きめ細やかな個別ケアは困難になり、最低限のケアしか提供できなくなるかもしれません。人手不足の進行は、日本の社会保障制度の根幹を揺るがし、高齢者が安心して暮らせる社会の維持を困難にするのです。
介護業界の人手不足は、賃金や労働環境、社会的なイメージといった複合的な原因が絡み合う根深い課題です。この問題への対応は、企業の持続的な成長と社会的な役割を果たす上で不可欠といえます。人手不足の現状と原因を正しく理解し、効果的な対策を講じることが、今後の事業運営を成功させるための突破口となります。
採用活動の強化や効果的な情報発信には、マーケティングの専門知識を持つ人材の力が求められます。なお、DYMテックでは、フリーランスマーケター向けのエージェントサービスとして、専任カウンセラーが一人ひとりのスキルやキャリアプランに合わせた案件マッチングをサポートしています。最高単価1,250,000円の案件紹介実績や面談満足度88.5%という高い評価をいただいており、質の高いマッチングを実現しています。採用ブランディングやデジタルマーケティングの強化をお考えの介護事業者様は、まずはお気軽に無料相談から始めてみてください。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。