Page Top

採用活動において、複数の求人媒体からの応募者情報管理や、選考状況の共有、面接日程の調整などに多くの時間と手間がかかっていませんか。これらの煩雑な業務を劇的に効率化し、採用の質を高めるために注目されているのが「ATS(採用管理システム)」です。ATSを導入することで、これまで手作業で行っていた多くの業務を自動化し、人事担当者は候補者とのコミュニケーションといったコア業務に集中できます。
本記事では、ATSの基本的な機能から、導入することで得られるメリット・デメリット、そして自社の課題に合ったシステムの選び方までを分かりやすく解説します。採用活動を次のステージに進めるためのヒントがここにあります。
<この記事で紹介する3つのポイント>

ATSとは「Applicant Tracking System」の頭文字を取った略称で、日本語では「採用管理システム」と呼ばれています。その主な役割は、求人情報の作成から応募者の受付、選考の進捗管理、内定者フォローに至るまで、複雑な採用業務に関する情報を一元的に管理し、プロセスを効率化することです。近年、ダイレクトリクルーティングやSNS採用など採用手法が多様化し、応募者との接点が増えたことで、人事担当者の情報管理業務は煩雑化しています。
ATSを導入することで、複数の求人媒体からの応募者情報や選考状況などを一つの画面で把握できるようになり、採用担当者の業務負担を大幅に軽減することが可能です。これにより、従来は管理業務に割かれていた時間を候補者とのコミュニケーションなど、より戦略的な採用活動に充てられるようになります。
採用管理システム(ATS)を導入することは、単なる業務効率化に留まらず、採用活動の質そのものを向上させる多くのメリットをもたらします。最も直接的な効果は、複数の求人媒体からの応募者情報取り込みや面接日程の調整といった、これまで手作業で行っていた煩雑な業務を自動化し、採用担当者の工数を大幅に削減できる点です。これにより、応募者一人ひとりへのきめ細やかな対応が可能になり、選考辞退を防ぎます。
また、全ての応募者情報が一つのプラットフォームに集約されるため、対応漏れや連絡ミスといったリスクを無くし、採用チーム全体でリアルタイムに選考状況を共有できるようになります。迅速で丁寧な応募者対応は候補者の満足度を高め、ひいては企業の採用ブランド強化にもつながるでしょう。さらに、蓄積されたデータを分析することで、費用対効果の高い採用チャネルの特定や、選考プロセスの課題発見が可能となり、データに基づいた戦略的な採用コストの削減が実現します。
ATSを導入する最大のメリットは、採用に関するさまざまな業務の作業時間を大幅に削減できる点です。複数の求人媒体や人材紹介会社からの応募者情報を手動で転記・集計する作業は不要になり、システムが自動でデータを取り込み一元管理します。また、面接日程の調整も、担当者や面接官のカレンダーと連携し、候補日を自動でリストアップする機能を使えば、何度もメールで往復する手間が省けます。
実際に、これまでExcelで1時間かかっていた管理・分析業務がATS導入によって大幅に短縮されたという事例もあります。採用媒体別の効果測定レポートなども自動で作成できるため、分析や報告資料の作成にかかる工数も削減され、担当者はより重要なコア業務に集中できるのです。
採用活動において、多数の応募者をExcelやスプレッドシート、あるいは紙で管理していると、情報の散逸や入力ミス、更新漏れが発生しやすくなります。その結果、有望な候補者への連絡が遅れたり、最悪の場合には選考案内を忘れてしまったりといった致命的なミスにつながる可能性があります。ATSを導入すれば、求人媒体や自社サイトなど、あらゆる経路からの応募者情報が自動的に一つのプラットフォームに集約されます。
各応募者の選考ステータスはリアルタイムで可視化され、「誰に何をすべきか」が一目でわかるため、対応漏れのリスクを根本から無くすことが可能です。システムから連絡を一括送信できる機能もあり、候補者への案内漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失を最小限に抑えます。

ATSは、採用担当者だけでなく、面接官や役員など、採用プロセスに関わる全てのメンバー間でのスムーズな情報共有を実現します。従来、面接官への候補者情報の共有を紙やメールで行っていると、情報の伝達に時間がかかったり、最新の状況が分からなくなったりすることがありました。ATSでは、候補者の履歴書や職務経歴書、過去の面接評価、現在の選考状況といった全ての情報がシステム上に集約されています。
関係者はいつでも最新情報にアクセスでき、評価の入力やフィードバックもシステム内で完結するため、選考のスピードアップが図れます。専任の採用担当者が不在で情報が分散していた企業が、ATS導入によってリアルタイムに状況を共有できるようになった事例もあり、全社的な採用活動の推進につながります。
ATSの導入は、採用業務の効率化を通じて、応募者の満足度向上にも直接的に貢献します。システムによって面接日程の調整や合否連絡といったコミュニケーションが迅速化されるため、応募者は「待たされている」というストレスを感じにくくなります。スピーディで丁寧な対応は、応募者が企業に対して抱く印象を良くし、選考辞退や内定辞退の防止にもつながる重要な要素です。
また、一部のATSにはアンケート機能が搭載されており、選考プロセスを通じて応募者から直接フィードバックを収集することが可能です。この生の声を分析し、選考体験の改善に活かすことで、企業の採用ブランドはより強固なものになります。良い採用体験はSNSなどで拡散されることもあり、将来的な母集団形成にも好影響を与えるでしょう。
ATSは、採用活動に関するあらゆるデータを蓄積・可視化し、戦略的な意思決定を支援します。例えば、どの求人媒体や人材紹介会社からの応募が多く、そこから何人が内定に至ったのかといった費用対効果を正確に分析できます。これにより、効果の薄い媒体への広告出稿を止め、成果の出ているチャネルに予算を集中させるといった採用コストの最適化が可能です。
また、書類選考や一次面接など、各選考ステップでの通過率(歩留まり)を分析することで、「どの段階で候補者の離脱が多いか」といった採用プロセスの課題を特定できます。データに基づいた改善策を講じることで、採用活動全体の質が向上し、結果的に一人当たりの採用単価を引き下げる効果が期待できるのです。
多くのメリットがある一方で、ATSの導入にはいくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。最も現実的な課題は、初期費用や月額利用料といった継続的なコストが発生することです。自社の採用規模や予算に見合っているか、長期的な費用対効果を慎重に検討する必要があります。
また、新しいシステムであるため、採用担当者や面接官がその操作に慣れるまでには一定の習熟期間が求められ、一時的に業務が非効率になる可能性も考えられます。システムに採用情報を集約するという特性上、万が一システム障害が発生した場合には採用活動が停止してしまうリスクも抱えています。加えて、非常に独自性の高い採用フローを持つ企業では、システムの標準機能が自社のプロセスに完全に適合しない場合も想定されます。既存の応募者データを新システムへ移行する作業も、計画的に進めなければ現場の混乱を招く一因となり得ます。

ATS導入の最も大きなデメリットは、コストが発生することです。多くのATSは無料で利用できるものではなく、初期費用や月額の利用料金が必要となります。料金体系はサービスによってさまざまで、月額数千円から利用できるものもあれば、月額5万円以上かかる高機能なシステムも存在します。
また、利用する機能や登録する応募者数に応じて追加料金が発生するプランもあります。これらの費用は継続的に発生するため、導入前に自社の採用規模や予算を正確に把握し、長期的な視点で費用対効果を慎重に検討することが不可欠です。無料プランを提供しているATSもあるため、まずはコストをかけずに試してみるのも一つの方法でしょう。
新しいシステムを導入する際には、必ず操作に慣れるための期間が必要になります。ATSも例外ではなく、採用担当者や面接官が全ての機能をスムーズに使いこなせるようになるまでには、ある程度の時間と学習が必要です。特に、多機能で複雑なシステムの場合、導入後のトレーニングやマニュアルの読み込みが不可欠となり、一時的に業務効率が低下してしまう可能性も否定できません。
この習得期間をなるべく短くするためには、導入前に無料トライアルやデモ版を利用し、実際の操作感を確認することが極めて重要です。担当者にとって直感的で分かりやすいインターフェースを持つシステムを選ぶことで、導入後の定着をスムーズに進めることができます。
ATSは採用業務を大幅に効率化する一方で、システムへの依存度が高まるというリスクも内包しています。応募者情報から選考スケジュール、コミュニケーション履歴まで、全てのデータをシステム上で管理するため、万が一、ベンダー側で大規模なシステム障害やサーバーダウンが発生した場合、採用活動が完全に停止してしまう恐れがあります。応募者情報の確認や面接日程の連絡ができなくなり、選考プロセス全体に深刻な影響を及ぼしかねません。
このようなリスクを軽減するためには、システムの安定性やセキュリティ対策、障害発生時のサポート体制などを提供会社に事前に確認しておくことが重要です。また、重要なデータは定期的にバックアップを取るなどの対策も検討すべきでしょう。
多くのATSは、さまざまな企業で利用できるよう汎用的な機能設計がされています。そのため、非常にユニークで特殊な採用プロセスや独自の評価基準を持つ企業の場合、システムの標準機能だけでは完全に対応しきれないケースが出てきます。例えば、独自の選考ステップや特殊な評価シートをそのままシステム上で再現することが難しい場合があります。
多くのシステムではある程度のカスタマイズが可能ですが、それにも限界があり、場合によっては自社の採用プロセスの方をシステムに合わせて変更する必要に迫られることも考えられます。導入前に、自社の譲れない採用プロセスは何かを明確にし、それがシステムで実現可能かどうかをデモやトライアルを通じて入念に確認することが不可欠です。
ATSを新たに導入する際、これまでExcelやスプレッドシート、あるいは別のシステムで管理していた既存の応募者データを移行する作業が発生します。このデータ移行は、想像以上に時間と手間がかかるプロセスであり、一時的に業務が混乱する原因となり得ます。データのフォーマットを新しいシステムに合わせて整形したり、情報の重複や欠損がないかを確認したりする作業が必要です。
特に、長年にわたって蓄積された膨大な量のデータを扱う場合、その負担は大きくなります。移行期間中は、新旧両方のシステムを併用せざるを得ない状況も発生し、現場の混乱や入力ミスを招くリスクも高まります。スムーズな移行を実現するためには、事前の計画と十分な作業時間の確保が欠かせません。

ATS(採用管理システム)は、採用活動の各フェーズを円滑に進めるための多彩な機能を標準で搭載しています。その中核となるのが、複数の求人媒体や人材紹介会社からの応募者情報を自動で取り込み、一つのデータベースで管理する「応募者情報の一元管理」機能です。これにより、情報の散逸や転記ミスを防ぎます。
また、各応募者がどの選考段階にいるのかを可視化する「選考進捗管理」機能により、対応漏れをなくし、スムーズな選考を実現します。多くの担当者を悩ませる「面接日程の自動調整」機能は、カレンダーツールと連携し、候補者とのやり取りを最小限に抑えます。その他にも、専門知識なしで魅力的な採用サイトを作成する機能や、内定承諾率を高めるための「内定者フォロー」機能など、採用活動の川上から川下までを包括的にサポートする機能が備わっています。
ATSの基本的な機能として、求人情報の管理と外部媒体との連携が挙げられます。システム上で作成した求人情報を、連携している複数の求人媒体へ一括で掲載したり、更新したりすることが可能です。これにより、媒体ごとにログインして求人票を管理する手間を省けます。
また、各媒体からの応募があった際には、応募者情報が自動的にATSに取り込まれるため、手作業でのデータ入力や転記ミスがなくなります。さらに、多くのATSには自社の採用サイトを簡単に作成できる機能も備わっており、専門知識がなくても魅力的な求人ページを公開し、母集団形成の新たなチャネルとして活用することができます。
ATSの最も中核的な機能は、応募者に関するあらゆる情報を一元的に管理することです。さまざまな求人媒体、人材紹介会社、自社の採用サイトなど、複数の経路から集まる応募者のプロフィール、履歴書、職務経歴書といったデータを一つのプラットフォームに集約します。これにより、情報が分散することなく、必要な時に必要な情報を迅速に検索・確認できるようになります。
また、候補者とのメールやチャットでのやり取り履歴、面接の評価なども応募者情報に紐づけて管理できるため、担当者が変わっても過去の経緯を正確に把握することが可能です。閲覧権限の設定機能を使えば、個人情報を安全に取り扱いながら、関係者間での情報共有を行えます。
ATSを導入することで、応募者一人ひとりが現在どの選考段階にいるのか、その進捗状況をリアルタイムで可視化し、管理できます。書類選考、一次面接、最終面接、内定といった各ステップをフロー図のように表示し、誰がどこで滞留しているのかを一目で把握することが可能です。これにより、「面接後の合否連絡が遅れている」「次のステップへの案内が漏れている」といった対応の遅延や見落としを防ぎます。
また、面接官が入力した評価やフィードバックもシステム上で共有されるため、次の選考官はそれらの情報を踏まえた上で面接に臨むことができます。チーム全体で選考状況を正確に把握することで、一貫性のあるスムーズな選考プロセスを実現します。
採用担当者の業務の中でも特に時間のかかる作業の一つが、応募者と面接官双方のスケジュールを調整する業務です。ATSには、この煩雑な日程調整を効率化するための機能が搭載されています。多くのシステムでは、GoogleカレンダーやOutlookカレンダーといった外部ツールと連携し、面接官の空き時間を自動で抽出します。その候補日時を応募者に提示し、希望の時間を選んでもらうだけで調整が完了するため、何度もメールでやり取りする必要がありません。
さらに、「ジョブカン採用管理」のような一部のシステムでは、AIが自動で最適な面接日時を調整してくれる機能も備わっています。これにより、日程調整にかかる工数を大幅に削減し、面接設定率の向上にもつながります。

多くのATSには、プログラミングなどの専門知識がなくても、自社独自の採用サイトを簡単に作成・更新できる機能が備わっています。用意された豊富なデザインテンプレートやパーツをドラッグ&ドロップで組み合わせるだけで、企業の魅力や文化を伝えるオリジナルの採用ページを構築できます。
動画や社員インタビューといったコンテンツを掲載することも可能で、求人媒体だけでは伝えきれない情報を発信し、応募者の入社意欲を高めることができます。作成したサイトは、求人検索エンジンに自動で最適化される機能を搭載したシステムもあり、広告費をかけずに応募者を集める強力なツールとなり得ます。
採用活動は、内定を出したら終わりではありません。優秀な人材ほど複数の企業から内定を得ている可能性が高く、入社までの期間に内定辞退となるケースも少なくありません。ATSは、この重要な内定者フォローの期間においても役立ちます。システム上で内定者とのコミュニケーションを一元管理し、定期的な連絡や情報提供を計画的に行うことができます。
一部のシステムでは、内定者専用のマイページを作成し、限定コンテンツや動画を配信する機能も備わっています。これにより、内定者の帰属意識を高め、入社への不安を解消することが可能です。内定承諾後のやり取りの履歴も全て記録されるため、きめ細やかなフォローが実現し、内定辞退率の低下につながります。
数多く存在するATSの中から自社に最適なシステムを選ぶためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。まず最も重要なのは、「自社の採用規模や課題に合っているか」という点です。母集団形成、選考スピード、内定承諾率など、最も改善したい課題を明確にし、その解決に強みを持つシステムを選びましょう。
次に、採用担当者や面接官など、実際にシステムを使用するメンバーが「直感的に使える操作性」であることも欠かせません。無料トライアルなどを活用し、使用感を確認することが不可欠です。もちろん、「料金体系と費用対効果」も重要な判断基準であり、自社の予算内で最大の効果が見込めるかを検討します。
加えて、現在利用している求人媒体やカレンダー、チャットツールといった「外部サービスや既存システムとの連携」がスムーズに行えるかどうかも業務効率を左右します。最後に、導入後の活用を支える「サポート体制の充実度」も確認し、信頼できるパートナーとなるベンダーを選ぶことが成功の鍵となります。
ATSを選ぶ上で最も重要なのは、自社の採用活動の実態に合ったシステムを選ぶことです。まず、採用の主な領域が新卒なのか、中途なのか、あるいはアルバイトなのかによって、必要とされる機能は異なります。例えば、新卒採用であればLINE連携やイベント管理機能が、中途採用であれば多様な求人媒体との連携が重要になるでしょう。
また、「応募者が集まらない」「選考中の離脱が多い」「採用コストが高い」など、自社が抱える採用課題を明確にすることも不可欠です。母集団形成に強いタイプ、選考管理の効率化に特化したタイプ、データ分析機能が豊富なタイプなど、ATSにはそれぞれ得意分野があるため、自社の課題を解決できる強みを持ったシステムを選びましょう。
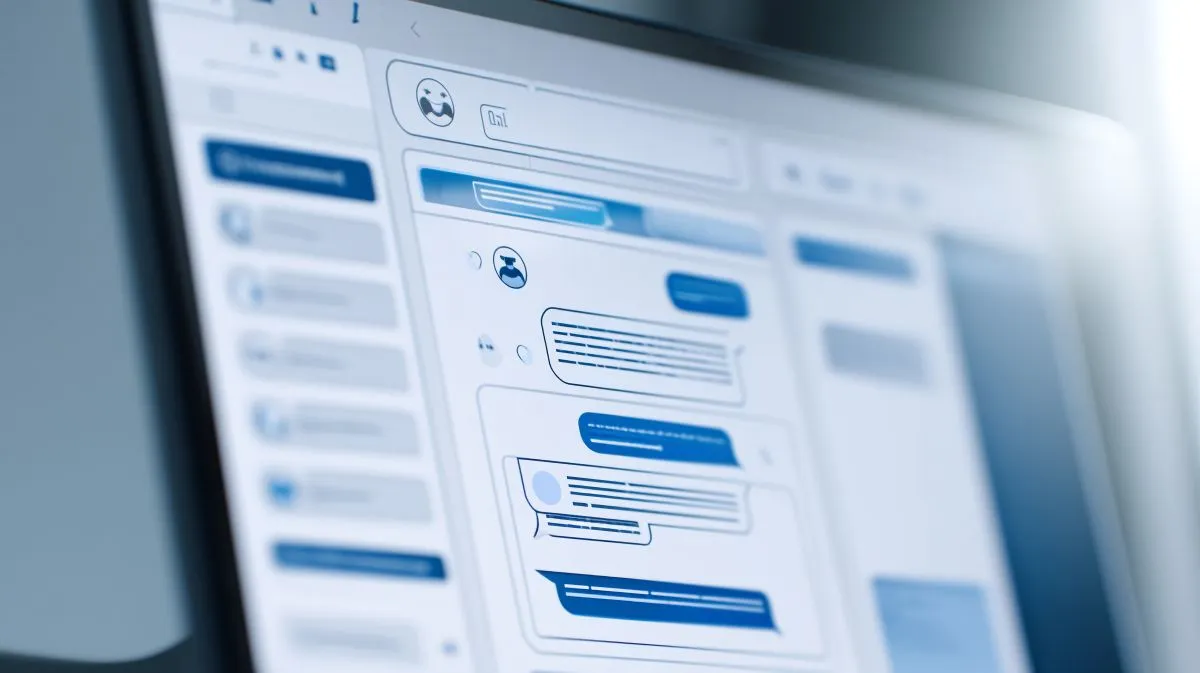
ATSは、採用担当者が日常的に最も多く触れるツールの一つです。そのため、機能の豊富さだけでなく、誰にとっても分かりやすく、直感的に操作できるかどうかが非常に重要な選定ポイントとなります。どれだけ高機能なシステムであっても、操作が複雑で使いこなせなければ、かえって業務効率を下げてしまうことにもなりかねません。選考に関わる面接官など、ITツールに不慣れなメンバーが利用することも想定し、シンプルで分かりやすい画面設計(UI)であるかを確認しましょう。
ほとんどのATSでは無料トライアル期間やデモ画面が用意されているので、導入を決定する前に必ず複数の担当者で実際にシステムに触れ、日々の業務をシミュレーションしながら操作性を確かめることを強くお勧めします。
ATSを導入する際には、料金体系を正確に理解し、自社の予算と照らし合わせて慎重に検討する必要があります。料金プランは、初期費用、月額基本料金、応募者数や機能に応じた従量課金など、サービスによって大きく異なります。月額料金だけでなく、将来的に採用規模が拡大した場合や、追加機能が必要になった場合の総コストもシミュレーションしておくことが重要です。
単に価格が安いという理由だけで選ぶのではなく、そのコストに見合った効果が得られるか、つまり費用対効果を長期的な視点で見極めなければなりません。解決したい採用課題に対して、システムの機能が十分であるか、導入によってどれだけの工数削減や採用コスト削減が見込めるかを具体的に算出し、投資対効果を判断しましょう。
ATSを最大限に活用するためには、現在社内で利用している他のシステムや外部サービスとの連携性が重要なポイントになります。まず、自社が頻繁に利用している求人媒体や人材紹介会社とスムーズに連携できるかを確認しましょう。連携できれば、応募者情報を手動で取り込む手間が省けます。
また、日常業務で使っているGoogleカレンダーやOutlookカレンダー、SlackやChatworkといったコミュニケーションツールと連携できるかもチェックすべきです。スケジュール調整や社内での情報共有が格段にスムーズになります。さらに、将来的に人事管理システム(HRM)などとデータを連携させる可能性も考慮し、システムの拡張性やAPI連携の可否も確認しておくと、長期的に活用しやすいシステムを選ぶことができます。
ATSは導入して終わりではなく、継続的に活用していくことで真価を発揮するツールです。そのため、導入後のサポート体制が充実しているかどうかは、非常に重要な選定基準となります。システムの使い方で不明な点があった場合や、トラブルが発生した際に、電話やメール、チャットなどで迅速に対応してくれる窓口があるかを確認しましょう。
サービスによっては、各企業に専任のカスタマーサクセス担当者がつき、システムの定着支援だけでなく、蓄積されたデータを基にした採用活動の改善提案まで行ってくれる場合もあります。自社のITリテラシーや採用ノウハウのレベルに合わせて、どこまで手厚いサポートが必要かを検討し、信頼できるパートナーとなり得るベンダーを選ぶことが成功の鍵です。

ATSの導入効果を最大化するためには、事前の準備と計画的な進行が不可欠です。まず、システム選定に着手する前に、「現在の採用プロセスを必ず整理・文書化する」ことが重要です。現状の業務フローと課題点を可視化することで、ATSに求めるべき機能が明確になります。
次に、候補となるシステムが見つかったら、「無料トライアル期間中に実際の採用業務で必ず検証する」ステップを踏みましょう。操作性や自社のフローとの適合性を現場の担当者自身が確認することで、導入後のミスマッチを防ぎます。また、過去の応募者データを移行する際は、「段階的に行い必ずバックアップを取る」ことで、データ損失などのリスクを回避できます。
セキュリティ面では、「社内の権限設定とセキュリティルールを事前に決める」ことが情報漏洩防止の観点から必須です。最後に、契約内容を精査し、「ベンダーのサポート体制と契約条件を詳細まで確認する」ことで、長期的に安心してシステムを利用できる基盤が整います。
ATS導入を成功させるためには、システム選定に入る前に、まず自社の現在の採用プロセスを徹底的に整理し、文書化することが不可欠です。どの求人媒体を利用し、誰がどのように応募者と連絡を取り、どのようなステップで選考が進み、誰が承認するのか、といった一連の流れをフロー図などで可視化します。この作業を通じて、「どこに時間がかかっているのか」「どの部分にミスが発生しやすいのか」といった現状の課題が明確になります。
課題がはっきりすれば、ATSに求めるべき機能(例えば、日程調整の自動化や情報共有の円滑化など)もおのずと見えてきます。現状把握を怠ったまま導入を進めると、自社の実態に合わないシステムを選んでしまい、宝の持ち腐れになりかねません。
多くのATS提供ベンダーは、無料のトライアル期間やデモ環境を用意しています。この機会を最大限に活用し、実際の採用業務を想定した検証を行うことが極めて重要です。単に機能を一つずつチェックするだけでなく、採用担当者や面接官など、実際にシステムを利用する複数のメンバーで触ってみることが大切です。
応募者情報の登録から、面接日程の調整、評価の入力、候補者への連絡まで、一連の業務フローを実際にシミュレーションしてみましょう。その中で、「操作は直感的で分かりやすいか」「自社の採用フローに違和感なくフィットするか」「レスポンス速度に問題はないか」といった点を厳しく評価します。この検証作業によって、導入後のミスマッチを大幅に減らすことができます。
ATSを導入する際には、過去の応募者データなどを新しいシステムへ移行する作業が必要になる場合があります。このデータ移行は、慎重に進めなければトラブルの原因となります。一度に全てのデータを移行しようとすると、予期せぬエラーが発生した際に原因の特定が難しくなったり、業務への影響が大きくなったりする可能性があります。そのため、まずは一部のデータでテスト移行を行い、問題がないことを確認してから、段階的に移行作業を進めるのが安全です。
また、最も重要なのは、移行作業を開始する前に、必ず既存データの完全なバックアップを取得しておくことです。万が一、移行に失敗してデータが破損・消失してしまった場合でも、バックアップがあれば元の状態に復旧できるため、最悪の事態を避けることができます。

ATSには、役員、人事部長、採用担当者、現場の面接官など、さまざまな役職のメンバーがアクセスします。しかし、全てのメンバーが全ての情報にアクセスできる状態は、情報漏洩のリスクを高めます。特に、応募者の個人情報や給与といった機密性の高い情報が含まれるため、セキュリティ対策は万全でなければなりません。
ATS導入前には、「誰がどの情報まで閲覧・編集できるのか」という権限設定のルールを社内で明確に定めておく必要があります。例えば、面接官は担当する候補者の情報のみ閲覧可能にし、給与情報は人事担当者しか見られないようにするなど、役職に応じた適切な権限を付与します。このルールを事前に決めておくことで、スムーズかつ安全なシステム運用が可能になります。
ATSは長期的に利用するシステムであり、提供会社(ベンダー)とは長い付き合いになります。そのため、契約前には、ベンダーのサポート体制と契約条件を隅々まで確認することが重要です。サポート体制については、電話やチャットなど問い合わせ方法の多様性、対応時間、返答の速さなどをチェックします。専任の担当者がつくかどうかも大きなポイントです。
契約条件に関しては、最低利用期間の縛りや、解約時の手続き、データの取り扱い(解約後にデータをエクスポートできるかなど)について、書面で詳細に確認しましょう。特に、料金体系については、基本料金に含まれる機能の範囲や、応募者数が増えた場合の追加料金などを正確に把握しておかないと、後々予算オーバーとなる可能性があるので注意が必要です。
採用管理システム(ATS)は、複雑化する採用業務を効率化し、担当者の負担を軽減する強力なツールです。自社の採用課題を明確にし、本記事で解説した機能や選び方のポイントを参考にすることで、最適なシステムの導入が可能になります。戦略的な採用活動を実現するための第一歩として、ATSの活用をぜひご検討ください。
「どのATSを選べば良いか分からない」「導入サポートも重視したい」という企業様には、DYMの採用管理ツール「rakusai」がおすすめです。「rakusai」は、採用業務の効率化はもちろん、手厚いサポートで導入から活用までを支援します。貴社の採用課題解決に向けて、まずはお気軽にご相談ください。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。