Page Top
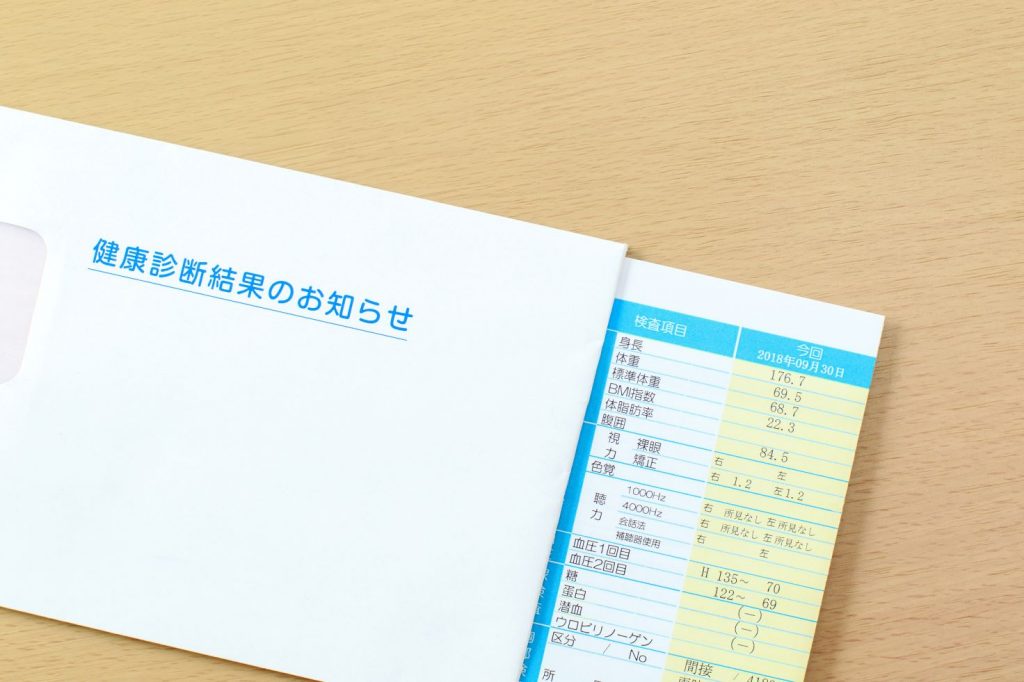
企業が従業員の雇用時に実施する入社前健康診断は、従業員の健康状態を把握し、職場でのリスクを未然に予防します。当記事は、入社前健康診断の概要や対象者、診断項目、費用負担について詳しく解説します。
よくある質問や受診に際してのポイント、企業向けの診断結果の活用方法なども紹介するため、入社前健康診断の理解にお役立てください。
<この記事で紹介する3つのポイント>
目次
入社前健康診断は、労働安全衛生法に基づき企業が従業員の雇用前に実施する健康診断です。
企業は従業員に対して定期的な健康診断を行う義務がありますが、入社前の段階でも健康診断を行う必要があります。
ここからは、入社前健康診断について以下の3点を解説します。
基礎的な内容をしっかりと理解し、健康診断の正しい実施に努めましょう。
| 法的根拠 | 労働安全衛生法第66条労働安全衛生規則第43条 |
| 目的 | 従業員を適切な職場に配置する従業員自身が自分の健康を適切に管理する |
入社前健康診断は企業の義務として、労働安全衛生法第66条と労働安全衛生規則第43条に定められています。実施する主な目的は、以下の2つです。
入社前健康診断を行うのはあくまでも入社後の配置や健康管理のためであり、応募者の採否を決定するためではないと覚えておきましょう。
企業にとって入社前健康診断は、以下2つの観点からリスク管理の一環として重要な役割を果たします。
従業員を健康状態に見合った場所に配置できれば、生産性の向上や離職率の低下が見込めます。また、従業員が何らかの病気になった時、職場の影響を疑われる可能性があります。その際、入社前健康診断の結果は職場の影響を考えるひとつの基準となるでしょう。
一般的な入社前健康診断は、雇入れの直前または直後に実施します。ただし、従業員が入社3ヶ月以内に受診した健康診断の結果を提出すれば、同じ項目の内容は省略可能です。特に、重労働や危険を伴う業務に従事する場合には、事前の健康状態の把握が欠かせません。実施する期限について「入社後何日までに」という記載はないものの、「従業員の適正な配置」という観点からすると、遅くとも配属を決定する前には実施するべきでしょう。

入社前健康診断を実施する際は、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、対象者、診断項目、費用負担の観点から入社前健康診断について解説します。
入社前健康診断の対象者は、企業が新たに採用するすべての常時使用する従業員です。たとえば正社員のみでなく、パートタイムや、契約社員なども含まれます。具体的には、以下の2つをどちらも満たすものとされています。
また、1週間の労働時間が2分の1以上の従業員については、義務ではないものの、健康診断の実施が望ましいとされています。
従業員の種類ごとに、入社前健康診断の詳細をまとめました。
【正社員】
正社員を採用する場合、企業は必ず入社前健康診断を行います。
【パートタイム・アルバイト】
正社員でないパートタイムやアルバイトも、契約期間の定めがないもしくは1年以上の雇用が見こまれる場合は入社前健康診断が必要です。
【契約社員・派遣社員】
契約社員や派遣社員も、正社員と同様に入社前健康診断の対象です。派遣社員の場合、派遣先企業が健康診断を実施する場合と、派遣元企業が実施する場合があります。いずれにしても、契約社員や派遣社員が業務に適した健康状態であるかの確認が重要です。
入社前健康診断は、基準を満たすすべての新規採用者に対して行われます。企業は従業員の健康を守るために必要な対応を取る責任があるのです。
入社前健康診断で実施される診断項目は、労働安全衛生法に基づいて以下のように定められています。
| 既往歴及び業務歴の調査 | 雇入れまでにかかった疾病を経時的に調査雇入れまでに従事したことのある主要な業務についての経歴を調査 |
| 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | 当該労働者の予定する業務に必要な身体特性の把握に必要な検査を含む検査項目の選定は医師の判断に委ねられる |
| 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 | 体形の変化や生活習慣病のリスクを把握できる |
| 胸部エックス線検査 | 肺や心臓の状態を確認する検査結核や肺がん、心臓肥大などを早期に発見できる |
| 血圧 | 高血圧や低血圧のリスクを確認心血管疾患のリスクを評価できる |
| 貧血検査 | 血色素量及び赤血球数を検査高齢期に増加する貧血や食生活の偏り等による貧血を把握できる |
| 肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GPTを検査肝機能障害を早期に把握できる |
| 血中脂質検査 | LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライドを検査 |
| 血糖検査 | HbA1cでも可糖尿病のリスクや状態を把握できる |
| 尿検査 | 尿中の糖及び蛋白の有無を検査腎機能低下や糖尿病のリスクを把握できる |
| 心電図検査 | 不整脈、虚血性心疾患、高血圧に伴う心臓の異常を把握できる標準的には安静時の標準12誘導心電図を記録する |
上記の項目は全項目実施する必要があり、省略はできません。ただし、労働者が3か月以内に自分で受診した健康診断の結果を提出した場合は、同じ項目を省略できます。
入社前健康診断の費用は、企業が負担します。企業が費用を負担すれば、従業員の負担が軽減し、安心して健康診断を受けられるでしょう。
【企業の負担額】
健康保険が適用されないため、健康診断の費用は診断項目や利用する医療機関によって異なります。自費の場合、金額の相場は10,000円から15,000円程度ですが、加入する健康保険組合の補助が使えると負担額の軽減が可能です。基本的な診断項目のみを行う場合、費用は比較的低額です。追加の検査が必要な場合や特定の医療機関を利用する場合は、高額になるケースもあります。
【費用負担の法的根拠】
企業が健康診断の費用を負担する義務は、労働安全衛生法第66条に明記されています。国は従業員個人ではなく企業に健康診断の義務を課しているのが特徴です。原則として、従業員に健康診断の費用を請求することはできません。
【企業にとってのメリット】
企業が健康診断の費用を負担することで、従業員の健康状態を把握し、リスク管理を徹底できます。適正に合わない配置を避けることで労働災害や健康障害のリスクが低減し、職場全体の安全性も向上するでしょう。

入社前健康診断に関して、求職者や企業が抱える疑問は多岐にわたります。ここでは、入社前健康診断でよくある質問にお答えします。
入社前健康診断の結果を採用の可否に影響させることは、望ましくありません。
なぜなら、基本的に入社前健康診断は応募者の採用を決定するために実施するものではないためです。入社前健康診断は、適切な配置と労働者の健康状態把握のために行うものであり、「採用選考のための健康診断」ではないことを理解しておきましょう。
なお、過去に労働省(現在の厚生労働省)職業安定局は「採用選考時に労働安全規則第43条を根拠として採用可否決定のための健康診断を実施することは、適切さを欠くものである」といった事務連絡を出しています。
入社前健康診断で異常や再検査、要治療の判定があった場合、まずは本人に結果を伝え、医療機関での精密検査や治療を促します。その上で、就業場所の変更や労働時間の調整など、本人の健康維持のために必要な配慮を検討するのが望ましい対応といえるでしょう。
基本的に、入社前健康診断は健康保険の適用外です。
なぜなら、健康保険が適用されるのは、病気やケガの治療のために必要な診療に限られるためです。入社前健康診断は、疾病治療や予防を目的とした医療行為ではないため、健康保険の適用外となります。また、前述したように入社前健康診断の費用は、原則として企業負担です。
ただし、企業が加入する健康保険組合によっては、定期健康診断の補助制度を利用できる場合があります。金額や利用条件などは保険組合によって異なるため、確認してみるとよいでしょう。
前述の条件を満たす従業員を雇い入れた場合、入社前健康診断は法律で定められた義務にあたります。つまり従業員は、企業に自分の健康状態を提出する義務があるといえるでしょう。
入社前健康診断を受診する際は、いくつかのポイントに留意する必要があります。ここでは、適切な受診時期や受診場所、検査に要する時間、結果が出るまでの時間について詳しく説明します。
どのタイミングで健康診断を受けるのがベストなのかは、企業に確認するのが確実です。
入社前健康診断を受ける基本的な時期は、内定が出た後から入社前までの期間です。しかし、自分で受けた健康診断を入社前健康診断として使用する場合、「健康診断を受けてから3か月以内」という規定に注意する必要があります。健康診断書に有効期限が設けられているケースもあります。受診が早すぎる場合、入社直前に再度健康診断を受けなければならない可能性もあるのです。
また、受診が遅すぎる場合も注意が必要です。健康診断書の提出後に最終的な採用手続きを進める場合、企業が手続きを進めるのに一定の期間が必要になります。また、新年度の前など、健康診断の希望者が多い時期は診断の予約が取りにくいケースも考えられます。
内定確定日と入社日が近い場合は、健康診断の指示を受けた地点で速やかに診断の予約をするのがおすすめです。
受診が早すぎる場合、遅すぎる場合に起こりうる可能性を以下にまとめました。
| 受診が早すぎる | 健康診断書の期限が切れて、再受診が必要になる可能性がある |
| 受診が遅すぎる | 新年度の前後などは予約が取りにくいケースがある最終的な採用手続きに時間がかかる |
スムーズに入社手続きを進められるよう、適切な受診タイミングを事前に確認しましょう。
入社前健康診断を受ける場所は、企業が指定した医療機関やクリニックが一般的です。企業によっては、提携する特定の医療機関での受診を求める場合もあります。
企業が提携する医療機関を受診する場合、診断内容や費用があらかじめ決められているため、手続きがスムーズです。特に大企業や公的機関は複数の医療機関と提携するケースも多く、従業員が自宅や勤務先からアクセスしやすい場所を選べるでしょう。
提携医療機関が指定されていない場合は、自分で受診場所を選ぶ必要があります。自分で選ぶ際は、以下の2点は必ずチェックしましょう。
また、利便性を考えるとアクセスの良さや診療時間なども重要です。自分にとって最適な受診場所を選んでみてください。
一部の医療機関では、オンラインを活用した入社前健康診断を提供しています。上手に活用すれば、効率的に受診できるでしょう。
入社前健康診断にかかる時間は、受診する医療機関や診断項目によって異なります。一般的には、1時間から2時間程度と考えておきましょう。
基本的な健康診断のみであれば、1時間以内で終了するケースが一般的です。視力・聴力検査や血液検査、尿検査、身体計測などの標準的な項目は比較的短時間で完了できます。ただし、心電図検査や胸部X線検査、詳細な血液検査などは、時間がかかることもあります。
受診者が多い時期や予約が集中する時間帯は、待ち時間が発生する可能性もあります。予定どおりの時間に終わらない可能性もあるため、受診時は余裕を持ったスケジュール設定が重要です。また、診断結果が即日発行されない場合は、後日結果を受け取りに行く、郵送を待つなどのケースもあります。
その場で検査結果が出ない可能性も考慮して計画を立てるようにしましょう。
入社前健康診断の結果が出るまでの時間は、受診する医療機関や検査内容によって異なります。一般的には、1週間から2週間程度で結果が出るケースが多いです。
一部の医療機関では、診断結果の即日発行が可能です。ただし、即日発行ができるのは基本的な診断項目に限られる場合が多く、詳細な血液検査や特殊な検査が含まれる場合は、後日結果を受け取る形になります。即日発行が可能かどうかは、受診前に医療機関に確認しておきましょう。
医療機関によっては、診断結果を郵送で送付するケースがあります。受診から結果が届くまでの一般的な期間は1週間から2週間ほどです。郵送での結果受け取りを希望する場合は、正確な住所を記入し、結果が確実に届くよう手配しましょう。
診断結果が遅れる場合、結果が遅れる理由や状況を企業に報告して提出期限を延長できないか交渉する必要があります。結果が遅れた時に困らないよう、早めの受診が大切です。
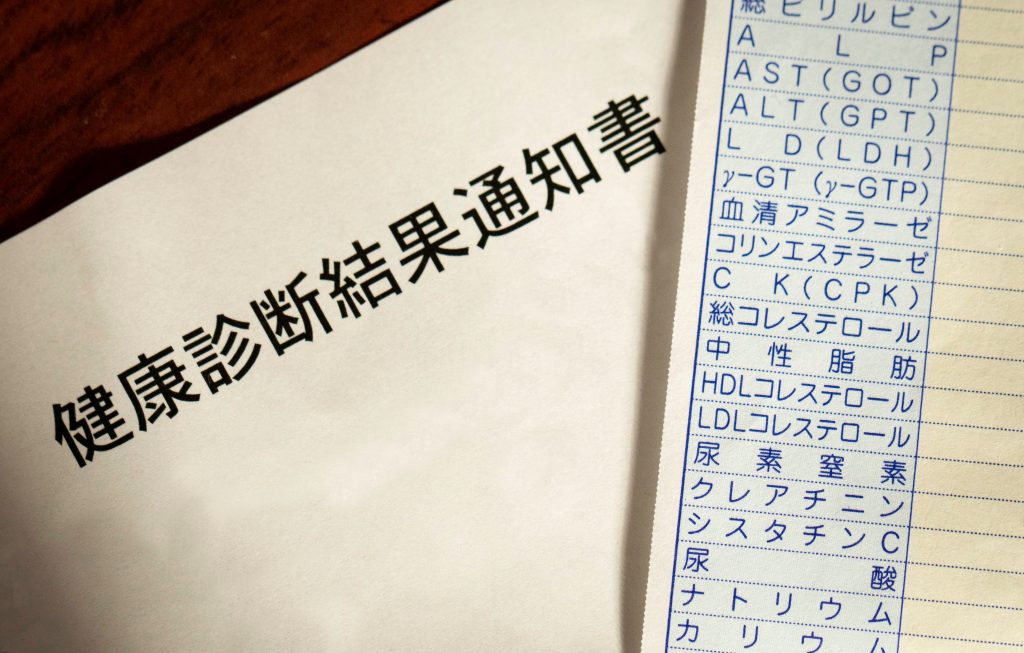
ここからは、企業向けに診断結果の主な活用方法を3つ紹介します。
入社前健康診断の結果は、企業にとって重要な情報源です。上手に活用して、マネジメントに役立ててみてください。
診断結果に基づいて、従業員が特定の業務に適した健康状態であるのかを確認し、必要に応じて業務内容や従業員の配属を調整します。たとえば重労働が困難と分かった場合は、体力的に無理のない部署に配置する、適切なサポートを提供するなどの対処を検討してみてください。
入社前健康診断の結果は、従業員の健康リスク把握や、労働災害や健康障害のリスク低減にも利用できます。特に、生活習慣病のリスクが高い従業員に対しては、健康管理の指導や定期的なフォローアップにより、健康状態の改善が期待できるでしょう。
診断結果をもとに従業員が安心して働ける職場環境を提供すれば、従業員満足度も向上します。健康管理に対する企業の姿勢が従業員に伝われば、企業への信頼が高まり、長期的な雇用関係を構築できます。企業は、入社前健康診断の結果を積極的に活用し、従業員の健康管理とリスクマネジメントに役立てることが重要です。
入社前健康診断を受けずに入社してしまうと、従業員の健康状態が把握できず、リスク管理が困難になります。また、入社前健康診断は企業の義務として定められているため、未受診の場合は労働安全衛生法第120条によって罰金が課される可能性もあります。
未受診を防止する主な方法は、以下の4つです。
これから紹介する方法を活用し、従業員の未受診を防ぎましょう。
重要性を知らないと、従業員が入社前健康診断を受けない可能性があります。そのため、入社前健康診断の重要性を従業員に周知しましょう。具体的には、健康診断が採用プロセスの一環であり、従業員の健康と安全を守るために必要な手続きであると説明するのがおすすめです。
企業の採用説明会や面接時に、健康診断の意義と受診の必要性を強調すると、従業員の理解を深められるでしょう。
入社前健康診断の日程が決まり次第、従業員に受診のリマインダーを送付するのも、未受診のリスクを減らす有効な方法です。たとえば、メールや電話で受診場所や期限を伝える方法があります。診断結果が従業員に直接渡される場合は、速やかに診断結果を企業に提出する旨も伝えましょう。
受診が困難な従業員に対しては、受診のサポートを検討しましょう。提携医療機関の紹介や受診日の調整、交通費の補助などのサポートが有効です。
未受診者が発生した場合は、速やかに連絡を取り、受診の再調整を行います。受診が遅れる理由を確認して必要な個別対応を行うと、すべての従業員が健康診断を受けられるでしょう。
健康診断を受けずに入社することがないよう、採用プロセスの厳格な管理が大切です。
企業は、未受診を防止するために積極的な対応を行い、従業員の健康管理を徹底しましょう。
入社前健康診断は、企業が従業員を採用する際に必要なプロセスです。健康診断によって従業員の健康状態が把握でき、適切な配置や職場におけるリスク軽減が可能です。健康診断の未受診を予防する工夫も行い、企業の義務をしっかりと果たしましょう。
DYMの医療事業では、タイ・香港・アメリカ・ベトナム滞在者向けの海外クリニック事業を行っています。現地では受けにくい日本基準の健康診断も取り扱っており、安心して受診できると高い評価を受けています。DYMの各クリニックの詳細は、以下よりご覧ください。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。