Page Top
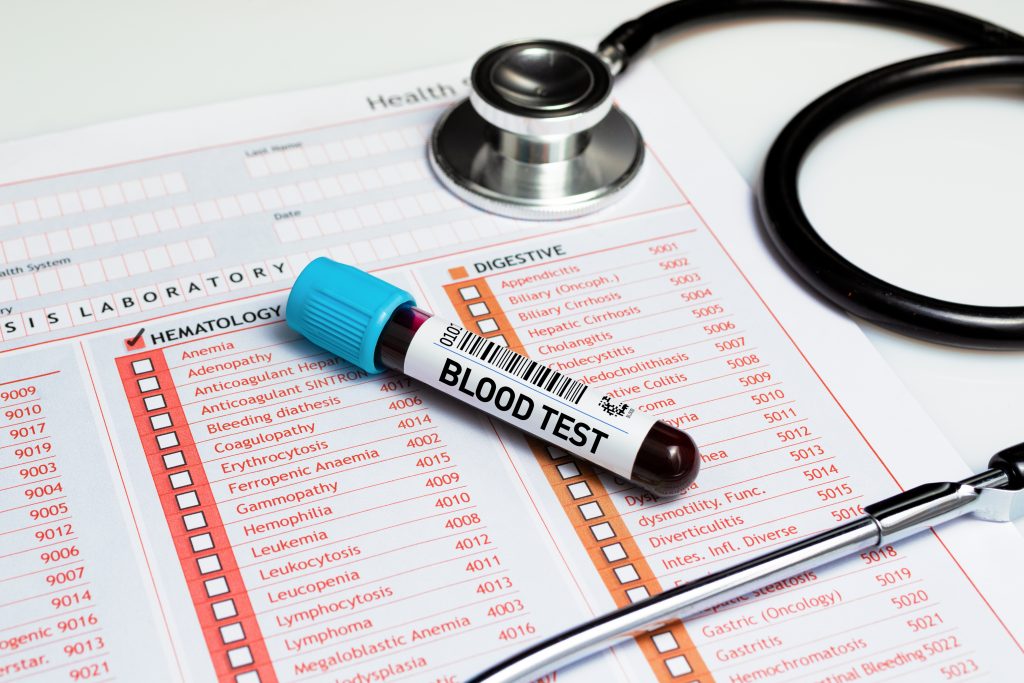
健康診断の血液検査は、体内の健康状態を把握するための重要な手段です。本記事では、血液検査で何がわかるのか、そしてその結果の見方や注意点を詳しく解説します。血液検査に関する基礎知識を身に付け、結果を理解することで、検査結果を自身の健康管理に役立てられるようになるでしょう。
特に、検査結果に異常が見つかった場合の対応方法についても解説するため、血液検査を検討している方は参考にしてみてください。
<この記事で紹介する3つのポイント>
目次
血液検査は、健康診断や定期的な健康チェックの一環として広く行われています。血液を採取し、その成分を分析することで、健康状態を詳しく把握できます。血液検査の基礎知識について、以下の内容を知っておくとよいでしょう。
それぞれ説明します。
血液検査は、体の中で起きている変化を把握するのに役立つでしょう。わずかな血液サンプルから、多くの情報を得ることができます。実際に、血液検査で得た情報から以下のことにつながります。
血液検査は、体内のさまざまな状態を正確に把握するための重要な検査方法と言えるでしょう。血液は体内を循環し、各組織に栄養や酸素を供給しています。そのため、血液の状態を分析することで、体のどこかに異常がある場合、早期に発見することができます。
糖尿病や高血圧といった生活習慣病は、初期段階では自覚症状が少ないのが特徴です。しかし、血液検査で血糖値やコレステロール値を調べることで、病気の兆候を早期に察知できます。また、肝臓や腎臓の機能異常も、血液検査で発見可能です。血液検査は、病気が進行する前に対処することができ、健康を維持するための重要な手段となっています。
血液検査では、多くの病気の徴候を見つけられるでしょう。体の異変を早い段階で発見できるため、深刻な病気の予防にもつながります。血液検査で見つかる病気の例として、以下の病気が代表的です。
| 貧血 | 赤血球に関する値が低い場合、貧血の可能性がある |
| 肝炎や肝機能障害 | 肝臓の酵素値が異常な場合、肝炎や肝機能障害の可能性がある |
| 腎臓病 | クレアチニン値や尿素窒素値の異常は腎臓機能の低下を示す |
| 脂質異常症 | 血中脂肪値が高いと動脈硬化のリスクが高まる |
| 糖尿病 | 血糖値が正常範囲を超えている場合、糖尿病の可能性がある |
これらの病気は、初期段階では自覚症状がないことも多いです。だからこそ、定期的な血液検査が重要です。健康であると思っていても、年に1回は血液検査を受けてみましょう。
血液検査の前日に食事を控えるのは、正確な検査結果を得るためです。食事の影響を受けやすい検査項目があるため、空腹時の状態で測定しなければなりません。具体的には、以下のような項目が食事の影響を受けやすいです。
もし食後に血液検査を行うと、血糖値や中性脂肪値が高く出た場合、それが通常の状態なのか、単に食事の影響なのか判断するのが難しいです。そのため、空腹時の状態で測定することで、正確に検査できます。検査前日の食事制限は面倒に感じるかもしれませんが、絶食を守りましょう。

血液検査では、さまざまな項目を調べられます。各項目は特定の臓器や代謝機能を評価するために使用され、これによって体内の状態を総合的に把握できるでしょう。血液検査の主な項目は、以下の5つです。
それぞれ説明します。
血球関連の検査は、血液中の細胞の状態を調べるものです。赤血球、白血球、血小板の数や形態を確認することで、さまざまな病気を発見できます。血球関連の検査では、主に以下の項目をチェックします。
| 検査項目 | 正常値 |
|---|---|
| 赤血球数(RBC) | 男性:377~555×104/μL女性:355~503×104/μL |
| 白血球数(WBC) | 3,100〜8,400/μL |
| 血小板数(PLT) | 14.5〜32.9万/μL |
| ヘモグロビン(Hb) | 男性:13.7~16.8g/dL女性:11.6~14.8g/dL |
| ヘマトクリット(Ht) | 男性:40.7~50.1%女性:35.1~44.4% |
赤血球の数が少ないのは貧血徴候かもしれません。逆に、赤血球が多すぎる場合は、多血症や脱水症状が疑われるでしょう。
白血球数が増加していると、細菌感染症や白血病が考えられ、減少している場合は免疫不全やウイルス感染症の可能性があります。血小板の数が異常な場合、出血傾向や血栓症のリスクが考えられる状況です。
ヘモグロビンとは、赤血球に含まれるタンパク質のことで、酸素を運搬する役割を担っています。ヘモグロビンは貧血の診断や全身の酸素供給能力を評価できます。
ヘマトクリットとは、血液中の赤血球の占める割合を示す指標のことです。具体的には、全血液量に対する赤血球の容積比を表すものです。ヘマトクリットは通常パーセンテージで表され、血液中の赤血球の量や粘度を評価するために使用されます。ヘマトクリットは貧血、脱水、多血症などの診断の判断材料になります。
肝臓関連の検査では、肝臓の機能や状態を評価します。肝臓は体内の解毒作用を担う重要な臓器なため、定期的にチェックしましょう。肝臓関連の主な検査項目は、以下のとおりです。
| 検査項目 | 正常値 |
|---|---|
| 総蛋白(TP) | 6.5~8.0g/dL |
| アルブミン(ALB) | 3.9~5.0g/dL |
| AST(GOT) | 30IU/L以下 |
| ALT(GPT) | 30IU/L以下 |
| γ-GTP | 男性:50IU/I以下女性:30IU/I以下 |
| ALP | 38~113U/L |
| 総ビリルビン(T-bil) | 0.4~1.5mg/dL |
総蛋白は血中のすべてのタンパク量を示す値です。低値の場合、栄養失調やネフローゼ症候群、悪性腫瘍などが考えられるでしょう。一方、高値の場合は多発性骨髄腫や慢性的な炎症、体内の水分不足などが疑われる状況です。
血液中のタンパク質の中で最大の割合を占めるのがアルブミンで、その生成は肝臓で行われます。アルブミンの値は、肝機能障害や栄養不良、ネフローゼ症候群などの際に低下します。
ASTは心臓や筋肉、肝臓に豊富に存在する酵素で、GOTとも呼ばれているものです。ALTは主に肝臓に多く見られる酵素で、GPTとしても知られています。これらの数値が上昇している場合、急性または慢性の肝炎、脂肪肝、肝臓がん、アルコールによる肝炎などの可能性があります。
γ-GTPはタンパク質を分解し、肝臓の解毒作用に関与する酵素の一つです。肝臓や胆道系に問題がある場合、血中のγ-GTP値が上昇します。高値を示す場合、アルコールによる肝障害や慢性肝炎、胆汁の流れが滞る状態、薬物による肝障害などが考えられるでしょう。
ALPは体内のほぼすべての器官に含まれる酵素であるものの、特に肝臓、胆管、骨、胎盤に多く分布しています。これらの器官に疾患がある場合、高値を示します。
総ビリルビンは、赤血球が寿命を迎え分解される際にヘモグロビンから生成される物質です。血中ビリルビン値を測定することで、黄疸の程度を含め、肝臓や胆道系の疾患の有無やその重症度を評価することができます。
肝臓は体内の解毒作用を担っており、肝酵素の異常は肝細胞が破壊されていることを示します。肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど症状が出にくく、慢性的な肝疾患が進行すると肝硬変や肝がんのリスクが高まるため、定期的なチェックが欠かせません。
腎臓関連の検査は、腎臓の働きを確認するためのものです。腎臓は体内の老廃物を排出する役割があり、その機能が低下すると全身に影響を及ぼします。腎臓関連の主な検査項目は、以下のとおりです。
| 検査項目 | 正常値 |
|---|---|
| クレアチニン(CRE) | 男性:0.65~1.07mg/dL女性:0.46~0.79mg/dL |
| 尿素窒素(BUN) | 8~20mg/dL |
| 尿酸(UA) | 男性:3.4~7.0mg/dL女性:2.6~5.5mg/dL |
| eGFR(推算糸球体濾過量) | 60mL/min/1.73m²以上 |
クレアチニンは、筋肉中のクレアチンから生成される物質です。腎臓によってろ過され体外へ排出されるため、腎機能を測る重要な指標として広く用いられています。
尿素窒素は、体内でタンパク質が代謝された際に生じる老廃物の一種です。通常、腎臓を通じて尿中に排出されるものの、腎機能が低下すると血中濃度が上昇する傾向にあります。
尿酸は、細胞核に含まれるプリン体の分解によって生成される物質です。尿酸の産生増加、組織の崩壊、あるいは腎臓での排泄機能低下などにより血中濃度が上昇します。高濃度の尿酸は関節に蓄積して痛風を引き起こしたり、腎臓に沈着して腎機能障害の原因となったりします。また、長期的な高尿酸血症は動脈硬化のリスク因子となるかもしれません。
e-GFRは、腎臓の老廃物排出能力を評価する指標となっています。血清クレアチニン値、年齢、性別をもとに算出されるもので、慢性腎臓病(CKD)の重症度を判定する際に活用されることが多いです。
腎臓関連の検査項目では、血液中のクレアチニンや尿素窒素などが測定され、腎臓の機能が評価されます。これにより、腎臓が老廃物を適切に排出しているかどうかを確認できます。クレアチニンや尿素窒素の値が高い場合、腎不全や腎炎の可能性が考えられるでしょう。
脂質関連の検査は、血液中の脂質の量を測定するものです。脂質の異常は動脈硬化や心臓病のリスクを高めます。脂質関連の主な検査項目は、以下のとおりです。
| 検査項目 | 正常値 |
|---|---|
| 中性脂肪(TG) | 空腹時30〜149mg/dl |
| HDLコレステロール(HDL-C) | 40mg/dL以上 |
| LDLコレステロール(LDL-C) | 60~119mg/dL |
| nonHDLコレステロール(nonHDL-C) | 90〜149mg/dL |
過剰なカロリー摂取やアルコールの摂取により、余ったエネルギーは中性脂肪として体内に貯蔵されます。さらに蓄積が進むと、皮下脂肪や肝臓に蓄えられていきます。中性脂肪の上昇は、内臓脂肪の増加や脂肪肝の発症リスクを高めるでしょう。
コレステロールとは、体内のほぼすべての細胞に存在する脂質の一種のことです。体内にはさまざまな種類のコレステロールが存在します。
HDLコレステロールは、血管壁に付着したコレステロールを血中に回収する機能を持つため、「善玉コレステロール」と呼ばれることも多いでしょう。高値であると動脈硬化の予防に貢献するものの、低値の場合は血管壁へのコレステロール沈着が促進され、動脈硬化の進行が加速する可能性があります。
LDLコレステロールは、コレステロールを末梢組織へ運搬する役割を担うのが特徴です。血液中に含まれるLDLコレステロールの数値が高くなると、心臓の冠状動脈に関わる病気を引き起こす可能性があります。高値の場合は、バランスの取れた食生活と適切な運動習慣を心がけることが推奨されます。
nonHDLコレステロールは、LDLに限らず、動脈硬化を引き起こしたり促進したりする可能性があるすべてのコレステロールを示す値です。総コレステロール値からHDLコレステロール値を差し引くことで算出されます。
糖代謝関連の検査は、体内での糖の処理能力を調べるものです。血糖値が高い状態が続くと、糖尿病やその合併症のリスクが高まります。糖代謝関連の主な検査項目は、以下のとおりです。
| 検査項目 | 正常値 |
|---|---|
| 空腹時血糖(GLU) | 73~109mg/dL |
| HbA1c | 4.6~6.2% |
血糖は体内の主要エネルギー源で、グルコースとも呼ばれる物質です。食事後に血中グルコース濃度は増加するものの、インスリンの機能により正常値に戻ります。しかし、糖尿病によりインスリンの効果が低下すると、血中グルコース濃度が高くなります。
HbA1cは、ヘモグロビンとブドウ糖が結合したものです。赤血球の寿命である約120日間、この物質は安定した状態を保ちます。そのため、HbA1cは過去1~2ヶ月の平均血糖値を反映しており、長期間の血糖コントロールの状態を確認するのに有用です。
空腹時血糖検査とHbA1cの結果を組み合わせることにより糖尿病の診断が可能です。
糖尿病は進行すると心血管疾患や腎臓病、視力低下など、さまざまな合併症を引き起こすかもしれません。血糖値やHbA1cが高い場合、生活習慣の改善や薬物療法が必要になるでしょう。

血液検査で異常が見つかると、不安になるかもしれません。しかし、すぐに深刻な病気かもしれないと心配する必要はありません。異常が見つかった場合の対応は、主に以下の4つに分類されます。
それぞれ説明します。
軽度の異常である場合は、しばらく様子を見る場合もあるでしょう。一時的な体調の変化や生活習慣の乱れ、ストレスなどが原因で数値が変動する場合もあるためです。経過観察が必要なケースは、以下のとおりです。
軽微な異常値である場合、すぐに治療を開始するのではなく、しばらく様子を見ることもあります。経過観察の期間中は、生活習慣の改善や定期的な再検査を行い、状態が悪化しないかどうかを確認します。経過観察を行うことで、一過性の変化を見極め、本当に治療が必要かどうかを判断できるでしょう。
検査結果に疑問がある場合や、確認が必要な場合は再検査を行います。再検査によって、最初の異常値が本当に問題なのかどうかを判断できるためです。再検査が必要になるケースは、以下のとおりです。
経過観察を行った結果、異常値が改善しない場合や、新たな異常が発見された場合には、再検査が必要となります。再検査では、最初の検査で得られたデータを再確認し、より詳しい検査を行うことで、異常の原因を特定することが目的です。
最初の検査で誤って採取された血液サンプルや、検査機器の不具合が原因で異常値が出た可能性も否定できません。再検査を行うことで、より信頼性の高い結果を得られ、必要に応じて治療方針を決定することができます。
血液検査で異常が見つかり、原因の特定が必要な場合は精密検査を行います。精密検査では、より詳しい検査や別の種類の検査を組み合わせて調べます。精密検査が必要になるケースは、以下のとおりです。
再検査でも異常が見つかった場合や、より詳細な診断が必要とされる場合には、精密検査が行われます。精密検査では、CTスキャンやMRI、内視鏡検査など、より高度な医療機器の使用によって体内の状態を詳細に調べます。
精密検査を行うことで、通常の血液検査では発見できなかった病変や異常を特定することができるでしょう。肝臓や腎臓の異常が疑われる場合、超音波検査やCTスキャンを用いて、臓器の状態を詳しく観察できます。
精密検査の結果、病気が見つかった場合は治療が必要になります。治療の内容は、病気の種類や進行度によって大きく異なります。治療が必要になるケースは、以下のとおりです。
精密検査の結果、異常が確定した場合には、適切な治療が必要となります。治療は、病気の種類や進行度によって異なるものの、薬物療法、手術療法、生活習慣の改善などが一般的です。
早期に適切な治療を行うことで、病気の進行を防ぎ、健康を維持することが可能なためです。糖尿病の場合は、血糖値をコントロールするための薬物療法や、食餌療法が行われます。高血圧や高コレステロール血症の場合も、薬物療法と併せて、食事や運動の改善が推奨されます。適切な治療を行うことで、病気の合併症を予防し、健康を維持できるでしょう。
血液検査は、体内の健康状態を把握するためには必要不可欠です。血液検査を通じて、糖尿病や肝臓病、腎臓病、脂質異常症など、さまざまな病気を早期に発見できます。また、検査結果に異常が見つかったとしても、適切に対処することで健康を維持できます。
本記事では、血液検査の基礎知識から、検査で発見される可能性のある病気、異常が見つかった場合の対処法について詳しく説明しました。血液検査を受ける際には、検査前日の食事制限を守り、結果を正しく理解し、必要に応じて医師の指導を仰ぐことが大切です。
DYMの医療事業では海外駐在者と現地に住む日本人向けに、以下の国でクリニックを展開しています。
人間ドックや健康診断にも対応しているため、検査を検討している方はお気軽にご相談ください。
>>>>DYMの「医療事業」サービスページはこちら

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。