Page Top
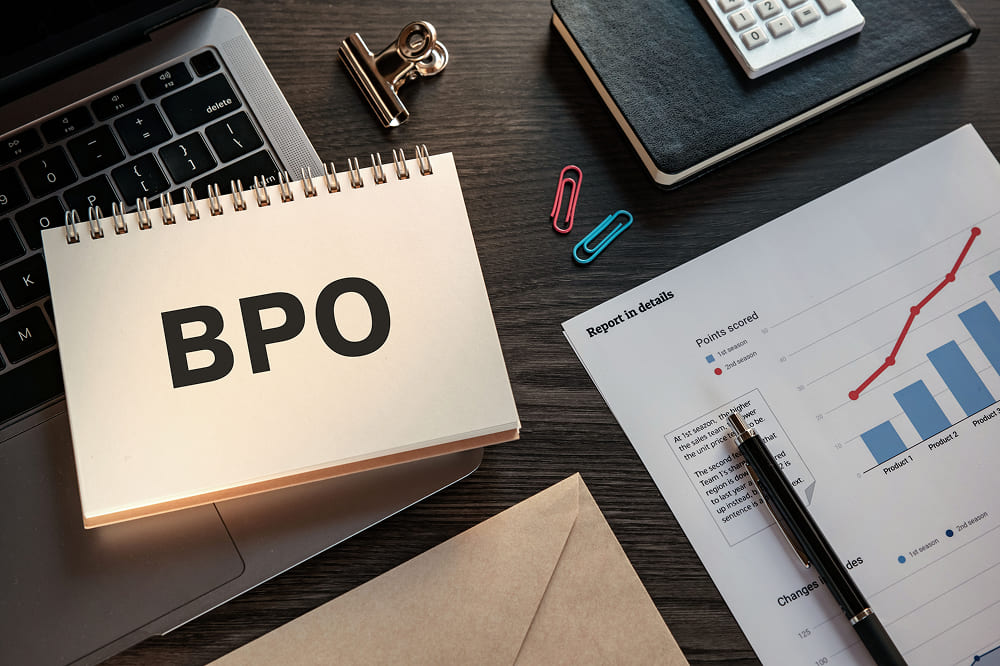
企業の競争が激化し、業務の効率化が求められる中、自社のリソースを最適化できているか不安を感じている企業は少なくありません。日々の業務に追われ、本来注力すべきコア業務に十分な時間を割けないと感じている方も多いでしょう。
そこで注目されているのがBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)です。BPOを活用することで、コスト削減や業務品質の向上が実現し、企業の成長を加速させることができます。本記事では、BPOの基本から導入メリット、活用事例まで分かりやすく解説します。
<この記事で紹介する4つのポイント>
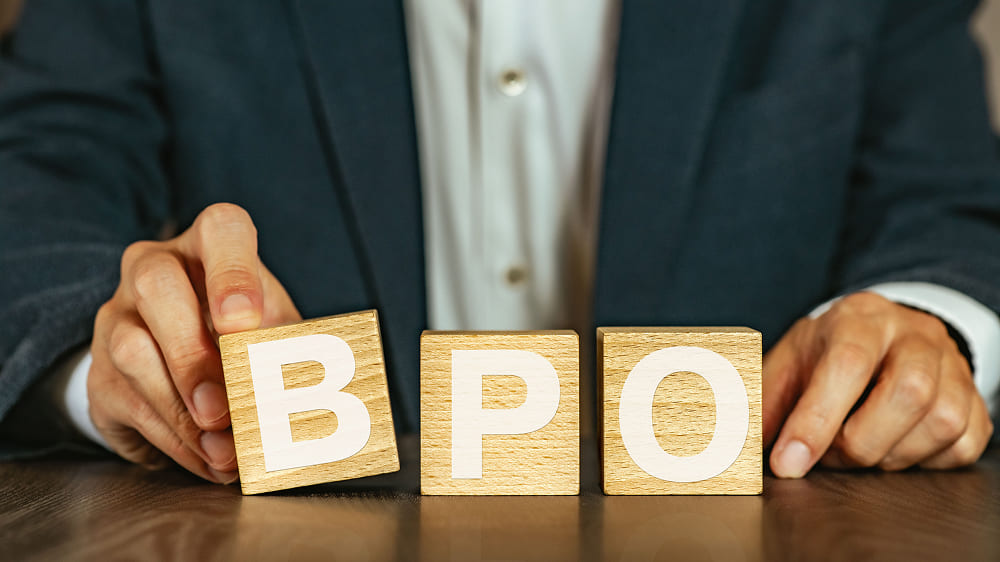
ビジネスの効率化が求められる現代において、業務プロセスを外部に委託するBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)が注目されています。
しかし、似た概念であるアウトソーシングやITO(ITアウトソーシング)、BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)、シェアードサービスとの違いを明確に理解していない方も多いのではないでしょうか。ここでは、それぞれの概念の違いを整理し、BPOがどのような特徴を持つのかを解説します。
アウトソーシングとBPOの違いは、委託範囲と目的にあります。アウトソーシングは特定の業務を切り出して外部委託し、人手不足を補うなど一時的な活用が多いのが特徴です。
一方、BPOは業務プロセス全体を一括して委託し、業務の企画設計から実行、継続的な改善活動までを含みます。
また、アウトソーシングが単なる外注であるのに対し、BPOは経営戦略の一環として位置づけられ、業務効率化や品質向上など企業の抱える課題解決を目指す長期的な取り組みとなります。
ITOとは「Information Technology Outsourcing(インフォメーション・テクノロジー・アウトソーシング)」の略で、IT分野に特化した外部委託を意味します。
BPOが業務プロセス全般を対象とするのに対し、ITOはIT関連業務に焦点を当てています。ITOの委託形態はさまざまで、ヘルプデスクやサーバー運用保守など特定業務に限定したタイプもあれば、BPO同様に企画設計からシステム開発・運用まで一連の業務を担うタイプもあります。
DX時代には、ITの専門知識や人材が不足する企業でも、ITOを活用して最新技術に対応できる点が大きな魅力となっています。
BPRは「Business Process Re-engineering(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)」の略で、業務プロセスを根本から見直し、抜本的に再構築する取り組みを指します。
BPOが業務の外部委託を通じた効率化や改善を目指すのに対し、BPRは業務そのものの必要性から見直す「業務改革」です。BPOがノンコア業務の外部化によって業務改善を図る手段であるのに対し、BPRはより上位概念として業務全体の変革を目指します。
近年ではDX推進の観点から、BPOを活用したBPRの実現に取り組む企業も増えており、両者は相互補完的な関係にあると言えるでしょう。
シェアードサービスとは、グループ企業や企業内の各事業部に分散している間接部門(人事・総務・経理など)の業務を1カ所に集約し、効率化を図る経営手法です。
BPOと同様に業務効率化やコスト削減を目的としますが、外部企業への委託ではなく、自社グループ内で集約する点が大きな違いです。シェアードサービスを担う組織は、企業内の一部門として設置されるケースや、グループ内に専門の法人を設立するケースがあります。
BPOが外部の専門性を活用するのに対し、シェアードサービスは社内リソースの最適化を図る内部施策といえるでしょう。

近年、企業を取り巻く環境は大きく変化しており、BPOへの注目度が高まっています。人材不足の深刻化や急速なデジタル化など、さまざまな経営課題に対応するため、企業はより効率的な業務体制の構築を迫られています。
ここでは、BPOの需要が高まる背景として、市場規模の推移や人材不足の影響、ビジネス環境の変化について解説します。
国内のBPO市場は年々拡大しており、企業の業務効率化ニーズの高まりとともに市場規模が成長しています。特にコールセンター業務やバックオフィス業務を中心にBPOの導入が進んでおり、業務の最適化とコスト削減を実現する手段として広く活用されています。
近年では、AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などのテクノロジーと組み合わせることで、より高度な業務効率化が可能になり、BPO市場の成長をさらに加速させています。今後も企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)が進むにつれ、BPOの活用範囲が拡大し、市場規模は引き続き拡大していくと予測されています。
日本国内では少子高齢化の影響により、労働力の確保が難しくなっています。特に、事務職やカスタマーサポート業務においては、十分な人材を確保することが企業にとって大きな課題となっています。そのため、業務負担を軽減し、限られた人材をより戦略的な業務へと集中させる手段として、BPOの導入が進んでいます。
また、BPOを活用することで、採用や教育にかかるコストを削減できるだけでなく、専門的なスキルを持つ外部のリソースを活用することで業務の品質向上も期待できます。人材不足が深刻化する中、企業にとってBPOの導入は不可欠な経営戦略の一つとなっています。
現代は、将来の予測が困難なVUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代といわれています。デジタル技術の急速な進化やグローバル化の加速により、ビジネスの複雑性とスピードは増す一方です。このような変化の激しい環境下で競争力を維持するには、迅速な対応と戦略的な経営資源の配分が不可欠です。
BPOはこうした課題解決の有効な手段となっています。外部の専門知識や最新テクノロジーを活用することで、自社だけでは対応困難な変化にも柔軟に対処できます。特に、AIやRPAなどの最新技術を取り入れたBPOサービスの登場により、従来の業務プロセスを大きく変革し、企業の変化対応力を高める効果が期待されています。

BPOは、企業のさまざまな業務に適用され、業務の効率化やコスト削減を実現する手段として広く活用されています。特に、バックオフィスやフロントオフィス、カスタマーサポート、IT・システム部門といった領域で導入が進んでいます。ここでは、業務別にBPOの対象となる業務を解説します。
バックオフィス(間接部門)は、会社の売上に直接的な関わりを持たないものの、企業運営において欠かせない業務を担当する部門です。職種によってはバックオフィスとも呼ばれます。
経理業務では伝票入力、支払い代行、請求書作成、入金消込、債権・債務管理、固定資産管理、月次・年次決算業務などが対象となります。人事・労務業務においては給与計算、社会保険手続き、採用管理、福利厚生施策の運用管理、教育研修支援などが挙げられます。
また総務業務では社内問い合わせ対応、受付、備品管理、文書管理、名刺管理、防災対応、社内イベント運営などがあります。法務業務としては契約書チェック、株主総会対応、登記業務、特許・商標管理などがBPOの対象となります。
バックオフィス業務は繁閑の波があるため、BPOを導入することで人員配置の柔軟性が高まり、コスト削減と業務効率化の両立が可能になります。
フロントオフィス(直接部門)は、会社の売上に直結する業務を担う部門です。顧客との折衝を担当することからフロントオフィスとも呼ばれます。
営業業務では顧客リスト管理、資料作成、データ入力、アポイント獲得、セールス活動などがBPOの対象となります。マーケティング業務においてはWEB広告運用、アンケート調査、イベント運営、データ分析などを外部委託できます。
販売業務では受発注管理、在庫管理などが対象です。製造関連業務としては設計開発支援、実験・試作代行なども委託可能です。
フロントオフィスでは、主にノンコア業務を切り出して外注するケースが多いですが、自社に営業部門がない企業では、営業戦略の立案から提案活動まで一貫して外注するケースもあります。外注することにより、社内リソースをコア事業に集中させることが可能になります。
カスタマーサポート部門では、顧客対応の品質向上やコスト削減の観点から、BPOの活用が進んでいます。特に、コールセンター業務では、受電対応(インバウンド業務)と架電対応(アウトバウンド業務)に分かれ、それぞれの業務に特化したBPOサービスが提供されています。
インバウンド業務は、顧客からの問い合わせやサポート依頼に対応する業務です。商品やサービスに関する問い合わせ、クレーム対応、予約受付などが含まれます。BPOを活用することで、24時間対応のカスタマーサポートを実現したり、多言語対応を導入したりすることが可能になります。
また、AIチャットボットと組み合わせることで、簡単な問い合わせを自動対応し、オペレーターの負担を軽減することもできます。
アウトバウンド業務は、企業側から顧客へ架電を行い、営業活動や市場調査を実施する業務です。テレマーケティング、アンケート調査、休眠顧客の掘り起こしなどが代表的な業務として挙げられます。
BPOを導入することで、専門のオペレーターが効率的に架電を行い、企業の営業活動を支援することが可能になります。特に、顧客リストの管理やスクリプト作成などの業務もBPO業者が担うことで、より高い成果を期待できます。
IT・システム部門のBPOは「ITO(Information Technology Outsourcing)」とも呼ばれ、専門性の高いIT関連業務を外部に委託するものです。システム運用保守、ITヘルプデスク、セキュリティ管理、ネットワーク管理、システム開発・保守、ITインフラ整備などが主な対象業務です。
IT分野は専門性が高く、技術の進化も速いため、自社で一から体制を整えるよりもBPOを活用する方が効率的です。特にDX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、企業のIT活用ニーズは高まっており、ITO市場も拡大傾向にあります。
BPOの活用により、各部門の業務効率化や品質向上が期待できます。自社の課題や目標に合わせて、最適な業務領域からBPOの導入を検討してみましょう。
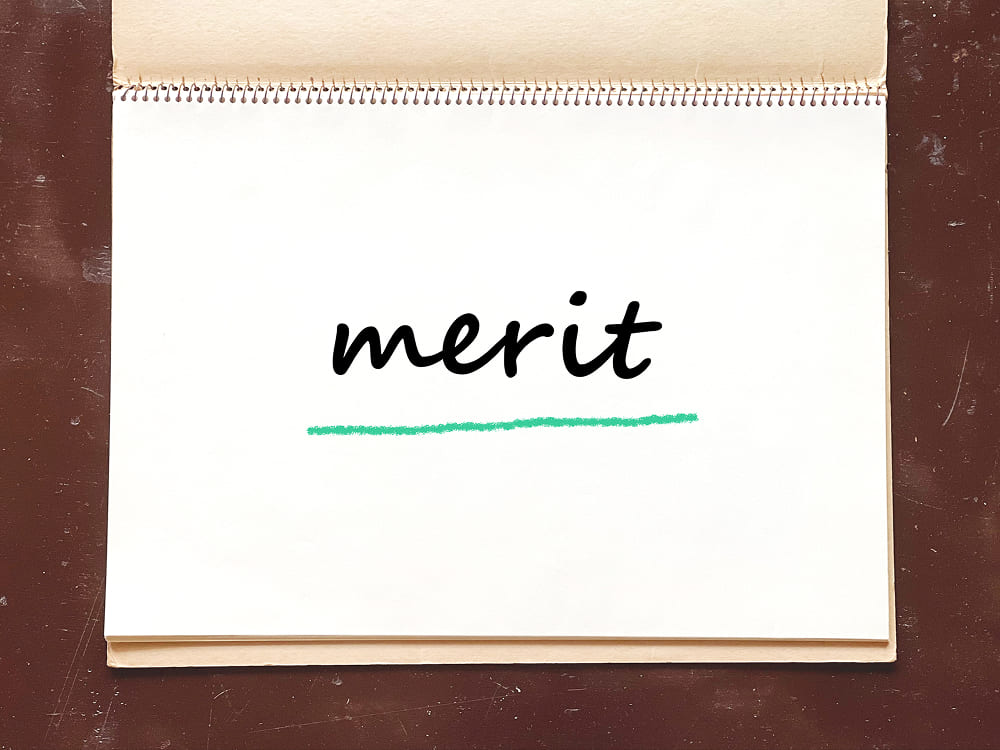
BPOの導入は、企業の業務効率化や生産性向上に大きく貢献します。特に、企業が持つ限られたリソースを最大限に活用し、業務品質の向上やコスト削減を実現する手段として、多くの企業で導入が進んでいます。ここでは、BPOの導入によって得られる具体的なメリットについて解説します。
BPOを活用することで、企業はノンコア業務を外部に委託し、自社の経営資源をコア業務に集中させることができます。人材不足が深刻化する中、限られた人的リソースを効率的に活用することが企業の競争力維持には不可欠です。
多くの企業では、一人の従業員が複数の業務を兼務することがあり、本来集中すべきコア業務に十分な時間を割けないケースが少なくありません。BPOによりノンコア業務を外部委託することで、従業員は自社の利益に直結するコア業務に集中でき、業務の生産性向上が期待できます。
例えば、営業担当者が営業事務作業に時間を取られることなく、顧客との商談や新規開拓などの営業活動に注力できるようになれば、売上向上に直接つながるでしょう。このように、BPOは単なる業務の外部化ではなく、企業の競争力強化のための戦略的な手段といえます。
BPOを導入することで、専門性の高い外部企業のノウハウを活用し、業務品質の向上が期待できます。BPO事業者は各分野のスペシャリストを擁し、最新の知識や技術を持っているため、自社で対応するよりも高品質なサービスを提供できることが多いです。
例えば、コールセンター業務を委託した場合、専門的な研修を受けたオペレーターによる正確で丁寧な対応が実現し、「サポート体制が充実している」という顧客の好印象につながります。また、待ち時間の短縮などによる顧客ストレスの軽減も、顧客満足度向上に貢献します。
さらに、BPO事業者は多くの企業との取引経験から、業界のベストプラクティスや効率的な業務手法に精通しています。これらの知見を取り入れることで、業務の質が向上するだけでなく、自社では気づかなかった改善点が見つかることもあります。
BPOを導入する過程で、委託先企業は現状の業務フローを整理するため、業務の全体像が可視化されます。可視化することで、これまで属人化していた業務や、ブラックボックス化していた工程、非効率な手順などが明らかになり、業務の標準化と効率化が進めることが可能に。
業務が標準化されることで、個人の裁量や経験に左右されない一定品質のサービス提供が可能になります。また、業務マニュアルの整備や作業の定型化により、業務の引き継ぎやトレーニングが容易になるメリットもあります。
さらに、BPO事業者は複数の企業の業務を請け負っているため、業界の標準的な業務フローや最新の効率化手法を熟知しています。そのノウハウを生かした業務プロセスの再設計により、従来よりも効率的な業務運営が実現します。例えば、不要な承認プロセスの削減や、デジタルツールの活用による作業時間の短縮など、さまざまな改善が期待できるでしょう。
自社のみで業務を行う場合、社員の離職や休職のたびに新たな人材を教育する必要があり、その都度、時間とコストがかかります。特に専門性の高い業務では、一人前になるまでに長い時間を要することもあります。
BPOを活用すれば、そうした教育コストを大幅に削減できます。BPO事業者はすでに専門的なスキルと経験を持つスタッフを配置し、継続的な教育体制も整えています。人材の入れ替わりがあっても、サービスの質を一定に保つための仕組みを持っているため、安定したサービス提供が可能です。
また、ビジネス環境の変化に伴い必要となる新たなスキルやノウハウについても、BPO事業者が対応してくれます。例えば、法改正への対応や新しい技術の導入など、自社で対応するとなると大きなコストと時間がかかる変化も、BPO事業者であれば迅速かつ適切に対応できるでしょう。
このように、BPOは短期的なコスト削減だけでなく、長期的な視点でも人材育成や教育にかかるコストを抑制する効果があります。加えて、企業は本業に関する教育にリソースを集中させることができ、さらなる競争力の強化につながります。

BPOには多くのメリットがある一方で、導入時に考慮すべきデメリットや注意点も存在します。BPOを検討する際には、これらの課題を理解し、適切に対処することが成功への鍵となります。ここでは、BPO導入時に考慮すべき主要なデメリットと注意点について詳しく解説します。
BPOを導入する際には、委託先との要件定義やマニュアル作成など、一連の運用フロー構築のための初期費用が発生します。さらに、運用開始後も継続的なランニングコストがかかります。これらのコストが当初想定していたよりも高額になる場合もあり、特に初期段階では費用対効果が見えにくいことがあります。
BPOを導入する目的がコスト削減である場合は、初期費用やランニングコストも含めた中長期的なコストパフォーマンスを事前に試算することが重要です。単純に現在の人件費と比較するだけでなく、将来的なコスト変動も考慮に入れた総合的な判断が必要です。
また、BPOサービスの料金体系は事業者によって異なり、固定料金制や従量課金制、成果報酬型などさまざまです。自社の業務特性や予算に合った料金プランを選択することも、コスト面での課題を解決するポイントとなります。
BPOの導入には委託のための準備コストがかかります。業務を外部委託するためには、現状の業務フローの可視化やマニュアル作成、委託範囲の明確化など、入念な準備が必要です。この準備段階では、自社内のリソースを多く割く必要があり、通常業務を滞らせる可能性もあります。
特に業務の属人化が進んでいる場合や、業務フローが明確に整理されていない場合は、委託準備に想定以上の時間とコストがかかることがあります。また、業務の引き継ぎ期間中は、自社従業員とBPO事業者のスタッフが二重で稼働することになり、一時的にはコストが増加することも考慮しておく必要があります。
このような準備コストを最小限に抑えるためには、日頃から業務の可視化や標準化を進めておくことが重要です。また、BPO導入に関する社内の協力体制を整え、スムーズな移行を実現するための環境づくりも欠かせません。
BPOでは業務の一部を外部に委託するため、必然的に機密情報や個人情報の共有が生じます。そのため、情報漏えいのリスクに関しては十分な対策が必要です。外部企業がセキュリティ対策を万全にしていたとしても、情報漏えいが起きた場合の責任は最終的に委託元である自社にも及びます。
実際に情報漏えいが発生した場合、委託先の過失であっても、情報の所有者である自社の社会的信用の失墜は避けられません。顧客情報や財務情報などの重要データが流出すれば、多額の損害賠償や行政処分のリスクもあります。
このリスクを軽減するためには、BPO事業者の選定時にセキュリティ体制を徹底的に確認することが重要です。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格である「ISO:27001」やプライバシーマークの取得状況、過去のセキュリティインシデントの有無などを確認するとよいでしょう。また、契約書に情報セキュリティに関する条項を盛り込み、違反時のペナルティを明確にしておくことも重要です。
BPOを導入すると、業務の一部が自社の直接的な管理下から外れるため、業務の進捗状況や品質の把握が難しくなることがあります。業務をBPO事業者に任せたことで、業務内容がブラックボックス化し、社内にノウハウが蓄積されにくくなるという課題もあります。
特に長期間にわたってBPOを利用していると、その業務に関する知識やスキルが社内から失われ、BPO事業者への依存度が高まる傾向があります。この状態は、将来的に契約条件の交渉や業務内容の変更が必要になった際に、自社の立場を弱めることにもなりかねません。
これらの課題に対処するためには、定期的な報告会や業務進捗の共有の機会を設け、BPO事業者との密なコミュニケーションを図ることが大切です。また、業務の可視化ツールを活用するなど、業務状況を適切にモニタリングできる仕組みを整えることも効果的です。
さらにBPO事業者と協力して、業務改善のためのPDCAサイクルを回していくことで、より効果的なBPO運用が実現できるでしょう。
BPOを行う際、自社とBPO事業者との間にコミュニケーションギャップが生じることがあります。特にオフサイト型の場合、直接的な対面コミュニケーションの機会が少なくなるため、意思疎通の齟齬が生じやすくなります。また、BPO事業者が自社の企業文化や業務プロセスに精通していないことも、コミュニケーション上の課題となります。
例えば、業務の緊急度や優先順位の認識の違い、業界特有の専門用語や暗黙知の理解度の差などが、業務の遅延や品質低下の原因となることがあります。特に海外のBPO事業者を利用する場合は、言語や文化の違いによる誤解も発生しやすいでしょう。
こうした課題を解決するためには、初期段階での十分なコミュニケーションと期待値の擦り合わせが重要です。定期的な進捗会議やリアルタイムでの情報共有ツールの活用、緊急時の連絡体制の整備など、コミュニケーションを密に取れる環境を構築することが求められます。
また、自社の業務特性や企業文化についても丁寧に説明し、相互理解を深めることがスムーズな業務連携につながります。
BPO契約を解約し、再び業務を内製化する場合に生じる負担も考慮すべき重要な点です。BPOにより業務の運用ノウハウが社内に蓄積されにくくなると、再内製化の際に必要なスキルや知識を持つ人材の確保や、業務プロセスの再構築に多大な時間とコストがかかる可能性があります。
特に長期間にわたってBPOを利用していた場合、業務の変化や改善が進んでいることも多く、解約時点での業務内容は当初委託した時点とは大きく異なっていることもあります。そのため、内製化に際しては単なる元の状態への回帰ではなく、新たな業務設計が必要になることもあるでしょう。
このリスクを軽減するためには、BPO利用中も自社内に一定の業務知識を保持する担当者を配置し、業務の変更や改善の履歴を把握しておくことが重要です。
また、契約時にBPO解約時の引き継ぎ条件を明確にしておくことや、定期的に業務マニュアルや手順書を更新してもらい共有を受けることも、将来的な内製化の負担を軽減するポイントとなります。
BPOの導入に際しては、これらのデメリットや注意点を十分に理解し、対策を講じておくことが重要です。短期的な視点だけでなく、中長期的な視点からBPOの活用方法を検討し、自社の経営戦略に合致した形で導入を進めることが、BPOを成功させる鍵となります。

BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)を成功させるためには、単に業務を外部委託するだけでなく、適切な準備と導入後の管理が重要です。
業務の選定から委託先の評価、導入後の運用まで、各段階で適切な対応を行うことで、業務の効率化やコスト削減の効果を最大化できます。ここでは、BPO導入の手順と重要なポイントについて解説します。
BPOを導入する前に、まず業務要件と目標を明確にすることが重要です。なぜBPOを導入するのか、どのような課題を解決したいのかを整理することで、適切な業務範囲を決定しやすくなります。
例えば、「業務負担の軽減」「コスト削減」「業務品質の向上」などの具体的な目標を設定することで、BPOの効果を最大限に引き出すことが可能です。また、定量的なKPI(重要業績評価指標)を設定することで、導入後の成果を可視化しやすくなります。
BPOを導入する際には、どの業務を委託するのかを明確にする必要があります。業務の特性や重要度を整理し、BPOに適した業務を選定することが成功の鍵となります。
例えば、定型的な業務や反復作業が多い業務は、BPOによって効率化しやすい一方で、社内でしか対応できない業務も存在します。そのため、社内業務とBPO業務の役割分担を明確にし、委託業務の範囲を慎重に検討することが重要です。
BPOの委託先を選定する際には、業者の実績や提供可能なサービス範囲を慎重に評価することが必要です。特に、自社の業務に適した専門性を持つBPO業者を選ぶことで、より高い効果を得ることができます。
業務品質を確保するために、過去の実績や他社の導入事例を確認し、必要に応じてトライアル導入を実施するのも有効な手段です。また、BPO業者との契約に際しては、業務範囲やSLA(サービスレベルアグリーメント)を明確にし、成果を測定する指標を設定することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
BPO導入後は、委託業務が適切に遂行されているかを定期的にモニタリングすることが重要です。業務品質やKPIの達成状況を確認し、必要に応じて改善策を講じることで、BPOの効果を維持し、最大限に活用することができます。
また、BPO業者とのコミュニケーションを定期的に行い、業務の進捗や課題を共有することで、よりスムーズな運用を実現できます。
BPOの導入は、単なる業務の外部委託にとどまらず、企業全体の業務プロセスを見直す機会にもなります。BPOを通じて得られた知見を生かし、社内の業務フローを改善することで、さらなる業務効率化を図ることが可能です。
また、BPO業者と連携し、継続的な業務改善を行うことで、業務の最適化を促進し、より高い競争力を確保することができます。
BPOは企業の業務効率化と競争力強化に欠かせない経営戦略です。人材不足が深刻化し、ビジネス環境が急速に変化する中、適切な業務を外部の専門家に委託することで、コア業務への集中や業務品質の向上が実現します。
バックオフィスやカスタマーサポート、IT部門など幅広い業務領域でBPOを活用できますが、導入には準備コストやセキュリティリスクなどの課題も存在します。成功のカギは、明確な目標設定と委託業務の適切な選定、信頼できるパートナー企業の選択にあります。計画的なアプローチと継続的なモニタリングを通じて、BPOのメリットを最大限に引き出し、企業の持続的な成長を実現しましょう。
当社では事務代行事業、コールセンター事業など、さまざまなHR事業に関するサービスを展開しています。ご興味がある方はぜひ下記より当社へご相談ください。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。