Page Top
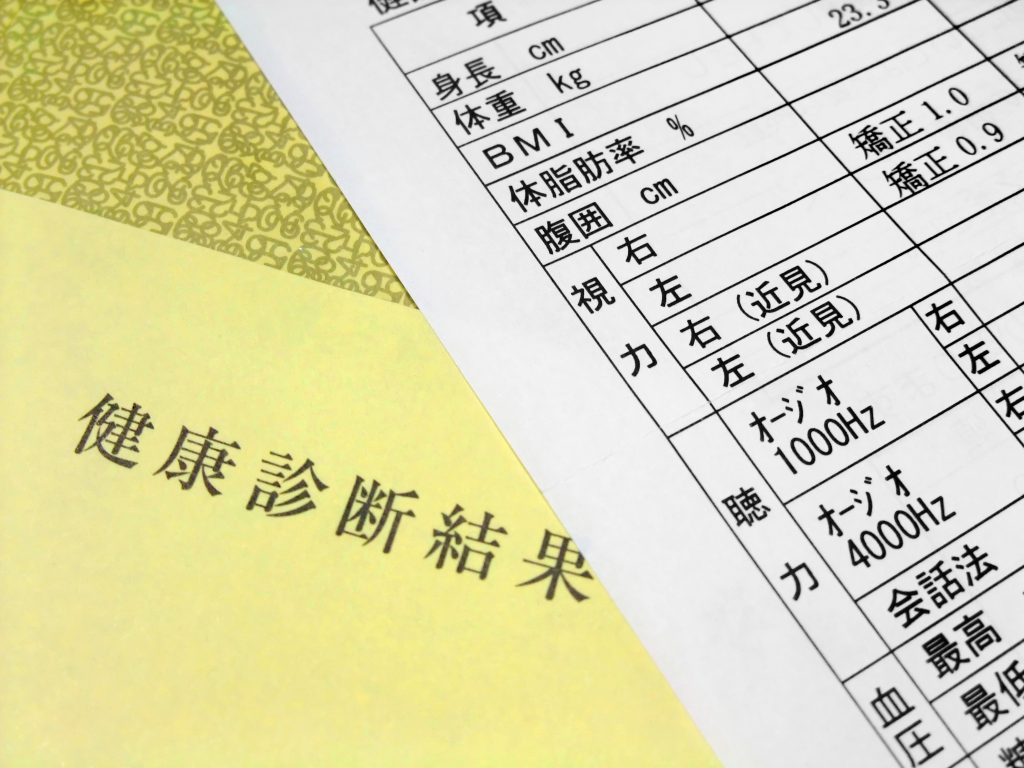
健康管理において、「健診」と「検診」という言葉をよく耳にしますが、違いを正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。両者は似たような目的を持ちながらも、実施方法や対象範囲に違いがあります。本記事では、健康診断(健診)と検診の違い、それぞれの目的や意義、具体的な内容について詳しく解説します。健康維持に欠かせない検査について、正しい知識を身につけましょう。
<この記事で紹介する3つのポイント>
目次
健診は全身の健康状態のチェックを目的としている一方で、検診は特定の疾患の発見に焦点を当てた検査を指します。
健診は、法律によって義務付けられた「法定健診」と「任意健診」があります。法定健診は乳児や妊婦、一般、労働者などによって内容が決められており、問診と身体測定、視力・聴力検査、血圧測定、尿検査、胸部エックス線検査などにより受診者の健康状態を確認することが目的です。
また、40歳以上には生活習慣病予防を目的とした「特定健康診査(メタボ健診)」が実施されます。特定健診の項目は血液検査や肝機能検査、血中脂質検査、空腹時血糖、心電図検査などです。
任意健診には、法定健診より多くの項目について検査する「人間ドック」などがあります。
一方、検診は特定の疾患の早期発見を目的として、対象となる疾病や臓器に特化した検査をおこないます。たとえば、胃がん検診、大腸がん検診、乳がん検診などが該当します。検診は任意で受けることが多く、自治体や医療機関が提供するサービスとして実施されるのが一般的です。
健診と検診の大きな違いは、実施の法的根拠にもあります。健診は医療保険法や健康増進法、労働者においては労働安全衛生法などいくつかの法律に基づいておこなわれますが、検診は健康増進法に基づき実施されています。

健康診断(健診)は、個人の健康状態を評価し、疾病の早期発見や予防を目的とした医学的検査です。最も一般的なものは労働安全衛生法に基づいて実施される定期健康診断です。また、40歳以上の方を対象とした特定健康診査(特定健診)も広く知られています。健診は、生活習慣病の予防や早期発見、職場における労働者の健康管理に重要な役割を果たします。
健康診断の目的は、個人の健康状態を総合的に評価し、疾病の早期発見や予防をおこなうことです。とくに、自覚症状がないまま進行する生活習慣病の早期発見に重視されています。定期的な健康診断を受けることで、自身の健康状態を客観的に把握し、必要に応じて生活習慣の改善や適切な医療を受けるきっかけになるのです。
職場における健康診断の目的は、労働者の健康管理と安全な労働環境の確保です。企業は従業員の健康状態を把握し、必要に応じて就業上の配慮をおこなうことで、労働生産性の向上や職場の安全性確保にもつなげます。
定期健康診断(一般健康診断)のポイントは、総合的な健康状態の評価です。従業員の健康状態を定期的にチェックし、職場における健康管理を目的としています。検査項目は、身長・体重測定、視力・聴力検査、血圧測定、胸部X線検査、尿検査、血液検査などです。
血液検査では血糖値、コレステロール値、肝機能などを調べることで、糖尿病や脂質異常症、肝疾患のリスクを評価します。胸部X線検査では肺の状態を確認し、結核や肺がんなどの早期発見に役立ちます。とくに注目すべき点は、検査結果を経年的に比較することです。毎年の健診結果を比較することで、健康状態の変化を把握し、生活習慣病の予防や早期対策につながります。
特定健康診査、通称「特定健診」または「メタボ健診」は、40歳から74歳までの方を対象とした健康診査です。目的は、メタボリックシンドロームの予防と改善です。メタボリックシンドロームは、内臓脂肪の蓄積に加え、高血糖、高血圧、脂質異常のうち2つ以上の状態が重なった状態を指し、心臓病や脳卒中などの生活習慣病のリスクを高めます。
特定健診の特徴は、内臓脂肪の蓄積に着目している点です。腹囲測定を必須項目とし、男性85cm以上、女性90cm以上を基準としています。加えて、血圧測定、血糖検査・血中脂質検査をおこない、メタボリックシンドロームのリスクを総合的に評価します。特定健診は生活習慣の改善を支援するプログラムです。健診結果に基づき、必要な方には特定保健指導をとおして、食事や運動習慣の見直しをおこないます。
健康診断(健診)は、疾病の早期発見や予防を目的とし、各検査項目が重要な役割を果たします。検査項目の意味を理解し、生活習慣の改善や適切な医療を受けることが大切です。主な検査項目には、聴力検査、尿検査、血液検査、循環器系検査、呼吸器系検査があります。
聴力検査は、労働者の聴力の状態を評価し、聴覚障害の早期発見や予防を目的としています。とくに、騒音の多い職場で働く方々にとって、聴力検査は非常に重要です。聴力検査の主な方法は、オージオメーターを使用した純音聴力検査です。1000Hzと4000Hzの周波数の音を用いて、左右の耳の聴力を測定します。
聴力検査の意義は、騒音性難聴の早期発見や職場環境の改善、労働者の健康管理にあります。定期的な聴力検査で、聴力の変化を早期に発見し、適切な治療を受けることが可能です。
尿検査では尿蛋白、尿糖、尿潜血などをチェックします。
尿検査の役割は腎臓疾患の早期発見や尿路感染症の検出、糖代謝の評価などです。
血液検査では、赤血球、白血球、血小板などの血球成分や、肝機能、腎機能、脂質代謝、血糖値などを評価します。血液検査を実施する目的は貧血の検出、炎症や感染症、肝機能、腎機能、脂質代謝、糖代謝の評価などです。
循環器系検査は、心臓や血管の健康状態を評価するためにおこなわれる検査です。主な項目には、血圧測定、心電図検査、胸部X線検査などがあります。高血圧や不整脈、心筋梗塞、心不全などの循環器疾患を早期に発見し予防するために行われます。
呼吸器系検査は、肺や気道の健康状態を評価するためにおこなわれます。主な項目は、胸部X線検査、肺機能検査などです。肺炎、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺がんなどの呼吸器疾患を早期に発見し、予防するために実施されます。
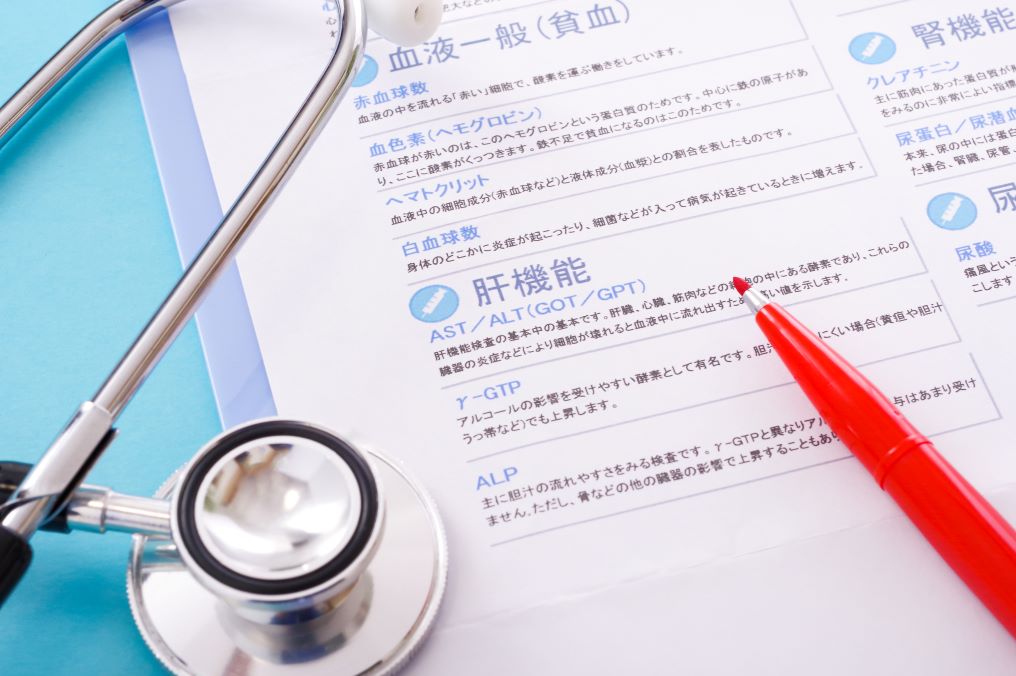
検診は、特定の疾病、主にがんの早期発見を目的とした医学的検査です。健診が全般的な健康状態を評価するのに対し、検診は特定の疾病に焦点を当てた専門的な検査です。検診の種類には、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がん検診などがあります。症状が現れる前に疾病を発見し、早期治療につなげることを目的としています。
検診の目的は、特定の疾患を早期に発見し、早期治療につなげることです。とくにがんの早期発見は治療の選択肢の幅を広げ、治癒の可能性も高くなります。早期発見・早期治療により、身体的・精神的負担、経済的負担を軽減できます。
検診の具体的な目的は以下のとおりです。
検診は疾患の早期発見・早期治療に役立ちますが、偽陰性や過剰診断などのデメリットもあるため、個人の状況に応じて適切な時期に受診することが大切です。
検診にはさまざまな種類がありますが、主にがんの早期発見を目的としたものが多く実施されています。国が推奨するがん検診は以下のとおりです。
上記の検診は、対象年齢や受診間隔が定められており、多くの場合、自治体や職場を通じて受診の機会が提供されています。
検診には「対策型検診」と「任意型検診」の2つのタイプがあります。対策型検診は、公的機関が実施主体となり、集団全体の死亡率減少を目指しておこなわれる検診です。
対策型検診の特徴は以下のとおりです。
対策型検診は、公衆衛生の観点から重要で、多くの人々が定期的に受診することで、がんによる死亡率の低減が期待されています。
任意型検診は、個人の判断で受診する検診で、医療機関や検診機関が独自に提供するものです。特徴は以下のとおりです。
任意型検診は、個人のニーズに応じて、詳細な健康チェックや対策型検診では対象外の年齢や検査項目を希望する場合に選択されることがほとんどです。ただし、任意型検診を選択する際は、検査の有効性や必要性について医療専門家に相談し、適切に判断することが重要です。偽陰性や過剰診断によるデメリットも十分に理解します。
健診と検診は、私たちの健康を守るために重要な役割を果たしていますが、目的や実施方法には明確な違いがあります。
疾病の早期発見・早期治療を通じて、健康寿命の延伸と生活の質の向上に貢献し、定期的に受診することで、健康意識が高まり、健康的な生活習慣の維持につながります。
健診や検診は偽陰性や過剰診断などのデメリットもあるため、年齢や性別、家族歴、生活習慣などを考慮し、適切な健診・検診を選択することが重要です。
健診や検診は疾病の早期発見に役立つツールですが、日々の健康的な生活習慣が重要であることを忘れてはいけません。バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠、ストレス管理などを心がけ、健診・検診と合わせて総合的な健康管理をおこなうことが、真の健康づくりにつながります。
DYMが運営している海外のクリニックでは、日本の法律に基づく健康診断を受けられます。健診時は日本語での対応も可能です。現地にお住まいの方はぜひご利用ください。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。