Page Top
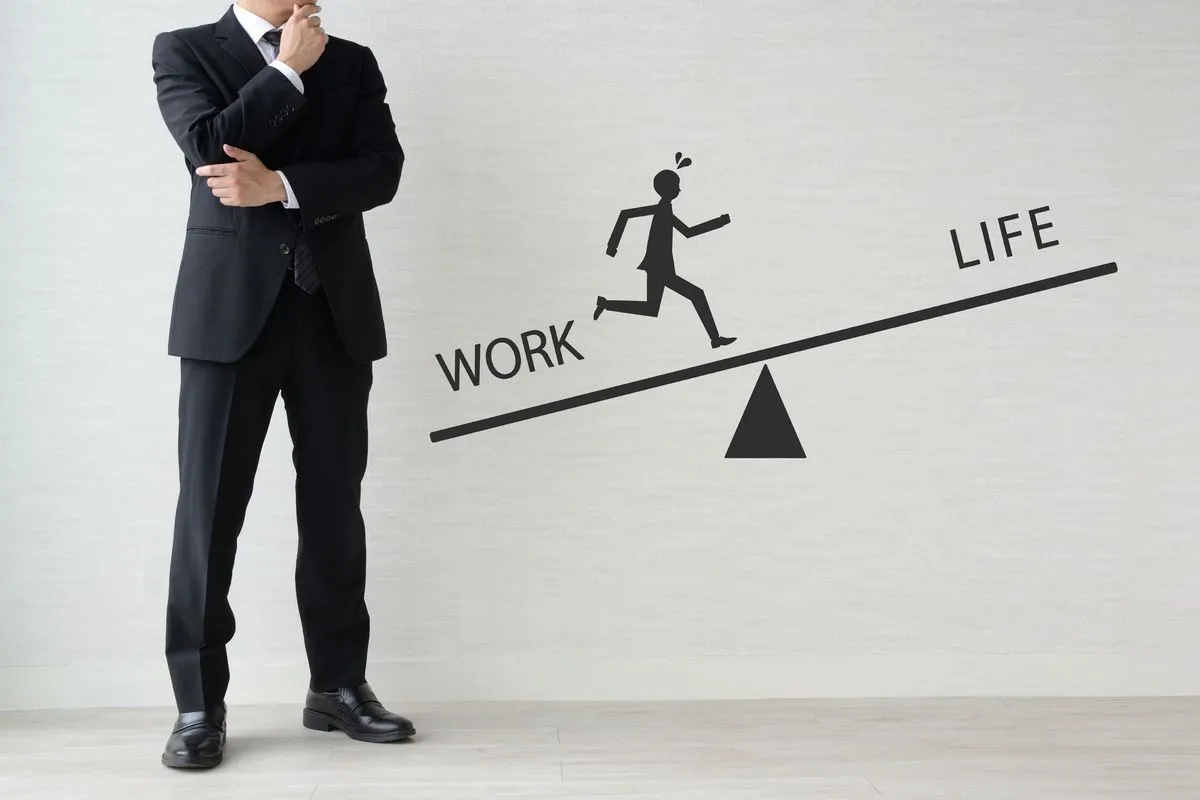
有給休暇は労働者にとって大切な権利ですが、「いつから何日もらえるのか」「会社ごとに違いがあるのはなぜか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。実際、有給休暇の付与には法律で定められた要件や基準日があり、勤務年数や雇用形態によって日数やタイミングが異なります。
この記事では、有給休暇が付与されるタイミングと日数の基本ルール、契約形態別の付与日数、さらに基準日の考え方やよくある疑問までをわかりやすく解説します。
<この記事で紹介する3つのポイント>
目次

有給休暇の付与タイミングは労働基準法で明確に定められており、法定要件を満たした従業員には必ず付与しなければなりません。初回の付与から2年目以降の継続的な付与まで、それぞれに明確なルールが存在しています。
有給休暇の初回付与は、労働基準法第39条により「雇い入れの日から起算して6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者」に対して10日間付与されると定められています。この規定により、例えば4月1日に入社した従業員の場合、6ヶ月後の10月1日が有給休暇の初回付与日となります。
付与される日数は一律10日間であり、この日数は労働基準法で定められた最低基準です。企業は法定基準を下回る日数を設定することはできませんが、10日を上回る日数を独自に設定することは可能です。実際に、福利厚生の一環として法定基準を上回る日数を付与している企業も存在しています。
重要な点は、有給休暇の付与が労働者の申請や会社の許可を必要としない自動的な権利であることです。法定要件を満たした時点で、労働者には当然に有給休暇を取得する権利が発生します。この権利は労働者の心身の疲労回復とゆとりある生活の実現を目的としており、企業は適切な付与を行う法的義務を負っています。
有給休暇の2回目以降の付与は、初回付与日を基準日として毎年1年ごとに行われます。労働基準法第39条第2項では、「1年6ヶ月以上継続勤務した労働者に対しては、6ヶ月経過日から起算した継続勤務年数1年ごとに」付与すると定められています。
具体的には、4月1日入社で10月1日に初回付与を受けた従業員の場合、2回目の付与は1年後の翌年10月1日となり、以降毎年10月1日が付与日となります。付与日数は勤続年数に応じて段階的に増加し、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日と続き、最終的に6年6ヶ月以上で最大20日に達します。
この継続的な付与システムにより、長期勤続者ほど多くの有給休暇を取得できる仕組みが構築されています。ただし、出勤率が8割を下回った年については有給休暇の付与は行われませんが、その年も継続勤務年数としてはカウントされるため、翌年に条件を満たした場合は、その勤務年数に応じた日数が付与されることになります。

有給休暇の付与には労働基準法で定められた明確な要件があり、これらの条件をすべて満たした労働者に対してのみ有給休暇が付与されます。要件を正しく理解することで、適切な有給休暇の管理が可能になります。
継続勤務とは、事業場における在籍期間を意味しており、実質的に労働契約が存続しているかどうかを勤務の実態に即して判断されます。単純な雇用期間ではなく、実際の勤務実態を基準とした判定が行われる点が重要です。継続勤務の判定においては、雇用形態の変更は継続勤務を中断させません。
例えばアルバイトから正社員になった場合、アルバイト期間も含めた在籍期間で継続勤務年数が計算されます。同様に、定年退職者を嘱託社員として再雇用した場合も、形式的に一度退職して再雇用契約を結んだとしても、実質的には労働契約は継続しているため、定年退職前の当初の入社年月日から通算して取り扱われます。
また、事業の縮小による解雇後の再雇用や、M&Aによる企業合併、在籍出向からの復帰なども、実質的に同一の事業所で雇用関係が継続していれば在籍期間は通算されます。これらの判定は労働者の不利益を防ぐため、形式的な契約関係よりも実質的な雇用関係の継続性を重視して行われています。
出勤率の要件は「出勤日数÷全労働日×100」で算定され、8割以上の出勤が必要です。全労働日とは算定期間の暦日数から就業規則などで定めた企業の休日を除いた日数であり、実際に出勤すべき日数を指します。
出勤したものとして扱われる日には、業務上の負傷・疾病による休業期間、産前産後休業期間、育児・介護休業期間、年次有給休暇を取得した期間が含まれます。これらの期間は労働者の責に帰さない事由による休業であるため、出勤として計算されます。
一方、全労働日から除外される日には、使用者の責に帰すべき事由による休業日、正当なストライキなどによる労務提供がなされなかった日、通勤災害による休業日などがあります。ただし、通勤災害による休業、生理休暇、母性健康管理のための休暇、慶弔休暇などの会社休暇日については、法律上の規制がなく企業の任意の扱いとなるため、あらかじめ就業規則で明確に定めておく必要があります。
出勤率が8割を満たない年は有給休暇が付与されませんが、その年も継続勤務年数には含まれるため、翌年に条件を満たした場合は、その勤務年数に応じた日数が付与されることになります。

有給休暇の付与日数は雇用形態や労働条件によって異なる体系となっており、フルタイム労働者と短時間労働者では付与基準が大きく異なります。また、育児・介護休業中の労働者に対しても特別な配慮が必要です。
正社員や契約社員などのフルタイム労働者は、週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上の場合、継続勤務期間に応じて段階的に有給休暇が付与されます。初回付与は6ヶ月経過時に10日、その後は勤続年数に応じて増加していきます。
具体的な付与日数は、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、4年6ヶ月で16日、5年6ヶ月で18日、6年6ヶ月以上で最大20日となります。この20日が法定の上限日数であり、勤続6年6ヶ月を超えても付与日数は増加しません。
注意すべき点は、2019年4月から施行された働き方改革関連法により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者には年5日の取得が企業に義務付けられていることです。この義務は管理監督者も含むすべての対象労働者に適用され、企業が適切な取得促進を行わなければ30万円以下の罰金が科される可能性があります。
フルタイム労働者の有給休暇は、労働者の心身の疲労回復と生産性向上を目的としており、企業にとっても労働者の満足度向上や離職率低下などのメリットをもたらします。
パートタイム労働者の有給休暇は、週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下の場合、所定労働日数に応じた比例付与が適用されます。この比例付与制度により、勤務日数が少ない労働者にも公平に有給休暇が付与される仕組みとなっています。
具体的な付与日数は、週4日勤務(年169~216日)の場合、6ヶ月で7日、1年6ヶ月で8日、最大15日まで付与されます。週3日勤務(年121~168日)では6ヶ月で5日、最大11日、週2日勤務(年73~120日)では6ヶ月で3日、最大7日、週1日勤務(年48~72日)では6ヶ月で1日、最大3日となります。
重要な点は、週所定労働日数が5日以上または年間所定労働日数が217日以上の場合、パートタイム労働者であってもフルタイム労働者と同様の日数が付与されることです。また、週所定労働時間が30時間未満であっても、週5日以上勤務の場合はフルタイム勤務と同様の日数が付与されます。
パートタイム労働者であっても、年10日以上の有給休暇が付与される場合は年5日の取得義務の対象となり、企業は確実な取得促進を図る必要があります。
育児休業や介護休業中の労働者に対する有給休暇の付与においては、休業期間中であっても出勤したものとみなして計算されます。これは労働基準法の規定により、育児・介護休業期間は出勤日として取り扱われるためです。
具体的には、入社3年目で育児休業を取得し1年間休業したフルタイムの従業員が、入社4年目に復帰した際に付与される有給休暇の日数は14日間となります。これは継続勤務年数3年6ヶ月に相応する日数であり、休業期間中であっても勤務年数は継続してカウントされることを示しています。
同様に、業務上の負傷・疾病による休業期間も出勤扱いとなるため、労災による休職から復帰した労働者にも適切な有給休暇が付与されます。ただし、私傷病による休職については企業の規定によって取り扱いが異なるため、就業規則や社内規定に従って判定する必要があります。
この制度により、育児や介護という重要な家庭事情により休業した労働者が、復帰後に不利益を受けることなく適切な有給休暇を取得できる環境が確保されています。

有給休暇の基準日は労務管理の効率性と従業員の公平性を両立させる重要な仕組みです。労働基準法では原則的な基準日設定方法を定めていますが、企業の実情に応じた柔軟な運用も認められています。
労働基準法の原則では、雇い入れの日から6ヶ月が経過した日を基準日として有給休暇を付与します。この基準日が以降の有給休暇付与の起点となり、毎年同じ日に有給休暇が付与される仕組みです。
例えば4月1日入社の従業員の場合、基準日は6ヶ月後の10月1日となり、以降毎年10月1日に有給休暇が付与されます。この個別付与方式では、従業員それぞれの入社日に基づいて基準日が設定されるため、企業にとっては付与する有給休暇の日数を法定最低限に抑えられるメリットがあります。
しかし、従業員の入社日が多様な企業では、年間を通じて複数の付与日が発生し、管理が煩雑になる課題があります。また、月途中の入社者が多い場合、基準日が月の中旬や下旬になることで、労務管理の手間が増加する傾向があります。
このような管理上の課題から、多くの企業では後述する斉一的付与制度の導入を検討し、効率的な有給休暇管理を実現しています。付与漏れなどのリスクを防ぐためには、システム化された管理体制の構築が重要です。
斉一的付与制度は、労働者に不利益を与えない範囲で全従業員の有給休暇付与日を統一する制度です。この制度により、年1回または数回の一斉付与日を設定することで、労務管理の大幅な効率化が実現できます。
斉一的付与を実施する場合、法定の基準日より前倒しでの付与が必要です。例えば基準日を4月1日に統一する場合、4月1日入社者は入社時に10日、翌年4月1日に11日が付与されます。6月入社者の場合、本来の基準日は12月ですが、翌年4月1日に11日が付与されることで、法定基準より前倒しとなり労働者に有利な扱いとなります。
斉一的付与の実施には厚生労働省の行政通達「年次有給休暇の斉一的取扱い」に従った適切な運用が必要です。短縮された期間は全期間出勤したものとみなし、次年度以降の付与日も初年度の繰り上げ期間と同等以上の期間を前倒しする必要があります。
この制度は企業の管理負担軽減と労働者の利便性向上を両立させる有効な手段であり、多くの企業で採用されている実用的な制度です。

有給休暇の付与タイミングに関しては、実際の運用において多くの疑問が生じます。入社時期による違いや付与後の利用開始時期、企業による日数の差異など、よくある質問について詳しく解説します。
4月入社の従業員に対する有給休暇の付与タイミングは、入社日によって決まります。4月1日入社の場合、労働基準法の原則に従えば6ヶ月後の10月1日が初回の有給付与日となり、10日間の有給休暇が付与されます。
ただし、企業によっては労働者の利便性を考慮して、入社時に有給休暇を前倒しで付与するケースもあります。例えば入社時に5日、6ヶ月後に残りの5日を付与する「分割付与」や、入社時に10日を一括付与する方法があります。このような前倒し付与を行う場合、基準日は最初に有給休暇を付与した4月1日となり、次回の付与日は翌年4月1日となります。
企業が斉一的付与制度を採用している場合は、さらに異なる付与パターンとなります。全社員の基準日を4月1日に統一している企業では、4月1日入社者は入社時に10日、翌年4月1日に11日が付与されます。一方、4月2日以降の入社者は、一度法定通りに付与を受けた後、次回から統一基準日での付与となる場合が多くあります。
このように4月入社であっても、企業の制度設計により付与タイミングは大きく異なるため、自社の就業規則を確認することが重要です。
付与された有給休暇は、付与日当日から即座に利用可能です。労働基準法では有給休暇の取得について労働者の時季指定権を認めており、付与された日から2年間の有効期限内であればいつでも取得できます。
有給休暇の取得理由は問われず、労働者は自由なタイミングで利用できます。旅行、通院、家族の用事、単純な休息など、どのような理由であっても企業は原則として取得を拒否できません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、企業は時季変更権を行使して他の時季への変更を求めることが可能です。
前倒しで付与された有給休暇についても、付与日から即座に利用可能です。例えば入社時に5日が付与された場合、入社初日からその5日間の有給休暇を取得できます。企業は労働者が6ヶ月継続勤務する前に退職した場合でも、すでに取得された有給休暇の返納を求めることはできません。
このように、有給休暇は付与と同時に労働者の確定した権利となり、企業は適切な取得環境を整備する義務があります。
企業によって有給休暇の付与日数が異なる理由は、労働基準法が最低基準を定めているためです。法律で定められた日数は下回ることができませんが、それを上回る日数を企業が独自に設定することは認められています。
多くの企業では福利厚生の充実を図るため、法定基準を上回る有給休暇を付与しています。例えば初回付与時に12日や15日を付与したり、最大付与日数を25日や30日に設定したりする企業もあります。これらの優遇措置は企業の人材確保戦略や従業員満足度向上の取り組みの一環として実施されています。
また、付与タイミングについても企業による差異があります。法定では6ヶ月後の付与が原則ですが、入社時から有給休暇を付与する企業や、試用期間終了時に付与する企業など、さまざまなパターンが存在します。これらは労働者にとって有利な扱いであるため、労働基準法上問題となることはありません。
企業規模や業界特性によっても付与条件は異なります。大企業ほど法定基準を上回る有給休暇を提供する傾向があり、優秀な人材の獲得・定着を目的とした競争力のある制度設計が行われています。
2回目の有給付与のタイミングは、初回付与の方法によって決まります。原則的な法定付与を行った場合、2回目の付与は初回付与日から1年後となり、継続勤務年数1年6ヶ月時点での付与となります。
4月1日入社で10月1日に初回付与を受けた場合、2回目の付与は翌年10月1日となり、付与日数は11日間です。このパターンでは入社から1年6ヶ月経過時の付与となり、以降毎年10月1日が付与日として固定されます。
前倒し付与を行った場合は付与タイミングが変更されます。入社時に10日を一括付与した4月1日入社者の場合、2回目の付与は翌年4月1日となり、通常より6ヶ月早い付与となります。分割付与を行った場合も、最初に付与した日が基準日となるため、同様に前倒しでの2回目付与が行われます。
斉一的付与制度を採用している企業では、全従業員の2回目以降の付与日が統一されます。例えば基準日を4月1日に設定している場合、入社時期に関係なく全従業員の2回目以降の付与が毎年4月1日に行われ、管理の大幅な効率化が実現されています。
有給休暇の付与タイミングと日数は労働基準法により明確に定められており、すべての従業員と人事担当者が理解すべき重要な制度です。原則として雇い入れから6ヶ月後に10日間が付与され、その後は継続勤務年数に応じて段階的に増加し、最大20日まで付与されます。
付与要件である「6ヶ月以上の継続勤務」と「全労働日の8割以上の出勤」を満たした従業員には、雇用形態に関係なく適切な有給休暇が付与される仕組みとなっています。
新卒での就職活動においても、入社後の労働条件として有給休暇制度の理解は重要です。DYMでは26・27卒の皆様に向けて、入社実績15,000名以上の豊富な経験をもとに、最短1週間で内定獲得を実現する就活サポートを提供しています。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。