Page Top

仕事が長続きせず転職を繰り返してしまうことに悩んでいませんか。実は短期間での離職は珍しいことではなく、その原因は性格だけでなく病気や特性が関係している場合もあります。この記事では仕事が続かない原因を解説し、あなたの特性に合った15の仕事を紹介します。自分を責めずに、新たな一歩を踏み出すきっかけにしてください。
<この記事で紹介する4つのポイント>
目次

仕事が続かないことに悩み、自己嫌悪に陥っていませんか。しかし、短期間での離職は決して珍しいことではありません。むしろ現代社会では多くの人が同じような悩みを抱えており、その背景にはさまざまな要因が存在します。
厚生労働省の調査によると、新卒入社3年以内の離職率は約3割に達しています。特に20代では転職経験者の割合が高く、複数回の転職を経験している人も少なくありません。
さらに、1年未満での離職を経験した人の多くが、その後も短期離職を繰り返す傾向にあることが分かっています。これは個人の問題というよりも、職場環境とのミスマッチや、自分に合った働き方を見つけられていないことが大きな要因です。
現代は終身雇用制度が崩壊し、転職が当たり前の時代になりました。そのため、仕事が続かないことを過度に悲観する必要はないでしょう。重要なのは、なぜ続かないのかを理解し、自分に合った働き方を見つけることです。
仕事が続かないことで「自分はクズだ」「社会不適合者だ」と自己否定してしまう人が多くいます。しかし、このような自己批判は問題解決につながりません。
仕事が続かない理由は人それぞれ異なります。職場の人間関係、業務内容とのミスマッチ、体調面の問題など、外的要因が大きく影響している場合も多いでしょう。また、発達障害やHSPなどの特性が関係していることもあります。
大切なのは、自分を責めるのではなく、冷静に原因を分析することです。自己否定は心身の健康を損ない、さらに状況を悪化させる可能性があります。まずは自分を受け入れ、前向きに解決策を探していきましょう。

仕事が続かない背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。ここでは主な5つの原因について詳しく解説します。自分に当てはまる項目がないか、じっくりと確認してみてください。
仕事が続かない原因として、うつ病や適応障害などの精神的な病気が潜んでいる可能性があります。これらの病気は、仕事のストレスや環境の変化によって発症することが多く、早期の対応が重要です。
うつ病の主な症状には、気分の落ち込み、意欲の低下、集中力の欠如、睡眠障害などがあります。朝起きられない、仕事に行くのがつらい、何をしても楽しくないといった症状が2週間以上続く場合は、専門医への相談を検討しましょう。
適応障害は、新しい環境や状況にうまく適応できずに起こる心の病気です。転職後や異動後に発症しやすく、不安感、緊張、抑うつ気分などの症状が現れます。職場でのストレスが原因となることが多いため、環境を変えることで改善する場合もあります。
ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害の特性が、仕事が続かない原因になっている場合があります。これらは生まれつきの脳の特性であり、適切な理解と対応が必要です。
ADHDの特性として、注意力の散漫、衝動性、多動性などがあります。仕事では、ケアレスミスが多い、締め切りを守れない、デスクが散らかりやすいといった困りごとが生じやすくなります。一方で、興味のあることには高い集中力を発揮できるという強みもあります。
ASDの特性には、コミュニケーションの困難さ、こだわりの強さ、感覚過敏などがあります。職場では、暗黙のルールが理解できない、急な予定変更に対応できない、雑談が苦手といった課題が生じることがあります。しかし、ルールやマニュアルに従った正確な作業は得意とする傾向があります。
HSPは病気や障害ではなく、生まれつき感受性が強く、刺激に敏感な気質を持つ人のことを指します。全人口の約15~20%がHSPだといわれており、職場環境によっては働きづらさを感じることがあります。
HSPの人は、職場の雰囲気や人間関係の微妙な変化を敏感に感じ取ります。他人の感情に影響されやすく、騒がしい環境や強い照明、においなどの刺激にストレスを感じることもあるでしょう。また、深く考える傾向があるため、決断に時間がかかることもあります。
このような特性から、オープンオフィスでの勤務や、顧客対応が多い仕事では疲れやすくなります。一方で、細やかな気配りができる、創造性が高い、共感力があるといった強みを持っています。
仕事が続かない原因として、個人の性格や価値観と職場の文化が合わないことも挙げられます。これは決して悪いことではなく、自分に合った環境を見つけるための重要な気づきといえるでしょう。
例えば、自由を重視する人が厳格なルールのある職場で働くと、息苦しさを感じます。逆に、安定を求める人がベンチャー企業のような変化の激しい環境では不安を感じるかもしれません。また、ワークライフバランスを大切にする人が、長時間労働が当たり前の職場では続けることが困難でしょう。
価値観の不一致は、給与、キャリアアップ、人間関係、社会貢献など、さまざまな面で起こります。自分が仕事に何を求めているのかを明確にすることで、より適切な職場選びができるようになります。
職場環境や仕事内容が自分に合っていないことも、仕事が続かない大きな要因です。これは採用時の情報不足や、実際に働いてみて初めて分かることが原因となっています。
職場環境のミスマッチには、人間関係の問題、労働時間の長さ、通勤の負担、オフィス環境などがあります。特に人間関係は離職理由の上位に挙げられることが多く、上司や同僚との相性が仕事の継続に大きく影響します。
仕事内容のミスマッチは、スキルレベルと業務の難易度が合わない、興味のない分野の仕事を任される、単調な作業の繰り返しで成長を感じられないなどがあります。また、入社前のイメージと実際の業務内容が大きく異なることも、早期離職につながる要因となっています。

仕事が続かない人には、いくつかの共通する特徴があります。これらの特徴を理解することで、自己分析が深まり、改善点が見えてくるでしょう。
まず挙げられるのは、完璧主義の傾向です。高い理想を持つことは素晴らしいことですが、すべてを完璧にこなそうとすると、小さなミスで自信を失い、仕事へのモチベーションが下がってしまいます。また、他人と自分を比較しがちで、劣等感を感じやすいという特徴もあります。
次に、コミュニケーションが苦手という特徴があります。職場での人間関係構築が難しく、孤立しやすい傾向にあります。相談相手がいないため、悩みを一人で抱え込み、ストレスが蓄積していきます。結果として、職場に居づらくなり、退職を選択することになります。
さらに、飽きやすい性格も特徴の一つです。新しいことには興味を持ちますが、慣れてくると物足りなさを感じます。ルーティンワークが苦手で、常に刺激や変化を求める傾向があります。このような人は、同じ仕事を長期間続けることに苦痛を感じやすいでしょう。
ストレス耐性が低いことも共通する特徴です。プレッシャーに弱く、困難な状況に直面すると逃げ出したくなります。批判や注意を受けることに過敏に反応し、必要以上に落ち込んでしまうこともあります。
最後に、自己肯定感の低さが挙げられます。自分の能力や価値を過小評価し、「どうせ自分なんて」という思考に陥りやすくなります。成功体験があっても素直に受け入れられず、失敗ばかりに目が向いてしまいます。
これらの特徴は、必ずしも悪いものではありません。むしろ、自分の特性として受け入れ、それに合った環境や働き方を選ぶことが重要です。弱みと思える部分も、見方を変えれば強みになることもあるでしょう。
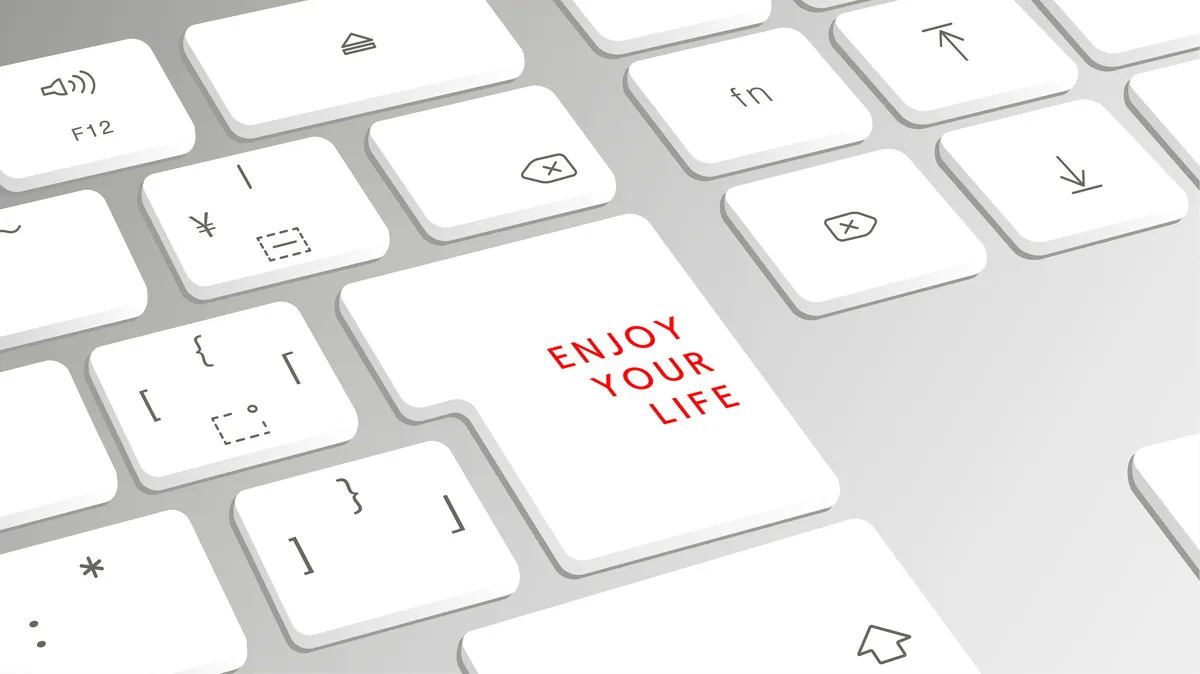
仕事が続かない原因は人それぞれ異なります。ここでは、原因別に適した仕事を15種類紹介します。自分の特性や悩みに合わせて、参考にしてください。
人間関係でストレスを感じやすい人には、対人接触が少ない仕事や、限定的なコミュニケーションで済む仕事が向いています。以下の3つの仕事は、人間関係の負担を最小限に抑えながら働くことができます。
ITエンジニアやプログラマーは、パソコンに向かって作業する時間が長く、人との直接的なやり取りが比較的少ない仕事です。技術力が評価の中心となるため、コミュニケーション能力よりもスキルで勝負できる環境があります。
基本的にはチームで開発を行いますが、担当箇所が明確に分かれているため、必要最小限のコミュニケーションで済むことが多いでしょう。また、リモートワークを導入している企業も多く、在宅で仕事ができる環境も整っています。
プログラミング言語の習得には時間がかかりますが、一度身に付ければ手に職となり、転職市場でも需要が高い職種です。未経験からでも独学やプログラミングスクールで学習を始められるため、キャリアチェンジを考えている人にもおすすめです。
Webライターは、インターネット上の記事やコンテンツを執筆する仕事です。クライアントとのやり取りは主にメールやチャットで行われ、対面でのコミュニケーションはほとんどありません。
フリーランスとして活動する場合は、完全に自分のペースで仕事ができます。納期さえ守れば、働く時間や場所は自由に選べるため、人間関係のストレスから解放されます。また、執筆テーマも自分の興味のある分野を選べることが多く、やりがいを感じやすい仕事です。
文章力は必要ですが、特別な資格は不要で、パソコンがあればすぐに始められます。最初は単価が低いかもしれませんが、実績を積めば収入アップも期待できます。コツコツと一人で作業することが好きな人に向いているでしょう。
工場での製造ラインや倉庫での仕分け作業など、決められた作業を黙々とこなす仕事です。基本的に個人作業が中心で、必要なコミュニケーションは業務連絡程度に限られます。
作業内容がマニュアル化されているため、覚えてしまえば人に聞く必要もありません。休憩時間も決まっており、無理に同僚と交流する必要もないでしょう。単純作業が多いため、考えすぎる傾向がある人にとっては、頭を休めながら働ける環境といえます。
シフト制の職場が多く、自分の都合に合わせて働けるのもメリットです。正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員など、さまざまな雇用形態があるため、まずは短期間から始めてみるのもよいでしょう。
マイペースな性格で、他人に合わせることが苦手な人には、時間や場所に縛られない仕事が向いています。以下の3つの仕事は、自分のリズムで働くことができます。
フリーランスのWebデザイナーや動画編集者は、完全に自分のペースで仕事ができる職業です。クライアントワークではありますが、作業は基本的に一人で行い、納期内に成果物を提出すれば問題ありません。
Webデザイナーは、ウェブサイトのデザインやバナー制作などを行います。デザインセンスは必要ですが、PhotoshopやIllustratorなどのツールの使い方は独学でも習得可能です。動画編集者は、YouTubeや企業のプロモーション動画などを編集する仕事で、需要が急速に拡大しています。
どちらも在宅で作業でき、複数のクライアントと契約することで収入を安定させることができます。最初は副業から始めて、軌道に乗ったら独立するという選択肢もあるでしょう。自由度が高い分、自己管理能力は求められますが、束縛されるのが苦手な人には理想的な働き方です。
タクシードライバーや配送ドライバーは、一人で車を運転する時間が長く、自分のペースで働ける仕事です。基本的に単独行動のため、職場の人間関係に悩まされることが少ないでしょう。
タクシードライバーは、歩合制の場合が多く、頑張った分だけ収入に反映されます。休憩も自分のタイミングで取れるため、体調に合わせて働くことができます。配送ドライバーは、決められたルートを回るため、慣れれば効率的に仕事をこなせるようになります。
運転免許は必要ですが、未経験でも始められる仕事が多く、年齢制限も比較的緩やかです。人と接する機会は限定的で、挨拶程度のコミュニケーションで済むため、対人ストレスを感じにくい環境といえます。
在宅コールセンターは、自宅で電話対応を行う仕事です。出社の必要がなく、通勤時間もゼロのため、時間を有効活用できます。シフト制の場合が多く、自分の都合に合わせて勤務時間を選べるのも魅力です。
顧客との電話対応がメインですが、マニュアルが整備されていることが多く、決められた対応をすれば問題ありません。職場の人間関係に悩む必要がなく、同僚との競争もないため、精神的な負担が軽減されます。
研修制度が充実している企業も多く、未経験でも始めやすい仕事です。インバウンド(受信)業務なら、自分から電話をかける必要がないため、プレッシャーも少ないでしょう。パソコンの基本操作ができれば、特別なスキルは不要です。
HSPや繊細な気質を持つ人には、静かな環境で集中できる仕事や、細やかな作業が求められる仕事が向いています。以下の3つの仕事は、繊細さを強みとして生かすことができます。
図書館司書や学芸員は、静かで落ち着いた環境で働ける仕事です。大声で話す必要がなく、ゆったりとしたペースで業務を進められるため、HSPの人にとって理想的な職場環境といえるでしょう。
図書館司書は、本の管理や貸出業務、レファレンスサービスなどを行います。利用者への対応も穏やかな雰囲気で行えるため、激しいクレーム対応などはほとんどありません。学芸員は、博物館や美術館で展示企画や資料管理を担当し、文化や芸術に関わる仕事ができます。
どちらも専門的な知識が必要ですが、繊細な感性を生かせる仕事です。細部にまで気を配る能力や、静かに集中して作業する力が評価される環境があります。公務員として働く場合も多く、安定した労働環境が期待できます。
データ入力や事務職は、決められた作業を正確にこなすことが求められる仕事です。騒々しい環境ではなく、オフィスで静かに作業できるため、刺激に敏感な人でも働きやすいでしょう。
パソコンに向かって数字や文字を入力する作業が中心で、深い思考力よりも正確性が重視されます。マイペースで進められる業務が多く、締め切りに追われることも比較的少ないでしょう。電話対応が少ない職場を選べば、対人ストレスも軽減できます。
事務職は幅広い業界で需要があり、経理事務、人事事務、営業事務など、さまざまな種類があります。自分の興味のある分野や、働きやすそうな環境を選ぶことができるのも魅力です。残業が少ない職場も多く、プライベートの時間を大切にできます。
校正・校閲は、文章の誤字脱字や内容の整合性をチェックする仕事です。細かい部分に気づく能力が必要とされるため、HSPの人が持つ繊細な観察力を存分に発揮できます。
基本的に一人で黙々と作業を進めるため、人間関係のストレスが少ない仕事です。出版社や印刷会社だけでなく、Web媒体でも需要があり、在宅で働ける案件も増えています。納期はありますが、自分のペースで進められる部分が大きいでしょう。
言葉や文章に対する感受性の高さは、この仕事において大きな強みとなります。読者の立場に立って文章を読み、違和感を感じ取る能力は、まさにHSPの特性が活きる場面です。フリーランスとして活動することも可能で、自分に合った働き方を選択できます。
同じことの繰り返しに飽きてしまい、常に新しい刺激を求める人には、変化に富んだ仕事が向いています。以下の3つの仕事は、日々新しい課題に取り組むことができます。
営業職は、さまざまな顧客と出会い、異なる課題解決に取り組む仕事です。毎日同じ作業をすることはなく、常に新しい刺激と変化がある環境で働けます。
顧客のニーズを聞き出し、最適な提案をする過程では、創造性と柔軟性が求められます。契約が取れたときの達成感は大きく、数字として成果が見えるため、モチベーションを保ちやすいでしょう。また、インセンティブ制度がある企業では、頑張りが収入に直結します。
人と話すことが好きで、チャレンジ精神がある人には最適な仕事です。業界や商材によって営業スタイルも異なるため、自分に合った分野を選ぶことができます。新規開拓営業なら、日々新しい出会いがあり、飽きることがありません。
企画・マーケティング職は、新商品の開発や販促キャンペーンの立案など、クリエイティブな仕事です。市場調査から戦略立案まで、幅広い業務に携わることができ、ルーティンワークとは無縁の環境です。
トレンドを追いかけ、消費者のニーズを分析する必要があるため、常に新しい情報に触れることができます。アイデアを形にしていく過程は刺激的で、自分の企画が世に出る喜びは格別でしょう。チームでプロジェクトを進めることが多く、さまざまな部署との連携も経験できます。
デジタルマーケティングの分野では、データ分析やSNS運用など、新しいスキルを身に付ける機会も豊富です。変化の速い業界のため、常に学び続ける必要がありますが、それが刺激となって仕事へのモチベーションにつながります。
コンサルタントは、企業の経営課題を解決する仕事で、プロジェクトごとに異なる課題に取り組みます。短期間で集中的に働き、次々と新しいクライアントや業界に関わるため、飽きる暇がありません。
問題解決能力と論理的思考力が求められ、知的好奇心を満たすことができる仕事です。クライアントの業界について深く学ぶ必要があるため、幅広い知識を身に付けることができます。また、経営層と直接やり取りする機会も多く、ビジネスの最前線を体験できます。
ハードワークになることもありますが、その分成長スピードは速く、キャリアアップも期待できます。独立して経営コンサルタントとして活動する道もあり、自分の専門性を活かして自由に働くことも可能です。
体力的な負担が少なく、座って作業できる仕事は、体力に自信がない人でも長く続けやすいでしょう。以下の3つの仕事は、身体への負担を最小限に抑えながら働くことができます。
一般事務や経理は、デスクワークが中心で、体力的な負担が少ない仕事です。空調の効いたオフィスで座って作業するため、天候や気温に左右されることもありません。
書類作成やデータ管理、伝票処理など、決められた業務を確実にこなすことが求められます。重い荷物を運んだり、長時間立ち続けたりする必要がないため、体力に自信がない人でも無理なく働けるでしょう。
残業が少ない職場も多く、規則正しい生活リズムを保ちやすいのもメリットです。経理の場合は、簿記などの資格を取得することで、専門性を高めることもできます。長期的に安定して働ける環境が整っています。
メールやチャットでのカスタマーサポートは、電話対応と違い、自分のペースで返信できる仕事です。座ったまま作業でき、声を出し続ける必要もないため、体力的な消耗が少ないでしょう。
問い合わせ内容に対して、マニュアルに沿って回答するケースが多く、慣れれば効率的に対応できるようになります。タイピングスキルは必要ですが、特別な体力は不要です。在宅勤務可能な企業も増えており、通勤の負担もなくせます。
シフト制の職場が多く、短時間勤務から始められることもあります。体調に波がある人でも、無理のない範囲で働き始めることができるでしょう。顧客の問題解決に貢献できるやりがいもある仕事です。
オンラインアシスタントは、リモートで企業や個人事業主の業務をサポートする仕事です。スケジュール管理、資料作成、リサーチ業務など、さまざまなタスクを在宅でこなします。
完全在宅で働けるため、通勤による体力消耗がありません。業務内容も比較的軽いものが多く、パソコンスキルがあれば対応できます。クライアントとのやり取りも基本的にオンラインで完結するため、対面での打ち合わせなどもありません。
フリーランスとして複数のクライアントと契約したり、オンラインアシスタントサービスに登録して働いたりと、さまざまな働き方が選べます。体調に合わせて仕事量を調整できるのも大きな魅力です。

仕事を長く続けるためには、自分に合った働き方を見つけるだけでなく、日々の心がけも重要です。ここでは、実践しやすい5つのコツを紹介します。
完璧主義は仕事が続かない大きな要因の一つです。すべてを100点満点でこなそうとすると、プレッシャーが大きくなり、小さなミスでも自己嫌悪に陥ってしまいます。
まずは60点を目指し、徐々に質を上げていく考え方を持ちましょう。新しい仕事では特に、最初から完璧にできる人はいません。失敗を恐れずに挑戦し、経験を積むことで成長していけます。
上司や同僚も、新人に完璧を求めているわけではありません。むしろ、素直に学ぶ姿勢や、改善しようとする意欲を評価しています。完璧でなくても、期限を守って仕事を進めることの方が重要な場合も多いでしょう。
「とりあえずやってみる」という気持ちで取り組むことで、精神的な負担が軽くなります。完成度は後から上げていけばよいのです。この考え方を持つことで、仕事へのハードルが下がり、長く続けやすくなります。
仕事だけが人生のすべてではありません。プライベートを充実させることで、仕事のストレスを上手に発散し、心のバランスを保つことができます。
趣味や運動、友人との交流など、仕事以外の楽しみを見つけましょう。週末に楽しみがあれば、平日の仕事も頑張れるようになります。また、仕事での嫌なことがあっても、プライベートで気分転換できれば、翌日また頑張る気力が湧いてきます。
オンとオフの切り替えも大切です。仕事が終わったら、仕事のことは考えないようにしましょう。家に仕事を持ち込まず、自分の時間を大切にすることで、心身のリフレッシュができます。
プライベートが充実していると、仕事に対する依存度が下がり、適度な距離感を保てるようになります。結果として、仕事のプレッシャーを感じにくくなり、長期的に働き続けることができるでしょう。
正社員だけが働き方のすべてではありません。契約社員、派遣社員、パート・アルバイト、フリーランスなど、さまざまな選択肢があります。自分のライフスタイルや価値観に合った働き方を選ぶことが重要です。
例えば、プライベートを重視したい人は、残業の少ない派遣社員や時短勤務を選ぶとよいでしょう。自由度を求める人は、フリーランスとして独立する道もあります。まずは副業から始めて、徐々に移行していくことも可能です。
職場環境も重要な要素です。大企業、中小企業、ベンチャー企業では、それぞれ文化や働き方が異なります。在宅勤務やフレックスタイム制度など、柔軟な働き方ができる企業も増えています。
自分に合った環境を見つけるためには、転職活動時にしっかりと情報収集することが大切です。企業の口コミサイトを確認したり、面接で質問したりして、入社後のミスマッチを防ぎましょう。
今の仕事が合わないと感じても、すぐに退職を考える必要はありません。まずは上司や人事部に相談し、異動や業務内容の変更ができないか確認してみましょう。
同じ会社でも、部署が変われば仕事内容や職場の雰囲気は大きく異なります。営業が合わなかった人が、事務職に異動して活躍するケースもあります。また、担当業務を少し変えるだけで、働きやすさが改善することもあるでしょう。
相談する際は、具体的に何が問題なのかを整理しておくことが大切です。単に「合わない」というだけでなく、「○○の業務が苦手だが、△△なら得意」といった建設的な提案ができるとよいでしょう。
企業側も、せっかく採用した人材を失いたくないと考えています。真摯に相談すれば、何らかの配慮をしてくれる可能性は高いでしょう。転職はいつでもできるので、まずは現在の職場でできることを試してみることをおすすめします。
長期的な目標だけでなく、短期・中期の目標を設定することで、仕事へのモチベーションを維持しやすくなります。達成可能な小さな目標を積み重ねることで、成功体験を得られます。
例えば、3か月後には「基本業務を一人でこなせるようになる」、1年後には「新しいスキルを習得する」といった具体的な目標を立てましょう。達成したら自分を褒め、次の目標に向かって進んでいきます。
目標は柔軟に修正してもかまいません。状況が変われば、目標も変わって当然です。大切なのは、常に前を向いて進んでいく意識を持つことです。小さな成長を実感できれば、仕事を続ける意欲も湧いてきます。
キャリアの目標があることで、日々の仕事にも意味を見出せるようになります。今の仕事が将来につながっていると感じられれば、多少の困難も乗り越えられるでしょう。

仕事が続かないことに悩んでいるなら、一人で抱え込まず、専門家に相談することをおすすめします。客観的なアドバイスを得ることで、新たな視点や解決策が見つかるかもしれません
うつ病や適応障害、発達障害などの可能性を感じたら、早めに心療内科や精神科を受診しましょう。専門医による適切な診断と治療を受けることで、症状の改善が期待できます。
受診をためらう人も多いですが、心の不調は誰にでも起こりうることです。風邪を引いたら内科に行くように、心の不調を感じたら専門医に相談するのは自然なことです。早期に対応することで、重症化を防ぐこともできます。
診断を受けることで、自分の特性を正しく理解できるようになります。発達障害の場合は、適切な支援を受けることで、働きやすい環境を整えることも可能です。投薬治療だけでなく、カウンセリングや認知行動療法など、さまざまな治療法があります。
医療機関では、仕事の悩みについても相談できます。医師やカウンセラーは多くの事例を知っているため、具体的なアドバイスをもらえることもあるでしょう。一人で悩むより、専門家の力を借りることで、解決への道が開けます。
キャリアの方向性に悩んでいる場合は、転職エージェントに相談するのも一つの方法です。プロのキャリアアドバイザーが、あなたの強みや適性を客観的に分析してくれます。
転職エージェントは無料で利用でき、キャリアの棚卸しから求人紹介まで、幅広いサポートを受けられます。自分では気づかなかった強みや、新たなキャリアの可能性を発見できることもあるでしょう。
必ずしもすぐに転職する必要はありません。まずは相談だけでも構いません。市場価値を知ることで、今の仕事を続けるべきか、転職すべきかの判断材料になります。また、転職市場の動向や、求められるスキルについての情報も得られます。
複数のエージェントに相談することで、さまざまな視点からアドバイスを受けることができます。相性の良いアドバイザーを見つけて、長期的な関係を築くことも可能です。
特に既卒の方の転職支援に強いDYM就職は、50,000名以上の面談実績を持ち、サービス満足度87%を誇る転職エージェントです。既卒者特有の悩みに寄り添った丁寧なサポートが受けられるため、キャリアの方向性に悩む既卒の方は一度相談してみてください。
—————————————————
—————————————————
キャリアコーチングは、自己分析を深め、自分らしいキャリアを築くためのサポートを受けられるサービスです。転職エージェントとは違い、求人紹介ではなく、自己理解とキャリア設計に特化しています。
プロのコーチとの対話を通じて、自分の価値観や強み、理想の働き方を明確にしていきます。これまでの経験を振り返り、本当にやりたいことは何かを見つめ直す機会になるでしょう。
キャリアコーチングでは、具体的な行動計画も立てられます。目標達成に向けて、どのようなステップを踏めばよいかを明確にし、実行をサポートしてもらえます。定期的なセッションを通じて、進捗確認や軌道修正も行えます。
有料のサービスですが、自己投資として考えれば、長期的に見て大きなリターンが期待できます。自分自身と向き合い、納得のいくキャリアを築きたい人には、価値のある選択肢といえるでしょう。
仕事が続かないことは、決して恥ずかしいことではありません。原因はさまざまで、病気や障害、HSPなどの特性、性格や価値観の違い、職場環境のミスマッチなど、複数の要因が絡み合っていることが多いでしょう。
大切なのは、自分を責めるのではなく、原因を理解し、適切な対策を取ることです。この記事で紹介した15の仕事は、それぞれの特性に合わせて選んだものです。完璧な仕事はありませんが、自分により合った環境を見つけることは可能です。
一人で悩んでいるなら、プロの力を借りることも検討してみてください。面談実績50,000名以上、サービス満足度87%を誇る就職支援サービス「DYM就職」では、あなたの特性や強みを丁寧にヒアリングし、長く続けられる仕事探しをサポートしています。
あなたには、必ず合う仕事があります。焦らず、自分のペースで、理想の働き方を見つけていきましょう。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。