Page Top

障害や難病があって、一般企業で働くことに不安を感じていませんか。「自分に合う仕事が見つかるだろうか」「職場で必要なスキルが足りないかもしれない」そんな悩みを抱える方の就職をサポートするのが「就労移行支援」制度です。この記事では、就労移行支援の利用を検討している方に向けて、制度の基本からサービス内容、事業所の選び方までを網羅的に解説します。この記事を読めば、就労移行支援の全体像を理解し、あなたに合った就職活動を始めるための第一歩を踏み出せます。
<この記事で紹介する3つのポイント>
目次
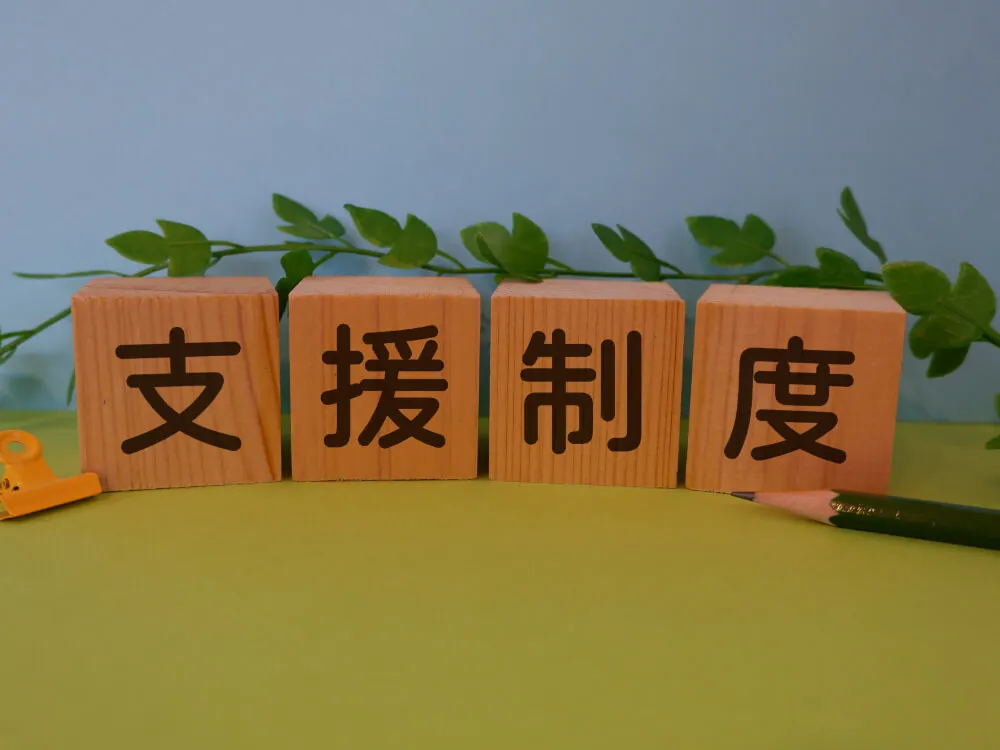
就労移行支援は、障害や難病のある方が一般企業へ就職し、安定して働き続けるために必要なスキルや知識を身に付けるための福祉サービスです。国が定めた制度であり、職業訓練から就職活動のサポート、さらには就職後の定着支援まで、一貫したサポートを受けられるのが大きな特徴です。一人ひとりの希望や特性に合わせた計画のもと、就職という目標達成に向けて専門スタッフが伴走します。
就労移行支援の最も大きな目的は、障害のある方が一般企業で活躍するための橋渡しをすることです。企業で働く上で求められるビジネスマナーやコミュニケーションスキル、パソコンスキルなどを学ぶ実践的なプログラムを通じて、就職への自信を深めます。また、自己分析や企業研究をサポートし、自分の強みや適性に合った仕事を見つける手助けも行います。障害への配慮を得ながら、一般の労働市場で働くことを目指す方のための心強い制度です。
就労移行支援は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づいて実施される公的な福祉サービスの一つです。この法律は、障害のある方が基本的人権を享受する個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことができるよう、必要な支援を総合的に行うことを目的としています。そのため、就労移行支援の利用料金は国の補助があり、多くの方が少ない負担でサービスを利用できる仕組みになっています。
就労移行支援のゴールは、単に内定を獲得することだけではありません。就職後に職場環境に慣れ、長期的に安定して働き続ける「職場定着」までを視野に入れた支援が特徴です。就職後は、新しい職場での人間関係や仕事上の悩みを相談できる「定着支援」を利用できます。定期的な面談を通じて、本人と企業の双方に働きかけ、課題の早期発見と解決をサポートします。これにより、安心して新しいキャリアをスタートさせ、長く働き続けることが可能になります。

就労移行支援は、一般企業への就職を希望する、原則として18歳以上65歳未満の障害や難病のある方が対象となるサービスです。利用にあたっては、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や指定難病など、幅広い方が対象に含まれます。ここでは、具体的な対象者の条件について詳しく見ていきます。
就労移行支援の対象は、障害者手帳の有無だけで決まるわけではありません。以下の障害や疾患のある方が広く対象となります。
これらに該当し、一般企業への就職を目指している方がサービスの対象です。
利用できる方の年齢は、原則として18歳以上65歳未満と定められています。これは、高校卒業後の進路として、あるいは社会人経験を経てから再就職を目指す方など、幅広い年代の方が活用できることを意味します。ただし、65歳に達する前日までに就労移行支援の支給決定を受けていた方は、65歳以降も引き続き利用できる場合があります。詳細はお住まいの自治体の障害福祉担当窓口にご確認ください。
就労移行支援を利用するための重要な条件として、本人が一般企業への就職を希望していることが挙げられます。このサービスは、職業訓練や就職活動支援を通じて一般就労を目指すためのものであるため、「働きたい」という明確な意思が前提となります。サービス利用開始時の面談などで、どのような仕事に就きたいか、どのように働きたいかといった希望や目標についてスタッフと話し合い、就職への意欲を確認します。
「障害者手帳を持っていないと利用できないのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、必ずしも手帳は必須ではありません。例えば、精神科に通院していて医師からの診断書がある場合や、難病と診断されている場合など、自治体が就労移行支援の必要性を認めれば、サービスの利用が可能です。手帳の有無で利用を諦める前に、まずはお住まいの自治体の障害福祉担当窓口や、気になる就労移行支援事業所に相談してみることをお勧めします。

就労移行支援事業所では、利用開始から就職、そして職場定着まで、一人ひとりの状況に合わせた一貫したサポートが受けられます。個別支援計画に基づいて、ビジネスマナーの習得から専門的な職業スキルの訓練、実践的な就職活動の対策まで、幅広い支援プログラムが用意されています。
サービスの利用を開始すると、まず専門の支援員が面談を行い、あなたの障害特性、得意なこと、課題、そして「どんな仕事に就きたいか」という希望を丁寧にヒアリングします。その内容をもとに、就職というゴールに向けたオーダーメイドの「個別支援計画」を作成します。計画作成後も定期的に面談を実施し、進捗状況の確認や目標の見直しを行うため、常に自分に合ったペースで訓練を進められます。
多くの事業所では、事務職などで必須となるWordやExcel、PowerPointといった基本的なPCスキルの訓練を行っています。電話応対、名刺交換、報告・連絡・相談(報連相)といったビジネスマナー研修も、働く上での基礎を固めるために重要です。さらに、事業所によっては、Webデザインやプログラミング、動画編集といった専門的なIT・Webスキルを学べる場所もあります。自分の目指す職種に合わせて訓練内容を選べるのが魅力です。
本格的に就職活動を始める段階になると、より実践的なサポートが受けられます。自分の強みや経験を効果的に伝えるための履歴書・職務経歴書の添削や、自信を持って本番に臨むための模擬面接を繰り返し行います。また、求人情報の探し方や企業研究の進め方など、就職活動全般にわたる相談が可能です。障害特性の伝え方(オープン就労かクローズ就労か)についても、専門スタッフと一緒に考えられます。
応募したい企業や興味のある業界が見つかったら、実際にその職場を見学したり、企業インターン(職場実習)に参加したりする機会があります。職場見学では、職場の雰囲気や仕事内容を直接見ることで、働くイメージを具体的にできます。職場実習では、一定期間、実際の業務を体験することで、仕事への適性や必要な配慮事項を確認できます。これにより、就職後のミスマッチを防ぎ、自分に本当に合った職場を見つけることに繋がります。
就労移行支援のサポートは、就職が決まったら終わりではありません。無事に就職した後も、最長で3年6ヶ月(※利用開始から)の「職場定着支援」を受けることができます。新しい環境での悩みや仕事上の課題について、事業所のスタッフが定期的に面談を実施し、相談に乗ってくれます。必要に応じてスタッフが職場を訪問し、上司や同僚との間に入って働きやすい環境を調整することもあります。この定着支援があることで、安心して社会人生活を継続できます。

就労移行支援を利用したいと考えてから、実際に就職するまでの大まかな流れは以下の通りです。まずは情報収集から始まり、自治体での手続きを経て、事業所での訓練へと進んでいきます。各ステップで専門スタッフのサポートを受けられるため、一人で悩まずに進められます。

就労移行支援は公的な福祉サービスであるため、利用者の金銭的な負担が少なくなるよう配慮されています。実際、利用者の約9割は自己負担なし(無料)でサービスを利用しており、利用できる期間も目標達成のために十分な時間が設定されています。
就労移行支援の利用料金は、前年度の世帯所得によって決まります。厚生労働省の調査によると、利用者のうち約9割の方が無料で利用しています。これは、生活保護受給世帯や、市区町村民税が非課税の世帯(低所得世帯)が自己負担0円となるためです。金銭的な心配をせずに、安心して訓練や就職活動に集中できる環境が整っています。
自己負担が発生する場合でも、所得に応じて1ヶ月あたりの上限額が定められており、それ以上の金額を請求されることはありません。具体的な区分は以下の通りです。
| 負担上限額 | 負担上限額 | |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※ | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は除く。
(参考:厚生労働省「障害者の利用者負担」)
就労移行支援を利用できる期間は、原則として24ヶ月(2年間)です。この期間内で、職業スキルの習得から就職活動、職場定着までを目指します。一人ひとりのペースに合わせて計画的に訓練を進めるため、2年間という期間は十分に活用できます。また、自治体の審査により必要性が認められた場合には、最大で12ヶ月の延長が可能な場合もあります。

障害のある方の「働く」を支援するサービスには、就労移行支援のほかに「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」があります。これらは目的や働き方が異なるため、自分に合ったサービスを選ぶことが重要です。大きな違いは、一般企業への就職を目指すか、福祉的なサポートのある環境で働くかという点です。
| 目的 | 一般企業への就職 | 福祉的配慮のある職場での就労 | 福祉的配慮のある職場での就労(非雇用) |
|---|---|---|---|
| 雇用契約 | なし | あり | なし |
| 給与/工賃 | なし | あり(最低賃金以上) | あり(工賃) |
| 利用期間 | 原則2年 | なし | なし |
| 対象者例 | 一般企業で働きたい方 | 企業等での就労経験がある方など | 就労経験がない方、体力に不安がある方など |
最も根本的な違いは「目的」です。
将来的に一般企業で働きたいと考えている方は、就労移行支援が適しています。
働き方と収入の面でも大きな違いがあります。
利用できる期間にも違いがあります。

就労移行支援のサービスは、全国にある「就労移行支援事業所」で受けられます。就職という目標を達成するためには、自分に合った事業所を選ぶことが非常に重要です。事業所ごとにプログラムの特色や雰囲気が異なるため、いくつかのポイントを押さえて比較検討しましょう。
就労移行支援事業所は、障害のある方が就職に必要な訓練を受けるために日々通う、学校や習い事のような場所です。多くは平日の日中に開所しており、利用者は自分の個別支援計画に沿ったプログラムに参加します。近年では、在宅での利用が可能な事業所も増えており、体調や障害特性に合わせて通所と在宅を組み合わせるなど、柔軟な利用形態を選択できる場合もあります。
事業所によって、強みとする分野や学べるスキルは様々です。例えば、以下のような特色があります。
自分がどんな職種を目指したいか、どんなスキルを身に付けたいかを考え、それに合ったプログラムを提供している事業所を選ぶことが大切です。
事業所の支援の質を判断する客観的な指標として、就職率(就職者数)と職場定着率があります。就職率は、その事業所からどれだけの人が就職できたかを示す数値です。定着率は、就職した人が半年後や1年後も働き続けている割合を示し、就職後のサポートの手厚さを反映します。多くの事業所は公式サイトなどで実績を公開しているため、必ず確認しましょう。
プログラム内容や実績も重要ですが、最終的には自分に合うかどうかが最も大切です。2年間通い続ける場所になるため、事業所の雰囲気、他の利用者との関わりやすさ、スタッフの対応などを自分の目で確かめることを強くお勧めします。ほとんどの事業所で無料の見学や体験利用が可能です。複数の事業所を実際に訪れて比較し、自分が「ここなら安心して通えそう」と感じられる場所を選びましょう。駅からの距離など、物理的な通いやすさも確認しておくと良いでしょう。
この記事では、就労移行支援制度の概要から対象者、サービス内容、利用料金、事業所の選び方までを詳しく解説しました。
就労移行支援は、障害や難病のある方が一般企業への就職という目標を叶え、自分らしく働き続けるためのスキルと自信を得られる公的な福祉サービスです。一人ひとりに合わせた手厚いサポートを通じて、職業訓練から就職活動、そして就職後の定着までをトータルで支援します。
「一般企業で働きたいけれど、何から始めればいいかわからない」と悩んでいるなら、まずは一歩踏み出して、お近くの就労移行支援事業所に相談してみてはいかがでしょうか。
特に、これからの時代に求められるWebスキルを身に付けて、在宅での働き方も視野に入れたいと考えている方には、専門的なITスキルを学べる事業所がおすすめです。 ワークスバリアフリーの就労移行支援サービスでは、Webスキル習得に特化したプログラムを提供しており、在宅での就業も可能です。事業所は松戸駅から徒歩4分と通いやすい立地にあり、ご自身のペースで就職準備を進めることができます。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。