Page Top

就労継続支援A型は、障害や病気のある方が雇用契約を結びながら働ける福祉サービスです。最低賃金以上の給料が保障され、スタッフのサポートを受けながら安定して働ける点が特徴です。しかし、同じ福祉サービスであるB型や就労移行支援との違いが分かりにくく、「自分はどの制度を利用できるのか」「仕事内容や給料はどの程度なのか」と悩む方も少なくありません。
本記事では、A型就労継続支援の基本的な仕組みから、B型や就労移行支援との違い、対象者や仕事内容、メリット・注意点まで詳しく解説します。
<この記事で紹介する3つのポイント>
目次
就労継続支援A型事業所は、障害や病気により一般企業での就職が困難な方が、支援を受けながら働ける場所を提供する重要な福祉サービスです。雇用契約を結んで働くことで、最低賃金が保障され、将来的な一般就労に向けたスキルアップも目指せます。
就労継続支援A型とは、障害などにより一般就労が難しい人が、雇用契約を結んだ上で、職業体験や訓練、就労に必要な能力の習得など一定の支援を受けて働くことができる障害福祉サービスです。
障害のある人の働き方は、大きく分けて「一般就労」と「福祉的就労」に分類されますが、就労継続支援A型は「福祉的就労」の一つに位置づけられています。福祉的就労とは、一般就労で仕事をすることに困難がある人が、障害福祉サービスの中で就労の機会を得て働くことを指します。
利用者は事業所と雇用契約に基づいて働くため、基本的には最低賃金額以上の給与が得られ、社会保険への加入義務も発生します。これにより、単なる作業の場ではなく、労働者としての権利と責任を持ちながら働くことが可能になります。
A型事業所は、一般企業などに就労することが困難な障害のある65歳未満の利用者に対して、雇用契約を締結して、生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うことを主な役割としています。
事業所での生産活動は、単に働く場所を提供するだけではありません。利用者が生産活動に携わることには、一般企業などに就職するために必要な知識・能力を身に付けるという重要な目的があります。継続的・安定的に利益を上げて、利用者の最低賃金を保証できる水準の生産活動を営むことが求められています。
最終的な目標として、一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労移行支援や一般就労を目指すことになります。つまり、A型事業所は一般就労への橋渡しとしての役割も担っているのです。
事業所では、公共職業安定所や障害者就業・生活支援センター、特別支援学校などの関係機関と連携して、事業所外の就労先や実習の受け入れ先を確保し、利用者の意向や適性を把握した上で、適切な仕事に携われるように支援を行っています。

就労継続支援A型を理解するには、類似する障害福祉サービスとの違いを把握することが重要です。就労継続支援B型や就労移行支援と比較すると、雇用契約の有無や対象者、利用目的などに明確な違いがあります。以下の表を参考に、それぞれのサービスの特徴を詳しく見ていきましょう。
| 雇用契約 | あり | なし | なし |
| 報酬 | 給料(最低賃金以上) | 工賃(作業対価) | 基本的になし(交通費など実費支給の場合あり) |
| 対象者 | 支援があれば雇用契約に基づき就労可能な方 | A型や一般就労が困難な方 | 一般就労を目指す方 |
| 利用期間 | 定めなし | 定めなし | 原則2年間 |
| 目的 | 働くこと・スキルアップ | 働くこと・居場所づくり | 一般就労のための訓練 |
就労継続支援A型と就労継続支援B型の最も大きな違いは、雇用契約の有無にあります。就労継続支援A型事業所は利用者と雇用契約を結ぶのに対し、就労継続支援B型事業所は雇用契約を結びません。この雇用契約の有無により、得られる報酬にも大きな差が生じます。就労継続支援A型では雇用契約に基づき最低賃金額以上の給与が保障されており、令和5年度の月額平均給与は86,752円となっています。
これは前年度の83,551円から上昇しており、近年は上昇傾向が見られます。一方、就労継続支援B型では雇用契約を結ばないため、生産活動の対価として「工賃」を受け取る形になります。B型の工賃は最低賃金を下回ることが多く、作業内容や時間に応じて支払われますが、A型と比較すると金額は低くなる傾向があります。
就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、社会保険への加入義務も発生し、一般企業と同様の労働関係法令が適用されます。これにより、利用者は労働者としての権利と責任を持ちながら働くことになります。
就労継続支援A型とB型では、利用対象者や年齢制限に違いがあります。就労継続支援A型の利用対象者は、身体障害、知的障害、精神障害や発達障害、難病がある原則18歳以上65歳未満の方で、適切な支援があることで雇用契約に基づく就労が可能な方となっています。
就労継続支援B型の対象者は、年齢や体力の面から一般企業や就労継続支援A型で働くことが困難な方、50歳以上または障害基礎年金1級受給者、就労移行支援事業者によるアセスメントにより就労面の課題が把握されている方などが含まれます。B型事業所には年齢制限がないため、高齢の方でも利用できる点が特徴です。
利用期間については、就労継続支援A型・B型ともに制限がありません。一度利用を開始すれば、期間の定めなく継続して利用することが可能です。ただし、A型事業所では雇用契約に期限がある場合、契約更新の有無によって利用期間が変わることもあります。
両サービスとも障害者手帳は必須ではありませんが、障害福祉サービス受給者証の取得が必要になります。医師の診断があれば、手帳を持っていない方でも利用できる可能性があります。
就労移行支援は、就労継続支援とは根本的に目的が異なるサービスです。就労移行支援事業所とは、一般企業などで働くことを希望している障害のある人に対し、就職に必要な知識や能力を実習などによって訓練の場を提供したり、職場探しを支援したりする事業所です。
最も大きな違いは利用期間で、就労継続支援A型事業所では利用期間が定められていないのに対し、就労移行支援事業所の利用期間は基本的に最長2年間と定められています。これは就労移行支援が一般就労への移行を前提としたサービスであるためです。
報酬面でも違いがあり、就労継続支援では働いた対価として給料や工賃を受け取れますが、就労移行支援では基本的に報酬はありません。一部の事業所では交通費などの実費支給がある程度です。
目的の違いも明確で、就労継続支援A型・B型が「働く場の提供」や「居場所づくり」を主な目的とするのに対し、就労移行支援は「一般就労のための訓練」が主目的となります。そのため、すでに働いている人は就労移行支援を利用できず、就労継続支援A型との併用もできません。

就労継続支援A型事業所を利用するには、特定の条件を満たす必要があります。障害の種類や年齢、就労経験などの要件が定められており、これらの条件を理解することで、自分や家族がサービスを利用できるかどうかを判断できます。また、障害者手帳の有無についても誤解されがちな点があるため、正確な情報を把握しておくことが重要です。
就労継続支援A型の利用対象者は、身体障害、知的障害、精神障害や発達障害、難病がある原則18歳以上65歳未満の方で、特定の条件を満たす必要があります。
具体的な条件として、就労経験があるが現在は離職している人が対象となります。また、就労移行支援サービスを利用して就職活動を行ったが、一般企業など通常の事業所での雇用に結びつかなかった人も利用できます。さらに、特別支援学校を卒業した後に就職活動を行ったが、一般企業など通常の事業所での雇用に結びつかなかった人も対象に含まれます。
年齢制限については、利用開始時点で65歳に達する前の5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けており、かつ65歳に達する前日に就労継続支援A型の支給決定を受けていた人は、その後も継続して利用することが可能です。
就労継続支援A型事業所では、さまざまな種類の障害を持つ方が利用対象となります。精神障害では、うつ病、適応障害、統合失調症、不安障害、パニック障害、てんかん、高次脳機能障害などが含まれます。
発達障害の分野では、ADHD(注意欠陥多動性障害)、自閉スペクトラム症(自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害)、学習障害、トゥレット症候群、吃音症などが対象となっています。
その他にも、知的障害や身体障害を持つ方も利用可能です。難病についても369疾病が対象に拡大されており、より多くの方がサービスを利用できるようになりました。これらの障害や疾病により一般企業での就労が困難でも、適切な支援があることで雇用契約に基づく就労が可能と判断される方が利用対象となります。
就労継続支援A型事業所を利用する際、障害者手帳の取得は必須ではありません。医師の診断があれば、手帳を持っていない方でも利用できる可能性があります。
実際にサービスを利用するために必要なのは「障害福祉サービス受給者証」です。この受給者証を申請するには、障害や疾患があることを証明する書類が必要になります。障害者手帳はその証明書類の一つですが、手帳を所持していない場合でも、自立支援医療受給者証や医師の診断書が証明書類として使用できます。
受給者証の申請手順や必要書類については、お住まいの市区町村の障害福祉窓口で詳しく確認することをおすすめします。障害福祉サービスの利用に関しては、最終的に自治体の判断により受給者証が発行されれば、どなたでも利用することが可能になります。手帳の有無に関わらず、まずは相談してみることが大切です。

就労継続支援A型事業所で行われる仕事は多岐にわたり、利用者の能力や興味に応じてさまざまな職種から選択できます。事務作業からWeb関連業務、製造業まで幅広い分野の仕事があり、一般企業と同様の業務内容を経験できることが特徴です。また、雇用契約に基づき最低賃金以上の給料が保障されているため、安定した収入を得ながらスキルアップを目指すことが可能です。
就労継続支援A型事業所の仕事内容は事業所によって異なり、軽作業からパソコンを使った高度な業務まで、利用者の適性やスキルに合わせてさまざまな選択肢があります。
主な仕事内容として、パソコンによるデータ入力代行やWebサイト作成などのIT関連業務があります。また、パンやお菓子などの製造業務、カフェやレストランでの接客業務も多くの事業所で行われています。工業関連では車部品などの加工作業、サービス業では清掃業務や配達業務なども実施されています。
近年では新型コロナウイルスの感染拡大以降、在宅勤務に対応した業務も増加しており、自宅でできるデータ入力やWeb制作業務なども選択できる事業所が出てきています。1日の実働時間は一般就労よりも比較的短い場合が多く、個人の体調や能力に合わせて調整可能です。
事務作業は就労継続支援A型事業所で最も一般的な仕事内容の一つです。パソコンによるデータ入力代行が主な業務で、企業から依頼された情報をシステムに入力したり、書類をデジタル化したりする作業を行います。
データ入力作業では、顧客情報の管理や売上データの整理、アンケート結果の集計など、企業の日常業務に欠かせない重要な作業を担います。書類作成業務では、会議資料の作成補助や報告書の整理など、オフィスワークの基本的なスキルを身に付けることができます。
これらの業務を通じて、パソコンの基本操作やビジネスマナー、正確性と集中力を養うことが可能です。事務作業の経験は一般企業への就職時にも活用でき、将来的なキャリアアップにつながる重要なスキルとなります。作業環境も静かで落ち着いており、集中して取り組みやすい特徴があります。
Web関連業務は、IT技術の発達により需要が高まっている分野で、多くのA型事業所でも取り入れられています。Webサイト作成業務では、企業のホームページ制作やECサイトの構築支援などを行います。
デザイン業務では、Webサイト用のバナー作成やロゴデザイン、チラシやパンフレットのデザインなど、創造性を生かした作業に従事できます。また、Web制作・運用アシスタントとして、サイトの更新作業やコンテンツの管理なども担当することがあります。
記事の編集やライティング業務も含まれており、企業ブログの執筆やSNS投稿の作成など、文章作成スキルを生かした仕事も可能です。これらの業務では、HTML/CSSの基礎知識やデザインソフトの操作方法、文章作成能力など、現代のデジタル社会で求められるスキルを習得できます。専門性の高い分野のため、習得したスキルは転職時にも大きなアドバンテージとなります。
軽作業は体力的な負担が少なく、多くの利用者が取り組みやすい仕事内容です。商品発送の梱包作業では、通信販売やECサイトで注文された商品を適切に梱包し、発送準備を行います。
倉庫での軽作業やパッキング業務では、商品の仕分けや在庫管理、商品の包装作業などを担当します。ピッキング作業では、注文書に基づいて倉庫内から必要な商品を集める作業を行い、検品作業では商品に不具合がないかを確認する重要な役割を果たします。
これらの作業は手先の器用さや集中力を生かせる業務で、正確性と責任感を身に付けることができます。また、チームワークを重視した作業が多く、コミュニケーション能力の向上にもつながります。作業手順が明確で覚えやすく、初めて働く方でも安心して取り組める特徴があります。物流業界の知識も身に付き、将来的な就職活動にも活用できる経験となります。
飲食・製造分野では、パンやお菓子などの製造業務が代表的な仕事内容です。パン製造では、生地の準備から焼き上げまでの一連の工程に携わり、製パン技術を習得することができます。
カフェやレストランでの調理補助業務では、食材の下処理や盛り付け、厨房の清掃など、飲食業界の基本的な業務を経験できます。接客業務も含まれる場合があり、お客様とのコミュニケーションスキルも向上させることが可能です。
お菓子製造では、クッキーやケーキなどの製造工程を学び、食品衛生の知識も身に付けられます。これらの業務では、手作業の技術や食品安全に関する知識、時間管理能力などを習得できます。製造した商品の販売を通じて、商品の品質管理や顧客満足度の重要性も理解できます。食品関連の資格取得支援がある事業所もあり、専門性を高めることも可能です。
清掃・施設管理業務は、オフィスビルや公共施設、商業施設などで行う重要なサービス業務です。屋内外の清掃作業では、床や窓の清掃、ゴミの回収、トイレの清掃など、施設の衛生環境を維持する役割を担います。
施設管理業務では、建物の設備点検や簡単なメンテナンス作業、来客対応なども含まれる場合があります。清掃作業は体を動かす仕事のため、適度な運動効果も期待でき、健康維持にも役立ちます。
この業務では、責任感と丁寧さが重要で、利用者や訪問者が快適に過ごせる環境づくりに貢献できます。清掃技術や洗剤の正しい使用方法、安全作業の知識などを習得でき、清掃業界での就職にも活用できるスキルが身に付きます。チームワークを重視した作業が多く、協調性やコミュニケーション能力の向上にもつながります。清掃業界は安定した需要があるため、将来的な就職先としても有望な分野です。
就労継続支援A型事業所では、雇用契約を結んで働くため、最低賃金額以上の給与が保障されています。これは就労継続支援A型で働くことの大きなメリットと言えるでしょう。
厚生労働省の調査結果によると、就労継続支援A型事業所の令和5年度月額平均給与は86,752円となっています。この金額は令和4年度の83,551円と比べると上昇しており、ここ数年は上昇傾向が見られます。各都道府県の最低賃金が適用されるため、地域によって給与水準に差はありますが、雇用契約に基づいた安定した収入を得ることができます。
ただし、給料から社会保険料などが差し引かれる場合もあるため、手取り収入は表示金額より少なくなることがあります。実際の収入は従事する仕事内容や勤務時間によって変動し、事業所によっても大きく異なります。長期間継続して働くことで昇給の可能性もあり、スキルアップとともに収入向上を目指すことも可能です。

就労継続支援A型事業所を利用することには、多くのメリットがあります。雇用契約に基づく安定した収入の確保、障害特性に配慮したサポート体制、そして将来的な一般就労に向けたステップアップの機会など、利用者にとって重要な利点が揃っています。
これらのメリットを理解することで、自分や家族にとって最適な働き方を見つける参考になるでしょう。
就労継続支援A型事業所の最大のメリットの一つは、雇用契約に基づく安定した収入が得られることです。利用者は事業所と雇用契約を結ぶため、基本的には最低賃金額以上の給与が保障されています。
厚生労働省の調査によると、就労継続支援A型事業所の令和5年度月額平均給与は86,752円となっており、B型事業所の工賃と比較して高い水準を維持しています。この安定した収入により、日常生活の基盤を築くことが可能になります。
また、雇用契約を結ぶことで社会保険への加入義務も発生し、勤務時間が週20時間以上の場合は労働保険にも加入できます。労働保険への加入により、離職時の失業保険の受給資格も得られるため、将来的な生活保障の面でも大きなメリットとなります。健康保険や厚生年金についても、勤務条件によって加入できる場合があり、一般企業と同様の福利厚生を受けられる可能性があります。
就労継続支援A型事業所では、障害特性や体調に配慮したきめ細かなサポートを受けながら働けることが大きな魅力です。丁寧な指導や職場体験、訓練の機会なども設けられており、一人ひとりに合わせたペースで働くことができます。
事業所のスタッフは障害への理解が深く、利用者の体調やスキル、適性などを考慮しながら適切な業務を提供します。体調が優れない日には休憩を取ったり、作業内容を調整したりするなど、柔軟な対応が可能です。また、短時間の利用から始めて徐々に勤務時間を延ばすことも可能で、無理なく働き続けられる環境が整っています。
職場でのコミュニケーションに不安がある方には、スタッフが仲介役となってサポートを行い、安心して業務に集中できる環境づくりに努めています。このような手厚いサポート体制により、一般企業での就労に不安を感じている方でも、自信を持って働くことができるようになります。
就労継続支援A型事業所は、将来的な一般就労に向けたステップアップの場としても機能します。事業所での経験を通じて就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には就労移行支援や一般就労を目指すことができます。
実際に、2022年(令和4年)には就労継続支援A型から4,818人が一般就労へ移行しており、多くの利用者が次のステップに進んでいます。事業所では利用者が一般就労を継続できるよう、就労移行支援体制加算として、利用後6か月以上継続して一般就労した場合の加算制度も設けられています。
A型事業所での経験は、履歴書に記載できる正式な職歴となるため、転職活動時にも有利に働きます。また、事業所での業務を通じて身に付けたスキルや経験は、一般企業での面接や実際の業務でも活用できます。さらに、事業所のスタッフから就職活動のサポートを受けることも可能で、求人情報の提供や面接対策なども実施しています。このように、A型事業所は単なる働く場ではなく、将来への橋渡しとしての重要な役割を果たしています。

就労継続支援A型事業所の利用を検討する際には、いくつかの注意点を理解しておくことが重要です。経済面での制約や事業所選びの競争率の高さなど、事前に把握しておくべきポイントがあります。
就労継続支援A型で働くことについて、大きなデメリットは特にありませんが、状況によっては経済面で不安を感じる場合があります。一般企業と比べて短時間勤務者も多いことなどから、賃金を上げるのが難しい事業所も存在します。
また、人気の事業所では採用募集を行っていない場合や、募集があっても面接の選考基準が高く、スキル不足などの理由で採用に至らないケースもあります。事業所によっては定員に限りがあるため、希望する場所で働けない可能性もあります。
さらに、雇用契約を結ぶ性質上、一般企業と同様に面接による選考があることも理解しておく必要があります。こうした注意点を踏まえ、複数の事業所を検討したり、事前の見学や体験利用を活用したりすることで、自分に適した事業所を見つけることが大切です。

就労継続支援A型事業所を利用するには、段階的な手続きが必要です。まず主治医に相談した後、就労継続支援A型事業所を探し、事業所の選考を受けます。選考に通過した後は、市区町村の障害福祉窓口で利用申請を行います。
具体的な流れとして、利用決定後に市区町村の障害福祉窓口で就労継続支援A型のサービス利用を申し出ます。その後、申請先の市区町村の担当職員から、生活状況などの聞き取り調査を受けることになります。次に、指定特定相談事業者に依頼するか、自分自身でサービス等利用計画案を作成し、提出します。
最終的に、利用サービスの内容が通知され、受給者証が発行されると、就労継続支援A型で勤務を開始できます。申請から支給決定までには約2か月程度かかることが多く、事業所探しと並行して申請を進めた方が良いケースもあります。詳しい手続きについては、事業所に相談することで適切なアドバイスを受けられます。利用開始前には、事業所の見学や体験利用を通じて、実際の作業内容や職場環境を確認することをおすすめします。
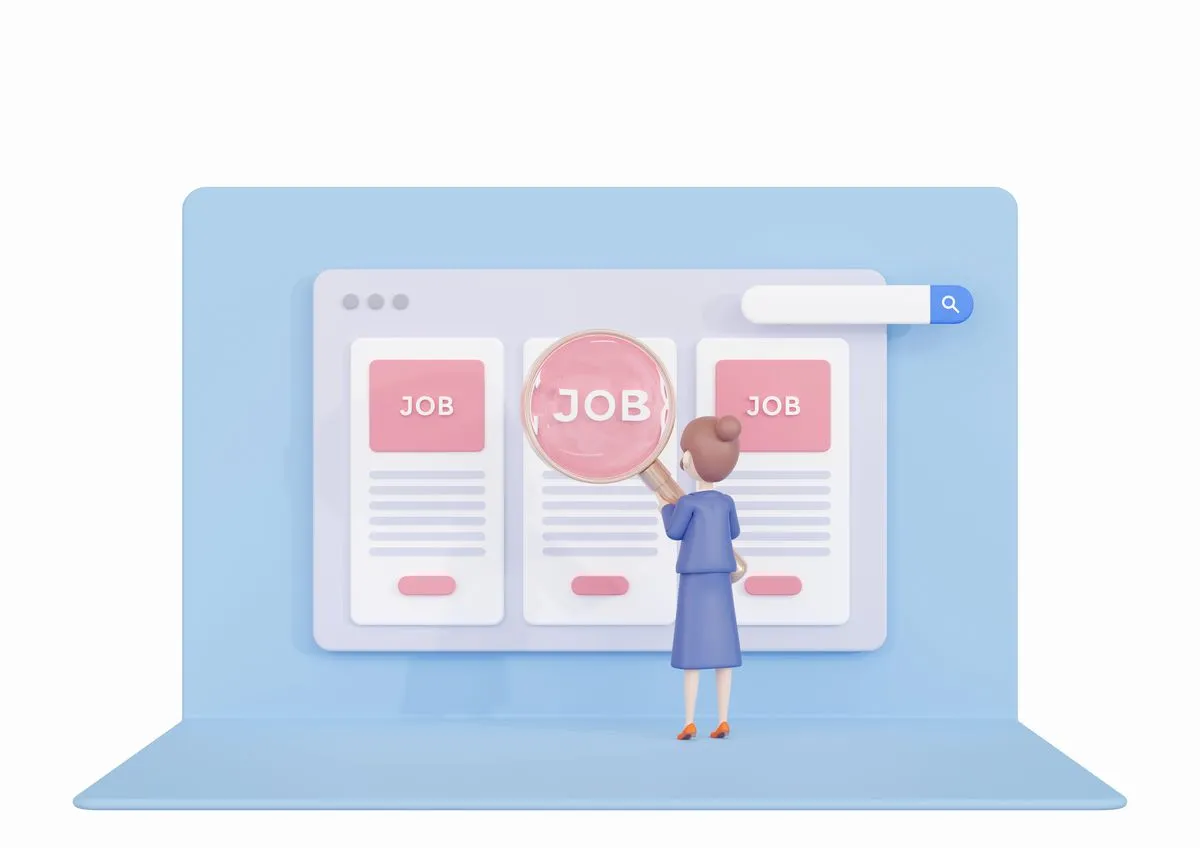
自分に合った就労継続支援A型事業所を見つけるには、適切な探し方と選定基準を知ることが重要です。事業所によって仕事内容や職場環境、給与水準が大きく異なるため、慎重に比較検討する必要があります。見学や体験利用を活用しながら、長く安心して働ける事業所を選ぶためのポイントを確認していきましょう。
就労継続支援A型事業所の探し方には複数の方法があります。市区町村の障害福祉窓口やハローワークなどで紹介してもらえるほか、インターネットで調べることもできます。
地域の障害福祉窓口では、担当者が利用者の状況や希望に応じて適切な事業所を紹介してくれます。ハローワークでは障害者向けの求人として就労継続支援A型事業所の募集が掲載されており、専門の相談員からアドバイスを受けることも可能です。
インターネットを活用する場合は、就労支援専門のサイトや各事業所の公式ホームページから情報収集できます。応募前に見学や体験ができるところもありますので、気になる事業所があれば事前に問い合わせしてみましょう。複数の方法を組み合わせることで、より多くの選択肢から自分に適した事業所を見つけることができます。
事業所選びの際には、仕事内容は自分に合っているか、事業所の雰囲気はどうか、給与の金額はどうか、通いやすい場所にあるかといった重要なポイントを確認する必要があります。
仕事内容については、求められるスキルや作業の難易度が自分の能力に適しているかを慎重に判断しましょう。事業所の雰囲気では、利用者をサポートする職員の人数やサポート内容、支援方法なども重要な確認事項です。給与については最低賃金が保障されているものの、事業所によって金額に差があるため事前確認が必要です。
数日間の実習を体験できる事業所もあります。実際に体験し、自分のやりたいことか、自分のスキルに合った仕事内容や環境かなど、チェックしてみましょう。通勤の利便性についても、交通費の支給有無や通勤時間を含めて総合的に検討することが大切です。
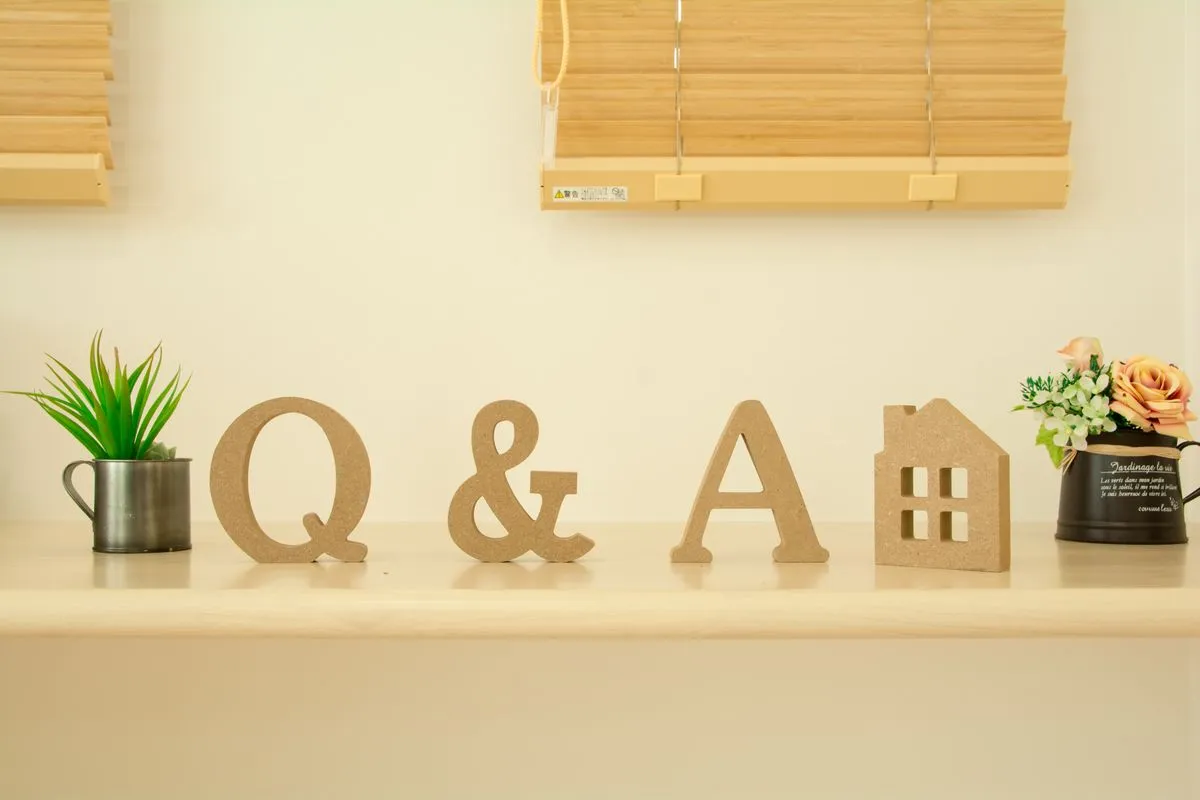
就労継続支援A型事業所の利用を検討する際に、多くの方が疑問に感じる点があります。勤務日数や利用期間、雇用関係に関する不安など、事前に知っておくべき重要な情報をQ&A形式で整理しました。これらの疑問を解消することで、より安心してサービスを利用できるでしょう。
勤務日数や勤務時間は事業所によって異なり、利用者の体調や能力に合わせて調整される場合が多いです。最初は短時間や少ない日数から始めて、慣れてきたら徐々に増やしていくことも可能です。
具体的な勤務日数については、各事業所に直接問い合わせて確認することが重要です。事業所によっては週2日から始められる場合もあれば、週5日を基本とする場合もあります。自分の体調や生活リズムに合わせて相談し、無理のない範囲で働けるよう調整してもらいましょう。見学や体験利用の際に、勤務日数についても詳しく相談することをおすすめします。
就労継続支援A型には、利用期間の制限はありません。一度利用を開始すれば、期間の定めなく継続して働くことが可能です。
ただし、利用する事業所と利用者との間で結ばれる雇用契約に期限がある場合は、契約更新の有無によって利用期間が異なります。雇用契約書を確認し、不明な点は契約している事業所に確認しましょう。
多くの事業所では、利用者の状況や希望に応じて長期間の利用を受け入れています。安定した働く場として継続的に利用できることは、A型事業所の大きなメリットの一つです。
ただし、利用者が一般就労への移行を希望する場合は、その支援も行われます。利用期間についての不安がある場合は、事業所の担当者に相談して明確にしておくことが大切です。
就労継続支援A型事業所では雇用契約を結んでいるため、一般企業と同様に労働関係法令が適用されます。
雇用契約に基づく労働者として働くため、労働基準法などの法令に従った適切な雇用管理が行われます。不当な解雇から労働者を保護する法的な仕組みも適用されます。
解雇の可能性や条件については、雇用契約書に記載されている内容を確認することが重要です。不明な点は契約している事業所に確認しましょう。多くの事業所では、利用者の障害特性や体調に配慮した働きやすい環境づくりに努めており、適切なサポートを受けながら安心して働ける体制が整えられています。
就労継続支援A型事業所は、障害のある方が雇用契約を結んで働ける重要な福祉サービスです。最低賃金以上の給与が保障され、障害特性に配慮したサポートを受けながら、さまざまな仕事に取り組むことができます。B型事業所や就労移行支援との違いを理解し、自分の状況に適したサービスを選択することが大切です。
事業所選びでは、仕事内容や職場環境、給与水準、通いやすさなどを総合的に判断し、見学や体験利用を活用して慎重に検討しましょう。利用期間に制限はなく、将来的には一般就労への移行も目指せるため、長期的なキャリア形成の場としても活用できます。
一般就労を目指す方には、DYMグループの就労移行支援がおすすめです。WEBスキルの習得や在宅利用の相談も可能で、松戸駅徒歩4分の好立地でサポートを提供しています。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。