Page Top
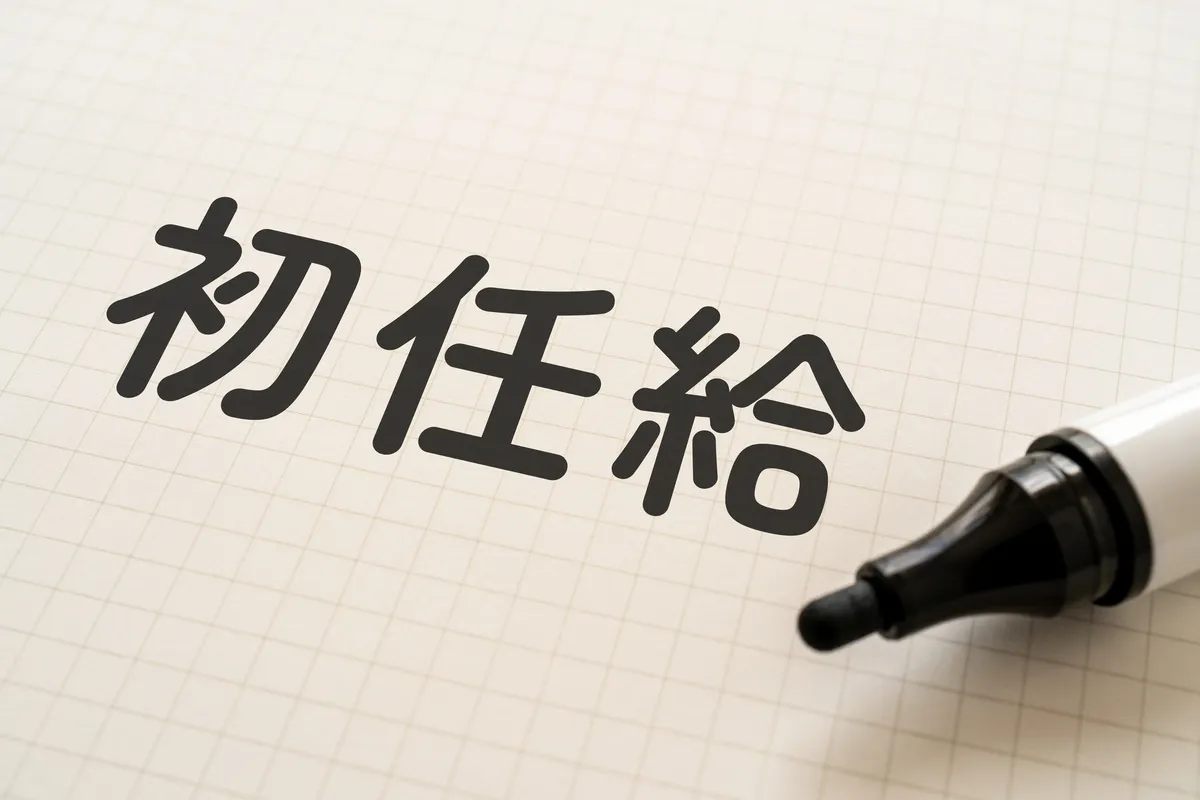
高卒で就職を考えている方にとって、初任給がどのくらいなのかは重要な関心事でしょう。この記事では、最新の統計データに基づく高卒の平均初任給や、実際に手元に残る手取り額、さらに大卒などほかの学歴との給与差について詳しく解説します。将来の収入アップの方法も紹介しているので、就職活動の参考にしてください。
<この記事で紹介する4つのポイント>
目次

高卒で就職する際、最も気になるのが初任給の金額でしょう。初任給は単なる数字以上の意味を持ちます。それは社会人としての第一歩を踏み出す際の経済的な基盤となり、将来のライフプランを考える上での重要な指標となるからです。
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、高卒の平均初任給は19万1,500円です。この数値は男女を合わせた全体の平均値であり、実際の初任給は企業の規模や業種、地域によって大きく異なります。
企業規模別に詳しく見ていくと、従業員1,000人以上の大企業では初任給が平均よりも高く設定される傾向があります。大企業では福利厚生が充実していることも多く、基本給以外の各種手当も手厚いため、総合的な待遇は中小企業よりも良好なケースが多く見られます。一方で、従業員100人未満の中小企業では、初任給は平均を下回ることもありますが、その分アットホームな職場環境や、早期からさまざまな業務を任せてもらえるなど、大企業にはない魅力があります。
業種別では、製造業や建設業、情報通信業などの技術系職種で初任給が高めに設定される傾向があります。特に製造業では、技能職として専門的な技術を身につけることで、将来的な収入アップも期待できます。一方、サービス業や小売業では初任給がやや低めになることもありますが、接客スキルやコミュニケーション能力を磨くことで、キャリアアップの道が開けます。
地域による差も無視できません。東京都や大阪府などの大都市圏では、生活費が高い分、初任給も地方都市と比べて高く設定されています。東京都内の企業では、高卒初任給が20万円を超えることも珍しくありません。しかし、地方都市では家賃や物価が安いため、初任給が低くても実質的な生活水準は都市部と大きく変わらないこともあります。
男女別で見ると、統計上では男性と女性の初任給に差が存在します。この差が生じる主な要因は、男女で選択する業界や職種に偏りがあることです。男性は製造業や建設業、運輸業など、比較的賃金が高い業界に就職する傾向があります。これらの業界では、体力を要する仕事が多く、それに見合った給与設定がなされています。
女性の場合、事務職やサービス業、医療・福祉分野への就職が多く見られます。これらの職種では、初任給が製造業などと比べて低めに設定されることがあります。ただし、事務職では残業が少なくワークライフバランスを保ちやすい、医療・福祉分野では資格取得により専門性を高められるなど、それぞれの職種にメリットがあります。
近年では、男女雇用機会均等法の浸透や、ダイバーシティ推進の動きにより、性別による賃金格差を解消しようとする企業が増えています。同一労働同一賃金の原則に基づき、職務内容が同じであれば性別に関係なく同じ給与を支払う企業も増加しており、今後は男女の初任給差がさらに縮小していくことが期待されます。
また、女性の社会進出が進むにつれ、従来は男性が多かった業界にも女性が進出するケースが増えています。建設業界では女性技術者の採用を積極的に行う企業が増え、IT業界でも女性プログラマーやシステムエンジニアが活躍しています。こうした変化により、男女の職種選択の幅が広がり、初任給の差も縮小していく可能性があります。
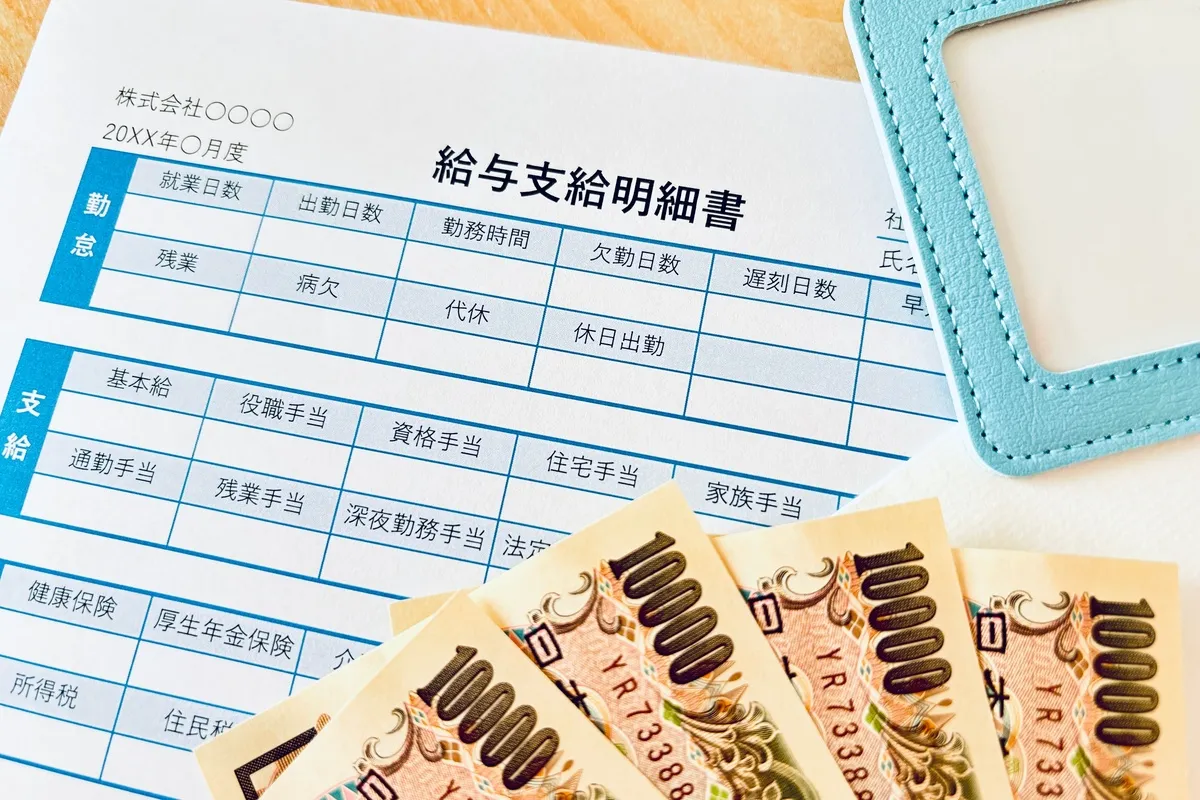
初任給19万1,500円と聞いて、そのまま全額が手元に残ると考えている方もいるかもしれません。しかし実際には、給与からはさまざまな控除があるため、銀行口座に振り込まれる金額は額面よりも少なくなります。ここでは、額面と手取りの違いについて、具体的な計算例を交えながら詳しく解説していきます。
額面とは、基本給に各種手当を加えた総支給額のことを指します。初任給19万1,500円という場合、これが額面金額にあたります。額面には基本給のほかに、さまざまな手当が含まれることがあります。
代表的な手当として、通勤手当があります。これは自宅から職場までの交通費を補助するもので、多くの企業で支給されています。公共交通機関を利用する場合は実費支給、自家用車通勤の場合は距離に応じた金額が支給されることが一般的です。住宅手当は、賃貸住宅に住んでいる従業員や、持ち家のローンを支払っている従業員に対して支給される手当です。企業によって支給条件や金額は異なりますが、月額1万円から3万円程度が相場となっています。
その他にも、家族手当(配偶者や子どもがいる場合)、資格手当(業務に関連する資格を保有している場合)、役職手当(リーダーや主任などの役職に就いた場合)など、企業によってさまざまな手当制度が設けられています。これらの手当は、基本給とは別に支給されるため、実際の収入は基本給よりも多くなることが一般的です。
求人票を見る際は、初任給の内訳をしっかり確認することが重要です。基本給が高い企業と、基本給は低いが手当が充実している企業では、額面は同じでも将来の昇給率や賞与額に差が出る可能性があります。基本給は昇給や賞与の計算基準となることが多いため、長期的な視点で判断することが大切です。
手取りとは、額面から社会保険料や税金などを差し引いた後、実際に銀行口座に振り込まれる金額のことです。一般的に、新卒者の手取り額は額面の約75~80%程度になることが多く、初任給19万1,500円の場合、手取りは約15万円から15万5,000円程度になると考えられます。
この計算をもう少し詳しく見てみましょう。額面19万1,500円から、健康保険料(約9,600円)、厚生年金保険料(約1万7,500円)、雇用保険料(約1,150円)、所得税(約3,600円)を差し引くと、手取りは約15万9,650円となります。ただし、これはあくまで概算であり、実際の金額は勤務地や扶養家族の有無などによって変動します。
手取り額を正確に把握することは、生活設計を立てる上で非常に重要です。家賃や食費、交際費など、毎月の支出を手取り額の範囲内でやりくりする必要があるからです。一般的に、家賃は手取りの3分の1以下に抑えることが理想とされています。手取り15万円の場合、家賃は5万円程度までに抑えることで、無理のない生活が送れるでしょう。
また、社会人2年目からは住民税の天引きも始まるため、手取り額がさらに減少することも覚えておく必要があります。1年目のうちから計画的に貯金をしておくことで、2年目以降の手取り減少にも対応できるようになります。
給与から天引きされる項目は、大きく分けて社会保険料と税金の2種類があります。これらは法律で定められた義務であり、すべての労働者が負担することになっています。それぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。
健康保険料は、病気やケガで医療機関を受診した際の医療費負担を軽減するための保険料です。日本では国民皆保険制度により、すべての国民が何らかの健康保険に加入することが義務付けられています。会社員の場合は、勤務先の健康保険組合または協会けんぽに加入することになります。
保険料率は加入する健康保険によって異なりますが、協会けんぽの場合、都道府県ごとに保険料率が設定されています。2024年度の全国平均は約10%で、この保険料を会社と従業員で折半します。つまり、従業員の負担は約5%となります。初任給19万1,500円の場合、健康保険料として約9,600円が天引きされることになります。
健康保険に加入することで得られるメリットは大きく、医療費の自己負担が原則3割に抑えられるほか、高額療養費制度により月々の医療費負担に上限が設けられています。また、病気やケガで働けなくなった場合の傷病手当金や、出産時の出産手当金など、さまざまな給付を受けることができます。
厚生年金保険料は、将来受け取る年金の財源となる保険料です。日本の年金制度は2階建て構造になっており、1階部分の国民年金(基礎年金)に加えて、会社員は2階部分の厚生年金にも加入します。これにより、将来受け取れる年金額が国民年金のみの場合よりも手厚くなります。
保険料率は18.3%で固定されており、これも会社と従業員で折半します。したがって、従業員の負担は9.15%となります。初任給19万1,500円の場合、厚生年金保険料として約1万7,500円が天引きされます。金額としては決して小さくありませんが、この保険料を納めることで、老後の生活保障が確保されることになります。
厚生年金の受給額は、加入期間と平均報酬額によって決まります。高卒で18歳から働き始めた場合、大卒者よりも4年長く保険料を納めることになるため、その分受給額も増える可能性があります。また、万が一の際には遺族年金や障害年金といった保障も受けられるため、単なる老後の備えだけでなく、現役世代の生活保障としても重要な役割を果たしています。
雇用保険料は、失業した際の失業給付や、育児休業給付金などの財源となる保険料です。雇用保険は、労働者の生活と雇用の安定を図るとともに、就職の促進を目的とした制度で、原則としてすべての労働者が加入対象となります。
保険料率は事業の種類によって異なりますが、一般の事業では2024年度は賃金の0.6%となっています。初任給19万1,500円の場合、雇用保険料として約1,150円が天引きされます。金額としては他の社会保険料と比べて少額ですが、その恩恵は決して小さくありません。
雇用保険に加入していることで、失業した場合には基本手当(いわゆる失業保険)を受給できます。また、育児休業を取得した際の育児休業給付金、介護休業を取得した際の介護休業給付金など、ライフステージに応じたさまざまな給付を受けることができます。さらに、スキルアップのための教育訓練を受ける際の教育訓練給付金制度もあり、キャリア形成の支援も受けられます。
所得税は、個人の所得に対して課される国税です。給与所得者の場合、毎月の給与から源泉徴収という形で天引きされます。所得税の税率は累進課税制度により、所得が多いほど高くなりますが、新卒者の場合は最も低い税率が適用されることがほとんどです。
初任給19万1,500円で扶養家族がいない場合、所得税として約3,600円程度が天引きされます。この金額は、給与額から給与所得控除や基礎控除、社会保険料控除などを差し引いた課税所得に対して計算されます。扶養家族がいる場合は、扶養控除が適用されるため、所得税額はさらに少なくなります。
年末には年末調整が行われ、1年間の所得税額が正確に計算されます。生命保険料控除や地震保険料控除など、年末調整で申告できる控除項目を活用することで、払いすぎた税金が還付される場合があります。新社会人のうちから、これらの控除制度を理解し活用することで、手取り収入を少しでも増やすことができます。
住民税は、居住している都道府県と市町村に納める地方税です。住民税の大きな特徴は、前年の所得に基づいて課税されるという点です。そのため、社会人1年目は前年の所得がないことから、住民税は天引きされません。
社会人2年目の6月から天引きが始まり、初任給ベースで計算すると月額約8,000円から1万円程度になることが一般的です。住民税は所得割と均等割から構成されており、所得割は前年の所得の約10%、均等割は自治体によって異なりますが年額5,000円程度です。これを12ヶ月で割った金額が、毎月の給与から天引きされることになります。
2年目になって急に手取りが減ったように感じるのは、この住民税の天引きが始まるためです。1年目のうちから、2年目以降の手取り減少を見込んで生活設計を立てておくことが重要です。また、ふるさと納税制度を活用することで、住民税の控除を受けることも可能です。自己負担2,000円で、それ以上の金額分の返礼品を受け取れるため、実質的に住民税の負担を軽減することができます。

学歴によって初任給にどの程度の差があるのか、厚生労働省の統計データをもとに比較してみましょう。この差は単に初任給だけでなく、その後の昇進スピードや生涯賃金にも影響を与える可能性があるため、しっかりと把握しておくことが重要です。
| 高校卒 | 191,500円 | – |
| 専門学校卒 | 223,000円 | +31,500円 |
| 高専・短大卒 | 220,000円 | +28,500円 |
| 大学卒 | 239,000円 | +47,500円 |
| 大学院卒 | 274,000円 | +82,500円 |
参考:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」
この表から分かるように、学歴が上がるほど初任給も高くなる傾向があります。特に大学院卒と高卒では、初任給に8万2,500円もの差があります。月額でこれだけの差があるということは、年収では約99万円の差になります。
しかし、この数字だけを見て判断するのは早計です。高卒で就職した場合、大卒者が大学に通っている4年間、すでに収入を得ることができます。仮に高卒の初任給19万1,500円で4年間働いた場合、約920万円の収入を得ることになります。この間、大卒者は学費を支払いながら学生生活を送ることになるため、実質的な経済的差はさらに大きくなります。
専門学校卒の初任給が高専・短大卒よりも高いのは興味深い点です。これは、専門学校で特定の分野に特化した実践的なスキルを身につけているため、即戦力として評価されることが要因と考えられます。美容師、調理師、自動車整備士など、専門的な資格を持って就職する場合、初任給が高く設定されることがあります。

給与に関する用語は似たようなものが多く、混同しやすいものです。特に「初任給」「基本給」「月給」の3つは、それぞれ異なる意味を持つにもかかわらず、しばしば混同されることがあります。ここでは、それぞれの違いについて整理して説明します。
初任給とは、新卒で入社した際に初めて受け取る給与のことを指します。文字通り「初めての給与」という意味で、入社後最初の給与支給日に受け取る金額です。多くの企業では、月末締めの翌月払いという給与体系を採用しているため、4月入社の場合は5月に初任給を受け取ることになります。
初任給には、基本給だけでなく各種手当も含まれているのが一般的です。例えば、初任給19万1,500円の内訳が「基本給16万5,000円+住宅手当1万5,000円+通勤手当1万1,500円」というようなケースがあります。この場合、求人票に記載される初任給は19万1,500円となりますが、実際の基本給は16万5,000円ということになります。
初任給は企業の採用戦略において重要な要素の一つです。優秀な人材を確保するため、競合他社よりも高い初任給を設定する企業もあります。しかし、初任給が高いからといって、必ずしもその企業が良い企業とは限りません。初任給以外にも、昇給率、賞与、福利厚生、職場環境など、総合的に判断することが大切です。
基本給とは、各種手当を除いた基本となる賃金のことです。時間外手当(残業代)、通勤手当、住宅手当、家族手当などは含まれません。基本給は、その従業員の基本的な労働に対する対価として支払われる金額で、年齢、勤続年数、能力、職務内容などを考慮して決定されます。
基本給が重要な理由は、多くの企業で昇給や賞与の計算基準となっているからです。例えば、「昇給率3%」という場合、基本給に対して3%の増額が行われます。初任給19万1,500円でも、基本給が16万5,000円の場合、昇給額は4,950円となります。同様に、賞与も「基本給の○ヶ月分」という形で計算されることが多いため、基本給が高いほど賞与額も大きくなります。
基本給と手当のバランスも重要なポイントです。初任給が同じ19万1,500円でも、「基本給18万円+通勤手当1万1,500円」の企業Aと、「基本給15万円+住宅手当3万円+通勤手当1万1,500円」の企業Bでは、将来的な収入に大きな差が出る可能性があります。企業Aの方が基本給が高いため、昇給や賞与の面で有利になるからです。
ただし、手当が充実していることにもメリットはあります。住宅手当や家族手当などは、生活費の負担を軽減してくれる重要な要素です。特に都市部で一人暮らしをする場合、住宅手当の有無は生活の質に大きく影響します。自分のライフスタイルや将来設計に合わせて、基本給と手当のバランスを考慮することが大切です。
月給とは、毎月固定で支払われる給与の総額を指します。基本給に加えて、毎月必ず支給される固定的な手当(役職手当、家族手当、住宅手当など)を含んだ金額です。ただし、時間外手当(残業代)など月によって変動する手当は含まれません。
月給制の最大の特徴は、欠勤や遅刻をしても基本的には減額されないという点です。これは「完全月給制」と呼ばれ、月の労働日数に関わらず一定額が支給されます。ただし、多くの企業では「日給月給制」を採用しており、欠勤した場合はその分が減額されることがあります。この違いは就業規則で確認することができます。
月給と月収の違いも理解しておく必要があります。月収は、月給に時間外手当や臨時の手当を加えた、その月に実際に受け取る給与の総額です。例えば、月給19万円の人が、ある月に3万円の残業代を得た場合、その月の月収は22万円となります。年収を計算する際は、この月収の変動も考慮する必要があります。

高卒の初任給は大卒と比べて低めですが、努力次第で将来の給料や年収を上げることは十分可能です。実際に、高卒で就職してから努力を重ね、大卒者以上の収入を得ている人は多くいます。ここでは、高卒者が収入アップを実現するための具体的な方法を詳しく紹介します。
まず重要なのは、専門的なスキルや資格を身につけることです。資格は客観的にスキルを証明できるため、昇進や転職の際に有利に働きます。業務に直結する資格を取得することで、資格手当が支給されたり、より責任ある仕事を任せられたりする可能性が高まります。
例えば、事務職であれば簿記検定やMOS(Microsoft Office Specialist)、製造業であれば各種技能検定、建設業であれば施工管理技士など、業界ごとに重要視される資格があります。これらの資格取得には時間と努力が必要ですが、長期的に見れば投資以上のリターンが期待できます。企業によっては資格取得支援制度を設けているところもあるため、積極的に活用しましょう。
次に、実務経験を積みながら実績を作ることが大切です。高卒で就職した場合、大卒者より4年早く社会人経験をスタートできるという大きなアドバンテージがあります。この期間を有効活用し、誰よりも早く実践的なスキルを身につけることができれば、学歴の差を埋めることができます。
具体的には、与えられた仕事に全力で取り組み、期待以上の成果を出すことを心がけましょう。また、自ら進んで新しい仕事にチャレンジし、スキルの幅を広げることも重要です。プロジェクトのリーダーを務めたり、業務改善の提案をしたりすることで、上司や同僚からの評価を高めることができます。こうした実績は、社内での昇進だけでなく、転職時のアピールポイントにもなります。
転職によるキャリアアップも有効な選択肢の一つです。ある程度の経験とスキルを身につけた後、より条件の良い企業に転職することで、大幅な年収アップを実現できる可能性があります。転職市場では、学歴よりも実務経験や実績が重視される傾向が強まっているため、高卒者にもチャンスは十分にあります。
副業や起業という選択肢もあります。本業で安定収入を確保しながら、休日や空き時間を活用して副業を行うことで、収入源を増やすことができます。最近では、インターネットを活用した副業も増えており、プログラミング、Webデザイン、ライティング、動画編集など、さまざまな分野で副業が可能です。
副業で得たスキルや人脈は、本業にも良い影響を与えることがあります。また、副業が軌道に乗れば、将来的に独立・起業という道も開けます。ただし、会社の就業規則で副業が禁止されている場合もあるため、事前に確認することが必要です。
高卒の平均初任給は19万1,500円で、手取りは約15万円から15万5,000円程度になります。大卒との初任給差は約4万7,500円ありますが、これは決して埋められない差ではありません。高卒で就職することで、大卒者より4年早く実務経験を積めるという大きなメリットがあり、この期間を有効活用することで、キャリアの差を縮めることができます。
重要なのは、初任給の金額だけで判断するのではなく、将来のキャリアプランを見据えて就職先を選ぶことです。企業の成長性、教育制度の充実度、昇進の可能性、職場環境など、さまざまな要素を総合的に判断することが大切です。初任給が低くても、その後の成長機会が豊富な企業であれば、長期的には高い収入を得られる可能性があります。
初任給はあくまでもスタートラインに過ぎません。そこからどのようにキャリアを積み重ねていくかは、一人ひとりの努力と選択にかかっています。高卒での就職活動に不安を感じている方や、自分に合った企業選びに迷っている方は、専門の就職支援サービスを利用することも有効な選択肢です。DYM就職では、既卒・第二新卒・フリーター・ニートの方を含む若年層の就職支援に特化しており、これまでに60,000名以上の面談実績とサービス満足度87%という高い評価をいただいています。書類選考なしで企業面接を設定できるため、学歴に関わらず就職のチャンスを広げることが可能です。経験豊富なキャリアアドバイザーが一人ひとりの適性や希望に合った企業を紹介し、面接対策から入社後のフォローまで、きめ細かなサポートを提供しています。まずはお気軽に無料相談から始めてみてください。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。