Page Top

少子高齢化を背景に、日本の多くの企業が深刻な人手不足に直面しています。特に、運輸や介護、建設業界など、社会インフラを支える分野での人材確保は喫緊の課題です。本記事では、人手不足の現状と根本的な原因を解説し、企業の採用力強化、従業員の定着率向上、生産性向上といった多角的な視点から、実践可能な解決策を具体的に紹介します。今後の見通しも踏まえ、企業がこの課題を乗り越えるためのヒントを提供します。
<この記事で紹介する3つのポイント>
目次
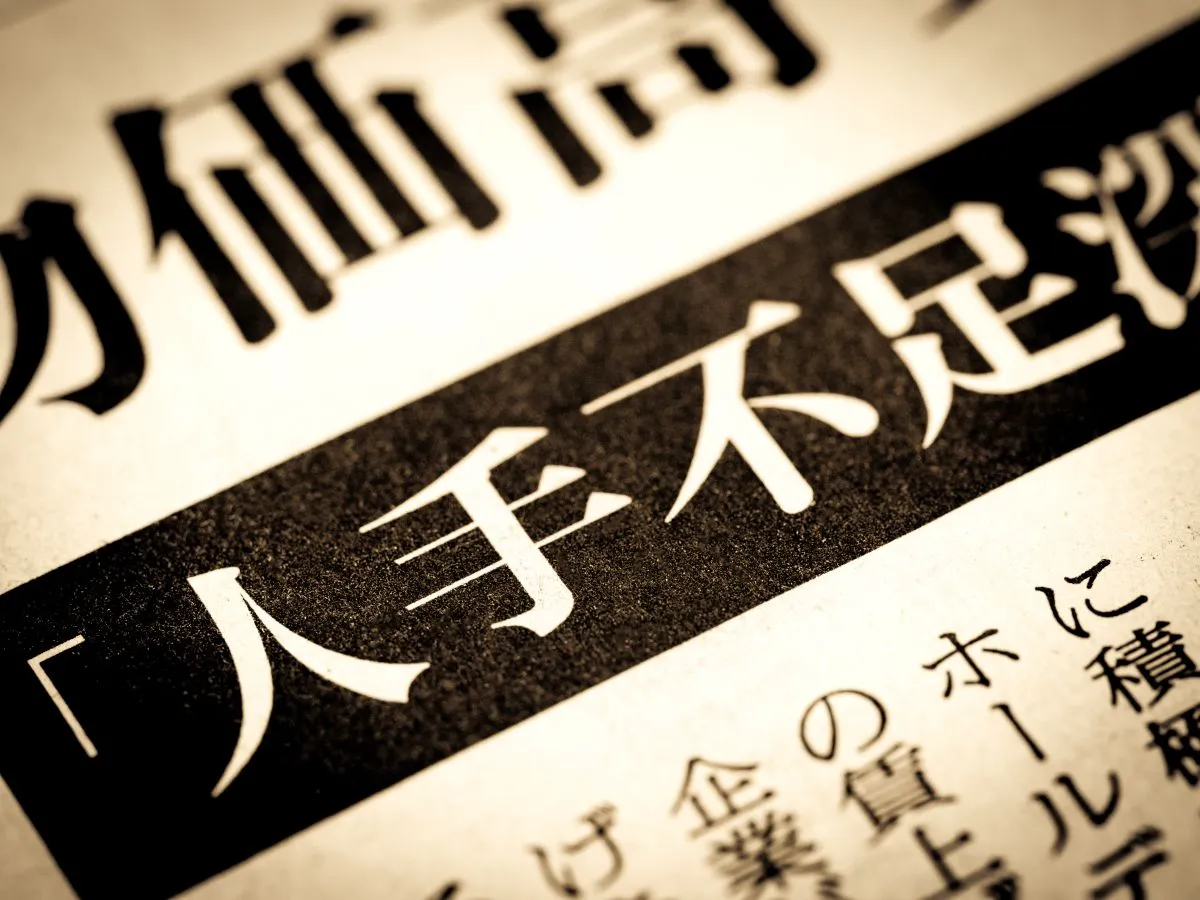
日本国内において、人手不足は多くの企業が直面する経営上の重要課題となっています。日本商工会議所が2023年に実施した調査では、中小企業の約7割が「人手不足」と回答し、そのうち6割以上が事業運営に影響が出ている状態です。
参考:日本商工会議所|「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」調査結果
労働政策研究・研修機構の雇用人員判断D.I.を見ても、2020年のコロナ禍以降、特に中小企業で不足感が悪化し続けています。帝国データバンクの2024年1月の調査では、正社員が不足していると感じる企業は52.6%にのぼりました。特に地方圏では、都市部への労働力人口の流出が原因で、大都市圏を上回る水準で人手不足が深刻化しており、企業の規模が小さいほどその傾向は強まっています。
参考:帝国データバンク|人手不足倒産、過去最多ペース「2024年問題」が直撃、物流業では倍増近くに
運輸・物流業界は、EC市場の拡大による宅配便取扱量の増加に反して、ドライバーの減少と高齢化が進むという構造的な問題を抱えています。2024年4月から働き方改革関連法に基づく時間外労働の上限規制が適用された、いわゆる「2024年問題」は、ドライバーの収入減少やさらなる人手不足を招き、物流の停滞を引き起こす可能性が懸念されています。
実際に、帝国データバンクの調査によれば、人手不足が原因で倒産した件数が過去最多を記録した2024年1月〜6月の期間において、建設業と並んで物流業が特に多い状況でした。パーソル総合研究所は、このまま対策が進まなければ2030年には約8.6万人のドライバーが不足すると推計しており、社会インフラの維持に向けた早急な対応が求められます。
介護・医療業界は、社会の高齢化に伴い需要が拡大し続ける一方で、供給が追いついていない典型的な分野です。特に介護分野では人手不足が顕著で、厚生労働省の推計によると、団塊ジュニア世代が高齢者となる2040年度には約272万人の介護職員が必要とされますが、現状のままでは約60万人が不足する見込みです。
参考:厚生労働省|第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について
また、医療分野でも2024年4月から医師の時間外労働に上限規制が課されたため、労働時間の短縮による医師不足が新たな課題として浮上しています。厚生労働省の「令和6年上半期雇用動向調査結果」では、「医療、福祉」業界の未充足求人数(人手を補充できていない求人数)は非常に多く、需要の高さに対して働き手が確保できていない実態が明らかになっています。
参考:厚生労働省|令和6年上半期雇用動向調査結果の概要 4 未充足求人の状況
建設業界は、人手不足が極めて深刻な業界の一つです。国土交通省の報告によると、建設業就業者数は1997年のピーク時(685万人)から2022年には479万人へと約200万人も減少しました。さらに、就業者の高齢化が著しく、2022年時点で55歳以上が全体の35.9%を占める一方、29歳以下は11.7%に過ぎず、次世代への技術継承が大きな課題となっています。
その一方で、インフラの老朽化対策や再開発などにより国内の建設需要は増加しており、2023年度の国内建設受注額は過去20年で最高額を記録しました。この需要と供給の大きなギャップにより、2025年には47万人から93万人の技能労働者が不足するという需給ギャップが予測されており、DX推進による生産性向上が不可欠です。

宿泊・飲食サービス業界は、コロナ禍で一度は需要が落ち込んだものの、その後の国内旅行やインバウンド需要の急回復により、人手不足が再燃しています。この業界は24時間体制のシフト勤務が多いことや、業務負担の大きさから離職率が高い傾向にあり、恒常的に人手が定着しにくいという課題を抱えています。
特に、少数の正社員と多数のアルバイト・パートタイム労働者で運営される店舗が多く、非正規社員の不足が事業運営に直結しやすい構造です。帝国データバンクの調査では、非正規社員の人手不足が最も深刻な業界は「飲食店」で64.3%、次いで「旅館・ホテル」が60.9%となっており、サービス提供に支障をきたすケースも少なくありません。
参考:帝国データバンク|人手不足に対する企業の動向調査(2024年10月)
IT・情報通信業界は、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進が加速する中で、システム開発や運用を担うIT人材の需要が急増しています。しかし、その需要に対して人材の育成や供給が追いついておらず、深刻な需給ギャップが生まれています。
経済産業省の調査では、IT人材の不足数は2030年に最大で45万人に達すると試算されました。特に、単にITツールを運用するだけでなく、最先端技術を扱える高度なスキルを持つ人材の不足が顕著です。帝国データバンクの調査では、正社員の人手不足割合が全業種の中で最も高いのが「情報サービス業」であり、企業の競争力を左右するDXのボトルネックとなっています。
帝国データバンク|人手不足に対する企業の動向調査(2024年10月)
日本で人手不足が起きる背景には、単一ではなく複数の要因が複雑に絡み合っています。最も根源的な原因は、少子高齢化の加速による生産年齢人口(15〜64歳)の絶対数の減少です。これに加えて、産業構造の変化と働き手の価値観の変化が、労働市場における需要と供給のミスマッチを深刻化させています。
事務職のように働き手が過剰な職種がある一方で、建設や介護といった社会に不可欠な職種で深刻な人手不足が生じる「構造的失業」が起きています。さらに、個々の企業に目を向けると、長時間労働や休日出勤の常態化、労働負荷に見合わない賃金・待遇、不公平な人事評価といった労働環境の問題が、既存従業員の離職や新規採用の困難を招き、人手不足に拍車をかけているのが現状です。
日本における人手不足の最も根源的な原因は、少子高齢化による生産年齢人口(15〜64歳)の減少です。日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少に転じており、今後もこの傾向は続くと予測されています。内閣府の将来推計によれば、日本の総人口は2060年には1億人を下回り、2070年には人口の約40%を65歳以上の高齢者が占めるようになるとのことです。
これまで日本企業の多くが採用の主軸としてきた若年層や中堅層が絶対数として減少していくため、従来通りの採用活動を続けていては、必要な労働力を確保することが構造的に困難になります。この人口動態の変化は、企業にとって長期的な視点での人材戦略の見直しを迫るものです。

若者世代を中心に、仕事に対する価値観が大きく変化していることも人手不足の一因です。かつて重視された安定性だけでなく、自己のスキルアップやキャリア成長の機会を職場に求める傾向が強まっています。これにより、企業の育成体制やキャリアパスが魅力的でない場合、優秀な人材ほど早期に転職を選択するようになりました。
また、産業構造の変化により、企業が求める職種と求職者が希望する職種が一致しない「構造的失業」も深刻化しています。例えば、一般事務職の有効求人倍率は1倍を大きく下回る一方で、建設、介護、サービスといった職種では2倍を超える高い倍率となっており、人手が余っている職種と足りない職種の二極化が進んでいます。
求職者が企業を選ぶ上で、労働環境や待遇は極めて重要な判断基準です。人手不足に悩む企業の中には、労働負荷の大きさと給与・待遇が見合っていないことが原因で、人材の採用難や早期離職を招いているケースが少なくありません。特に小売業や飲食サービス業などでは、休日の取りにくさや長時間労働が常態化している職場もあり、働き手から敬遠される要因となっています。
また、業務に必要な専門知識のアップデートが常に求められるような仕事では、精神的な負担も大きくなります。さらに、年功序列の風土が根強く残り、個人の成果や能力が公平に評価されない人事制度は、特に優秀な若手社員のモチベーションを削ぎ、離職につながる大きなリスクとなります。
深刻化する人手不足に対応するため、企業は多角的な視点から対策を講じる必要があります。人手不足は構造的な問題であるため、単一の施策で解決することは難しく、複数のアプローチを組み合わせて実践することが重要です。具体的には、まず新たな人材を惹きつけるための「採用力の強化」が挙げられます。
同時に、今いる従業員が働き続けたいと思える環境を整え、流出を防ぐ「従業員の定着率向上」も欠かせません。さらに、限られた人員で事業を維持・成長させるためには、DX推進やITツールの活用による「生産性の向上」が不可欠です。そして、従来の採用ターゲットに固執せず、高齢者や女性、外国人といった「多様な人材の活用」を進めることで、新たな労働力を確保することが可能になります。
人手不足が深刻化し、求職者優位の「売り手市場」が続く中、従来のように求人広告を出して応募を待つだけの採用手法では、必要な人材を確保することが困難になっています。これからの採用活動には、自社の魅力を積極的に発信し、求める人材へ直接アプローチする「攻め」の姿勢が不可欠です。採用活動にマーケティングの視点を取り入れ、自社で働くことの価値を高めていく必要があります。
具体的には、採用ブランディングの推進やダイレクトリクルーティングの活用、さらには社員紹介を促すリファラル採用といった能動的な手法へ転換し、採用戦略そのものを見直すことが求められます。
売り手市場が続く現代において、応募者を待つだけの姿勢では優秀な人材の確保は困難です。マーケティングの考え方を応用した「採用マーケティング」の視点を取り入れ、自社の魅力や働きがいを積極的に発信し、求職者から選ばれる企業になるための「採用ブランディング」が重要になります。
具体的には、自社が求める人材像を明確にした上で、その人材に対して仕事のやりがい、自己成長の機会、企業文化といった要素を正確に伝えることが求められます。単に労働条件を提示するだけでなく、入社後にどのようなキャリアを築けるのか、働くイメージを具体的に持たせることが、応募者の意欲を高め、入社後のミスマッチを防ぐ鍵となるでしょう。

従来の求人広告や人材紹介エージェントに頼る「待ち」の採用手法だけでは、母集団形成が難しくなっています。そこで有効なのが、企業側から直接、求める人材にアプローチする「ダイレクトリクルーティング」です。これは、データベースなどから自社の要件に合う候補者を探し出し、スカウトメールを送るなどして積極的に働きかける「攻め」の採用手法を指します。
この方法により、転職をまだ具体的に考えていない潜在層にもアプローチすることが可能になります。自社の事業内容や求める役割を直接伝えることで、候補者の興味を引きつけ、より質の高いマッチングを実現する効果が期待できるでしょう。
自社を深く理解している社員からの紹介を通じて候補者を募る「リファラル採用」は、ミスマッチの防止に非常に効果的な手法です。紹介する社員は、候補者のスキルや人柄だけでなく、自社の文化や働き方にフィットするかどうかを判断した上で推薦するため、入社後の定着率が高い傾向にあります。
また、一度退職した元社員を再雇用する「アルムナイ採用」も有効な選択肢の一つです。彼らは既に企業文化や業務内容を熟知しているため、即戦力として期待できるだけでなく、外部で得た新たな知見を組織にもたらしてくれる可能性もあります。これらの方法は、採用コストを抑制しながら、自社との親和性が高い人材を確保する上で大きなメリットがあります。
どれだけ採用活動を強化しても、新たに入社した人材がすぐに辞めてしまっては、人手不足は一向に解消されません。これは「穴の空いたバケツで水を汲む」のと同じ状態であり、採用コストが無駄になるだけでなく、既存社員の負担を増大させる悪循環に陥ります。したがって、人手不足解消の第一歩は、現在在籍している従業員の定着率を上げることです。
厚生労働省の調査でも離職理由の上位に労働条件の悪さが挙げられており、給与や休日といった待遇の改善、公平な人事評価制度の構築、そして従業員が将来像を描けるキャリアパスの明示と教育制度の充実が重要な鍵となります。
新たな人材を採用しても、すぐに離職されては人手不足は解消されません。まずは従業員の定着率を高めるため、労働条件の見直しと待遇改善が不可欠です。給与水準の向上や休日数の確保はもちろんのこと、現代の多様な働き方のニーズに応えることも重要になります。
具体的には、テレワーク制度の導入や、育児・介護と両立しやすい時短勤務、フレックスタイム制など、従業員一人ひとりの事情に合わせた柔軟な働き方を許容することが、企業の魅力向上につながります。厚生労働省の調査でも、離職理由の上位に「労働時間・休日等の労働条件が悪かった」が挙げられており、この点の改善は定着率向上に直結するといえるでしょう。
従業員が自身の働きや貢献に対して正当な評価を受けていると感じることは、仕事へのモチベーションや企業へのエンゲージメントを維持する上で極めて重要です。特に年功序列の風土が根強く残っている場合、成果を出している若手や優秀な人材が不満を抱きやすく、「優秀な人から辞めていく」という事態を招きかねません。
そのため、年齢や社歴に関わらず、個々の成果や能力、業務への貢献度を客観的かつ公平に評価する制度を構築することが求められます。評価基準を明確にし、フィードバックを通じて従業員の成長を促す仕組みは、納得感を高め、組織全体の活性化にもつながるでしょう。
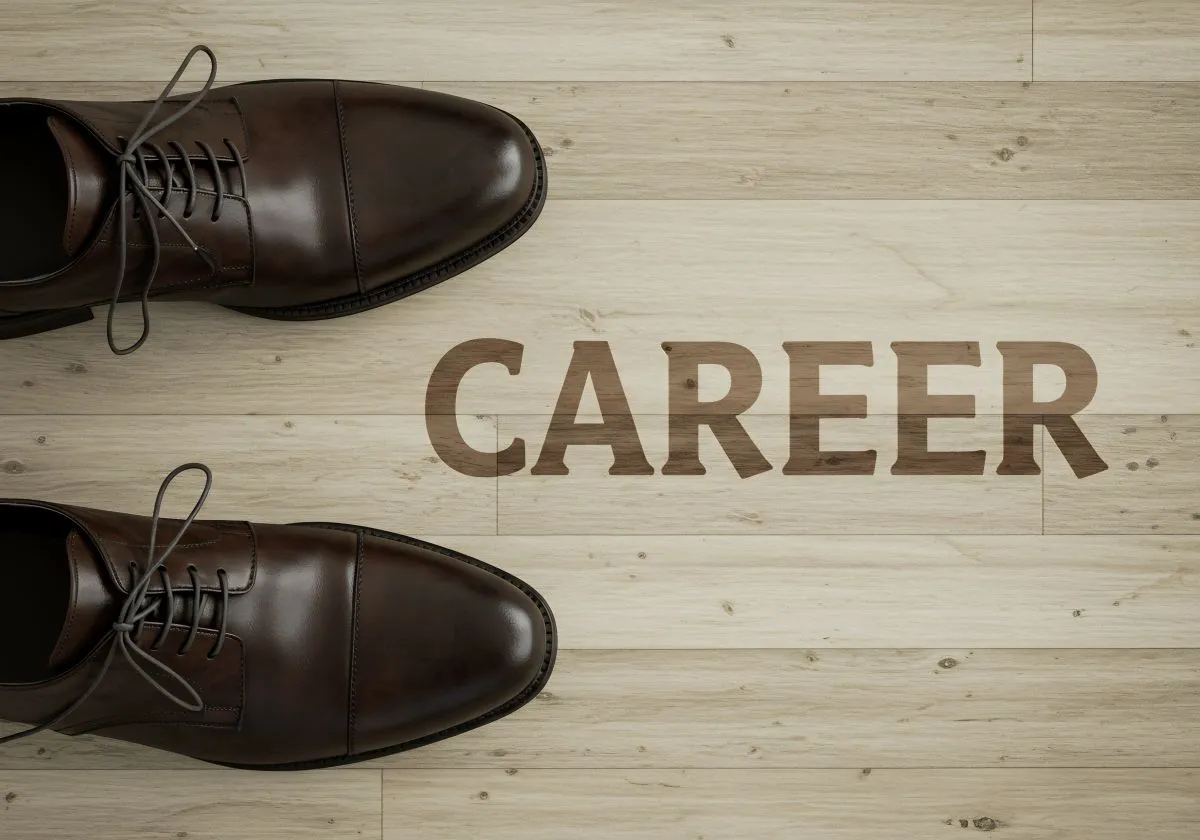
従業員がこの会社で働き続けることで、どのように成長し、どのようなキャリアを歩んでいけるのかを具体的に示すことは、将来への安心感と働く意欲を高めます。キャリアパスを透明化し、社内でのキャリアアップが目指せる仕組みを整えることが重要です。
加えて、従業員の学び直しを企業が支援する「リスキリング」や「リカレント教育」を推進することも効果的でしょう。新しいスキルを習得する機会を提供することで、従業員は自身の市場価値を高めることができ、企業は内部から必要な人材を育成できます。こうした人的投資は、従業員のエンゲージメント向上と離職防止に大きく貢献します。
労働力人口の減少が避けられない以上、少ない人員でより多くの成果を創出するための生産性向上の取り組みは、企業が存続していく上で不可欠です。人手が足りないのであれば、従業員一人ひとりの労働生産性を高めることで、企業全体の生産力を維持・向上させることが可能になります。その最も有効な手段が、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進やITツール・ロボットの導入による業務改善です。
手作業で行っていた定型業務を自動化・省力化することで、従業員はより付加価値の高いコア業務に集中できるようになり、業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を排除できます。
限られた人員で成果を最大化するためには、生産性の向上が不可欠であり、その鍵を握るのがDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進です。DXは単にITツールを導入することではなく、デジタル技術を活用して業務プロセスやビジネスモデルそのものを変革し、企業価値を高める取り組みを指します。
例えば、紙の書類や押印といったアナログな作業をデジタル化することで、業務は大幅に効率化され、従業員の負担も軽減されます。特に中小企業では、古いシステムを使い続けることで非効率な業務が温存されがちですが、DXによってこれらの課題を解決し、従業員が付加価値の高いコア業務に集中できる環境を整えることが可能です。
具体的な生産性向上の手段として、ITツールやシステムの導入が挙げられます。例えば、定型的なパソコン作業を自動化するRPA(Robotic Process Automation)は、請求書作成やデータ入力といった業務の負担を大幅に削減します。西洋フード・コンパスグループ株式会社では、RPA導入により店舗の事務作業を本社に集約・自動化し、フルタイム10人分に相当する時間を削減することに成功しました。
また、AI-OCR(AIによる文字認識)とRPAを組み合わせれば、紙の書類からのデータ転記作業を自動化できます。その他、飲食店における配膳ロボットや、建設現場での遠隔臨場を可能にするネットワークカメラなど、各業界の特性に合わせたツールの活用が業務の省力化と効率化を実現します。
社内の業務の一部を、専門的なノウハウを持つ外部の企業に委託するアウトソーシングは、人手不足を補う有効な手段です。経理や人事、コールセンター業務など、専門性は高いものの必ずしも社内で対応する必要がないノンコア業務を外部に委託することで、自社の従業員は事業の核となるコア業務に集中できます。これにより、企業全体の生産性向上や競争力強化が期待できるでしょう。
特に、年末調整や決算期など業務量が時期によって大きく変動するバックオフィス部門では、繁忙期に合わせて人材派遣やアウトソーシングを活用することで、柔軟に人手を確保し、従業員の業務負荷を平準化することが可能です。

少子高齢化により、これまで採用の主軸とされてきた若年層の労働力が先細りになる中、企業は採用の視野を広げ、多様な人材を積極的に活用していく必要があります。日本の就業者数は生産年齢人口が減る中でも微増していますが、その背景には65歳以上のシニア層や女性の労働参加率の上昇があります。
働く意欲のある高齢者や、出産などのライフイベントで一度離職した女性、さらには増加を続ける外国人材は、人手不足を解消する上で貴重な労働力です。こうした多様な人材がそれぞれの能力を最大限に発揮できるよう、時短勤務や再雇用制度の整備、ダイバーシティを尊重する企業文化の醸成が求められます。
生産年齢人口が減少する中で、働く意欲のある高齢者・シニア層は貴重な労働力です。実際に、日本の就業者数は生産年齢人口の減少に反して近年増加傾向にありますが、その大きな要因は65歳以上のシニア層と女性の労働参加が進んだことです。企業は法律で定められた65歳までの雇用確保措置に加え、70歳までの就業機会確保に努めることが求められています。
株式会社オハラの事例では、早朝の短時間勤務制を導入したことで意欲の高い高齢者が集まり、職場全体の活性化にもつながりました。定年制の廃止や引き上げ、経験豊富なシニア人材の知見を活かす再雇用制度の導入は、人手不足解消に直結する重要な取り組みです。
近年、女性の年齢階級別労働力率を示す「M字カーブ」は改善傾向にありますが、依然として出産や育児を機に離職を余儀なくされる女性は少なくありません。多様な人材を活用するためには、女性がライフイベントを経てもキャリアを継続できる環境整備が不可欠です。
具体的には、産休・育休制度の充実はもちろん、復職支援プログラムや、育児と両立しやすい時短勤務、テレワークといった柔軟な働き方の選択肢を提供することが求められます。こうした取り組みは、優秀な女性人材の離職を防ぎ、定着率を高めるだけでなく、多様な視点を経営に取り入れることで組織の活性化にもつながるでしょう。
国内での人材確保が困難になる中、外国籍の人材を積極的に採用することも有効な解決策となります。厚生労働省の発表によると、2023年10月末時点で日本で働く外国人労働者数は初めて200万人を超え、特に製造業や建設業でその活躍が目立っています。
参考:厚生労働省|「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)
外国人材の雇用は、単なる労働力の確保にとどまりません。多様な文化や価値観が組織にもたらされることでダイバーシティが推進され、新たなイノベーションの創出が期待できます。岡山県の興南設計株式会社では、外国人留学生の採用をきっかけに海外展開に成功しており、外国人の雇用が企業の新たな経営戦略につながる可能性を示しています。
人手不足は一過性の現象ではなく、今後も長期にわたって継続する可能性が極めて高いと考えられています。その根拠は、根本原因である少子高齢化の流れが今後も続くと予測されているためです。パーソル総合研究所は、2035年には約384万人もの人手不足が発生するという推計を発表しています。
参考:株式会社パーソル総合研究所|労働市場の未来推計2035
また、いわゆる「団塊ジュニア」世代の多くが定年退職を迎える2025年以降、労働力の中核を担ってきた人材の減少がさらに人手不足を深刻化させるとの見方もあります。一方で、AIやロボットといった技術革新は、この課題を乗り越えるための鍵となる可能性があります。単純作業や定型業務を自動化することで、人間はより付加価値の高い業務に集中できるようになり、労働生産性の向上が期待されるでしょう。

人手不足は短期的な問題ではなく、今後さらに深刻化することが予測されています。日本の少子高齢化はますます進行し、2025年以降は「団塊ジュニア」世代が定年退職の時期を迎え始め、労働力の中核を担ってきた層が大量に市場から去っていく見込みです。パーソル総合研究所の推計によると、2035年には約384万人もの人手が不足するとされています。
参考:株式会社パーソル総合研究所|労働市場の未来推計2035
さらに先の2040年には、団塊ジュニア世代が65歳以上の高齢者となり、社会保障の担い手が減少する一方で需要は増大します。特に介護業界では、2040年度には約60万人の介護職員が不足すると見込まれており、社会機能の維持が困難になるほどの深刻な事態が懸念されています。
参考:厚生労働省|第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について
長期化する人手不足への対応策として、AI(人工知能)やロボット技術の活用が一層重要になります。これらの技術は、人間の労働力を完全に代替するものではなく、人間と共存し、業務を効率化するパートナーとしての役割が期待されます。
例えば、データ入力や在庫管理、問い合わせ対応といった定型的な業務や単純作業をAIやロボットに任せることで、人間は企画立案や顧客との高度なコミュニケーションなど、より付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになります。すでにレストランの配膳ロボットや工場の運搬ロボットなどが実用化されており、今後は介護や医療といった分野でも、負担の大きい作業を支援する技術の導入が進むでしょう。
人口動態というマクロな変化を前に、企業が一社で人手不足の流れを止めることは不可能です。したがって、企業が今から備えるべきは、少ない人員でも高い成果を創出できる組織へと変革することです。その柱となるのは、「生産性の向上」と「多様な人材の活用」の二つに他なりません。
DXを推進して徹底的な業務効率化を図るとともに、これまで採用ターゲットとしてこなかった高齢者、女性、外国人など、多様な背景を持つ人々が活躍できる柔軟な働き方と公平な評価制度を整備することが不可欠です。従来の人口増加を前提としたビジネスモデルや人事制度から脱却し、変化に対応できる持続可能な組織体制を構築することが、今後の企業存続の鍵を握ります。
ここでは、人手不足という課題に対して多くの企業経営者や人事担当者が抱える、共通の疑問について解説します。特に資金や知名度で制約のある中小企業がすぐに着手できる具体的な対策や、若手人材の確保に苦戦する業界に共通する特徴など、より実践的で切実な問題を取り上げます。
また、それぞれの質問に対して、具体的な事例を基に解決のヒントとなる情報を提供していきます。自社の状況と照らし合わせながら、人手不足という複雑な問題を乗り越えるための一助としてご活用ください。

資金力や知名度で大企業に劣る中小企業でも、すぐに着手できる人手不足対策はあります。まず、業務プロセスを見直し、「ムリ・ムダ・ムラ」を洗い出して削減することです。これにより、既存の従業員の負担を軽減し、生産性を高めることができます。また、高額な設備投資が難しい場合でも、クラウド型のコミュニケーションツールや勤怠管理システムを導入すれば、情報共有の円滑化や事務作業の効率化が図れます。
人材の定着という観点では、三重県の大起産業株式会社が導入したメンター制度のように、新入社員と年齢の近い先輩が相談役となる仕組みは、早期離職の防止に効果的です。コストをかけずに従業員のエンゲージメントを高める施策から始めるのがよいでしょう。
国は人手不足対策として、企業の課題に応じた助成金・補助金制度を設けています。人材確保の面では、中途採用者や高齢者・障害者といった就職困難者の雇用を支援する「中途採用等支援助成金」や「特定求職者雇用開発助成金」などがあります。
既存従業員の能力向上には、研修費用を補助する「人材開発支援助成金」が有効です。さらに生産性向上を目的とした支援も手厚く、賃上げを伴う設備投資を助成する「業務改善助成金」、IoT・ロボット導入を後押しする「中小企業省力化投資補助金」、働き方改革に資するツール導入を支援する制度などが活用できます。
若手人材の確保に苦戦している業界には、いくつかの共通した特徴が見られます。一つは、肉体労働が中心であったり、ケガのリスクが伴ったりと、身体的な負担が大きいことです。建設業や運輸業がこれに該当します。また、宿泊・飲食サービス業のように、夜勤や土日祝日の出勤が常態化しており、ワークライフバランスを重視する若者の価値観と合わない場合も敬遠されがちです。
さらに、仕事の専門性が高いにもかかわらず、給与水準が他の業界と比較して高くない場合も、魅力的に映りません。現代の若者は自己成長を求める傾向が強いため、キャリアパスが不明確で、スキルアップの機会が少ない職場も選ばれにくいといえるでしょう。
人手不足は日本の多くの企業が直面する深刻な経営課題ですが、本記事で紹介したように対策は多岐にわたります。採用強化や定着率向上、生産性向上など、自社の状況に合った施策を組み合わせ、できることから着手することが、この課題を乗り越える鍵となります。
生産性向上の有効な一手として、ノンコア業務のアウトソーシングを検討しませんか。DYMの事務代行サービスは、煩雑な事務作業を専門スタッフに任せ、社員がコア業務に集中できる体制づくりを強力にサポートします。お気軽にご相談ください。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。