Page Top
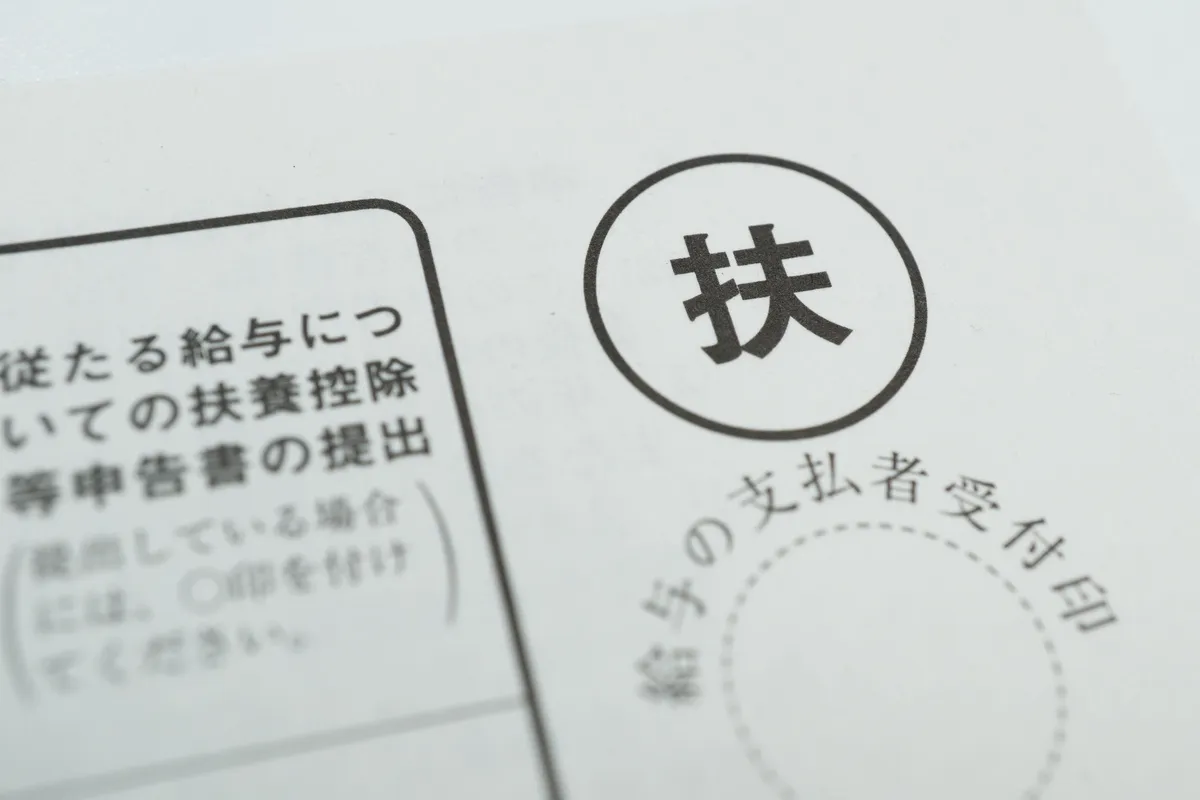
扶養とは、自分の収入だけでは生活が難しい家族や親族を経済的に支援することです。扶養制度を上手に活用することで、税金や社会保険料の負担を軽減でき、家計全体の経済的メリットが得られます。しかし、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」では条件や仕組みが異なるため、正しく理解することが大切です。この記事では、扶養の基本的な仕組みから、それぞれの違い、メリット・デメリットまで分かりやすく解説します。
<この記事で紹介する6つのポイント>

扶養制度には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」という2つの側面があります。それぞれ目的や対象となる範囲、条件が異なるため、混同しないよう注意が必要です。ここでは、扶養の基本的な意味から、税制上と社会保険上それぞれの特徴について詳しく解説していきます。
扶養とは、経済的に自立できない家族や親族に対して生活費を援助し、養うことを意味します。扶養する側を「扶養者」、扶養される側を「被扶養者」と呼びます。
日本の社会保障制度では、家族が互いに支え合うことを前提に設計されており、扶養制度を通じて家計の負担を軽減する仕組みが整えられています。例えば、収入のない専業主婦(主夫)や学生、高齢の親などが被扶養者となることで、扶養者の税負担が軽くなったり、被扶養者自身が保険料を納めなくても社会保険の恩恵を受けられたりします。
扶養には大きく分けて「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ異なる法律に基づいて運用されています。税制上の扶養は所得税法や地方税法に基づき、社会保険上の扶養は健康保険法や国民年金法に基づいています。両者は似ているようで実は条件や対象範囲が異なるため、正しく理解することが重要です。
税法上の扶養とは、所得税や住民税の計算において、扶養家族がいる納税者に対して税負担を軽減する制度です。扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除といった所得控除を受けることで、課税所得が減り、結果として納める税金が少なくなります。
対象となるのは、配偶者や子ども、両親、祖父母など6親等内の血族と3親等内の姻族です。ただし、年間の所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であることが条件となります。また、納税者と生計を一にしていることも必要です。「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はなく、仕送りなどで生活費を負担している場合も含まれます。
16歳未満の子どもは扶養控除の対象外ですが、住民税の非課税限度額の算定には含まれます。これは児童手当制度があるためで、税制上の優遇と現金給付の二重取りを防ぐ観点から調整されています。
社会保険上の扶養とは、健康保険や厚生年金保険において、被保険者(扶養者)に扶養されている家族が、保険料を負担することなく保険給付を受けられる制度です。
健康保険では、被扶養者として認定されると、病気やけがの際に医療給付を受けることができます。厚生年金では、配偶者のみが対象となりますが、第3号被保険者として国民年金に加入でき、保険料の納付義務がありません。
社会保険上の扶養の大きな特徴は、収入基準が税法上の扶養よりも高く設定されていることです。年収130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であれば、被扶養者として認定される可能性があります。また、社会保険では内縁関係の配偶者も対象となるなど、税法上の扶養とは異なる点があります。
被扶養者として認定されるには、被保険者により主として生計を維持されていることが条件となり、同居の場合は被扶養者の収入が被保険者の収入の2分の1未満であることが求められます。

税制上の扶養と社会保険上の扶養は、それぞれ異なる目的と仕組みで運用されています。以下の表で主な違いを整理しました。
| 目的 | 扶養者の税負担を軽減する | 被扶養者の保険料負担を免除する |
|---|---|---|
| 主な年収条件 | 103万円以下 | 130万円未満(※) |
| 対象者の範囲 | 6親等内の血族と3親等内の姻族 | 主に3親等内の親族 |
| 同居要件 | 親や祖父母は別居でもOK | 配偶者・子・孫・兄弟姉妹以外は同居が必須 |
| 管轄 | 税務署(国税庁) | 健康保険組合、年金事務所など |
(※)60歳以上または障害者の場合は180万円未満
それぞれの違いについて、より詳しく見ていきましょう。
税制上の扶養と社会保険上の扶養では、そもそもの目的が大きく異なります。
税制上の扶養の目的は、扶養者の税負担を軽減することです。家族を養っている人は、その分生活費がかかるため、税金の計算において配慮するという考え方に基づいています。扶養控除や配偶者控除を適用することで、課税所得が減少し、所得税や住民税の負担が軽くなります。
一方、社会保険上の扶養の目的は、被扶養者が保険料を負担することなく、医療保険や年金の保障を受けられるようにすることです。収入の少ない家族も、世帯主の加入する健康保険を通じて医療サービスを受けられ、配偶者であれば国民年金の第3号被保険者として将来の年金受給権も確保できます。
このように、税制上の扶養が「払う側」への配慮であるのに対し、社会保険上の扶養は「受ける側」への保障という性格が強いのが特徴です。
扶養の判定において最も重要な要素の一つが年収条件ですが、税制と社会保険では基準が異なります。
税制上の扶養では、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)が基準となります。この「103万円」は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を合わせた金額で、これを超えると本人に所得税が発生し、扶養者の扶養控除も受けられなくなります。
社会保険上の扶養では、年収130万円未満(月額108,333円未満)が基準となります。60歳以上または障害者の場合は180万円未満まで認められます。この収入には、給与だけでなく年金、失業給付、傷病手当金なども含まれる点に注意が必要です。
また、税制では前年の収入で判断しますが、社会保険では今後の収入見込みで判断する点も大きな違いです。
扶養の対象となる親族の範囲と同居要件にも違いがあります。税制上の扶養では、6親等内の血族と3親等内の姻族という広い範囲が対象となります。例えば、いとこの孫(6親等)や配偶者の甥・姪(3親等の姻族)まで含まれます。同居要件については比較的緩やかで、生計を一にしていれば別居でも認められるケースが多くあります。
社会保険上の扶養では、対象範囲が3親等内に限定されています。さらに、配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母などの直系親族は別居でも認められますが、それ以外の親族(義理の父母、甥・姪など)は同居が必須条件となります。
特徴的なのは、社会保険では内縁関係の配偶者も対象となる点です。税制上は法律婚のみが対象ですが、社会保険では事実婚も認められており、より実態に即した制度となっています。
手続きを行う管轄機関も異なります。税制上の扶養に関する手続きは、主に税務署が管轄します。会社員の場合は年末調整で勤務先を通じて手続きを行いますが、最終的な確認は税務署が行います。個人事業主などは確定申告で直接税務署に申告します。
社会保険上の扶養は、健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)、年金事務所が管轄します。手続きは勤務先を通じて行うのが一般的で、被扶養者の追加や削除の際は「被扶養者(異動)届」を提出します。
それぞれ管轄が異なるため、税制上は扶養に入っているが社会保険上は扶養から外れている、またはその逆という状況も起こり得ます。
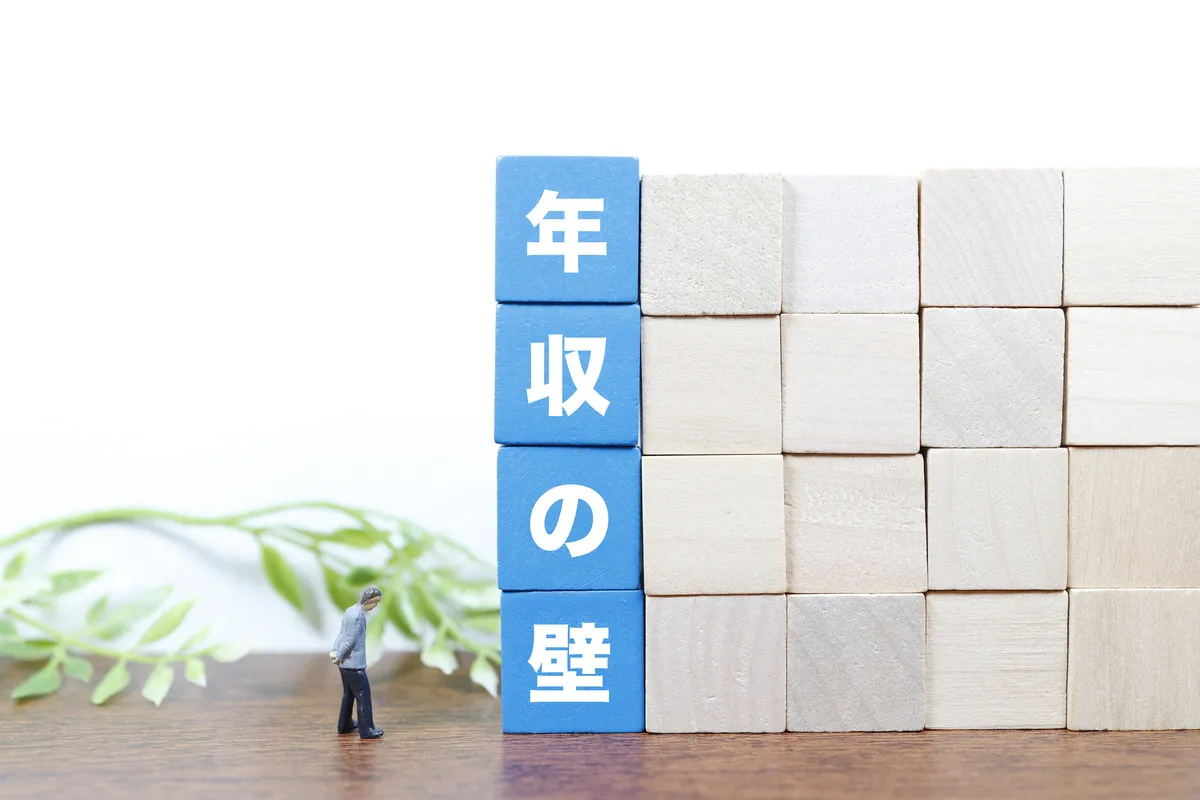
扶養を考える上で避けて通れないのが「年収の壁」の問題です。年収が一定額を超えると、税金や社会保険料の負担が発生したり、扶養から外れたりするため、働き方を調整する人も少なくありません。ここでは、主要な4つの壁について詳しく解説します。
「103万円の壁」は、最も有名な年収の壁です。パートやアルバイトで働く人の年収が103万円を超えると、本人に所得税が課税されるようになります。
103万円という金額は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計です。年収103万円以下であれば、これらの控除により課税所得がゼロになるため、所得税はかかりません。103万円を1円でも超えると、超えた分に対して所得税が課税されます。
また、配偶者や扶養親族の年収が103万円を超えると、扶養者は配偶者控除や扶養控除を受けられなくなります。ただし、配偶者の場合は配偶者特別控除に移行するため、急激に税負担が増えるわけではありません。
例えば、年収105万円の場合、103万円を超えた2万円に対して5%の所得税(1,000円)がかかります。金額としては大きくありませんが、心理的な影響は大きく、多くの人がこの壁を意識して働いています。
「106万円の壁」は、2016年10月から導入された社会保険の適用拡大に伴う新しい壁です。以下の条件をすべて満たす場合、年収106万円(月額8.8万円)以上で勤務先の社会保険への加入が義務付けられます。
社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料を負担することになり、手取り収入が減少します。年収106万円の場合、社会保険料は年間約15万円となり、手取りは約91万円になってしまいます。
ただし、社会保険加入にはメリットもあります。将来受け取る年金額が増える、傷病手当金や出産手当金を受けられる、といった保障の充実が図られます。
「130万円の壁」は、社会保険の扶養から外れる基準です。年収130万円以上になると、106万円の壁の条件に関係なく、配偶者や親の社会保険の扶養から外れなければなりません。
扶養から外れると、自分で国民健康保険と国民年金に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要があります。国民健康保険と国民年金の保険料は、合計で年間約30万円程度かかるため、手取り収入への影響は大きくなります。
130万円の判定は、今後1年間の収入見込みで行われます。月収が108,333円を継続的に超える場合は、年収130万円以上と判断されます。また、失業給付を受ける場合、基本手当日額が3,612円以上だと扶養から外れることになります。
この壁を超えるかどうかは、世帯全体の収支に大きく影響するため、慎重な判断が必要です。
「150万円の壁」は、配偶者特別控除が満額(38万円)受けられる上限です。配偶者の年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の額が段階的に減少していきます。
2018年の税制改正で、配偶者控除の対象は103万円のままですが、配偶者特別控除が拡充され、150万円まで38万円の満額控除が受けられるようになりました。これにより、103万円を超えても急激に税負担が増えることはなくなりました。
年収150万円を超えると、以下のように控除額が減少します。
そして、年収201.6万円以上になると配偶者特別控除はゼロになります。なお、この控除を受けるには、扶養者本人の合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。

扶養家族として認定されるには、続柄や年齢、収入などさまざまな条件があります。ここでは、配偶者、子ども、親、その他の親族それぞれについて、具体的な条件を解説します。
配偶者を扶養に入れる場合、税制上と社会保険上で条件が異なります。
税制上の扶養では、民法上の配偶者であることが条件です。内縁関係は認められません。年収103万円以下であれば配偶者控除、103万円超201.6万円未満であれば配偶者特別控除の対象となります。生計を一にしていることも条件ですが、単身赴任などで別居していても認められます。
社会保険上の扶養では、内縁関係も含めて配偶者として認められます。年収130万円未満で、被保険者の収入により主として生計を維持されていることが条件です。同居の場合は、配偶者の収入が被保険者の収入の半分未満である必要があります。
20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料の納付義務がありません。ただし、65歳以上で老齢年金を受給している場合は、年金額も含めて収入要件を判定します。
子どもや孫を扶養に入れる場合も、それぞれ条件があります。税制上の扶養では、16歳以上であることが条件です。15歳以下の子どもは児童手当の対象となるため、扶養控除は受けられません。大学生など19歳以上23歳未満の子どもは特定扶養親族として、通常より高い控除(63万円)を受けられます。
社会保険上の扶養では、年齢制限はありませんが、年収130万円未満であることが条件です。アルバイトをしている高校生や大学生は、収入に注意が必要です。また、子どもが就職して自身で社会保険に加入した場合は、収入に関係なく扶養から外れます。
別居している子どもでも、仕送りをしていれば扶養に入れることができます。ただし、社会保険の場合、16歳以上の学生を除き、仕送りの証明が必要になることがあります。
高齢の親や祖父母を扶養に入れるケースも増えています。税制上の扶養では、親や祖父母の年間所得が48万円以下であることが条件です。公的年金を受給している場合、65歳未満は年金収入108万円以下、65歳以上は158万円以下であれば対象となります。70歳以上の親は老人扶養親族として、通常より高い控除を受けられます。
社会保険上の扶養では、60歳未満は年収130万円未満、60歳以上は年収180万円未満が条件です。別居している場合は、親の収入より多い額を仕送りしている必要があります。
75歳以上になると後期高齢者医療制度の対象となるため、健康保険の扶養からは外れます。ただし、税制上の扶養は年齢制限がないため、収入条件を満たせば扶養控除の対象となります。
兄弟姉妹やその他の親族も、条件を満たせば扶養に入れることができます。
税制上の扶養では、6親等内の血族と3親等内の姻族が対象です。兄弟姉妹はもちろん、甥・姪、いとこ、配偶者の兄弟姉妹なども含まれます。年間所得48万円以下で、生計を一にしていることが条件です。
社会保険上の扶養では、3親等内の親族が対象ですが、兄弟姉妹は別居でも認められるものの、甥・姪などは同居が必須です。年収要件は他の親族と同じく130万円未満(60歳以上は180万円未満)です。
障害を持つ兄弟姉妹を扶養する場合は、障害者控除も併せて受けられる可能性があります。また、里子や養護を委託された老人も、一定の条件下で扶養親族として認められます。

扶養制度にはさまざまなメリットがある一方で、デメリットも存在します。扶養する側、される側それぞれの立場から、詳しく見ていきましょう。
扶養者にとって最大のメリットは、所得税と住民税の負担が軽減されることです。扶養控除や配偶者控除を適用することで、課税所得が減少し、結果として納税額が少なくなります。
具体的な軽減額は、扶養者の所得によって異なりますが、一般的な扶養控除(38万円)の場合、所得税率20%の人なら年間7.6万円、住民税と合わせると約11万円の税負担が軽減されます。特定扶養親族(63万円)や老人扶養親族(48万円~58万円)の場合は、さらに大きな節税効果があります。
また、会社によっては扶養手当(家族手当)が支給される場合もあります。金額は企業により異なりますが、配偶者で月1~2万円、子ども1人につき月5,000円~1万円程度が一般的です。
社会保険の被扶養者がいても、被保険者の保険料は変わりません。つまり、家族を何人扶養に入れても、追加の保険料負担はないということです。
例えば、配偶者が国民健康保険と国民年金に加入した場合、年間約30万円の保険料がかかりますが、被扶養者になれば、この負担がゼロになります。子どもや親を扶養に入れた場合も同様で、家計全体で見ると大きな節約になります。
特に、自営業者が会社員になった際に、それまで家族全員分払っていた国民健康保険料が不要になるケースでは、年間数十万円の負担軽減になることもあります。
大企業の健康保険組合では、法定給付に加えて独自の付加給付を行っている場合があります。被扶養者もこれらの恩恵を受けられるため、医療費の自己負担がさらに軽減されます。
例えば、高額療養費の自己負担限度額が、協会けんぽより低く設定されていたり、入院時の差額ベッド代の一部が補助されたりします。また、人間ドックの補助金や、予防接種の費用補助なども、被扶養者が利用できる場合があります。
こうした付加給付は、企業の福利厚生の一環として提供されており、被扶養者にとっても大きなメリットとなります。
被扶養者となる最大のメリットは、社会保険料を支払わずに保障を受けられることです。健康保険では医療給付を受けられ、配偶者であれば国民年金の第3号被保険者として将来の年金受給権も確保できます。
パートで年収100万円程度の場合、もし自分で国民健康保険と国民年金に加入すると、年間約20万円の保険料負担が発生します。被扶養者であれば、この負担がないため、収入のほぼ全額が手取りとなります。
また、扶養内で働く場合、労働時間を調整しやすいため、子育てや介護、自己啓発などに時間を使えるメリットもあります。ワークライフバランスを重視する人にとっては、重要な選択肢となるでしょう。
被扶養者自身の税負担も軽減されます。年収103万円以下であれば所得税がかからず、多くの自治体では年収100万円以下なら住民税も非課税となります。
また、配偶者の場合、年収103万円を超えても201.6万円未満であれば、配偶者特別控除により扶養者の税負担が軽減されるため、世帯全体で見ると税制上のメリットが継続します。
さらに、医療費控除など他の所得控除を受ける際も、世帯全体で最も効果的な申告方法を選択できるメリットがあります。
被扶養者になっても、扶養者の社会保険料は増えません。これは日本の社会保険制度の大きな特徴で、欧米の多くの国では家族の人数に応じて保険料が変わる仕組みになっています。
この制度により、専業主婦(主夫)世帯や、パートタイムで働く配偶者がいる世帯は、共働きでフルタイムの世帯と比べて、社会保険料の面で有利になっています。
ただし、この仕組みは「第3号被保険者問題」として議論の対象にもなっており、将来的に制度が変更される可能性もあります。
多くの企業では、扶養家族がいる従業員に対して扶養手当(家族手当)を支給しています。支給額や条件は企業により異なりますが、一般的には以下のような基準が設けられています。
配偶者:月額1万円~2万円程度(年収103万円または130万円以下が条件)
子ども:1人につき月額5,000円~1万円程度(年齢制限がある場合も)
年間で見ると、配偶者と子ども2人で30万円以上の手当を受けられるケースもあり、家計にとって大きな支援となります。ただし、近年は配偶者手当を廃止し、子ども手当に重点を移す企業も増えています。
被扶養者となることには、いくつかのデメリットもあります。これらを理解した上で、自身のライフプランに合った選択をすることが大切です。
扶養内で働くためには、年収を一定額以下に抑える必要があります。103万円や130万円といった壁を意識して、労働時間を制限したり、年末に仕事を控えたりすることになります。
この収入制限により、本来の能力を発揮できない、キャリアアップの機会を逃す、といった問題が生じることがあります。また、時給が上がると働ける時間が減るという矛盾も生じます。
企業側にとっても、年末の人手不足や、優秀な人材の能力を十分に活用できないといったデメリットがあり、社会全体の生産性にも影響を与えています。
国民年金の第3号被保険者期間は、基礎年金の受給資格期間に算入されますが、厚生年金は増えません。そのため、ずっと被扶養者でいた場合と、厚生年金に加入して働いた場合では、将来受け取る年金額に大きな差が生じます。
例えば、40年間第3号被保険者だった場合の老齢基礎年金は、満額でも月額約6.6万円です。一方、平均的な収入で40年間厚生年金に加入した場合は、基礎年金と合わせて月額15万円以上になることもあります。
老後の生活設計を考えると、扶養を外れて働くことも選択肢の一つとして検討する価値があります。
健康保険の被扶養者は、傷病手当金や出産手当金を受けることができません。これらは被保険者本人のみに支給される給付だからです。
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった場合に、給与の約3分の2を最長1年6ヶ月受け取れる制度です。出産手当金は、産前産後の休業期間中に、給与の約3分の2を受け取れます。
被扶養者として働いている場合、これらの所得補償がないため、万が一の際の備えを別途考える必要があります。民間の所得補償保険などを検討することも一つの方法です。
扶養者にもいくつかのデメリットがあります。特に高齢の親を扶養する場合は、注意が必要な点があります。
65歳以上の親を扶養に入れると、親が支払う介護保険料が増える可能性があります。介護保険料は、本人の所得だけでなく、世帯の課税状況によっても決まるためです。
親が単独世帯で非課税の場合と、子どもの扶養に入って課税世帯になった場合では、保険料の段階が上がり、年間数万円の負担増になることがあります。
また、介護サービスの利用料にも影響が出る場合があります。低所得者向けの軽減措置が受けられなくなる可能性があるため、事前に市区町村の介護保険課に確認することをおすすめします。
高齢の親を扶養に入れると、高額療養費の自己負担限度額が上がる場合があります。70歳以上の高額療養費制度では、世帯の所得によって自己負担限度額が決まります。
親が単独で住民税非課税世帯の場合、外来で月8,000円、入院で月15,000円が上限ですが、現役並み所得者の世帯になると、月約8万円まで上がることがあります。
医療費が高額になりがちな高齢者の場合、この差は大きな負担となる可能性があります。扶養に入れることで得られる税制上のメリットと、医療費負担の増加を比較検討することが必要です。
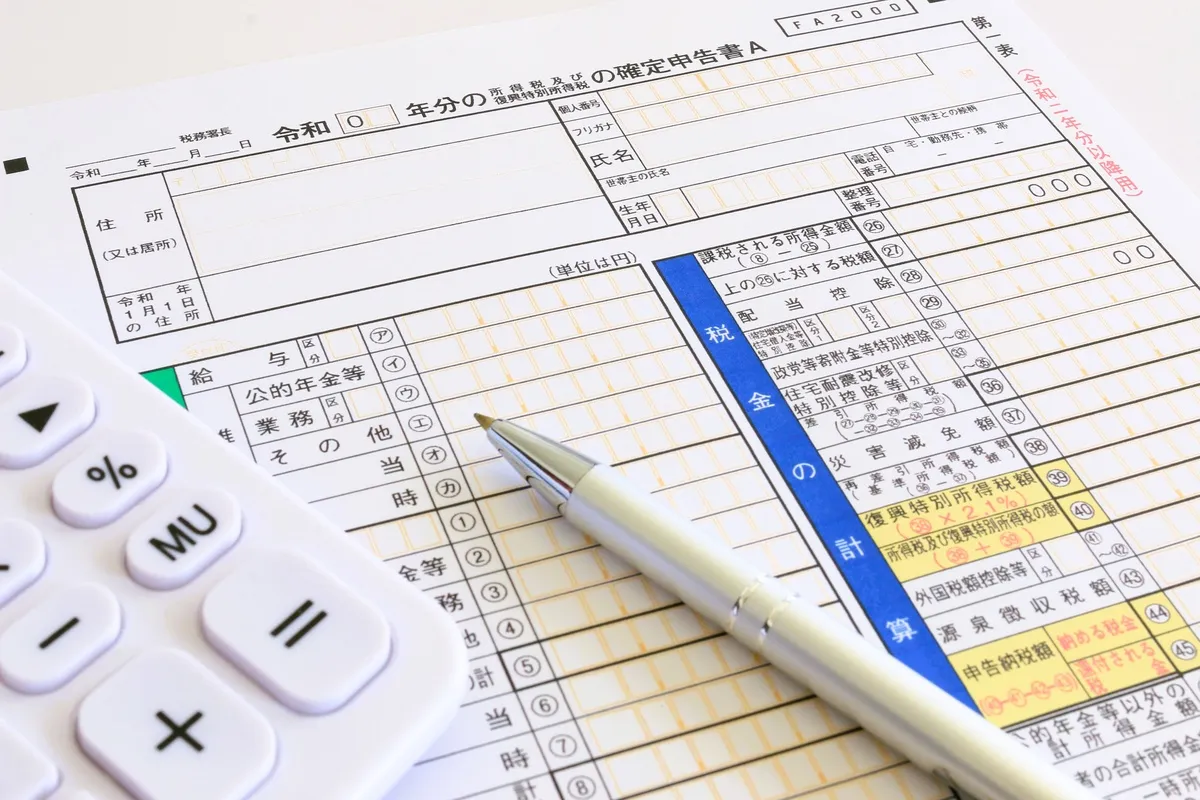
扶養に関する手続きは、税制上と社会保険上で異なります。それぞれの手続き方法と必要書類について、具体的に解説します。
会社員が家族を税制上の扶養に入れる場合、主に年末調整で手続きを行います。
毎年11月頃に会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、扶養親族の氏名、生年月日、続柄、所得の見積額などを記入します。配偶者がいる場合は、「給与所得者の配偶者控除等申告書」も併せて提出します。
年の途中で扶養家族に変更があった場合(結婚、出産、就職、死亡など)は、速やかに申告書を再提出する必要があります。申告内容に誤りがあると、後日税務署から是正を求められることがあります。
社会保険の扶養については、「被扶養者(異動)届」を会社の人事・総務部門に提出します。家族を扶養に入れる場合は、事実発生から5日以内の提出が原則です。必要書類は続柄や収入状況により異なるため、事前に確認しましょう。
個人事業主が家族を税制上の扶養に入れる場合は、確定申告で手続きを行います。
確定申告書の第二表「配偶者や親族に関する事項」欄に、扶養親族の氏名、続柄、生年月日、所得金額などを記入します。第一表では、該当する控除額を所得控除の欄に記入します。
扶養親族の所得を証明する書類の提出は原則不要ですが、税務署から求められた場合は提示する必要があるため、源泉徴収票や確定申告書の控えなどは保管しておきましょう。
個人事業主の場合、自身は国民健康保険と国民年金に加入しているため、社会保険の扶養という概念はありません。ただし、配偶者が会社員の場合は、配偶者の社会保険の扶養に入ることは可能です。
社会保険の扶養を追加する際に必要な主な書類は以下の通りです。
基本書類
状況に応じた追加書類
扶養から削除する場合は、削除理由(就職、収入超過、離婚、死亡など)と削除日を明記した被扶養者(異動)届を提出します。健康保険証の返却も必要です。
書類は健康保険組合により異なる場合があるため、事前に確認することが大切です。

扶養に関してよく寄せられる質問について、Q&A形式で解説します。
国民健康保険には扶養の概念がないため、家族全員がそれぞれ保険料を支払う必要があります。一方、社会保険(健康保険)では、被扶養者の保険料負担はありません。
例えば、4人家族(夫婦と子ども2人)の場合、国民健康保険では世帯で年間40~60万円程度の保険料がかかることもあります。しかし、会社員の健康保険なら、被保険者1人分の保険料で家族全員がカバーされます。
したがって、家族がいる場合は、一般的に社会保険の方が有利です。ただし、自治体により国民健康保険料の減免制度がある場合や、所得が低い場合は、個別に比較検討が必要です。
また、将来の年金額を考えると、厚生年金に加入できる社会保険の方が有利といえます。
75歳以上になると後期高齢者医療制度に移行するため、健康保険の扶養には入れません。しかし、税制上の扶養控除は年齢制限がないため、収入条件を満たせば扶養親族として申告できます。
75歳以上の親を税制上の扶養に入れる場合、年金収入に注意が必要です。公的年金控除があるため、年金収入158万円以下なら所得は48万円以下となり、扶養親族の対象となります。
ただし、親を扶養に入れることで、親自身の介護保険料や医療費の自己負担が増える可能性があります。市区町村により制度が異なるため、事前に確認することが重要です。
特に、親が介護施設に入所している場合や、医療費が高額になっている場合は、慎重に検討する必要があります。
社会保険の扶養判定において、失業保険(雇用保険の基本手当)は収入に含まれます。基本手当日額が3,612円以上の場合、年収130万円相当とみなされ、受給期間中は扶養に入れません。
一方、税制上の扶養判定では、失業保険は非課税所得のため収入に含まれません。したがって、失業保険を受給していても、その年の給与所得等が103万円以下なら、税制上の扶養には入れます。
公的年金については、税制上も社会保険上も収入に含まれます。ただし、税制上は公的年金控除があるため、65歳未満は108万円、65歳以上は158万円までは所得がゼロとなります。
遺族年金や障害年金は非課税ですが、社会保険の扶養判定では収入に含まれる点に注意が必要です。
扶養内で働く最適な収入は、個人の状況により異なりますが、一般的には以下のように考えられています。
100万円以下:住民税も所得税もかからず、手取りがそのまま収入となります。働く時間に余裕があり、家事や育児を優先したい人に適しています。
103万円以下:所得税はかかりませんが、住民税が少額かかります。税制上の扶養に入りながら、ある程度の収入を得たい人向けです。
130万円未満:所得税・住民税はかかりますが、社会保険の扶養には入れます。106万円の壁に該当しない職場なら、129万円程度が手取りを最大化できます。
150万円以下:配偶者特別控除が満額受けられる上限です。社会保険料を支払っても、世帯収入を増やしたい場合に適しています。
最終的には、家族構成、将来の年金、キャリアプラン、ライフワークバランスなどを総合的に考慮して決めることが大切です。
扶養制度は、日本の社会保障と税制の重要な柱の一つです。家族を経済的に支える人の負担を軽減し、収入の少ない家族も適切な保障を受けられるよう設計されています。
しかし、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」では、目的も条件も大きく異なります。税制上は103万円、社会保険上は130万円という収入基準の違いや、対象となる親族の範囲、同居要件の有無など、それぞれの特徴を正しく理解することが大切です。
最適な選択は、個人や家族の状況により異なります。現在の生活と将来の安心のバランスを考えながら、家族でよく話し合って決めることをおすすめします。必要に応じて、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することも検討してください。
このように自身のキャリアプランを考える中で、扶養から外れて正社員を目指したいけれど、経歴に自信がないという方もいるかもしれません。そうした場合、第二新卒や既卒、フリーターなどの就職支援に特化したDYM就職のような転職エージェントを活用するのも有効です。DYM就職では、面談実績60,000名以上、サービス満足度87%という実績を誇り、書類選考なしで優良企業の面接に進める点が大きな特徴です。専任のキャリアアドバイザーが一人ひとりに寄り添い、求人紹介から面接対策、内定後のフォローまで手厚くサポートします。一人で悩まず、まずは無料相談から始めてみてはいかがでしょうか。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。