Page Top

近年、不動産業界において注目を集める「不動産M&A」。単純な不動産売買とは異なり、株式譲渡や会社分割などの手法を用いて行われるこのスキームは、売り手・買い手双方に多くのメリットをもたらしますが、一方で、リスク引き継ぎや手間の多さといったデメリットも存在します。
この記事では、不動産M&Aの仕組みや市場動向から税金問題、実施時の注意点まで、不動産ビジネスの新たな選択肢として注目される不動産M&Aの全容を徹底解説します。
<この記事で紹介する3つのポイント>
目次

不動産M&Aは不動産の取得を目的として行われるM&Aで、特に課税面のメリットが大きい取引手法です。通常のM&Aが事業の買収や統合を目的とするのに対し、不動産M&Aでは不動産を取得するために対象企業をM&Aで統合するという逆転の発想が特徴です。
不動産自体の売買ではなく会社単位での取引となるため、特に課税面で大きなメリットがあります。多くの場合、不動産会社が当事者となりますが、不動産M&Aは必ずしも「不動産会社のM&A」ではなく、建設業など隣接業種とのM&Aも多く見られます。
M&A契約としては、対象不動産を所有する会社を株式譲渡により子会社化するか、会社分割で新設会社に不動産を移転させてから新設会社を子会社化するという形をとります。状況に応じて適切な手法を選択することが重要です。
株式譲渡による不動産M&Aは、対象不動産を所有する企業の全株式を買い手が取得し、完全子会社とするスキームです。これにより買い手は子会社を通して間接的に対象不動産を所有することになります。
事業が順調な会社が資産の一部である不動産を手放す場合は、通常の不動産売却が自然です。一方、不動産自体は魅力的でも事業の採算性・将来性が低く廃業を検討している場合は、会社清算と不動産M&Aが比較検討の対象となるでしょう。
不動産M&Aを利用する買い手側は、売り手企業の扱いを検討する必要があります。事業継続価値がないと判断した場合は、目的の不動産を自社に移転後、売り手企業を解散させるケースが多いです。また、売り手側の責任で一部の資産や負債を事前に処分しておくよう取り決めるケースもあります。
売り手企業に存続させる価値があると判断した場合は、不動産管理・運営子会社として残すことになりますが、目的はあくまで不動産の活用です。不動産の収益性を高めてから売却すること(M&A投資の成果の回収=イグジット)を目指す形が一般的です。
会社分割(新設分割)と株式譲渡を組み合わせれば、不動産のみを切り出して不動産M&Aで譲渡することが可能です。具体的には、新設分割を用いて売り手企業を「売却対象の事業(目的の不動産のみを所有する事業)」と「それ以外の事業」に分割し、前者を株式譲渡により買い手に売却します。
新設分割のプロセスには複数の選択肢がありますが、不動産M&Aでは「売却対象事業を売り手企業に残し、それ以外を新設会社に移転する方式」で、「対価を売り手企業株主が取得する分割型分割」が一般的に採用されます。これは、ほかの方法で新設分割を行うと、組織再編税制の特例措置を受けられなくなる(税制非適格となる)ためです。
この結果、「売り手企業(対象不動産を所有)」と「新設会社(それ以外の事業資産を所有)」に分かれ、売り手企業を買い手が取得するというスキームとなります。新設会社はそのまま事業を継続することもありますが、後継者へ承継するなどの手続きが並行して行われるのが一般的です。
不動産M&Aと通常の不動産売買には明確な違いがあります。もっとも大きな違いは譲渡の対象です。通常の不動産売買では不動産そのものが譲渡対象となるのに対し、不動産M&Aではその不動産を所有している企業の株式が譲渡対象となります。
この違いにより課税関係も異なります。売り手側での課税対象は、不動産売買の場合は不動産の売却益ですが、不動産M&Aの場合は株式の譲渡益になります。買い手側では、不動産売買では不動産取得税や登録免許税などが課されますが、不動産M&Aでは基本的にこれらの税金は課されません(役員変更を伴う場合は登録免許税が必要な場合があります)。
また、不動産M&Aでは不動産だけでなく、企業の抱えるほかの資産や負債、従業員なども一緒に引き継ぐことになるため、デューデリジェンスの範囲や深さも通常の不動産取引と比較して広範囲になります。取引の複雑さから専門家の関与が不可欠であり、実行までの期間も通常の不動産取引より長くなる傾向があります。
不動産業界は日本経済において大きな存在感を持っています。内閣府の「国民経済計算」によると、2023年の日本のGDPは591兆円であり、このうち不動産業は約69兆円と全体の約11.7%を占めています。これは製造業の127兆円、卸売・小売業の77兆円に次ぐ規模であり、日本のGDPの約1割を占める3番目に大きい市場となっています。
国税庁および国土交通省の資料によれば、2022年度の日本の全法人数は約290万社で、そのうち不動産業は約37万社となっており、全産業の約12.9%を占めています。就業者数で見てみると、2017年度のデータになりますが、不動産業の就業者数は133.7万人で、全産業に占める割合は2.7%となっています。この比率から見ても、不動産業は少ない人員で高い価値を生み出す産業といえます。
不動産業界を代表する企業としては、三井不動産、三菱地所、住友不動産、東急不動産ホールディングス、野村不動産ホールディングスの大手5社があり、2023年度の売上高合計は約7.8兆円に達します。これらの企業は総合ディベロッパーと呼ばれ、不動産業全体に大きな影響力を持っています。
一方で、不動産業界は中小企業が大多数を占める業界でもあります。資本金1億円未満の中小企業が法人数の99%以上を占めているものの、売上高では全体の52%程度にとどまり、大規模法人との競争は依然として厳しい環境にあります。特に近年は都市部への人口集中が進み、地域間格差も拡大傾向にあります。
参考:
国税庁|令和4年度分 会社標本調査結果について
国土交通省|国土交通白書2024
国土交通省|不動産業ビジョン2030
不動産M&Aの価格相場は、対象となる不動産の資産価値、企業の財務状況、将来の収益性などさまざまな要素に左右されるため、一律に定めることは困難です。M&Aの価格は最終的には売り手と買い手の交渉によって決まります。
一般的に不動産M&Aでは、株主価値を算定し、それに基づいて譲渡対価を決定します。売り手企業が会社清算を予定していた場合は、清算を実行したと仮定した場合の残余財産額をM&Aの株主価値と見なす「清算価値法」が用いられることが多いです。この場合、譲渡対価は基本的に残余財産額と同等の金額になります。
売り手企業を子会社として存続させるケースでは、期待収益力などのプラス要素と経営統合に伴うリスクというマイナス要素を加味して株主価値が算定されます。ただし、不動産M&Aが検討される場合は収益力などへの期待が低いケースが多く、残余財産額より譲渡対価が大きくなることは稀です。逆に、残業代未払いや訴訟リスクなどのマイナス要素がある場合は、企業価値の算定額が減額され、残余財産額を下回る可能性もあります。
不動産業界ではM&Aが活発に行われています。国土交通省が2019年に発表した「不動産業ビジョン2030」によると、2015年時点において、不動産業の60歳以上の割合は約50%に達し、29歳以下は6%台にとどまり、深刻な高齢化と若手不足を示しています。
2024年の特徴的な傾向として、不動産テック企業による従来型不動産会社の買収や、地方での再編加速が挙げられます。また、建設業や金融機関との業界横断的な統合も増加しており、ワンストップサービス提供を目指す動きが顕著になっています。

不動産M&Aを行う売り手側には複数のメリットがあります。特に注目すべきは税制面での優位性と廃業コストの削減効果です。また、企業の継続による雇用維持も大きなメリットとなります。これらのメリットを組み合わせることで、売り手は最適な形で不動産を手放すことが可能になります。
不動産M&Aの最大のメリットは、通常の不動産売却と比較して大幅な節税が可能な点です。不動産の売却と会社清算を行う場合、2段階での課税が発生します。まず売却益に対して約30%の法人税が課され、さらに残った資金を株主に配当する際に最大で55%の所得税・住民税が課されます。
一方、不動産M&Aの場合、株主が株式を譲渡することになるため、株式の譲渡所得に対する約20%の税率で完結します。例えば、清算価値3億円の法人のM&Aを行った場合、通常の不動産売却と清算では最終的な手取りが約1.2億円になるのに対し、不動産M&Aでは約2.4億円となり、2倍もの差が生じることもあります。
この税率の差は特に含み益の大きい不動産を保有する法人にとって重要です。長期間保有して価値が上昇した不動産ほど、通常の売却では多額の税金がかかりますが、不動産M&Aではその負担を大幅に軽減できます。こういった節税効果は、特に相続対策や事業承継を検討している経営者にとって非常に魅力的です。
参考:
国税庁|No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
国税庁|No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
不動産M&Aのもう一つの大きなメリットは、廃業に伴うさまざまなコストを削減できる点です。通常の会社清算では、設備や在庫の処分にかかる費用、賃貸物件の原状回復費、解散・清算のための手続きの事務コスト、官報掲載や登記の費用、司法書士や税理士などの専門家への支払いなど、多くのコストが発生します。
不動産M&Aでは会社ごと譲渡するため、廃業にかかる、これらの手間とコストが不要になります。例えば、官報公告費用は約3万~4万円、登記手続きで約4万1,000円の費用がかかりますが、これらを節約できます。また、不動産の原状回復費用も場合によっては数千万円に上ることがあり、その削減効果は大きいといえます。
ただし、M&Aにも独自のコストがかかるため、具体的な案件ごとにコスト比較を行うことが重要です。一般的に株式譲渡のみのスキームは比較的短期間で低コストに実行できるため、廃業コスト削減の効果が高いでしょう。また、売り手企業が財政的に困難な状況にあったり、訴訟リスクを抱えていたりする場合でも、M&Aによって会社自体が譲渡されるため、売り手企業としては債務整理や訴訟リスクの回避にもつながる可能性があります。
不動産M&Aでは、買い手が売り手企業を子会社として存続させる場合、従業員の雇用を維持できる可能性があります。通常の廃業では従業員は全員解雇されますが、不動産M&Aではその不動産を活用した事業継続により、従業員のキャリアを守ることができます。
特に、地方の不動産会社や長年の経験を持つ従業員を抱える企業にとって、雇用維持は社会的責任の観点からも重要です。また、不動産業界は高齢化が進んでおり、熟練した人材の確保は買い手にとっても大きなメリットになります。
実際のケースでは、買い手が売り手企業のブランドや営業エリアを維持したまま事業を継続することで、地域密着型のサービスを継続できるケースもあります。これにより顧客との関係も維持され、事業価値の毀損を最小限に抑えることができます。また、従業員にとっても突然の失業を避けられるメリットがあり、Win-Winの関係が構築できます。

不動産M&Aには多くのメリットがある一方で、売り手側が認識しておくべきデメリットも存在します。これらの課題を事前に把握し対策を講じることで、より円滑なM&Aの実現が可能になります。
不動産M&Aの大きなデメリットの一つは、適切な買い手を見つけることの難しさです。不動産を単体で売却する場合に比べ、企業ごと譲渡する相手を見つけるのは一般的に困難です。特に、単なる不動産の魅力だけでなく、会社の財務状況や将来性、潜在的なリスクなど総合的に評価してもらう必要があるからです。
また、買い手候補は通常のM&A市場と不動産市場の両方を見ている企業に限られるため、母数自体が少なくなります。有望な買い手が見つからないまま不採算事業を継続すれば、赤字が膨らむリスクもあります。
この問題に対処するためには、M&A専門の仲介会社や不動産M&Aに精通したアドバイザーの活用が効果的です。彼らは幅広いネットワークを持ち、潜在的な買い手候補を見つけ出す能力を有しています。また、匿名性を保ちながら市場調査を行えるため、従業員や取引先に不安を与えることなく買い手探しを進められます。
不動産M&Aは、通常の不動産売買に比べて手続きが複雑で、完了までに長い時間がかかる点がデメリットです。特に新設分割と株式譲渡を組み合わせるスキームでは、会社法や労働契約承継法に従った手続きが必要となり、相当の時間と労力を要します。
株主総会決議、反対株主の株式買取請求・債権者異議申し立てへの対応、事業に関係する従業員や労働組合との協議など、それぞれの手続きには法定の期限があり、これらをクリアしていく必要があります。M&Aの交渉開始から基本合意、デューデリジェンス、最終契約締結、クロージングまで、最低でも半年から1年程度かかるケースが一般的です。
株式譲渡のみのスキームは比較的手続きが簡便ですが、それでも通常の不動産売買に比べると時間がかかります。特に、株主が多数いる場合や株式の名義と実質所有者が異なるケース、定款で株券発行会社となっているのに株券を発行していないケースなどでは、さらに時間を要します。
不動産M&Aを実行する際には、M&A専門の仲介業者や各種専門家への報酬が発生します。これらの手数料は通常の不動産売買における仲介手数料よりも高額になる可能性があり、売り手にとって負担となります。
不動産仲介の場合、宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限が設定されていますが、M&Aの仲介に関しては特定の業法がなく、料金体系は各業者の裁量に委ねられています。一般的なM&A仲介手数料は成功報酬制が多く、譲渡金額の数%から10%程度が相場とされています。着手金は、小規模な案件であれば数十万円から100万円程度ですが、大規模な案件では数百万円と高額になる場合もあります。
さらに、法務、財務、税務などの専門家によるデューデリジェンスや契約書作成などの費用も別途発生します。これらの費用は案件の規模や複雑さによって大きく変動しますが、数百万円から数千万円に上ることもあります。
不動産M&Aによって得られる税制メリットは大きいものの、こうした手数料や諸費用も考慮した総合的な判断が必要です。複数の業者から見積もりを取得し、費用対効果を慎重に検討することをお勧めします。

不動産M&Aは買い手側にとっても多くのメリットがあります。通常の不動産取引では得られない特別な価値や機会を提供してくれる可能性があります。以下では、買い手側の主なメリットについて詳しく解説します。
不動産M&Aの大きなメリットの一つは、場合によって通常の不動産取引よりも割安な価格で不動産を取得できる可能性がある点です。これは主に2つの要因によるものです。
まず、売り手側の税制メリットが交渉の余地を生み出します。通常の不動産売却と会社清算では二重課税により手取り額が大幅に減少しますが、株式譲渡では税率が低く抑えられます。この差額の一部を買い手側にも還元する形で、市場価格よりも低い金額で合意できることがあります。
また、不動産M&Aでは不動産取得税(固定資産税評価額の4%程度)や登録免許税(固定資産税評価額の2%程度)、印紙税などが基本的に不要となるため、これらの節税分を取得コストの削減に充てることができます。大規模な不動産であれば、この節税効果は数千万円から数億円にもなり得ます。
特に複数の不動産を保有する企業を買収する場合、このコスト削減効果は非常に大きくなります。
参考:
総務省|不動産取得税
国税庁|No.7191 登録免許税の税額表
不動産M&Aのもう一つの大きなメリットは、通常の不動産市場では入手困難な優良物件を取得できる可能性がある点です。自社ビルや事業用不動産など、企業が保有する不動産は必ずしも売買目的で所有しているわけではないため、通常の不動産市場には出回りにくい特性があります。
特に、立地条件のよい都心部や商業地域の物件、歴史的価値のある建物、大規模な開発が可能な土地などは、一般の売買市場では競争が激しく高値になりがちですが、不動産M&Aでは相対取引によって適正価格で取得できる可能性があります。
また、企業が経営不振や後継者不足などの問題を抱えている場合、その保有不動産の潜在的価値が十分に認識されていないケースもあります。不動産M&Aを通じて、このような「埋もれた宝石」を発掘できる可能性があります。
不動産投資家やディベロッパーにとって、こうした市場に出回らない物件の取得は、競争優位性を確立する重要な戦略となり得ます。リノベーションや用途変更によって収益性を高められる物件であれば、さらに大きなリターンが期待できます。
不動産M&Aは、新しいエリアへの事業展開を図る際の効果的な手段となります。特に地方都市や未進出のエリアにおいて、ゼロから営業基盤を構築するのは時間とコストがかかりますが、そのエリアですでに事業を展開している企業を買収することで、一気に市場参入が可能になります。
このアプローチでは、物理的な不動産だけでなく、地域での知名度やブランド力、顧客基盤、地元の不動産業者や行政との関係など、無形の資産も同時に獲得できる点が大きなメリットです。特に不動産業は地域特性が強く、地元の情報や人脈が重要な役割を果たすため、こうした無形資産の価値は非常に高いといえます。
例えば、首都圏を中心に事業展開している不動産会社が地方進出を図る場合、その地域で実績のある企業を買収することで、地域固有の市場特性や規制についての知識、地元顧客との信頼関係などを効率的に獲得できます。これにより、進出にかかる時間を大幅に短縮し、失敗リスクを低減することが可能です。
また、隣接県や都心と地方など、互いの営業エリアを補完し合う形でのM&Aは、両社のシナジー効果を最大化し、市場での競争力強化につながります。
不動産業界では専門知識や経験を持つ人材の確保が重要な課題となっていますが、不動産M&Aはこの問題を解決する有効な手段となります。買収を通じて売り手企業の従業員を一挙に獲得できるため、人材不足に悩む企業にとって大きなメリットとなります。
特に宅地建物取引士や一級建築士、不動産鑑定士などの専門資格を持つ人材は、資格取得の難易度が高く市場での争奪戦が激しいため、M&Aによる一括獲得は効率的です。例えば、宅地建物取引士の資格試験は合格率15%程度であり、有資格者は依然として貴重な人材資源といえます。
また、不動産業界は高齢化が進んでおり、若手人材の不足が深刻な問題となっています。総務省の「労働力調査」によれば、不動産業の60歳以上の割合は約50%と全産業平均の約2倍であり、若手人材の確保は最重要経営課題の一つです。不動産M&Aによって20代・30代の若手社員を獲得できれば、事業の継続性と発展性を高めることができます。
参考:総務省|労働力調査
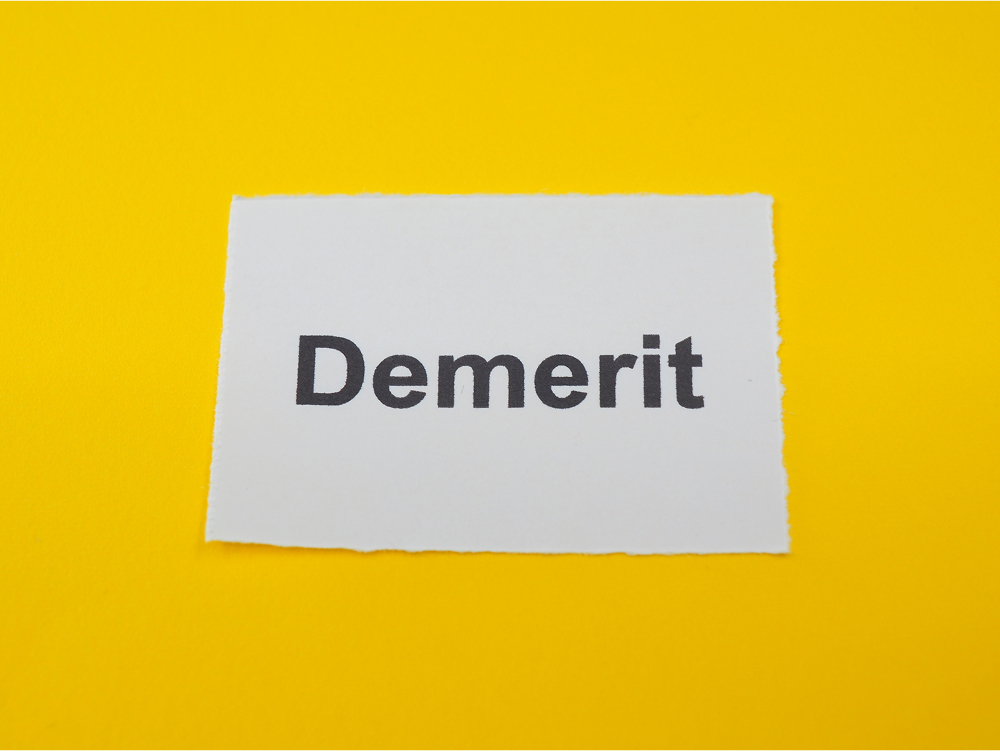
不動産M&Aのメリットは大きい一方で、買い手側にとってのデメリットやリスク要因も存在します。適切な対策を講じるためにも、これらのデメリットを十分に理解しておくことが重要です。
不動産M&Aの最大のデメリットは、不動産だけでなく企業全体のリスクも引き継いでしまう点です。通常の不動産取引では物件自体のリスクのみを考慮すればよいものの、企業買収の場合は簿外債務や偶発債務、訴訟リスクなど、表面化していない問題を抱え込む可能性があります。
具体的なリスクとしては、従業員への未払い残業代、脱税や不適切な会計処理、顧客とのトラブル、環境問題、不動産に関する瑕疵など多岐にわたります。これらは買収後に発覚すると、予想外の出費や企業価値の毀損につながりかねません。
このリスクを軽減するためには、徹底したデューデリジェンスが不可欠です。法務、財務、税務、労務など各分野の専門家による精査を行い、潜在的な問題点を洗い出す必要があります。また、表明保証条項や補償条項を盛り込んだ買収契約を締結し、発見されなかった問題が後日発覚した場合の対応策を事前に定めておくことも重要です。
不動産M&Aは通常の不動産取引に比べて複雑な手続きが必要であり、買い手側にとっても大きな労力と時間的コストがかかります。特に初めてM&Aを行う企業にとっては、その複雑さに戸惑うことも少なくありません。
M&Aの主なプロセスとしては、案件の発掘、初期的な検討、基本合意の締結、デューデリジェンス、最終契約の交渉と締結、クロージング(決済)という流れになります。これらの全工程を完了するまでには、通常6ヶ月から1年程度の期間を要します。特にデューデリジェンスは専門家の協力を得て実施するため、相当の時間と労力が必要です。
また、M&Aは通常の業務と並行して進めることになるため、経営陣や担当部署の負担は小さくありません。特に中小企業では専門部署がないケースが多く、経営者自身が交渉や書類作成に関わることもあり、本業への影響が懸念されます。
このような手間と時間のコストを考慮した上で、不動産M&Aに取り組むかどうかを判断することが重要です。急いで不動産を取得したい場合には、通常の不動産取引のほうが適している場合もあります。

不動産M&Aを成功させるためには、適切な手法を選択し、正確なプロセスを踏むことが重要です。ここでは主な手法である株式譲渡と会社分割それぞれのプロセスについて解説します。
株式譲渡による不動産M&Aは、比較的シンプルな手法であり、一般的なM&Aのプロセスに沿って進められます。主なステップは以下の通りです。
最初のステップは、買い手・売り手双方の基本方針の決定と初期的な条件の摺り合わせです。この段階で、譲渡価格の目安、譲渡対象の範囲、譲渡後の経営方針などについて大まかな合意を形成します。その後、基本合意書(LOI)を締結し、本格的な交渉に入ります。
次のステップは、買い手側によるデューデリジェンスです。財務、法務、税務、事業内容など多角的な観点から対象企業の精査を行います。不動産M&Aの場合は、対象不動産の物理的・法的状況についても詳細な調査が必要です。例えば、土壌汚染や建物の構造的問題、権利関係のトラブルなどがないか確認します。
デューデリジェンスの結果を踏まえて、最終的な譲渡条件を交渉し、株式譲渡契約を締結します。契約では、株式の譲渡価格、支払条件、表明保証、補償条項などを詳細に定めます。特に、発見されなかった問題が後日発覚した場合の対応については、慎重に協議することが重要です。
最後に、契約に基づき株式の移転と代金の支払いを行うクロージングを実施し、株式譲渡が完了します。譲渡後は、不動産の運営方針や組織体制の見直しなど、統合作業(PMI)を進めていきます。
会社分割を利用した不動産M&Aは、株式譲渡に比べてより複雑なプロセスとなります。主に新設分割と株式譲渡を組み合わせる形で進められ、大まかには、以下のようなステップを踏みます。
まず、売り手企業は分割計画書を作成します。分割計画書には、新設会社の商号や本店所在地、承継する資産・負債・契約関係の明細、対価の内容などを記載します。特に不動産M&Aの場合、どちらの会社に不動産を帰属させるかが重要なポイントとなります。
次に、分割計画書を本店に備え置き、債権者保護手続きを行います。会社分割の場合、債権者が不利益を被る可能性があるため、債権者に対して分割について個別に催告するか、官報や日刊紙で公告を行います。債権者は一定期間内に異議を述べることができ、異議があった場合には、会社は弁済や担保提供などの対応が必要となります。
株主総会での承認も必要です。特に、分割型分割の場合は特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席した上で、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要となります。また、労働契約承継法に基づき、承継される事業に従事する労働者に対して、分割についての通知や協議も行わなければなりません。
これらの手続きが完了すると、法務局での登記申請を行い、新設会社が設立されます。その後、新設会社の株式を買い手に譲渡することで不動産M&Aが完結します。
このように、会社分割を利用した不動産M&Aは手続きが複雑であり、法律上の要件も多いため、専門家のサポートを受けながら慎重に進める必要があります。

不動産M&Aを検討する上で、税金に関する理解は非常に重要です。適切な手法を選ぶことで大幅な節税が可能になる一方、適切でない方法を選ぶと予想外の税負担が生じることもあります。ここでは、不動産M&Aにおける主な税金について解説します。
株式譲渡による不動産M&Aの場合、主に売り手側の株主に対して課税が生じます。個人株主の場合、株式の譲渡所得に対して約20%の税率(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)で課税されます。これは、株式の譲渡価額から取得費と譲渡費用を差し引いた金額に対して課される申告分離課税です。
法人株主の場合は、株式譲渡益が通常の法人所得として課税されます。法人税率は企業規模によって異なりますが、概ね23.2%(資本金1億円超の場合)となります。加えて、地方法人税、法人住民税、法人事業税などが課されます。
買い手側については、株式取得時に直接的な課税は発生しませんが、不動産M&Aのメリットである不動産取得税や登録免許税の節約効果を享受できます。これらの税金は高額な場合が多く、例えば固定資産税評価額10億円の不動産であれば、不動産取得税が約4,000万円、登録免許税が約2,000万円となり、大きな節税効果があります。
ただし注意が必要なのは、所有資産の70%以上が土地等である法人の株式を譲渡する場合、一定の条件下では「短期所有土地の譲渡」とみなされ、通常の株式譲渡より高い税率(約40%)が適用される可能性があることです。
参考:
国税庁|No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
総務省|不動産取得税
会社分割を活用した不動産M&Aの場合、税制上の取り扱いはより複雑になります。会社分割に対する課税関係は、その分割が「適格分割」に該当するかどうかで大きく異なります。
適格分割の場合、資産・負債の移転に伴う譲渡損益は繰り延べられ、分割会社には課税されません。また、分割対価として株式のみが交付され、それが株主の持分比率に応じて分配される場合、株主段階での課税も基本的に発生しません。
一方、非適格分割の場合、資産・負債の時価での譲渡があったものと見なされ、含み益がある場合は分割会社に法人税が課されます。また、分割対価を株主が受け取る場合、みなし配当として課税される可能性があります。
不動産M&Aで重要な不動産取得税についても、適格分割で一定の要件を満たせば非課税となります。具体的には、分割事業の主要資産が新設会社に移転していること、分割事業が新設会社で継続されること、従業員の概ね80%以上が新設会社に移籍することなどが条件となります。
不動産M&Aにおいて組織再編税制を活用する場合、租税回避行為と見なされないよう留意が必要です。法人税法第132条の2の「包括的な租税回避行為防止規定」に基づき、税負担軽減以外に合理的な目的がない組織再編は、税務当局に否認される可能性があります。
通常の不動産売買と不動産M&Aを税金面で比較することで、不動産M&Aのメリットがより明確になります。ここでは、通常の不動産売買に課される主な税金について解説します。
不動産売買では、売り手側には、売却で生じた利益に対して法人税、地方法人税、法人住民税、法人事業税などが課されます。税率は合計で30~34%程度となり、株式譲渡に比べて高くなります。また、土地の取引は消費税が非課税ですが、建物については10%の消費税がかかります。
買い手側には、不動産取得税が課されます。これは固定資産評価基準に基づく不動産評価額に対し、住宅用が3%、非住宅用が4%の税率で計算されます。また、所有権移転登記を行う際に登録免許税(税率2%)が必要です。さらに司法書士への登記手続き費用や、売買契約に貼付する印紙税なども発生します。
会社を清算して不動産を処分する場合、さらに複雑な税金問題が生じます。法人の残余財産がプラスであれば、不動産売却益と同様に法人税などが課税されます。さらに残余財産を株主に分配すると、株主には高額な所得税が課されます。例えば、法人税率35%、所得税率40%と仮定すると、残余財産の61%が税金として徴収され、株主の手取りは39%にしかなりません。
このように、通常の不動産売買では多段階で高率の課税が行われるため、不動産M&Aの税制上のメリットは極めて大きいといえます。特に含み益の大きい不動産を保有する企業では、その差は顕著になります。

不動産M&Aの実行には多くの複雑な要素があり、いくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。以下では、主要なリスク要因と対策について解説します。
不動産M&Aにおける最大のリスクの一つは、簿外債務の存在です。簿外債務とは、貸借対照表に記載されていない負債のことで、発覚すると買収後の収支計画に重大な影響を与える可能性があります。
典型的な簿外債務としては、未払い残業代、未払い税金、訴訟リスク、保証債務、環境汚染対策費用などが挙げられます。特に不動産業界では、顧客とのトラブルや契約上の瑕疵から生じる損害賠償リスクも存在します。このようなトラブルが買収後に表面化すると、予期せぬ負担を強いられる恐れがあります。
簿外債務のリスクを軽減するためには、入念なデューデリジェンスが不可欠です。法務・財務・税務・労務などの専門家によるチェックに加え、重要な契約書の精査、従業員インタビュー、顧客クレーム履歴の確認なども重要です。さらに、株式譲渡契約において表明保証条項と補償条項を適切に設けることで、買収後に発見された問題に対する保護策を確保することができます。
不動産M&Aでは、不動産自体が抱えるリスクにも注意が必要です。通常の不動産取引と同様、物件の状態や権利関係、法的規制などに関する問題が存在する可能性があります。
特に重要なリスクの一つは、不動産の減損リスクです。財務総合政策研究所の「法人企業統計調査(2023年度)」によれば、2023年の不動産業の固定比率(固定資産÷純資産)は243%と全産業平均の128%を大きく上回っており、自己資本比率は31.5%にとどまっています。つまり、多額の借入金により不動産を保有している状態です。このような状況では、不動産価値の下落時に含み損が顕在化し、大きな損失につながるおそれがあります。
また、土地の地質や汚染状況、建物の構造的問題、アスベストや土壌汚染などの環境問題、境界紛争などの権利関係の問題も潜在的なリスクです。さらに、都市計画や用途地域の変更、容積率・建ぺい率の制限など、行政上の規制によって不動産の利用価値が変わる可能性もあります。
こうしたリスクに対処するためには、不動産鑑定士や建築士による物件調査、弁護士による権利関係の精査、環境コンサルタントによる汚染調査など、専門家による多角的な調査が重要です。また、必要に応じて保険の活用や契約上の保証を求めることも検討すべきでしょう。
不動産M&Aにおいて見落とされがちなリスクの一つが、人材の流出問題です。M&Aの発表や実行により、従業員の間に不安が広がり、優秀な人材が退職してしまうケースは少なくありません。特に不動産業では人的資本が重要であり、顧客との信頼関係や専門知識を持つ従業員の流出は大きな損失となります。
人材流出のリスクを軽減するためには、M&Aのプロセスにおいて従業員への配慮が欠かせません。具体的には、M&Aの目的や今後のビジョンを明確に伝え、不安を取り除くコミュニケーションが重要です。また、キーパーソンには個別面談を行い、処遇や役割について丁寧に説明することも効果的です。
場合によっては、重要な従業員に対して継続的な勤務を促すためのインセンティブプランの導入や、一定期間の雇用保証を提供することも検討すべきでしょう。さらに、企業文化の融合にも配慮し、買収後の統合プロセス(PMI)を慎重に計画することが、人材流出を防ぐ上で重要です。
不動産M&Aは単なる物件売買とは異なり、法人としての取引であるため複雑なスキーム設計や税務知識が必要となります。売り手・買い手それぞれに大きなメリットがある一方で、リスク管理や専門的な手続きが欠かせません。成功させるためには、M&A専門の知見を持つコンサルタントによるサポートが不可欠です。
DYM株式会社のM&Aコンサルティングサービスでは、不動産業界に精通した専門家が、企業価値評価から交渉、デューデリジェンス、クロージングまで一貫してサポート。豊富な実績とノウハウを生かし、お客様の事業戦略に最適な不動産M&Aをご提案します。事業拡大や承継問題の解決に向けて、まずはDYMの無料相談をご利用ください。専門家があなたの課題に最適なソリューションをご提案いたします。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。