Page Top

履歴書は、あなたの第一印象を決める重要な応募書類です。書き方一つで採用担当者に与える印象が大きく変わるため、正しい作成方法を理解しておくことが大切です。本記事では、日付や氏名などの基本項目から、志望動機や本人希望欄まで、項目別の書き方テンプレートを分かりやすく解説します。また、作成前に押さえるべきポイントや注意点も網羅しています。この記事を参考に、あなたの魅力が伝わる、通過率の上がる履歴書を作成しましょう。
<この記事で紹介する3つのポイント>
目次

履歴書は、あなたの経歴や人柄を企業に伝えるための最初の公式な書類です。各項目には、それぞれ書き方のルールやマナーが存在し、それを守ることで採用担当者に丁寧で誠実な印象を与えられます。このセクションでは、提出日を記載する「日付」や「氏名」といった基本情報欄から、「学歴」「職歴」、そしてアピールの要となる「志望動機」や「本人希望記入欄」まで、項目別に書き方のポイントを詳しく解説します。
さらに、趣味・特技や健康状態など、履歴書のフォーマットによっては記載が必要な項目についても触れていきます。これから解説する内容に沿って作成することで、迷うことなく、完成度の高い履歴書を準備できるでしょう。
履歴書に記入する日付は、書類を提出する日を正確に記載します。郵送の場合はポストへの投函日、メールで送付する場合は送信する日が該当します。事前に作成しておく際は日付欄を空けておき、提出直前に忘れずに記入するようにしましょう。
年号の表記は西暦(例:2025年)と和暦(例:令和7年)のどちらでも問題ありませんが、学歴や職歴欄など、履歴書全体で必ずどちらかに統一することが重要です。表記の混在は、採用担当者に雑な印象を与えかねません。また、数字やハイフンなどの記号は、会社名などの固有名詞を除いて半角で記載するのが一般的です。過去に作成したものを使い回すことは避け、常に最新の日付に更新して提出するよう心がけてください。
氏名欄には、戸籍に登録されている正式な字体で、姓と名の間にスペースを空けて記載します。読みやすさを考慮し、他の項目よりもやや大きめのフォントサイズで書くと良いでしょう。ふりがなは、履歴書の様式に合わせて「ふりがな」とあればひらがなで、「フリガナ」とあればカタカナで記入します。
パソコンで作成する際には、ふりがなが漢字の真上にくるようにレイアウトを調整すると、より丁寧な印象を与えられます。旧字体を常用している場合でも、戸籍に登録されている字体を用いるのが原則です。氏名は応募者を特定する最も基本的な情報であるため、正確かつ丁寧に記載することが、信頼性の第一歩となります。
住所は、企業からの郵便物送付などに使用されるため、省略せずに正確に記載する必要があります。都道府県名から始め、市区町村、番地、建物名、そして部屋番号に至るまで、すべての情報を詳細に書きましょう。郵便番号も忘れずに正確に記入してください。
ふりがなは、一般的に市区町村まで記載しますが、マンションやアパートの名前が漢字で読みにくい場合は、建物名にもふりがなを振ると親切です。また、履歴書の提出時点で引っ越しが決まっている場合は、空欄に新住所を記載した上で、「〇月〇日に転居予定」と書き添えておきましょう。これにより、採用担当者は連絡先の変更を事前に把握でき、スムーズなコミュニケーションが可能になります。
生年月日と年齢は、応募者の基本情報を構成する項目です。年号の表記は、西暦(例:2025年)と和暦(例:令和7年)のどちらを使用しても構いませんが、履歴書全体で必ず統一することが求められます。例えば、学歴や職歴欄で和暦を使用した場合、生年月日も和暦で記載します。この一貫性が、丁寧な書類作成の印象を与えます。
年齢の欄には、履歴書を企業に提出する日(郵送の場合は投函日、メールの場合は送信日)時点での「満年齢」を記載してください。誕生日を迎える直前などの場合は特に注意が必要です。近年、厚生労働省は公正な採用選考を目的とし、性別欄を任意記入とする履歴書様式を推奨しており、能力とは関係ない情報に対する配慮が進んでいます。そのため、この欄も正確な情報を記載することが肝心です。

連絡先欄は、現住所以外の場所(例えば、一時的に滞在している実家など)への連絡を希望する場合に記載する項目です。現住所と連絡先が同じである場合は、空欄のままにせず、「同上」と明記しましょう。空欄だと採用担当者が記入漏れと判断してしまう可能性があるため、明確に意思表示をすることが大切です。
この項目は、応募者のプライベートな状況に配慮しつつ、企業との円滑なコミュニケーションを確保するために設けられています。特に、転居を控えている場合や、長期不在の予定があるなど、現住所での連絡受け取りが難しい事情がある際に活用すると、選考過程でのすれ違いを防ぐ効果が期待できるでしょう。
電話番号とメールアドレスは、選考案内などで頻繁に利用されるため、日中につながりやすく、確実に連絡が取れる情報を記載することが極めて重要です。電話番号は、自宅の固定電話よりも携帯電話のほうが連絡を取りやすいのであれば、携帯電話の番号を記載して問題ありません。
メールアドレスについては、現在勤務している会社のドメインが入った社用アドレスの使用は厳禁です。必ず普段使用しているプライベートなアドレスを記載し、持っていない場合はフリーメールサービスで新たに取得しましょう。在職中などの理由で、電話に出られない時間帯がある場合は、本人希望欄に「平日12時〜13時、または18時以降にご連絡いただけますと幸いです」のように書き添えておくと、採用担当者とのやり取りが円滑に進みます。
職歴は、これまでのキャリアを客観的に示すため、原則としてすべての入退社歴を時系列に沿って正確に記載します。短期間で退職した経歴であっても、省略せずに記入することが信頼につながります。会社名は「(株)」などと略さず、「株式会社」といった正式名称で記載してください。所属部署や役職名も同様に正式名称を用います。
退職理由は、自己都合であれば「一身上の都合により退職」と記すのが一般的です。会社の倒産や解雇など、企業側の事情で離職した場合は「会社都合により退職」と事実を記載します。現在も勤務している場合は、最後の職歴のあとに「現在に至る」と書き、次の行に右詰めで「以上」と記します。すでに退職している場合も、最終職歴を記したあとに「以上」で締めくくりましょう。
免許・資格欄は、自身のスキルを客観的に証明する機会です。原則として取得した年月順に、必ず正式名称で記載してください。「普通免許」ではなく「普通自動車第一種運転免許」のように書きます。一般的に、運転免許は最初に記載すると分かりやすいでしょう。
保有資格が多い場合は、すべてを羅列するのではなく、応募する職種と関連性の高いものを優先的に選んで記載すると、自身の強みが効果的に伝わります。記載できる免許や資格がない場合は、空欄にせず「特になし」と記入します。また、「〇〇取得に向けて勉強中」「〇月に受験予定」など、現在学習中の資格について記載することも、学習意欲の高さを示す有効なアピールになります。
志望動機は、入社意欲と企業への貢献可能性をアピールする中心的な項目です。なぜ転職を考え、その中でも特にこの企業を選んだのか、という一貫したストーリーを伝えることが求められます。自身の経験やスキルが、応募先企業でどのように活かせるのかを、具体的なエピソードを交えながら明確に記述しましょう。
例えば、「前職の〇〇という経験で培ったスキルは、貴社の△△事業に貢献できると考えております」といった具合です。その企業の事業内容や理念への共感を述べ、「この会社でなければならない理由」を伝えることが不可欠です。記入欄の7割以上、文字数にして200~300字程度を目安に、熱意が伝わるようにしっかりと書き込むことが大切です。
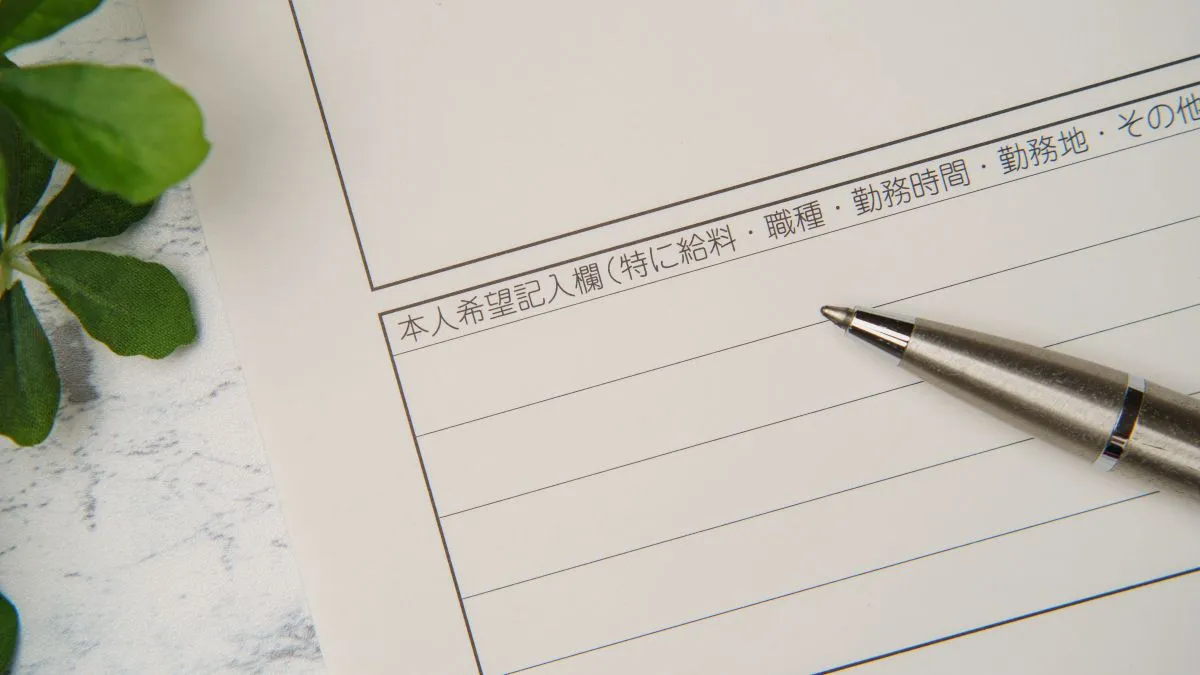
本人希望記入欄は、特別な希望がない場合でも必ず記載が必要です。その際は、空欄にせず「貴社規定に従います」と記入するのがビジネスマナーとされています。「特になし」という表現は一般的ではないため避けましょう。勤務地や勤務時間、職種など、どうしても譲れない条件がある場合に限り、その理由と共に具体的に記載します。
ただし、給与や待遇に関する希望は、この段階では記載せず、面接や内定後の交渉の場で伝えるのが適切です。この欄は、在職中のため連絡が取りにくい時間帯(例:「平日18時以降に連絡希望」)を伝えたり、複数の職種で募集が出ている場合に希望職種を明記したりと、円滑なコミュニケーションのためにも活用できます。
使用する履歴書のフォーマットによっては、これまで解説してきた基本項目以外にも、応募者の個性や働く上での諸条件を伝えるためのさまざまな記入欄が設けられていることがあります。これには、趣味・特技、長所・短所、賞罰、通勤時間、扶養家族、健康状態といった項目が含まれます。
これらの欄は、職務経歴だけでは伝わらないあなたの人柄をアピールしたり、入社後の円滑な手続きに必要な情報を提供したりする重要な役割を持っています。些細な項目と捉えずに一つひとつ丁寧かつ正確に記入することが、自己アピールの機会を増やし、企業とのミスマッチを防ぐことにつながります。以下では、これらの各項目について、書き方のポイントを詳しく解説します。
趣味・特技欄は、職務経歴だけでは伝わらない個性や人柄をアピールするための貴重なスペースです。採用担当者が応募者の人間性に興味を持つきっかけとなり、面接時の会話が弾む糸口にもなり得ます。難しく考えず、「読書(年間100冊)」「ジョギング(毎週末5km)」のように、具体的な数字などを少し加えるだけで、あなたの個性や継続力を示すことが可能です。
応募企業の社風や事業内容と関連付けられる趣味(例:チームワークを重視する企業に団体スポーツの経験を記載)があれば、それを記載するのも有効でしょう。ただし、内容は冗長にならないよう、箇条書きや短い文章で簡潔にまとめることを心がけてください。
長所と短所の項目は、応募者の自己分析能力や客観性、そして改善意欲を確認するために設けられています。長所を述べる際は、単に「協調性があります」と書くだけでなく、それを裏付ける具体的なエピソードを添えることが重要です。応募先企業でその長所がどう活かせるかを意識して選びましょう。
一方、短所については、正直に認めつつも、それを改善するためにどう努力しているか、あるいは業務に支障が出ないようどう工夫しているかをセットで記載することが不可欠です。「慎重すぎる点がありますが、タスクの優先順位付けと時間管理を徹底することで、迅速な意思決定を心がけています」といった形で、前向きな姿勢を示すことで、マイナスの印象を払拭できます。
賞罰欄は、特筆すべき受賞歴や刑事罰の有無を申告する項目です。「賞」には、全国大会や国際的なコンクールでの入賞経験、国や地方公共団体といった公的機関からの表彰歴などが該当します。社内表彰などは、職務経歴書でアピールするのがより適切です。
「罰」とは、有罪判決が確定した刑事罰を指し、これに該当するものがある場合は正直に記載する義務があります。ただし、反則金の納付で済むような軽微な交通違反は行政罰にあたるため、記載する必要はありません。多くの人はこの欄に記載すべき事項がない場合がほとんどですが、その際は空欄にせず「特になし」と明確に記入してください。これにより、記入漏れではないことを示せます。
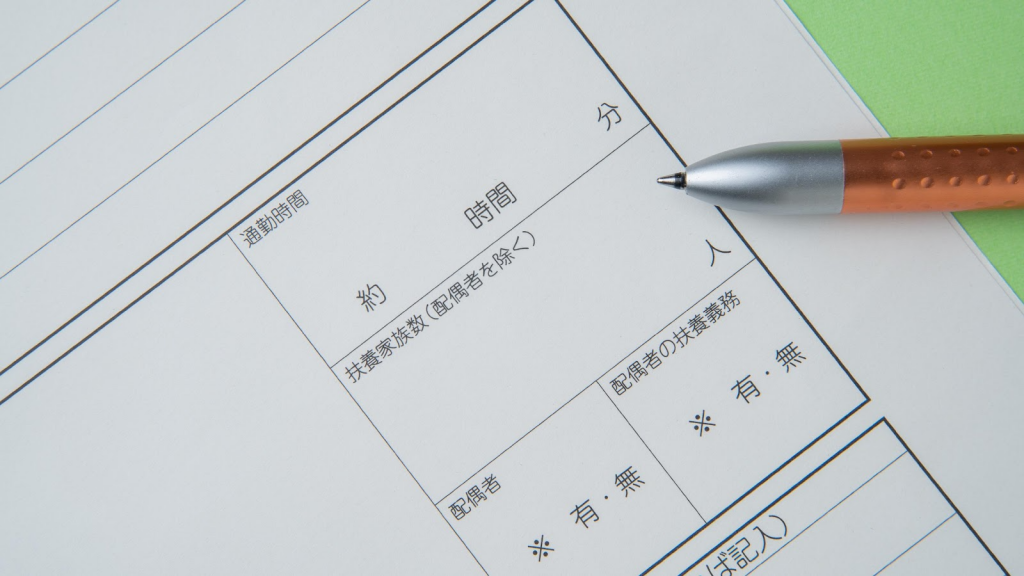
通勤時間欄には、自宅から応募先企業の勤務予定地までの片道の最短所要時間を記載します。公共交通機関の乗り換え時間や徒歩の時間を含めた、ドアツードアの時間を計算し、5分単位で記入するのが一般的です。例えば、計算上の所要時間が43分であれば「45分」とします。
応募する企業に支社や事業所が複数あり、配属先が明確でない場合は、どこを基準に算出した時間なのかを明記する必要があります。「本社勤務の場合約1時間15分」のように、基準となる場所を併記しておくと採用担当者にとって親切です。この情報は、応募者が無理なく通勤できるかの判断材料や、交通費算出の参考として利用されます。
この欄は、入社後の社会保険の手続きや家族手当の支給有無などを会社側が確認するために設けられています。扶養家族の欄には、所得税法または健康保険上の扶養に入っている家族の人数を記載します。一般的には、健康保険上の扶養家族数を書くことが多いです。
配偶者欄には、配偶者の有無と、その配偶者を扶養しているかどうかを事実に基づき記載します。なお、2021年4月に厚生労働省が公正な採用選考を推進する目的で示した履歴書の様式例では、「扶養家族数」「配偶者」といった項目は削除されています。これは、応募者の能力とは直接関係のない情報で採否が判断されることをなくすための動きです。企業指定の様式に欄がある場合のみ、正確に記入しましょう。
健康状態の欄は、入社後の業務遂行に支障がないかを確認するための項目です。業務に影響するような持病や怪我がなく、問題がない場合は「良好」と記載します。一方で、会社側に事前に伝えておくべき事項がある場合は、正直に記載することが重要です。
例えば、定期的な通院が必要な場合は、「業務に支障はありませんが、〇〇のため月に1回定期健診が必要です」のように、業務への影響がないことを前置きした上で具体的に説明します。もし特定の業務(重量物の運搬など)に制限が生じる可能性がある場合も、その旨を正直に記載しておくことで、入社後のミスマッチを防ぎ、企業側も適切な配慮をしやすくなります。
実際に履歴書を書き始める前に、いくつか確認しておくべき重要な準備段階のポイントがあります。この事前の確認を怠ると、後から大幅な書き直しが必要になったり、企業の採用方針に沿わない書類を提出してしまったりするリスクが生じます。企業によっては、公平性の担保のために独自のフォーマットを指定している場合があるため、まずはその有無を確認することが不可欠です。
また、手書きで熱意を伝えるか、あるいは効率的に作成できるパソコンを選ぶか、どちらの方法で作成するかも最初に決めておくべき事柄です。ここでは、スムーズかつ効果的な履歴書作成のための第一歩として、こうした作成の前提となるポイントを具体的に解説していきます。
履歴書の作成に取り掛かる前に、まず応募先企業から特定のフォーマットが指定されていないかを確認することが不可欠です。企業によっては、応募者間の公平性を保つためや、独自の選考基準に沿って情報を整理するために、専用の履歴書テンプレートを用意している場合があります。募集要項や企業の採用ページを注意深く確認し、指定のフォーマットがある場合は、必ずそれをダウンロードして使用してください。
指定があるにもかかわらず市販の履歴書などで提出すると、指示を読んでいないというマイナスの印象を与えかねません。特に指定がない場合は、厚生労働省が推奨する様式や、自身の経歴や強みをアピールしやすいテンプレート(例:自己PR欄が大きいもの)などを選び、活用すると良いでしょう。

企業から特に指示がない限り、履歴書は手書きとパソコン作成のどちらを選んでも問題ありません。手書きは熱意や人柄が伝わりやすいという利点がありますが、書き損じた場合に修正液や修正テープが使えず、一から書き直す手間がかかります。作成する際は、にじみにくい黒のボールペンや万年筆を使用しましょう。
一方、パソコン作成は修正が容易で、データを保存しておけば他の企業に応募する際に効率的に編集できるのがメリットです。フォントは「明朝体」や「ゴシック体」などの読みやすいものを選び、文字サイズは10.5~11ポイントを目安に統一します。作成後は、レイアウト崩れや第三者による改ざんを防ぐため、PDF形式に変換して提出するのが一般的です。
履歴書の内容を充実させることと同じくらい、形式的なミスをなくし、細部まで配慮の行き届いた書類に仕上げることが重要です。小さなミスやビジネスマナー違反が、採用担当者に「注意力が不足している」「入社意欲が低い」といったマイナスの印象を与え、選考で不利に働く可能性があります。
このセクションでは、書き損じの際に修正液や修正テープを使わないといった基本的なルールから、空欄を放置しないこと、履歴書全体で年号の表記を統一すること、そして誤字脱字や略字を使わないことまで、作成時に必ず守りたい注意点を網羅的に解説します。完成した履歴書を提出する前の、最終チェックリストとしてご活用ください。
手書きで履歴書を作成する際に最も注意すべき点の一つが、書き損じの修正方法です。たとえ一文字の間違いであっても、修正液や修正テープ、消せるボールペンなどを使用してはいけません。履歴書は公的な性格を持つビジネス文書であり、修正の跡があると書類の信用性を損なう可能性があります。修正された履歴書は、採用担当者に「準備不足」「注意力が散漫」といったネガティブな印象を与えてしまう懸念があります。
面倒に感じても、書き損じた場合は新しい用紙に一から書き直すのが唯一の正しい対処法です。このようなリスクを避けたい方は、修正が容易なパソコンでの作成が推奨されます。
履歴書の各項目は、原則としてすべて埋めるようにしてください。記入欄に空欄が目立つと、採用担当者から「入社意欲が低いのではないか」「細部への注意ができない人物かもしれない」といったマイナスの評価を受ける可能性があります。また、単なる記入漏れなのか、意図的に書いていないのかが判断できず、不信感につながることも考えられます。
免許・資格欄や賞罰欄など、記載すべき事項が何もない場合は、空欄のままにせず「特になし」と必ず記入しましょう。同様に、本人希望欄で特に伝えることがなければ「貴社の規定に従います」と記載します。すべての欄を埋めることで、丁寧で誠実な姿勢を示すことができます。
履歴書全体の見た目の統一感は、読みやすさに直結し、採用担当者が受ける印象を左右します。特にパソコンで作成する場合、文字のフォントやサイズがバラバラだと、雑な印象を与えかねません。フォントは、ビジネス文書で一般的に使われる「明朝体」や「ゴシック体」といった、シンプルで可読性の高いものを選びましょう。
文字サイズは、10.5ポイントから11ポイントを基本とし、履歴書全体で統一します。文字サイズが不ぞろいだと、視認性が悪くなるだけでなく、「読み手への配慮が欠けている」と判断されるリスクもあります。手書きの場合も同様に、全体の文字の大きさがなるべく均一になるよう意識して書くことで、整然とした丁寧な印象を与えることが可能です。

履歴書に記載する日付や年月は、すべて西暦(例:2025年)か和暦(例:令和7年)のどちらか一方に統一することが必須のルールです。生年月日、学歴・職歴の入学・卒業・入社・退社年、そして免許・資格の取得年月日など、年号を記載するすべての箇所で表記を揃える必要があります。西暦と和暦が混在していると、採用担当者が時系列を把握しにくくなるだけでなく、「注意力散漫」「文書作成の基本ができていない」といったマイナスの印象を与えてしまいます。
また、同時に提出する職務経歴書とも年号の表記を統一しておくと、書類全体に一貫性が生まれ、より丁寧な印象を与えることができます。提出前には必ず全体の表記が統一されているかを確認してください。
複数の企業に応募する場合でも、一度作成した履歴書をそのまま他の企業に使い回すことは絶対に避けるべきです。志望動機や自己PRは、応募する企業に合わせて内容を調整するのが基本です。使い回しの履歴書では、その企業でなければならないという熱意が伝わらず、志望度が低いと見なされてしまうでしょう。
また、使い回しは単純なミスの原因にもなります。日付が古いままだったり、最悪の場合、別の企業名を記載したまま提出してしまったりする危険性があり、このようなミスは即不採用につながりかねません。手間はかかりますが、履歴書は必ず応募企業一社ごとに作成し、提出した書類のデータやコピーは面接対策のためにも必ず保管しておきましょう。
履歴書と職務経歴書を同時に提出する場合、両方の書類に記載された内容に矛盾や食い違いがないか、細心の注意を払う必要があります。特に、学歴や職歴の入退社年月日、保有している免許・資格の名称や取得日といった事実は、完全に一致していなければなりません。
これらの情報に齟齬があると、採用担当者はどちらが正しい情報か判断できず、応募者に対して不信感を抱く原因となります。「自己管理ができていない」「注意力が不足している」といった評価につながりかねません。2つの書類を何度も照らし合わせ、整合性が取れているかを入念に確認しながら作成を進めることが、信頼を得るための重要なステップです。
誤字・脱字のある履歴書は、それだけで評価を大きく下げてしまう要因となります。採用担当者から「注意力が散漫で、仕事においてもケアレスミスが多いのではないか」というネガティブな印象を持たれる可能性が高いです。また、「㈱」や「高」のように会社名や学歴を略字で記載することも、ビジネスマナーに反すると見なされます。
書類が完成したら、声に出して読み上げるなど、複数回にわたって入念にチェックしましょう。自分では気づきにくい間違いもあるため、可能であれば家族や友人、転職エージェントなど第三者に確認を依頼するのが効果的です。パソコンで作成する際は、内蔵されている校閲機能を活用することも、ミスを減らす上で有効な手段となります。
本記事では、履歴書の書き方を網羅的に解説しました。しかし、「自己PRが思いつかない」「忙しくて作成する時間がない」など、履歴書作りは悩みが尽きないものです。そんなお悩みを解決するのが、DYMのオンライン履歴書作成ツール『履歴書PLUS』です。
AIによる自己PR文の自動作成機能や、豊富なテンプレートを活用し、スマホやPCから短時間で魅力的な履歴書が完成します。作成したデータはPDF形式で保存でき、いつでも何度でも編集可能です。ぜひ『履歴書PLUS』で効率的に応募準備を整え、自信を持って理想のキャリアへの一歩を踏み出しましょう。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。