Page Top

店舗の売却を検討しているものの、「何から始めればいいの?」「税金は?」「少しでも高く売るには?」など、悩みは尽きないでしょう。
本記事では、店舗売却の全手順を7つのステップで分かりやすく解説。M&Aや居抜きといった売却方法の比較から、複雑な税金の話、査定額を上げる具体的なコツまで、売却に必要な情報を網羅し、後悔のない決断をサポートします。
<この記事で紹介する3つのポイント>

店舗を売却するといっても、その方法は一つではありません。内装や設備を残したまま売却する「居抜き」、すべてを撤去する「スケルトン」、そして事業そのものを譲渡する「M&A」という、主に3つの選択肢があります。
それぞれにメリットとデメリットが存在するため、ご自身の店舗の状況や目的に合わせて最適な方法を選ぶことが、売却を成功させるための第一歩となります。ここでは、各手法の特徴を詳しく解説します。
M&Aによる売却は、店舗という「モノ」だけでなく、事業そのものを第三者へ譲渡する方法です。この手法には、会社の経営権ごと売却する「株式譲渡」と、事業の一部または全部を切り出して売却する「事業譲渡」の2種類が存在します。
買主は、既存の顧客や従業員、運営ノウハウまで引き継げるため、安定した事業を迅速に始められる利点があります。売主にとっても、事業全体を評価されることで大きな売却益を得られる可能性があります。
ただし、赤字経営など事業の経営状況が悪い場合は、買い手を見つけるのが困難になるという側面も持ち合わせています。一般的に、店舗のM&Aにおける売却価格の目安は100万円から250万円程度とされています。
居抜き売却とは、店舗の内装、厨房設備、テーブルや椅子といった備品をそのままの状態で次の借主に売却する手法を指します。売主にとっては、設備を撤去する解体費用がかからない点が大きなメリットです。
一方、買主側も新たな設備投資を大幅に削減でき、スピーディーに営業を開始できるため、特に同業種での開業を考えている場合に魅力的な選択肢となります。
ただし、この方法は立地の良し悪しが売却の成否を大きく左右し、集客が見込めない場所では買い手探しが難航する傾向にあります。東京都内の約20坪の店舗の場合、造作の譲渡価格は50万円から300万円程度が相場とされていますが、立地条件によって価格は大きく変動します。
スケルトン売却は、居抜きとは対照的に、内装や設備をすべて解体・撤去し、建物の骨組みだけの状態にしてから売却する方法です。売主は解体費用を負担する必要がありますが、買主は業種や事業コンセプトの制約を受けずに、ゼロから自由に店舗空間を設計できるというメリットがあります。そのため、飲食店から物販店への転用など、異なる業種の買い手にもアプローチしやすくなり、購入者の対象が大きく広がります。
特に、独自の世界観やブランドイメージを重視するアパレル店や雑貨店などの業態では、スケルトン物件が好まれる傾向にあります。賃貸契約書に「原状回復義務」が明記されている場合は、この方法で返却することが一般的です。

店舗の売却は、多くの手続きを正しい順序で進める必要があります。思いつきで行動すると、不利な条件での契約や思わぬトラブルにつながりかねません。
ここでは、売却の検討を開始する「事前準備」から、専門家である「仲介業者の選定」、そして売却後の「廃業手続き」や「確定申告」に至るまで、一連のプロセスを7つの具体的なステップに分けて解説します。全体像を把握し、計画的に売却を進めましょう。
店舗売却を成功させる最初のステップは、入念な事前準備です。まず、M&A、居抜き、スケルトンのうち、どの方法で売却するのかを検討します。M&Aを選択する場合は、譲渡する事業の範囲、希望売却価格、時期といった基本条件を具体的に設定しておくことが重要です。
また、店舗内の設備にリース品やレンタル品が含まれていないかを確認し、リストアップしておきましょう。特に賃貸店舗の場合、貸主への解約予告を出すタイミングは慎重に判断すべきです。買い手が見つかる前に解約を予告すると、交渉期間が限定されてしまい、不利な条件での売却を迫られるリスクがあるため注意が必要です。
売却の方向性が定まったら、次に専門の仲介業者を選定します。店舗売却は一般的な不動産取引と異なる知識が求められるため、店舗の仲介を専門に扱う不動産会社やM&Aアドバイザーに相談するのが賢明です。業者を選んだら、売却活動を依頼するための媒介契約を締結します。契約形態には、複数の業者に依頼できる「一般媒介契約」と、1社に絞って依頼する「専任媒介契約」などがあります。
M&Aの場合は、仲介会社やFA(ファイナンシャル・アドバイザー)、M&Aプラットフォームといった支援サービスから、自社の規模に適したものを選びます。相談や査定は無料で行い、契約成立時に報酬が発生する完全成功報酬制を採用している業者が多いようです。
仲介業者と契約後、具体的な売却価格を決定するための査定が行われます。業者は店舗を実際に訪問し、立地、周辺の競合状況、建物の状態、設備のコンディションなどを専門家の視点で詳細に調査します。居抜き売却の場合は、主に立地や店舗の状態が査定額に影響を与えますが、M&Aの場合は、事業の収益性や純資産価値といった財務状況が評価の大きな基準となります。
仲介業者から提示された査定価格と、その算出根拠を十分に理解した上で、売主の希望も踏まえながら最終的な募集価格や売却条件を決定していくことになります。
売却価格と条件が決定したら、仲介業者による買主の募集活動が開始されます。業者は、自社で運営するマッチングプラットフォームや、提携する税理士や内装業者などの幅広いネットワークを駆使して、条件に合う購入希望者を探し出します。有望な候補者が見つかると、店舗の内見が行われ、具体的な条件交渉へと進みます。
M&Aの場合は、交渉に先立って秘密保持契約を締結し、財務情報などの詳細なデータを開示するのが一般的です。この段階で、売却後の従業員の雇用や役員の処遇といったデリケートな項目についても話し合われます。
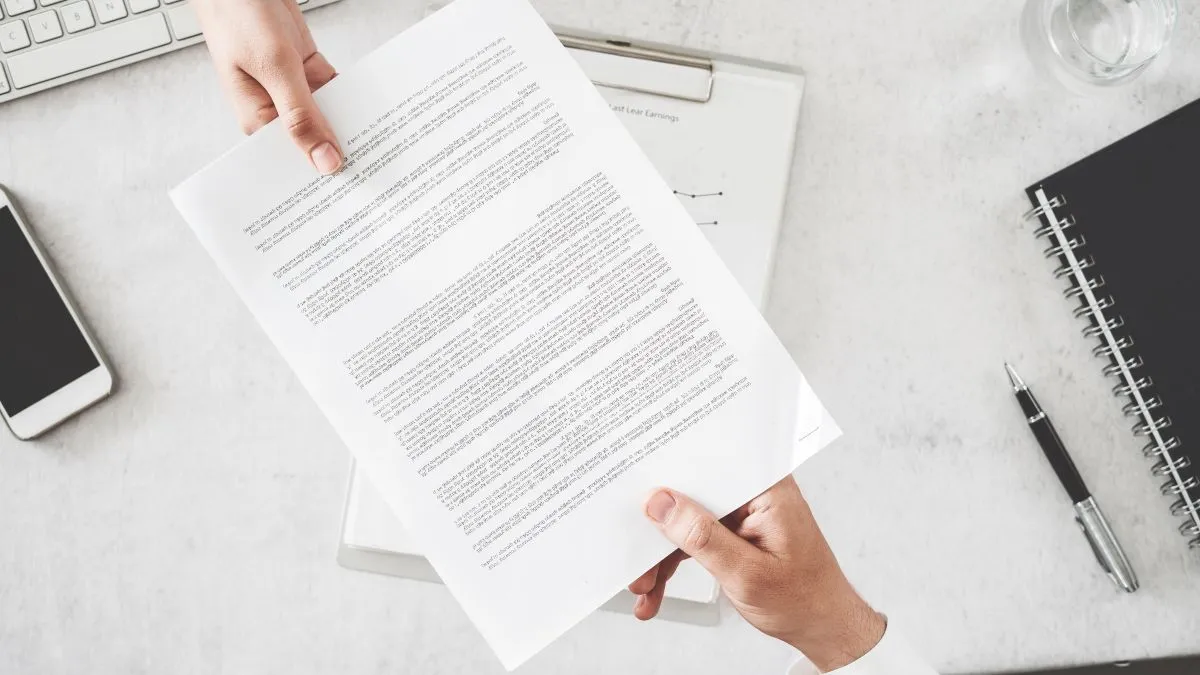
M&Aによる売却プロセスでは、最終契約の前に「基本合意書」を締結する工程が一般的です。この合意書は、これまでの交渉で合意に至った基本的な条件(譲渡価格の目安、譲渡対象の範囲など)や、今後のスケジュール、買主側に一定期間の独占交渉権を与えることなどを文書で確認するものです。これはあくまで最終契約に向けた方向性を固めるためのものであり、法的な拘束力を持つ売買契約そのものではありません。
また、次のステップであるデュー・ディリジェンス(買収監査)へ売主が誠実に協力する義務なども、この基本合意書に盛り込まれるのが通例となっています。なお、居抜き売却ではこのステップは省略されることがほとんどです。
すべての条件交渉がまとまれば、最終契約の締結へと進みます。居抜き売却の場合、「造作譲渡契約書」を取り交わし、譲渡代金の受け取りと物件の引き渡しを完了させます。この際、売却後に設備の不具合などが見つかった場合に備え、契約不適合責任の所在を明確にしておくことがトラブル防止の鍵となります。
一方、M&Aでは、基本合意の後、買主側が売主企業の財務や法務の実態を詳細に調査する「デュー・ディリジェンス」を実施します。その調査結果を基に最終的な条件を確定させ、株式譲渡契約や事業譲渡契約といった最終契約を締結し、取引を完了させる「クロージング」へと進みます。
店舗の売却に伴い事業を完全に終了する場合、各種行政機関への廃業手続きが不可欠です。事業内容に応じて、保健所への「廃業届」と「営業許可証」の返納、警察署への「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」に関する「廃止届」の提出などが必要になります。
また、税務署には「個人事業の開業・廃業等届出書」を、従業員を雇用していた場合は、公共職業安定所(ハローワーク)や年金事務所にも所定の届出を提出しなければなりません。これらの手続きにはそれぞれ提出期限が定められているため、計画的に進めることが重要です。そして、売却によって利益(譲渡所得)が生じた場合は、翌年に確定申告を行い、所得税や法人税を納税する必要があります。

店舗を売却して現金を得たとしても、その全額が手元に残るわけではありません。売却益に対して課される税金や、仲介を依頼した専門業者へ支払う手数料など、さまざまな費用が発生します。これらのコストを事前に把握しておかないと、「思ったより手残りが少なかった」という事態にもなりかねません。
ここでは、店舗売却に際して発生する代表的な税金と手数料について、それぞれ詳しく見ていきます。
個人事業主が店舗を売却して利益が出た場合、その利益に対して「譲渡所得税」が課されます。この税金は、売却した不動産の所有期間が5年を超えているか否かで税率が大きく変動するのが特徴です。
譲渡所得は、単純な売却価格ではなく、売却価格からその物件の取得にかかった費用や売却時の仲介手数料などを差し引いて計算されます。そのため、計算上の利益が発生しなければ、譲渡所得税が課税されることはありません。税額が高額になるケースも多いため、事前に税理士などの専門家に相談し、正確な税額を把握しておくことをお勧めします。
法人が所有する店舗を売却した場合は、譲渡所得税ではなく法人税の課税対象となります。課税されるのは、売却によって得た利益、すなわち資産の時価(売却価格)と帳簿上の価格(簿価)との差額部分です。この利益は、法人の他の事業利益と合算され、その合計額に対して法人税が課せられます。法人税と地方税を合わせた実効税率は約30%程度とされています。
個人の譲渡所得税とは計算方法や税率が異なるため、法人の場合は顧問税理士と連携し、納税額や節税対策について事前に検討しておくことが不可欠です。
店舗の売買契約書を作成する際には、「印紙税」の納付が必要です。これは、契約書に記載された売買金額に応じて定められた額の収入印紙を貼り付け、消印することで納税するものです。例えば、国税庁のウェブサイトによると、契約金額が1千万円を超え5千万円以下の不動産売買契約書の場合、本則税率は2万円ですが、令和6年3月31日までに作成されたものであれば1万円に軽減されます。
この印紙税は、通常、売主と買主がそれぞれで保管する契約書1通分ずつを負担します。不動産会社が立て替えて用意してくれる場合もありますが、誰が負担するのか事前に確認しておくとスムーズです。
仲介手数料は、店舗の売却を仲介した不動産会社に対して支払う成功報酬です。この手数料は、売買契約が成立して初めて発生します。宅地建物取引業法で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合、一般的に「(売却価格×3%+6万円)+消費税」という速算式で計算されます。例えば、売却価格が3,000万円の場合、仲介手数料は105万6,000円となります。
支払いのタイミングは、決済時に一括で支払うのが通例ですが、不動産会社によっては売買契約時と決済時に半金ずつ支払うケースもあるため、媒介契約を結ぶ際に確認しておくことが大切です。
M&Aの手法で店舗を売却する場合、不動産会社への仲介手数料とは別に、M&Aの専門業者へ支払う手数料が発生します。M&Aの手数料体系は業者によって多種多様であり、一般的には複数の手数料が組み合わされています。例えば、業務に着手する際に支払う「着手金」、基本合意書の締結時などに発生する「中間報酬」、そして最終契約が成立した際に売却価格に応じて支払う「成功報酬」などが挙げられます。
成功報酬のみの完全成功報酬制を採用している業者もありますが、着手金や中間金が必要な場合は、M&Aが成立しなくても費用が発生する点に注意が必要です。

長年大切に運営してきた店舗だからこそ、売却する際は少しでも有利な条件で手放したいと考えるのは当然のことです。店舗の売却価格は、立地や収益性、設備の状態といった多様な要因によって決まりますが、事前の準備や少しの工夫で査定額を高めることは可能です。
ここでは、売却価格の相場を把握する方法から、立地の価値の再確認、そして内装や設備の改善といった、査定額を最大化するための具体的なコツを解説します。
適正価格で店舗を売却するためには、まず大まかな相場を把握することが重要です。売却価格は、立地、規模、業態、収益性など多様な要因で決まります。
例えば、居抜き売却の場合、東京都内の約20坪の店舗で50万円から300万円程度が目安とされていますが、これはあくまで一例です。一方、M&Aの場合は、事業の将来性なども加味され、100万円から250万円程度が相場とされています。
しかし、これらは一般的な目安に過ぎません。正確な価値を知るためには、店舗売却を専門とする不動産会社やM&A仲介会社に相談し、詳細な査定を依頼することが不可欠です。
店舗の査定額を大きく左右する最も重要な要素の一つが「立地」です。多くの人が行き交う繁華街や観光地に位置する店舗は、それだけで高い集客力が見込めるため、資産価値が高く評価される傾向にあります。同じエリア内であっても、大通りに面しているか、一本路地に入っているかだけで評価は変わってきます。
また、周辺の競合店の状況も価格に影響を与える要素です。自店の立地が持つ強みと弱みを客観的に分析し、その価値を正しく評価してくれる専門家を見つけることが、高値売却への第一歩となります。隠れた価値を見出すためにも、複数の業者に査定を依頼して比較検討すると良いでしょう。
査定額を最大化するには、自身の店舗の状況に合わせて最適な売却方法を選択することが肝心です。それぞれの方法のメリットとデメリットを比較検討しましょう。
例えば、内装や設備が比較的新しく、同業者への売却が見込める場合は、解体費用がかからない「居抜き売却」が有利です。一方で、特殊な内装で買い手が限定されそうな場合や、異なる業種の需要を取り込みたい場合は、買主が自由に設計できる「スケルトン売却」の方が高値につながる可能性があります。さらに、顧客や従業員、ブランド価値を含めて事業全体を評価してほしい場合は、「M&A」が最も高い売却額を期待できる選択肢となるでしょう。
店舗の第一印象は査定額に直接影響します。特に居抜き売却を検討している場合、設備や内装の状態は重要な評価ポイントとなります。比較的新しい設備がそろっていたり、適切にメンテナンスされていたりすると、査定額が向上する可能性が高まります。日頃から清掃を徹底し、清潔な状態を保つことはもちろん、可能であれば専門業者によるクリーニングを実施するのも有効です。
また、買主候補が内見に来る際は、整理整頓された状態を見せられるように準備しましょう。顧客からの評判や口コミ評価も、店舗の価値を裏付ける材料となるため、良好な評判を維持しておくことも査定額アップにつながります。

店舗売却という複雑なプロセスを、専門知識なしに一人で進めるのは困難です。成功の鍵を握るのは、信頼できる仲介業者というパートナーを見つけることにあります。しかし、不動産会社やM&A専門業者と一括りにいっても、その専門性やサービス内容は多岐にわたります。
ここでは、豊富な実績や専門性、査定価格の透明性、そして販売活動の方法といった観点から、後悔しない仲介業者選びのポイントを詳しくご紹介します。
店舗売却を成功させるためには、信頼できるパートナー選びが不可欠です。まず確認すべきは、その業者が持つ実績と専門性です。特に、飲食店や美容室といった特定の業種には専門的な知識が必要となるため、自店の業種に特化した売却実績が豊富な業者を選ぶと、スムーズな取引が期待できます。
M&Aを検討する際は、小規模案件を得意とするM&A仲介会社や、幅広い相手と出会えるM&Aプラットフォームの利用が一般的です。また、地域に密着した不動産会社であれば、ウェブサイトには掲載されていない非公開の買い手情報を持っている可能性もあります。
適正価格での売却を実現するためには、査定価格の根拠を明確に説明してくれる業者を選ぶことが重要です。なぜその価格が算出されたのか、立地、設備、市場動向といった評価項目について、具体的に分かりやすく説明を求めましょう。複数の業者から査定を取り、その内容を比較検討することで、より客観的に自店の価値を把握できます。
また、手数料体系の透明性も重要な選定基準です。仲介手数料やM&A手数料について、「いつ」「いくら」発生するのかを契約前に詳細に確認してください。特に、着手金や中間金が必要な料金体系の場合は、万が一売却が成立しなかった場合のリスクも考慮する必要があります。
仲介業者を選ぶ際には、どのような販売活動を行い、どれくらいの集客力を持っているかを確認することも大切です。近年では、ウェブ上のマッチングプラットフォームを活用した買い手探しが主流となっています。業者がどのようなサイトに情報を掲載するのか、また、税理士や卸業者といった独自のネットワークを通じて、積極的に営業活動を行ってくれるのかを具体的に質問しましょう。
売却情報を広く公開したくない場合は、非公開での売却活動に対応してくれるかどうかも確認が必要です。自店の状況や希望に合わせた最適な販売戦略を提案してくれる業者を選ぶことが、より良い条件での売却につながります。
店舗売却は、売却方法の選択から複雑な手続き、税金対策まで、多岐にわたる知識と準備が不可欠です。本記事で解説した手順や査定額を上げるコツを参考に、計画的に準備を進めることが成功の鍵となります。そして、最も重要なのは、信頼できる専門家をパートナーに選ぶことです。後悔のない決断を下すために、専門家の知見を最大限に活用しましょう。
店舗のM&Aによる売却をご検討なら、専門的な知見と豊富な実績を持つDYMのM&Aコンサルティングにご相談ください。M&Aの専門家が、貴社の状況に合わせた最適な戦略を提案し、交渉から契約完了まで一貫してサポートします。貴社の大切な事業の価値を最大化し、円滑な事業承継を実現するため、ぜひ一度お問い合わせください。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。