Page Top

<この記事で紹介する3つのポイント>
目次
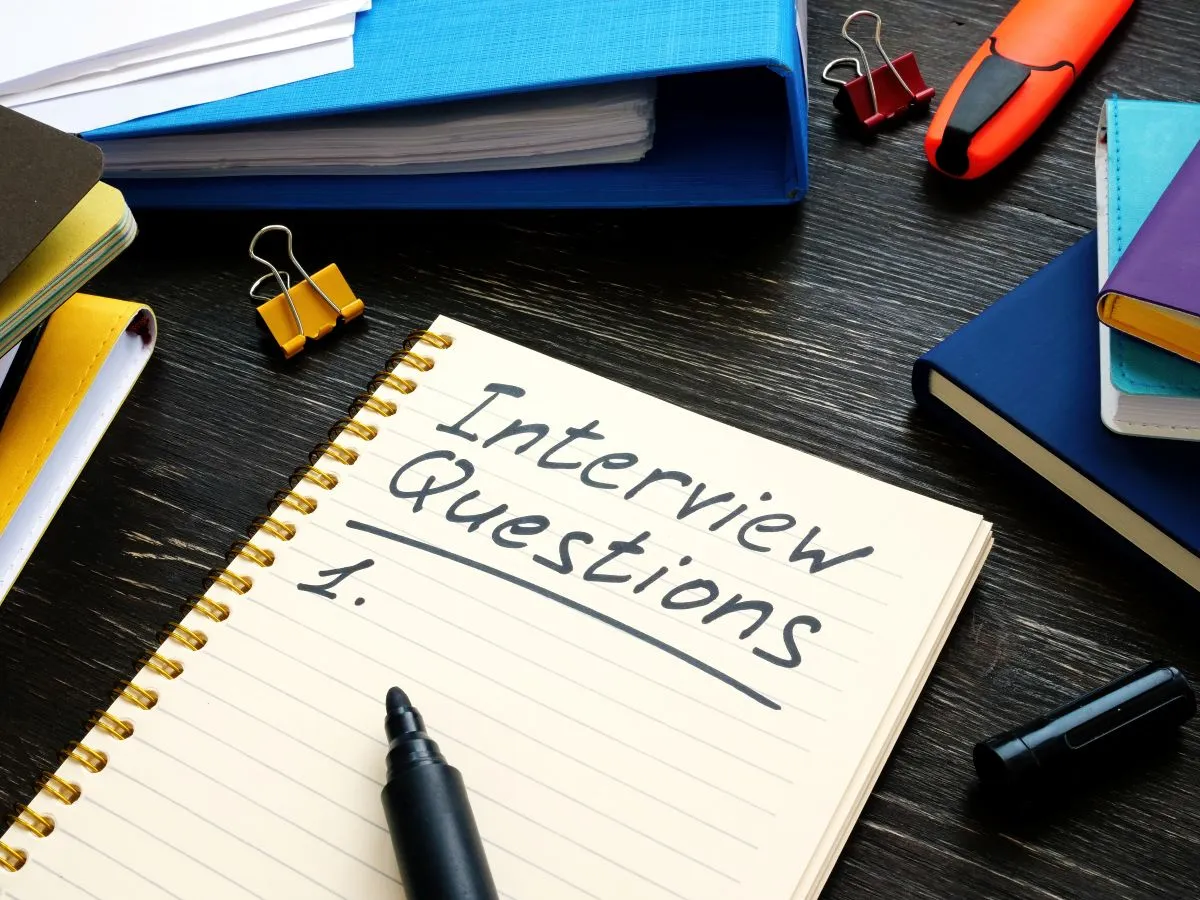
インタビュー記事とは、特定の人物や企業を対象に取材を行い、その過程で得られた考え、専門知識、あるいは生の意見を引き出し、読者に向けて分かりやすく再構成したコンテンツを指します。単なる情報の伝達に留まらず、対象者の言葉を通じてその人柄や背景にあるストーリーを伝えることで、読者の「共感」や「理解促進」を強く促す役割を果たします。
一般的なSEO記事が検索エンジンからの流入を主目的とするのに対し、インタビュー記事は取材対象者の専門知識や生の意見といった一次情報が基盤となるため、他にはない独自性とオリジナルな価値を発揮しやすいのが大きな特徴です。情報が溢れる現代において、作り手や企業の「顔」が見えるインタビュー記事は、読者との間に深い信頼関係を築くための有効な手段といえるでしょう。
インタビュー記事には、主に3つの代表的な形式があり、記事の目的や伝えたい内容に応じて最適なものを選択することが重要です。
インタビュアーの質問とインタビュイーの回答を対話のように見せる、最も一般的な形式です。会話の臨場感やリズムが伝わりやすく、インタビュイーが複数人いる場合でも誰が話しているかが明確になります。読者にとっても馴染み深く、親しみやすい構成のため、長い内容でもストレスなく読み進めてもらいやすいメリットがあります。
インタビュイー自身が一人で語りかける形式で、インタビュアーの存在を消して構成します。個人的な体験談や深い想いを伝えるのに適しており、読者は語り手の内面や感情に直接触れることで、より強く感情移入しやすくなります。著名人や専門家のストーリーをドラマチックに伝えたい場合に効果的です。
インタビュアーが第三者の視点から、取材内容を客観的に描写する形式です。インタビュイーの発言をカギ括弧で引用しつつ、その場の雰囲気、表情、仕草といった客観的な情報や背景説明を加えることができます。情報の整理や再構築が求められるため書き手の構成力が問われますが、読み応えのある深い内容に仕上げることが可能です。
インタビュー記事が特にその効果を発揮するのは、商品や企業、人物に対する読者の「理解促進」を目的とする場面です。例えば、商品・サービスの開発秘話や、顧客が導入に至った経緯と成果を語る導入事例、あるいは採用活動における社員紹介などが典型的な例です。これらのテーマでは、スペックやデータだけでは伝わらない、背景にあるストーリーや想い、個人の価値観といった「深さ」を届けることが重要になります。読者はインタビュイーの生の言葉に触れることで、対象への親近感や信頼感を抱き、より深いレベルでの理解へとつながるのです。
一方で、不特定多数への「認知拡大」が主目的の場面には、インタビュー記事は必ずしも最適とはいえません。企業やインタビュイーに相当な知名度がない限り、全く知らない人物のインタビュー記事を積極的に読もうと考える人は少ないため、目的を見極めて活用することが肝心です。
質の高いインタビュー記事を完成させるまでのプロセスは、大きく3つのフェーズに分けられます。それぞれの段階が密接に関連しており、特に最初のステップが後続の作業品質を大きく左右します。
インタビューの成否を決定づける最も重要なフェーズです。記事の目的とターゲットを明確にし、インタビュイーについて徹底的にリサーチを行います。その上で、話の核心に迫るための質問リストを作成し、相手方と共有するまでが含まれます。
準備段階で立てた仮説を基に、実際に取材を行うフェーズです。場の雰囲気作りから始まり、用意した質問を投げかけつつ、相手の回答に応じて柔軟に話を深掘りし、価値ある情報を引き出します。
取材で得た情報を記事として形にする最終フェーズです。録音データの文字起こしから始め、読者の心を動かす構成を組み立て、ライティング、編集・校正作業を進めます。最後にインタビュイーの確認を経て、ウェブサイトやSNSで公開・拡散します。
これら全てのフェーズは連動しており、特に丁寧な事前準備が、記事全体の質を決定づける土台となります。
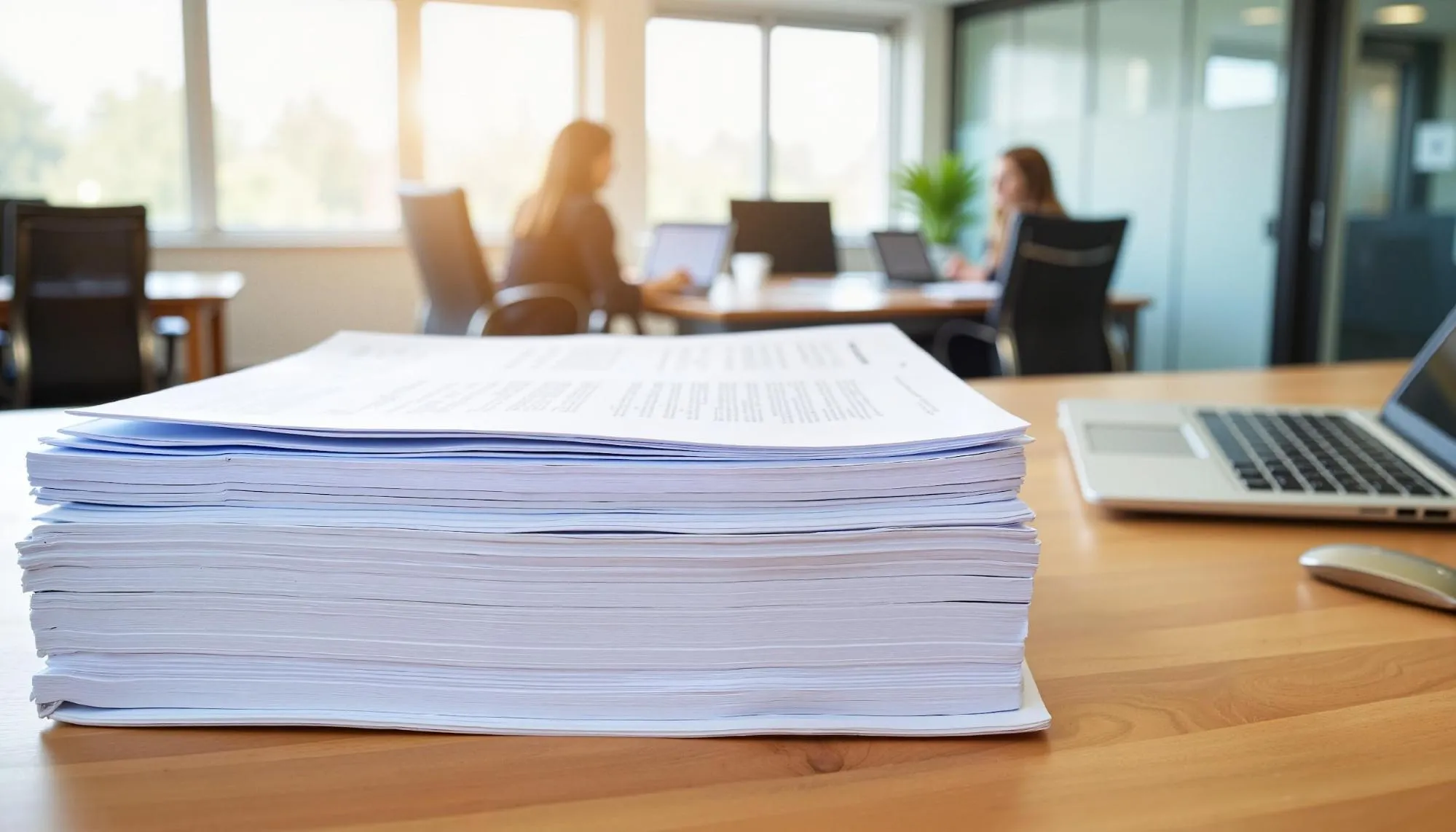
インタビュー記事の成功は、取材当日の立ち回りよりも、その前の事前準備の質で9割が決まるといっても過言ではありません。準備が不十分なまま本番に臨むと、質問が浅くなったり、話の核心に触れられなかったりする原因となり、結果として読後感の薄い記事に仕上がってしまいます。質の高いインタビュー記事は、インタビュアーの偶然のひらめきから生まれるのではなく、緻密な準備によって必然的に生み出されるものです。効果的な事前準備とは、単に質問事項をリストアップすることではありません。
目的の明確化、対象者の徹底的なリサーチ、そしてリサーチに基づいた戦略的な質問リストの作成という一連のプロセス全体を指します。この段階でどれだけ深く思考し、仮説を立てられたかが、インタビュイーから他のメディアでは語られていないような、価値ある一次情報を引き出すための鍵となるのです。
効果的な準備の第一歩は、「この記事を通じて、誰に、何を伝えて、どのような行動を促したいのか」を具体的に定義することから始まります。この軸が定まらないままでは、インタビューの方向性がぶれてしまい、結局何が言いたいのか分からない散漫な記事になってしまいます。まず目的として、「新サービスのプロモーションによる資料請求数の増加」や「採用活動における応募者への企業文化の魅力づけ」といった、具体的なゴールを設定します。
次にターゲットとして、「特定の業務課題を抱える中小企業の担当者」や「就職活動中の理系学生」のように、届けたい読者像を詳細に絞り込みます。例えば、「サービスの導入事例」を企画する場合、ターゲットを「導入を検討中の見込み顧客」、目的を「導入への不安払拭」、そして読後アクションを「サービス資料のダウンロード」と設定します。これにより、「導入の最終的な決め手」や「具体的な定量的成果」といった、目的達成のために不可欠な質問項目が自ずと明確になるのです。
インタビュイーに関するリサーチは、単なる情報収集作業ではなく、記事の核となる「ストーリー」の仮説を発見するための重要なプロセスです。このリサーチの深さが、インタビュー当日の質問の質、ひいては記事全体のクオリティを直接的に左右します。事前知識が浅いままでは、誰でも聞けるような表面的な質問しかできず、ありきたりな回答しか引き出せません。
リサーチ対象は、企業の公式サイトやプレスリリースといった一次情報源はもちろんのこと、個人のSNSアカウント(投稿内容だけでなく、何に「いいね」をしているかまで確認)、過去に受けたインタビュー記事、ブログ、関連する業界ニュースなど、多岐にわたります。これらの膨大な情報の中から、インタビュイーの経歴の転換点、繰り返し語られる価値観、最近の関心事などをつなぎ合わせ、「この成功の裏には、どのような苦労があったのだろうか」「この発言の真意は何か」といった仮説を立てます。この仮説こそが、当日のインタビューで話を深掘りするための強力な武器となるのです。

リサーチで得た情報と設定した目的を基に、インタビューの設計図となる質問リストを作成します。ここでのポイントは、「事実」を確認する質問よりも、その背景にある「考え・想い・理由」といった人間的な部分を深掘りする質問を中心に据えることです。例えば、「このサービスを開発しました」という事実だけでなく、「なぜこのサービスを開発しようと思ったのですか?」「開発中に最も苦労した点は何ですか?」といった問いが、記事に深みを与えるストーリーを引き出します。
質問リストが完成したら、インタビューの数日前までにはインタビュイーに共有しておくことが望ましいです。これを怠ると、相手が即答できない質問を投げかけてしまい、貴重な時間を無駄にする可能性があります。事前共有には、①相手が回答をじっくり準備でき、より具体的で深い話を引き出しやすくなる、②こちらの入念な準備姿勢が伝わり、信頼関係が構築され協力的な姿勢を得やすくなる、といった大きなメリットがあります。
インタビュー当日の機材トラブルは、それまでの入念な準備をすべて無駄にしてしまう可能性があります。特に音声の録音失敗は致命的であり、絶対に避けなければなりません。そのため、機材の準備と事前チェックは徹底して行いましょう。録音機材に関しては、スマートフォンのアプリでも代用は可能ですが、クリアな音質を確保し、万が一のトラブルを防ぐためにも、専用のICレコーダーの使用を強く推奨します。可能であれば、予備のレコーダーや電池も用意しておくとさらに安心です。
写真撮影に使用するカメラも同様に、前日と当日の2回にわたり、バッテリー残量、メモリーカードの空き容量、適切な設定(露出、ホワイトバランスなど)を入念に確認してください。写真は後から撮り直すことが極めて困難なため、どのような構図で撮影したいかを事前にリストアップし、試し撮りをしておくと当日の進行がスムーズになります。言うまでもありませんが、録音・撮影を行う際は、必ず事前にインタビュイーから明確な許可を得ることが必須のマナーです。
どれほど万全な事前準備を重ねても、インタビュー当日にインタビュイーから本音や深いエピソードを引き出せなければ、記事の質は高まりません。当日のインタビュアーに課せられた最大のミッションは、インタビュイーが「もっとこの人に話したい」と感じるような、心理的に安全で話しやすい場を創り出すことです。それは、単に用意した質問を順番に投げかけるだけの作業ではありません。雰囲気作り(アイスブレイク)に始まり、相手の一つひとつの発言に真摯に耳を傾け、質問の仕方(幅・深さ・時間軸)を臨機応変に工夫し、会話全体の流れを柔軟にコントロールする高度なコミュニケーション技術が求められます。
これから解説する各ポイントは、相手の心を能動的に開き、予定調和ではない、読者の心に突き刺さる「生きた言葉」を引き出すための実践的なテクニックです。

インタビュー本編が始まる前のわずか数分間で行うアイスブレイクが、その後の90分間の会話の質を大きく左右します。特に初対面の場合、インタビュイーは多かれ少なかれ緊張や警戒心を抱いているものです。この見えない心の壁を壊し、リラックスして本音を話せる心理的安全性を作り出すことがアイスブレイクの目的です。
最も効果的な話題は、事前リサーチで見つけた相手の趣味や最近の活動、あるいは共通の知人や出身地など、パーソナルな部分に軽く触れることです。例えば、「〇〇様のSNSを拝見したのですが、最近ゴルフに行かれたのですね」といった具体的な切り出し方は、相手に「しっかり調べてくれている」という好印象を与え、心を開くきっかけになります。天気や季節といった無難な話題も良いですが、一歩踏み込んだコミュニケーションが、より良い関係性のスタートを切る鍵となります。ただし、政治や宗教など、意見が対立しかねないデリケートな話題は避けるのが賢明です。
インタビュイーから一つの回答を得た後、その話をさらに豊かで立体的なものにするためには、「幅」「深さ」「時間軸」という3つのベクトルを意識して追加の質問を投げかける手法が極めて有効です。
これは、「その方法以外に、他の選択肢は検討されませんでしたか?」のように、話題を水平方向に展開させる問いです。これにより、一つの事象を多角的に捉え、意思決定の背景や全体像を明らかにすることができます。
「なぜそのように決断されたのですか?」「具体的には、どのようにしてその課題を乗り越えたのですか?」といった5W1H、特に「Why(なぜ)」「How(どのように)」を問うことで、事象の根底にある理由やプロセスを垂直に掘り下げます。記事に説得力と納得感をもたらすために不可欠な質問です。
「そのご経験は、10年後の未来にどうつながるとお考えですか?」のように、視点を過去や未来に移す問いです。これにより、話にストーリー性や奥行きが生まれ、インタビュイーの長期的なビジョンや価値観を引き出すことができます。
読者の記憶に残り、SNSなどでシェアしたくなるような魅力的な記事を作成するためには、論理的なストーリーラインだけでなく、読者の感情や注意を強く引くキャッチーな要素をインタビュー中に意図的に収集する意識が重要になります。その最も代表的なものが、具体的な「数字」です。例えば、「業績が改善した」という曖昧な話ではなく、「サービス導入後、問い合わせ件数が半年で約40倍に増加した」といった具体的な数値は、成果のインパクトを劇的に高め、記事の信頼性と説得力を裏付けます。
もう一つが、インタビュイーの哲学や想いが凝縮された象徴的な「フレーズ」です。「〇〇さんにとって、仕事とは一言で表すと何ですか?」といった問いかけは、相手の核心に迫る力強い言葉を引き出すきっかけになります。これらの数字やフレーズは、記事のタイトルや見出しに活用することで、読者の目を引きつけ、クリックさせるための強力な武器となるのです。

インタビュー中はICレコーダーで録音しているからといって、メモが全く不要になるわけではありません。しかし、メモを取る行為に没頭しすぎるのは、むしろ逆効果です。インタビュアーが終始うつむき、ペンを走らせることに集中していると、インタビュイーは「この人は本当に私の話に興味があるのだろうか」と不安に感じ、次第に口が重くなってしまいます。インタビューにおいて最も優先すべきは、相手の話に真摯に耳を傾け、目を見て、表情や相槌で「あなたの話に深く関心を持っています」という姿勢を示し続けることです。
メモを取るのは、次に深掘りしたいと感じたキーワードや、後で事実確認が必要な固有名詞、あるいは録音データには残らない相手の表情や仕草の変化など、要点に絞るべきです。会話の流れを止めない程度に、キーワードを書き留める。この録音とメモの適切な役割分担とバランスが、相手に気持ちよく話してもらうための信頼関係を築き、より本質的な言葉を引き出すことにつながるのです。
素晴らしいインタビューが実現し、価値ある情報が収集できたとしても、それがそのまま面白い記事になるわけではありません。取材で得られた大量の録音データという「素材」を、読者の心に響く「作品」へと昇華させるのが、執筆と編集のプロセスです。この段階で求められるのは、単に発言を時系列に沿って文字に起こす作業ではありません。読者の感情がどのように動くかを計算し、膨大な発言の中から最も伝えるべきメッセージを抽出し、魅力的なストーリーとして再構築する「編集者」としての視点です。
インタビュイーの人柄がにじみ出るような言葉を選び、読者がストレスなく、かつ楽しみながら最後まで読み進められるように文章を整えていく。これから、そのための具体的なライティングと編集の技術について、例文を交えながら解説していきます。
記事執筆の第一歩は、録音した音声データをテキスト化する文字起こしから始まります。この作業は非常に時間がかかるため、「Notta」などのAI文字起こしツールを積極的に活用することで、作業時間を大幅に短縮し、より創造的な作業に集中できます。
文字起こしが完了したら、次に行うのが記事全体の設計図となる構成の組み立てです。ここで重要なのは、インタビューで話された順番通りに記事を構成する必要は全くない、ということです。文字起こしされたテキスト全体を俯瞰し、読者が最も引き込まれ、メッセージが効果的に伝わるストーリーラインを再構築します。例えば、インタビューの最後に語られた最も感動的なエピソードを記事の冒頭(リード文)に持ってきて読者の心をつかんだり、あるいは苦労した失敗談から語り始め、それをどう乗り越えて成功に至ったかをドラマチックに見せる構成にしたりと、読者の感情の動きを設計することが肝心です。
インタビュー記事の最大の魅力の一つは、事実やノウハウだけでなく、語り手であるインタビュイーの「人柄」やその場の「熱量」が読者に伝わる点にあります。その人柄を効果的に表現するためには、すべての話し言葉を画一的な書き言葉に整えてしまうのではなく、その人らしさが滲み出る言葉遣いや表現を意図的に記事に残すことが有効です。
例えば、以下のようなテクニックが挙げられます。
【例文】
(修正前)
「そのプロジェクトは大変でしたが、最終的には成功して良かったです。」
(修正後)
「いやー、あのプロジェクトは本当に大変で…(苦笑)。でも、最終的に『やった!』ってガッツポーズできる結果になって、本当によかったんですよ。」
このように、文末表現を「〜だったんですよ。」といった柔らかな口調にしたり、「(笑)」や「!」といった記号で感情の機微を表現したり、「そうそう!」や「うーん」といった相槌を効果的に挿入することで、会話の温度感やリズムが生まれ、読者はまるでその場で対話を聞いているかのような臨場感を得られます。
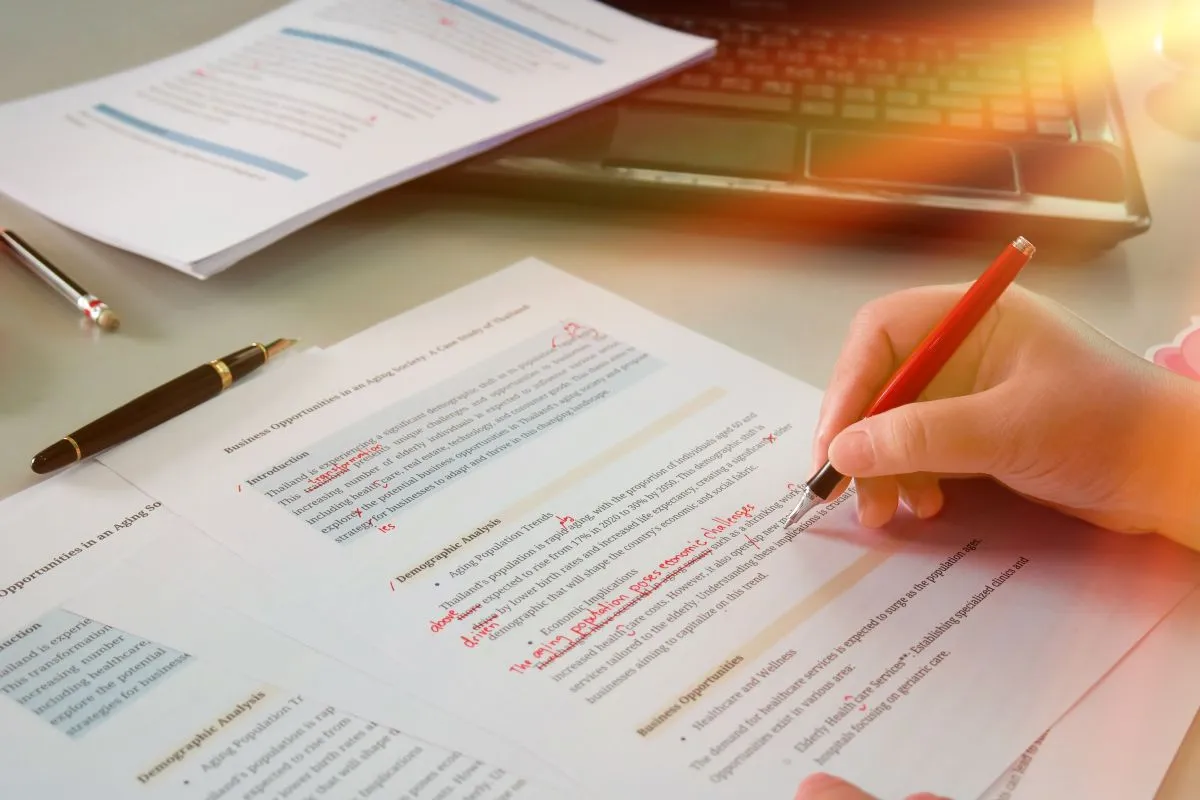
どれだけ内容が素晴らしくても、読みにくい記事は読者にストレスを与え、途中で離脱されてしまいます。執筆後は必ず、「初めてこの記事に触れる読者の気持ちになりきる」という視点で、客観的な編集・校正作業を行いましょう。
業界用語や専門用語が多用されていないかを確認し、読者のリテラシーに合わせて一般的な言葉に置き換えるか、「※〇〇:〜という意味」といった補足説明を加えます。
一文を40〜60文字程度の短い長さに保ち、意味の区切りで適度に改行や段落分けを行います。また、文字ばかりが続くと読者は疲れてしまうため、インタビュイーの表情がわかる写真や、話の要点をまとめた図解などを「1スクロールに1枚」程度の頻度で挿入すると、視覚的なアクセントとなり、読者を飽きさせません。
誤字脱字のチェック(校正)や、内容の矛盾・事実関係の確認(校閲)は、執筆者本人では気づきにくいものです。可能であれば、必ず社内の別の人など第三者に読んでもらい、客観的なフィードバックをもらうことが記事の品質を飛躍的に向上させます。
記事のタイトルは、読者がその記事を読むか読まないかを0.5秒で判断する、最も重要な要素です。SNSのタイムラインや検索結果に表示された際、読者の指を止めさせる力がなければ、本文が読まれることはありません。「【インタビュー】株式会社〇〇〇〇様」のような事務的なタイトルでは、相手がよほどの有名人でない限り、クリックされる可能性は極めて低いでしょう。読者の興味を引くためには、記事の中で最もインパクトのあるフレーズや具体的な数字をタイトルに盛り込むのが効果的です。
【タイトル例】
悪い例:【社員インタビュー】営業部・太田一郎さん
良い例:お客様と話すのが苦手「だからこそ」営業へ。入社半年でトップセールスになれた私の逆転仕事術
良い例のように、意外性や逆説(AなのにB)、読者が自分事として捉えられる課題解決のヒント、あるいは好奇心を刺激する問いかけなどを加えることで、「この記事を読めば、何か面白い発見や学びがありそうだ」という期待感を抱かせることが可能になります。記事本文だけでなく、このタイトル作成にこそ、最も知恵を絞るべきです。
多大な時間と労力をかけて制作したインタビュー記事も、ウェブサイトに公開して終わりでは、その価値を半分も活かせているとはいえません。記事の価値を最大化するためには、公開後の戦略的な「活用」の視点が不可欠です。完成した記事は、単独のコンテンツとしてだけでなく、様々なマーケティング活動や採用活動に応用できる貴重な「資産」と捉えるべきです。例えば、採用活動における企業文化の具体的な証明、営業活動における信頼獲得のための第三者の声、SNSでのエンゲージメント向上施策など、その活用法は多岐にわたります。
この記事という資産をどのように展開し、ビジネス上の目的に貢献させていくか。ここでは、記事の効果を何倍にも高めるための具体的な活用方法と、拡散を意識した制作のコツを解説します。

インタビュー記事は、その制作目的によって最適な活用方法が異なります。
社員インタビューは、求人情報だけでは伝わらないリアルな社風や働きがい、キャリアパスといった「生の情報」を求職者に届けるための強力なツールです。企業の採用サイトやオウンドメディアに掲載するだけでなく、採用イベントでQRコードを載せた資料を配布したり、スカウトメールの文面に記事URLを添付したりすることで、候補者の企業理解を深め、応募意欲を効果的に高めることができます。
顧客が語る導入事例インタビューは、製品やサービスの価値を客観的に証明する「第三者の声」として、絶大な信頼性を持ちます。営業担当者が商談時に提示する資料に組み込んだり、検討段階の見込み顧客リストに対してメルマガで配信したりすることで、導入への最終的な意思決定を力強く後押しします。
経営者や開発者のインタビューを通じて、企業のビジョンや製品開発に懸ける情熱、社会課題へのスタンスなどを発信することは、企業のブランディングに大きく貢献します。直接的な販促とは異なりますが、企業のファンを育成し、長期的な共感を醸成する上で重要な役割を果たします。
記事のリーチを最大化し、より多くの読者に届けるためには、SNSでの拡散が不可欠です。そのためには、記事制作の段階から「シェアされやすさ」を設計に組み込んでおくことが重要になります。最も効果的な施策は、インタビュー対象者本人やその所属企業に、記事の拡散を積極的に協力してもらうことです。彼らが自身の信頼するネットワークで記事をシェアすることで、自社のアカウントだけでは到底リーチできない新たな読者層へ情報を届けることが可能になります。
この協力をスムーズに得るために、記事公開時には、対象者が手間なくSNSに投稿できるよう、数パターンの紹介文や推奨ハッシュタグ、アイキャッチ画像や記事内の名言を切り抜いた引用画像などをセットで提供すると非常に親切で、喜んで協力してもらえる可能性が高まります。また、自社の社員にも個人アカウントでのシェアを推奨するなど、組織全体で情報を発信していくカルチャーを醸成することも、拡散力を高める上で有効です。
インタビュー記事と一括りにいっても、その形式によって目的と役割は異なります。代表的な3つの形式を適切に使い分けることが重要です。
製品・サービスの導入効果を第三者の声で客観的に証明することを目的とします。具体的な課題がどのように解決され、どのような定量的・定性的な成果が出たのかを示すことで、検討段階にいる見込み顧客の「本当にこのサービスで大丈夫だろうか」という不安を払拭し、導入を後押しする役割を担います。
働く「人」の魅力や独自の企業文化を伝えることを主目的とし、主に採用活動で絶大な効果を発揮します。求職者が知りたい「どんな人たちと、どんな雰囲気の中で働くのか」という疑問に、社員のリアルな声で応えることで、企業へのエンゲージメントを高めます。
自社の考えやポジションを、より客観的・多角的な視点から発信する際に有効な手法です。社外の専門家やパートナー企業の代表者などと特定のテーマについて語り合うことで、一つのテーマに対する深い洞察力を示し、業界内での専門性やリーダーシップをアピールするブランディング効果が期待できます。

インタビュー記事制作の過程では、特に経験が浅い場合に陥りがちな典型的な失敗パターンがいくつか存在します。これらを事前に把握し、対策を講じることが重要です。
会話を単に文字にしただけのコンテンツは、読者にとって冗長で退屈です。インタビューはあくまで素材であり、読者の興味を引き、メッセージが明確に伝わるように編集・再構成するプロセスが不可欠です。
「伝えたいことが多すぎる」という作り手の思いから記事を分割しがちですが、よほどの有名人や人気連載でない限り、後編まで読んでもらえる保証はありません。要点を絞り込み、一本の記事として潔く完結させる編集力が求められます。
これが最も根本的かつ致命的な失敗です。インタビュイーについてのリサーチ不足は、質問の浅さに直結し、結果としてどこかで読んだことのあるような表面的な記事しか生み出しません。対策は、目的を明確にし、徹底的に事前リサーチを行う以外にありません。記事の質は、取材前の準備量で決まることを肝に銘じるべきです。
今回はインタビュー記事の書き方を、事前準備から執筆、活用法まで網羅的に解説しました。重要なのは、読者の心を動かすための徹底した準備と、相手の魅力を引き出す技術です。しかし、どれほど素晴らしい記事を作成しても、読者に届かなければ意味がありません。
株式会社DYMのSEO対策事業では、貴社の魅力的なインタビュー記事が検索エンジンで適切に評価され、より多くの読者に発見されるよう支援します。コンテンツの価値を最大化する次の一手として、ぜひお気軽にご相談ください。

「世界で一番社会を変える会社を創る」というビジョンのもと、WEB事業、人材事業、医療事業を中心に多角的に事業を展開し、世界で一番社会貢献のできる会社を目指しています。時代の変化に合わせた新規事業を生み出しながら世界中を変革できる「世界を代表するメガベンチャー」を目指し、日々奮闘しています。